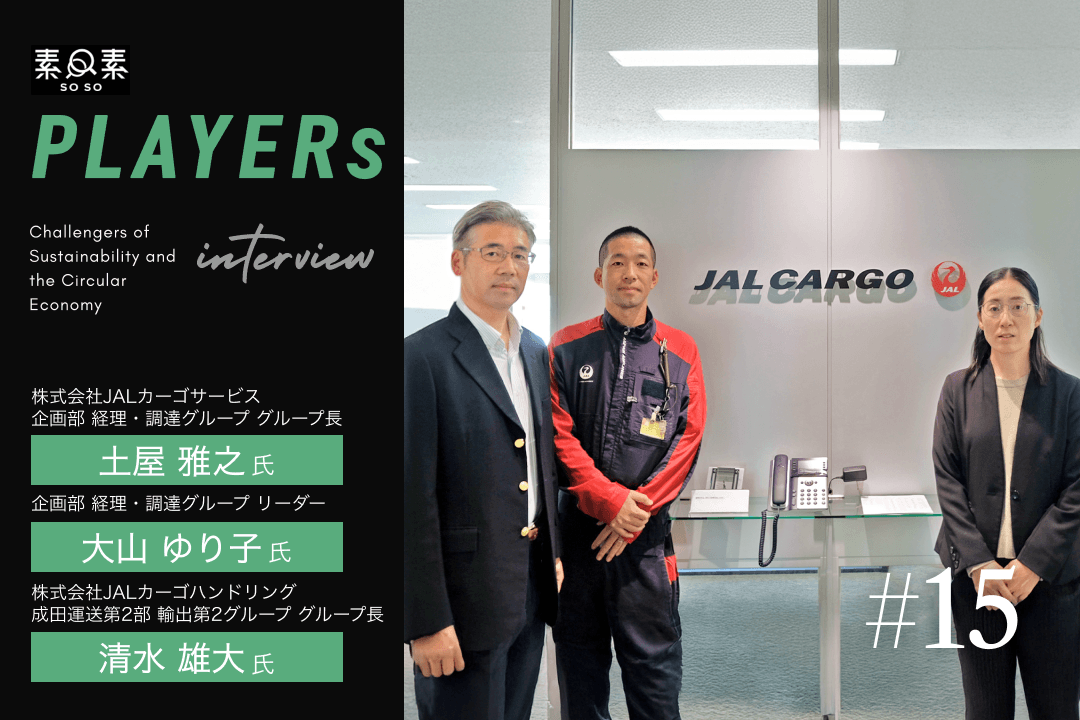取材現場で心を動かされた言葉、記事にはならなかった小さな発見、そして、日常の中でふと感じたサステナビリティのヒント。本コラムでは、編集局メンバーの目を通したそんな「ストーリー」を、少し肩の力を抜いて、ゆるやかにつづっていきます。
今回の担当は眞崎です。
穏やかな正月が一転
「今年こそ、平和な年になりますように」
1月3日、沖縄県南部の平和祈念公園で、そう手を合わせました。雲の切れ目からのぞく青空と、群青の海。観光客もまばらな園内には、静かな時間が流れていました。

その数時間後、スマートフォンに流れてきたのは、「米国、ベネズエラ大統領を拘束」というニュース速報でした。正直、言葉を失いました。昨年末から緊張が高まっているとは報じられていましたが、まさか現役の大統領が拘束され、「拉致」されるとは…。
さっきまで平和について考えていた頭が、一気に現実に引き戻されました。
逆回転する歴史
新年早々、世界は落ち着くどころか、むしろ不穏さを増しています。米トランプ政権による一連の強硬な動き、グリーンランドの領有を巡る発言、国連をはじめとする多くの国際組織からの脱退表明――。
歴史が、急速に逆回転しているように感じる瞬間が、確かにあります。分断と偏狭なナショナリズムが、じわりじわりと生活を脅かしつつある。そんな空気を、多くの人が肌で感じているのではないでしょうか。私自身も、その1人です。
サステナビリティを取り巻く状況も、楽観できるものではありません。脱炭素やESGへの逆風、反DEI(多様性・公平性・包括性)の動き、「今はそんな余裕はない」という空気感。正直に言えば、このテーマはここ数年で最も冷え込んでいると感じます。
ウーブン・シティで感じたこと
それでも、私たちはこのテーマから目をそらさない。そう思えたのは、年の瀬に取材した、トヨタの実証都市「ウーブン・シティ」(静岡県裾野市)での体験も大きいかもしれません。
富士山の麓で進むそのプロジェクトは、「ヒト中心の街」をコンセプトに、全ての人に対する「幸せの量産」を目指しています。モビリティやエネルギー、暮らしのインフラを一体で設計する実証がスタートしていますが、試行錯誤の連続で、想定通りには進んでいない面もあるようです。

それでも実証に参加する関係者は「すぐにビジネスになるかどうか」よりも、「より良い明日を届ける」ために、地道な実装に挑み続けています。こうした現場に立ち会うたびに、気付かされます。「成功事例」だけでなく、「失敗」や途中経過もしっかり伝えるべきではないか、と。
現場で交わされている悩みや葛藤、試行錯誤のプロセスそのものにこそ、次のアクションにつながるヒントが詰まっていると思うからです。私たちは国内外の事例や現場の声を通じて、「自社だったら何ができるだろうか」と考えるきっかけを届けるメディアでありたい。そして、その小さな問いが、新しいアクションやイノベーションの芽につながっていくことを願っています。
「Adapt and Accelerate」が示す、これからの姿勢
来月18日、19日には「サステナブル・ブランド国際会議 2026 東京・丸の内」が開かれます。今年は、節目となる10回目の開催。テーマは「Adapt and Accelerate」です。
このテーマは、今の時代を象徴しているように感じます。理想を掲げるだけでは前に進めない。現実の制約に向き合いながら、戦略的に対処し、新たな価値の創出へスピードを上げていく。そんな姿勢が、これまで以上に求められているのだと思います。
この不確実な時代に、この会議が開かれること自体に、私は大きな意味があると感じています。サステナビリティを多角的に学ぶだけでなく、現実を直視した上で、立場や業界を越えた共創により新たな価値を生み出す。そんな10周年にふさわしい場になることを、心から期待しています。
私たちが伝え続けたいこと
サステナビリティを取り巻く状況は、決して明るくはありません。それでも今年も私たちは、「より良い世界」を目指して試行錯誤する人や企業の声を拾い続けます。国内外の最新動向や現場の事例をできるだけ立体的に伝えながら、サステナビリティを「理念」ではなく、「次の一歩につながる現実的な選択肢」として提示していきたいと考えています。
この編集局コラムも、その意思表明の一つとして今年も続けます。今回は少し堅苦しくなりましたが、次回からはもう少し肩の力を抜いて、ゆるゆるとつづっていきます。本年も、読者の皆さまと一緒に考え続けていけたらうれしいです。どうぞよろしくお願いいたします。
眞崎 裕史 (まっさき・ひろし)
サステナブル・ブランド ジャパン編集局 デスク・記者
地方紙記者として12年間、地域の話題などを取材。フリーランスのライター・編集者を経て、2025年春からサステナブル・ブランド ジャパン編集局に所属。「誰もが生きやすい社会へ」のテーマを胸に、幅広く取材活動を行う。