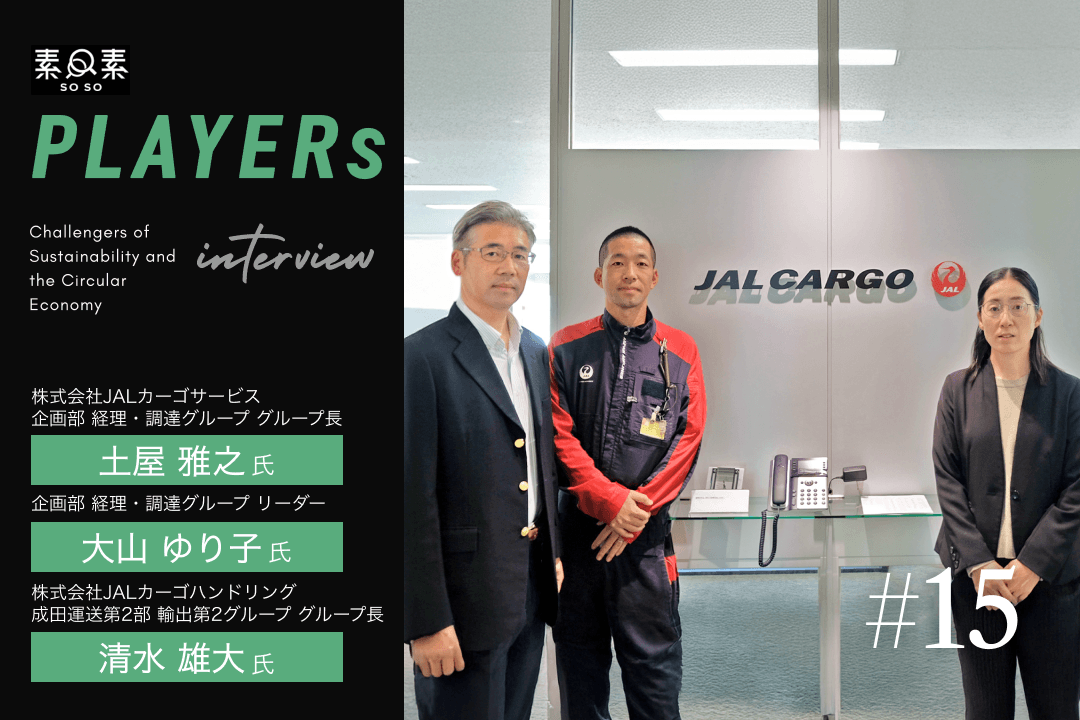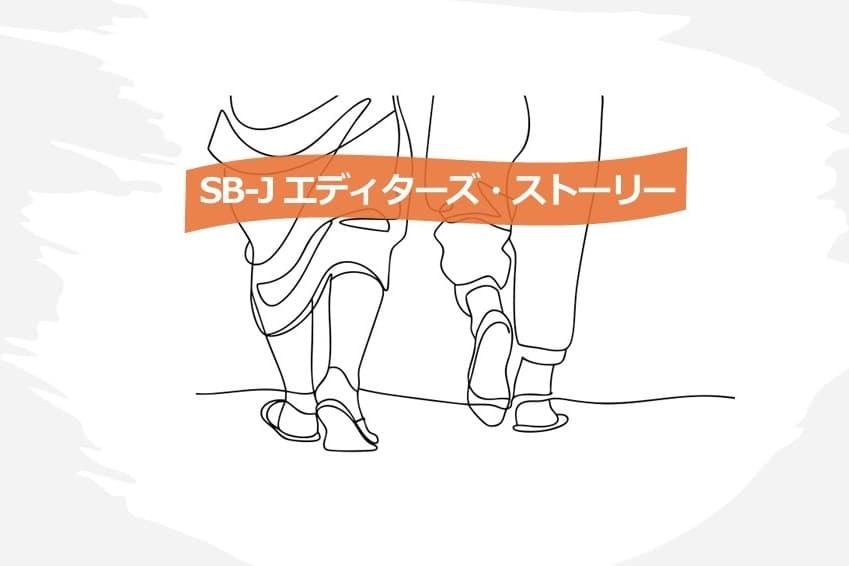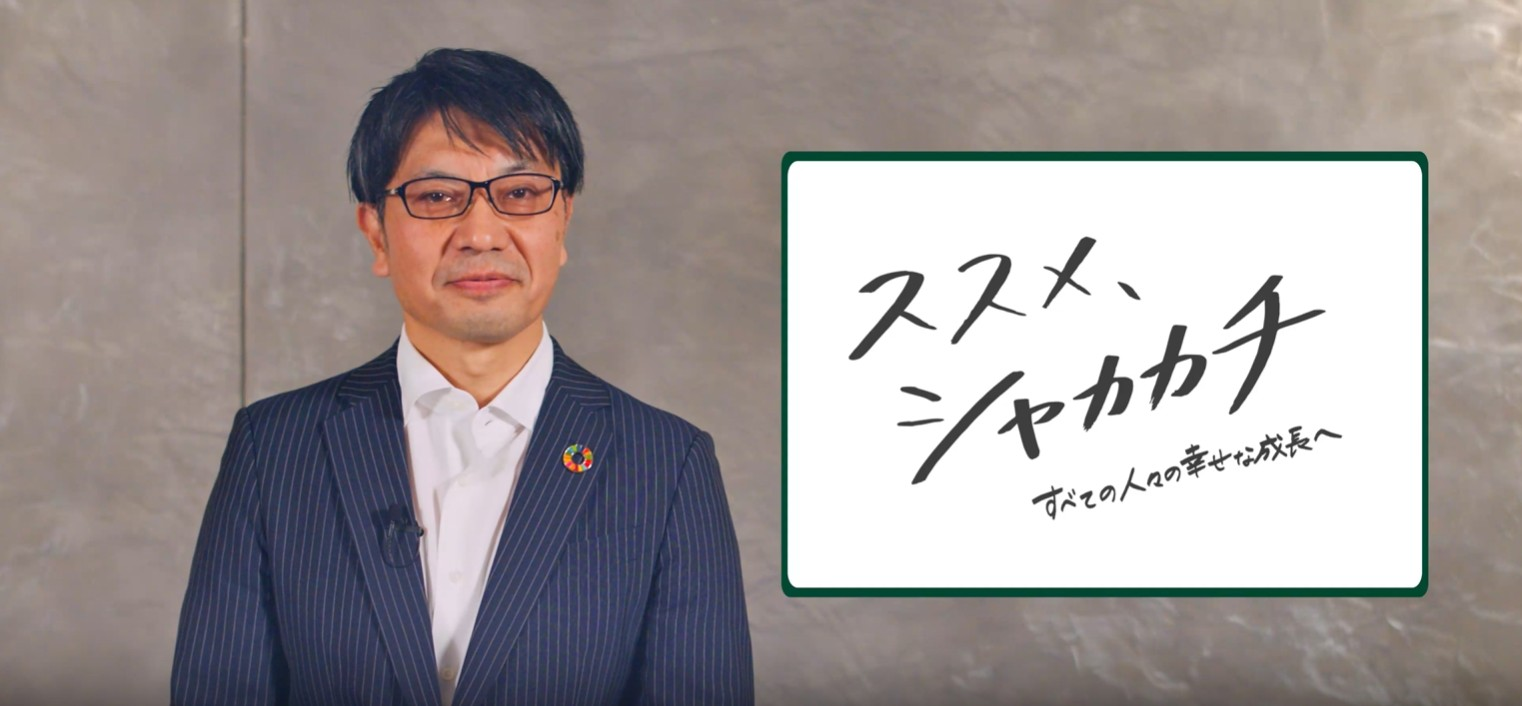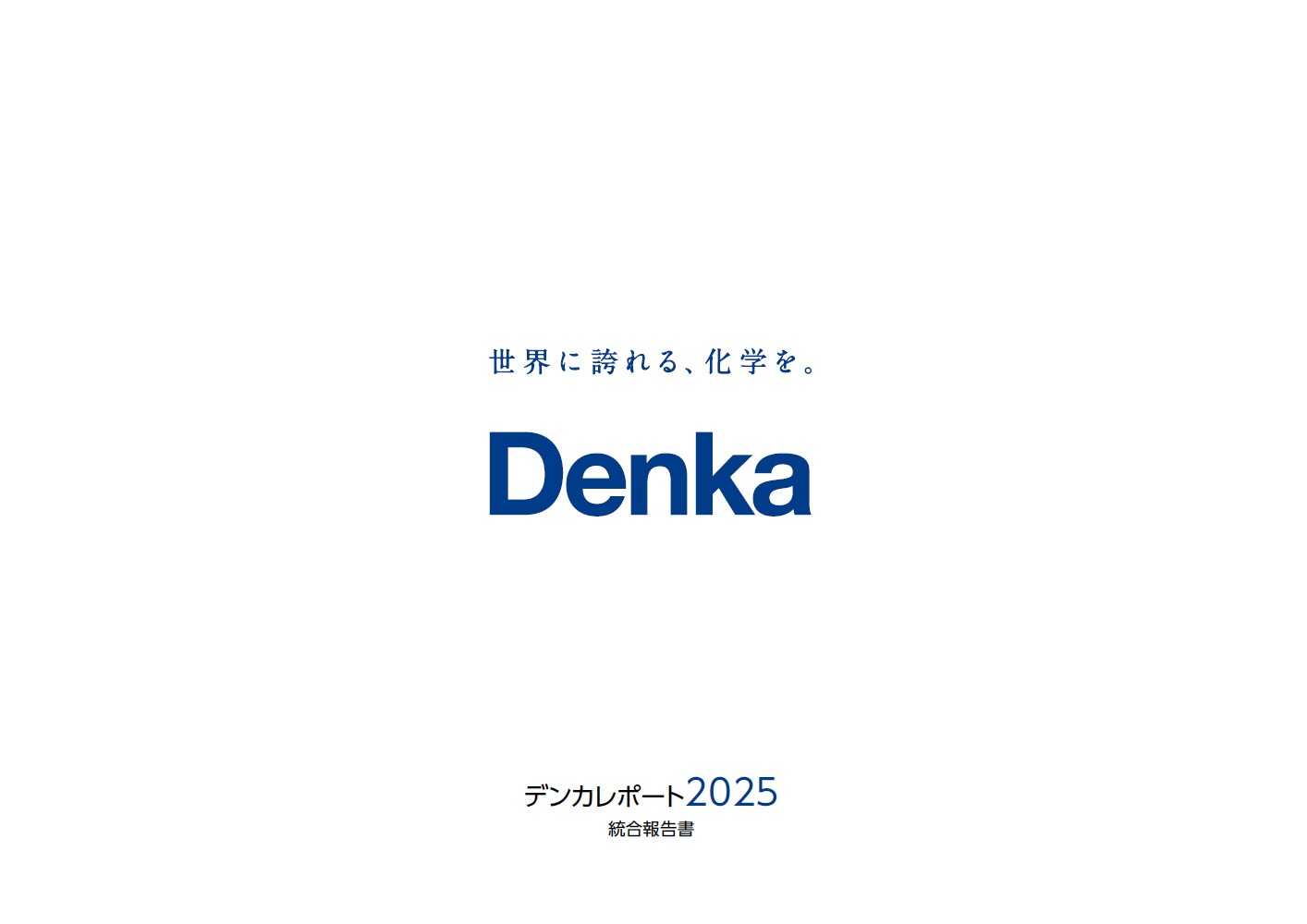サステナブルな活動を、
ブランド価値につなげる。
グローバルで活躍する日本企業・外資系企業のサステナビリティな取り組みや、コミュニケーション手法を例に、自社の現状や課題を洗い出し、実践に変えていくためのコミュニティ創造を行っています。
 News新着記事
News新着記事

News
新着記事
 WorldNewsワールドニュース
WorldNewsワールドニュース

WorldNews
ワールドニュース
 Interviewインタビュー
Interviewインタビュー

Interview
インタビュー
 SUSTAINABLEOFFICERS企業・団体のトップ、サステナビリティ担当役員インタビュー
SUSTAINABLEOFFICERS企業・団体のトップ、サステナビリティ担当役員インタビュー
SUSTAINABLEOFFICERS
企業・団体のトップ、サステナビリティ担当役員インタビュー
 Report Library様々な企業の情報開示資料や動画が閲覧できるライブラリー
Report Library様々な企業の情報開示資料や動画が閲覧できるライブラリー

Report Library
様々な企業の情報開示資料や動画が閲覧できるライブラリー
 Sponsoredスポンサー記事
Sponsoredスポンサー記事

Sponsored
スポンサー記事