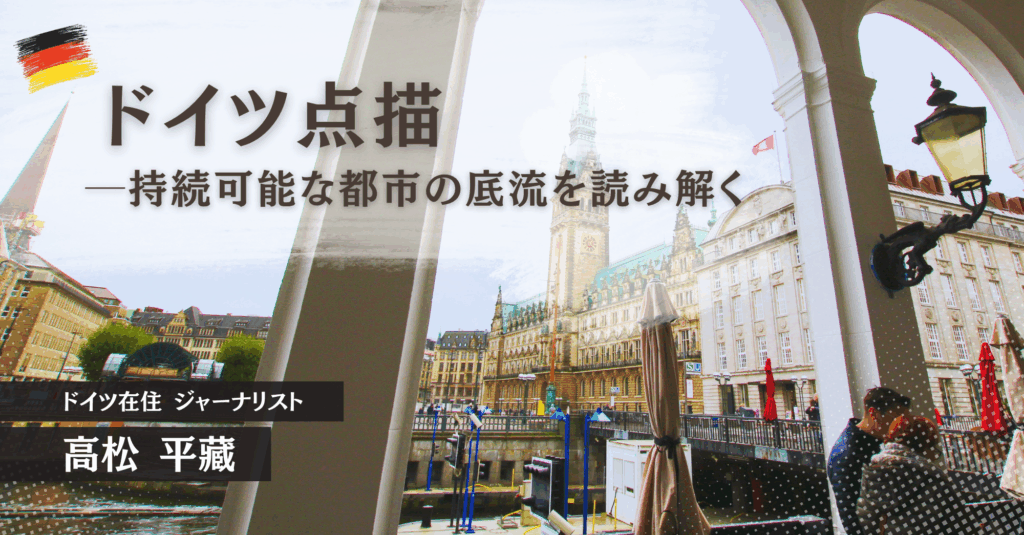
7月の参議院選挙では、争点の一つとして「外国人」の存在がクローズアップされた。世界全体を見れば、外国人問題は「古くて新しい」テーマだ。ここドイツでもこの20年あまり、難民や移民の流入は「新たな外国人問題」となってはいるが、その一方で、多文化共生や外国人政策は着実に前進している。これについて日本の大学などの講演で話すと、主に日本に住む外国ルーツの人たちから「ドイツの外国人がうらやましい」と言われることがある。日本とドイツで何が違うのかを考えてみた。
◾️多層的グローバル化は日常
20年以上前、ヒジャブを巻いたイスラム系女性がフォルクスワーゲンを颯爽(さっそう)と運転する姿に出会った。「フォルクス」はドイツ語で民族・国民。ユダヤ人を大量虐殺したナチス時代、国策として「国民の車」が作られた歴史を思えば、過去と現在の対比は鮮烈だ。戦後の経済成長期から旧西ドイツにはトルコなどから労働者が増えていたが、2000年になってようやく政府が「移民国家」と自認した。この光景はその象徴に思えた。
いまや外国人なしにドイツの社会・経済は成り立たない。二世三世も増え、国際結婚や複雑な家族ルーツも一般的。帰化者も多い。こうした人々は「移民背景」と定義され、国全体の約3割に及ぶ。その半数弱が外国籍だ。多層的なグローバル化は日常である。日本で類似の多様化が進むが、「移民政策」という言葉は依然慎重に扱われると聞く。まずは属性の概念整理を行うことで議論が深まるのではないか。
翻って、私の住むエアランゲン市(バイエルン州、人口約12万人)でも、例外ではない。約36%が「移民背景市民」。そんな町に、1974年から「外国人統合諮問委員会」がある。外国系の市民の権益や文化的ニーズを市政に反映する役割を果たす。反人種差別キャンペーンの展開や、異文化理解の教育プログラム、広報などの分野で市議会や市の取り組み強化に協力している。これは「外国人も地域社会の一部」「共に歩む仲間」という社会デザインの表れだ。
◾️民主主義と「外国人」の関係は?
2005年施行の移民法は象徴的で、外国人が暮らしやすいようドイツ語習得の場を「国の投資」と位置づけた。統合は「長期・双方向プロセス」とされ、同化ではなく相互の影響と共生を目指す。民主主義の基盤である自由・平等・人間の尊厳・宗教の自由は全市民に求められ、守られるべきものとされる。諮問委員会の委員は移民背景市民の選挙で選ばれ、自発的な政治参加が本格的統合の条件とされる。

EU市民は国籍がなくても地方選挙に参加できるが、非EU市民は選挙権がない。それでも委員会活動を通じて市政に意見を届け、間接的に民主主義に関わることができる。毎年帰化者を祝う式典で市長は「帰化は都市社会への信頼の表れ。ぜひ社会に関わってほしい」と語る。
ドイツの民主主義は、「多様性」と「結束」という矛盾するかのようなものを縫合し、地方の創造的エネルギーに変える装置でもあることが分かる。
外国系市民にとって国政も関心事だが、日々の生活に直結するのは地方政治だ。民主主義は選挙だけで成り立つものではなく、地域での意見表明や意思決定への関与が不可欠。この視点から見れば、日本における外国人の政治参加を巡る議論も、より現実に即したバランスの取れたものとなり、民主主義そのものを再解釈する契機になり得るだろう。
◾️リアルな多文化社会の現場が地方に
民主主義とは何かを考えさせられる、この町の事例をもう一つ紹介しよう。ドイツ語で「健康に対する運動投資」を略した「BIGプロジェクト」という運動プログラムがある。主に社会的弱者の女性(なかでもイスラム系含む外国ルーツの女性)がターゲットだ。
実はこのプログラムの担当者に取材した時、現場での同行もリクエストしたところ断られた経験がある。なぜなら、夫以外の男性と公的空間を共にできない宗教的背景があるからだ。だからトレーナーも女性である。そしてトレーナーによる「与えられたプログラム」をこなすのではなく「どういうことを、どのようにしていくか?」ということを参加者で話しあう。
イスラム系の女性は自分の意見を述べる機会も少ない傾向があるようだ。その上でこの現場をリアルに想像していただきたい。そんな女性たちにとって「考え」「話す」場に放り込まれることは、おそらく新鮮な体験ではないだろうか。実はこれこそ、民主主義の入口だ。意見表明は民主主義の作法だ。集団の意思決定に関わることが、個々の尊厳を保証する場所を得るのだ。リアルなドイツの多文化社会の現場が、ここにある。
◾️民主主義が守る多様性と人間の尊厳
ドイツで極右政党AfDが台頭し、外国人排斥を唱えているが、これは民主主義の基盤である多様性と共存に反する。ドイツは言論の自由を保障しつつ、民主主義の破壊に断固として闘う考え方がある。これが極右政党への反対派の根拠になる。
この姿勢は外国人を単に受け入れるだけでなく、「共生」を制度化し、「人間の尊厳」を実効ある形で守ろうとする強い意志に表れている。人間の尊厳とは「人をモノのように扱わない」ことであり、それを守る概念が人権だ。西洋的響きに違和感を覚える人もいるかもしれないが、ドイツでは生活の基層に深く刻まれ、多くの人々に内面化されている。こうした価値の蓄積が制度や運動に結びついていることが、「ドイツの外国人がうらやましい」という印象を生むのだろう。

高松 平藏 (たかまつ・へいぞう)
ドイツ在住ジャーナリスト
ドイツの地方都市エアランゲン市(バイエルン州)および周辺地域で定点観測的な取材を行い、日独の生活習慣や社会システムの比較をベースに地域社会のビジョンを探るような視点で執筆している。日本の大学や自治体などでの講義・講演活動も多い。またエアランゲン市内での研修プログラムを主宰している。 著書に『ドイツの地方都市はなぜクリエイティブなのか―質を高めるメカニズム』(学芸出版)をはじめ、スポーツで都市社会がどのように作られていくかに着目した「ドイツの学校には なぜ 『部活』 がないのか―非体育会系スポーツが生み出す文化、コミュニティ、そして豊かな時間」(晃洋書房)など多数。 高松平藏のウェブサイト「インターローカルジャーナル」










