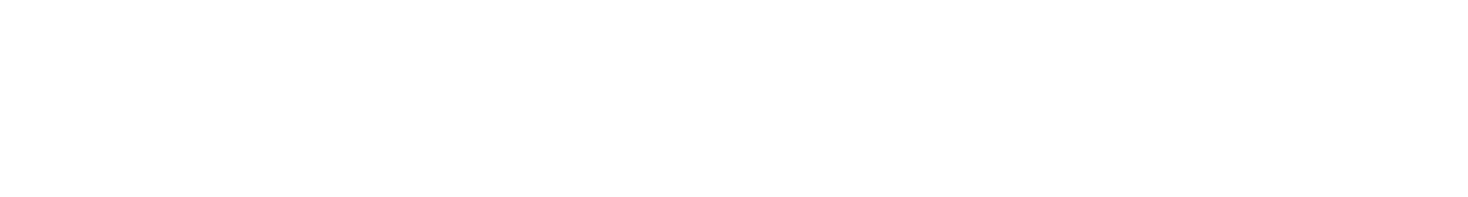『前向きに今日を生きる人の輪を広げる』――広島と共に歩んだマツダのDNAとは
- Interviewee
- 毛籠(もろ)勝弘・マツダ 代表取締役 社長兼CEO(最高経営責任者) コミュニケーション・サステナビリティ統括
- Interviewer
- 青木茂樹・SB国際会議 アカデミック・プロデューサー/ Aalborg University Business School Visiting Scholar (インタビュー時) / 駒澤大学 経営学部 市場戦略学科 教授

|
モビリティはどこまで人の力になれるか。走る歓び、その価値を電動化の時代になっても提供し続けたい――。2月に行われた「SB国際会議2024東京・丸の内」で、そう力強く語ったマツダ社長の毛籠(もろ)勝弘氏。広島を拠点に創立104年を迎える歴史の中で、ロータリーエンジンに代表される革新的な技術で異彩を放ってきたマツダは、カーボンニュートラルという時代の要請に向けて自動車業界が大変革期を迎えた今、そのマツダらしい価値をどう描き続け、それを実現していこうとしているのか。青木茂樹・SB国際会議アカデミック・プロデューサーが広島発、グローバル自動車メーカーの本音と戦略に切り込む。
お客さまから熱狂的に支持されることが生きていく源泉 そのために技術を磨く
青木:今回ご登壇いただいたプレナリーでは、広島で生まれ育った自動車メーカーとして、戦後の広島の復興に御社が深く関わり、日々前向きに取り組んできた先達の生きざまが、飽くなき挑戦というマツダのDNAを育んできたと話されました。
このマツダのDNA、マツダらしさというものを毛籠社長はどのように捉えていらっしゃるのか、改めてお聞かせください。
毛籠:はい。大戦当時、マツダの前身の東洋工業は、爆心地からは5キロほど離れた場所にあり、比治山や黄金山という小山が爆風を避けてくれたこともあって、幸運にも大きな被災を免れたんです。先輩たちは原爆投下の4カ月後に三輪トラックの生産を開始し、戦後の復興の一翼を担いました。広島の人たち、みんながそれぞれに全力を尽くして、1日1日を生きていった。大事なのは平和であり、平和の象徴としての人々の笑顔です。そういう風土の中で企業市民として育ってきたことが、世代を超えて当社の重要な軸となり、「飽くなき挑戦」というDNAを生み出したのだと思います。
もう一つ、やはり東京から地理的に離れていることが、当社にとっては大きかった。国策で、世界に向けて、競争力のある自動車を送り出そうとすると、当然ながら統合といった話も出てくるかと思いますが、当社は地域にしっかりと根付いてやり続けてきた。それには独自の技術が要る。つまり、お客さまから熱狂的に支持されることが、生きていく源泉であり、そのためには技術を、独自の価値を磨こうと。その最たるものが、世界中の自動車メーカーが実用化に断念するなか、6年半の歳月をかけて開発に取り組み、1967年に本格的な量産に成功をしたロータリーエンジンに象徴されていると思います。

サステナブル・ブランド国際会議2024東京・丸の内の展示ブースで、マツダのロータリーエンジンについて青木氏に説明する毛籠氏
|
青木:やはり、広島という場所が、御社の独自性を強固なものにしていったのですね。
毛籠:そうです。ロータリーエンジンの開発に成功したエンジニアたちのスピリットが世代を超えて受け継がれ、世界一の低燃費を目指したピストンエンジンであるSKYACTIV(スカイアクティブ)エンジンシリーズの開発へとつながっていきました。
青木:SKYACTIVエンジンの開発にシフトするために、ロータリーエンジンは一時期、生産終了という辛い決断をされたこともあったそうですね。
毛籠:はい。2012年のことです。しかし、その時期も、ほんの一握りのエンジニアがコツコツとロータリーエンジンの技術開発を続けていました。表には出ないで、深く地下に潜って、ずっと研究開発を続けていた。そういうものなんですね。きっと、いつの日か浮上してやると。いい意味で諦めが悪い(笑)。そんなところも当社の長所であり、非常にユニークなところだと思います。
勇気付けられたジャパンモビリティショーでのICONIC SPへの声援
|
昨年のジャパンモビリティショーに出展された未来のコンパクトスポーツカー、MAZDA ICONIC SP
|
青木:私は昨年のジャパンモビリティショーをデンマークでウェブサイトの動画で見たのですが、ICONIC(アイコニック)SPが登場した場面で一気にアクセス数が伸びたのに驚きました。毛籠社長ご自身は、このモビリティショーでの観客の反応をどのように受け止められましたか。
毛籠:おかげさまで世界各国から大きな反響をいただき、非常に嬉しく、勇気づけられました。ICONIC SPは、カーボンニュートラル時代に我々が作りたい車の一つの形として自信を持って提案したのですが、それが果たしてソリューションとして受け入れてもらえるのかは出展してみないと分かりません。新しい形の拡張性のある電気自動車という方向にアクセルを踏んでいくには、お客さまの支持が得られないといけない。そう考えていましたので、モビリティショーの『頑張れ』という熱い声援に大変勇気をもらい、今年2月のロータリーエンジン開発グループの再結成につなげることができました。
青木:御社の技術力が結集したロータリーエンジンの仕組みと、スポーツカーとしての美しさのバランスが評価されたのですね。私はロードスター世代で、RCOJ(Roadster Club of Japan)やMAZDA SPRIT RACINGなどのファンクラブにも、マツダらしさが表れていると思います。こうしたステークホルダーの存在についてはどう捉えていらっしゃいますか。
毛籠:発売34年のロードスターはこれまでに約120万台売れ、世界で一番たくさん作られたライトウェイトスポーツカーとしてギネスにも載っていますが、それだけヒットしたのは、お客さまに育てられたことが大きいと思っています。エンジンでパフォーマンスを出すタイプではなく、トータルパッケージで楽しいというスポーツカーですが、お客さまがいろんな使い方や楽しみ方を見つけて走る歓びを拡張してくれ、それに賛同する人がいろんな国で増えていったのだと。
全エンジニアのこだわり 人間が気持ちよく走るために車がどう動かないといけないか

展示ブースにはロータリーエンジンを搭載した「MX-30」の新型モデルも登場し、注目を集めた
|
青木:ロードスター以降、ライトウェイトスポーツカーの市場は一気に広がりました。その中でロードスターが支持され続けた、いちばんの理由はどこにあるとお考えですか。
毛籠:当社は、スポーツカー専用のプラットフォームを作っていますし、エンジニアは一人一人がこだわりを持って取り組んでいます。例えば、クロスメンバーを1ミリ削るのにも重量が何グラムか増えるからと言って悩みに悩んでいます。安全装置を追加しながらもおよそ1トンの車が作れているというのは全エンジニアのこだわりの結集と言えますし、お客さまはそういった姿勢も支持してくださっているのではないかと思います。RX-7でも「ゼロ作戦」などと名付けて徹底して軽量化しましたが、これは当社の系譜なんです。他社と同じやり方をなかなか良しとしない、そこは面倒くさい会社かも知れません。
だから、RX-7でも250馬力しか出ません。他社は280と規制いっぱい出している。で、走らすとどちらが速いか、というところではエンジニアが負けん気で技術を究める。そこで、車の運動性能に特化し、車の動き方が人の気持ちや動作にどうつながるかということをずっと解析・分析してきました。今の時代のセンシング技術です。当社のSKYACTIVエンジンが採用している協調制御のコンピューターは、計算スピードが速いので、エンジンをふかしながらブレーキをつなぐといったこともできてしまう。とにかく人間が気持ち良く走るためにはどう車が動かなきゃいけないかというところを開発の中心に置いており、それが他の車にも展開されているという流れです。
時代の要請に適合させていくのは社会的使命――積み上げてきた技術開発
青木:一方、電気自動車では欧米や中国のメーカーが先行し、トヨタは“全方位”での展開を進める戦略を打ち出す中で、御社はどのような時間軸で電気自動車にシフトしていくことを考え、今回のMX-30やICONIC SPの提案につなげられたのでしょうか。
毛籠:自動車メーカーとして時代の要請に応え、京都議定書以降は排ガスやCO2削減の規制に適合してきた歴史があり、これは社会的使命だと捉えています。最初に欧州でCO2規制があった時、我々は長期的な技術ビジョンが要ると考え、ライフサイクル全体で排出量を引き下げるためには何がいちばん有効かという観点から、まずは内燃機関の効率を上げることだ、となった。2005年頃のことです。
そして、のちにSKYACTIVエンジンと命名する、熱効率が世界最高のエンジンをつくるという技術課題に取り組みました。ガソリンエンジンとしてはフェラーリですら12.6しかない圧縮比を14にすることに成功し、それまでの常識を覆した。繰り返しになりますが、そういう技術開発を、ロータリーエンジンの開発をストップしてまでやったんです。
これは、ビルディングブロック構想というもので、我々、リソースがそんなに大きな会社ではないので、一つ一つ技術開発のテーマが積み重なっていくように、将来使える要素技術を段階的、長期的に開発していこうという思いでやってきたんですね。
つまりそこから、我々のカバーするプロダクトラインの範囲で技術を積み上げ、内燃機関、内燃機関と組み合わせた電動化技術と展開し、ソリューションとして提供できる形を整えてきた。水素やバイオといったカーボンニュートラル燃料でそういう技術をつくるロードマップも描きつつ、一つ一つやってきたので、“全方位”とはちょっと違うんですよ。

|
青木:なるほど。今まではガソリンで走ることを前提に車を開発してきたのが、インフラの整備や原料調達の実現可能性をにらみながら、多様な事業ポートフォリオを描いてこられたということで、そこのバランスが難しかったでしょうね。
毛籠:はい。しかし、本当の意味でのCO2削減を考えた時、電源の構成や、お客さまがそこにどれだけ参画してくださるかはいちばん大きな要件です。我々としてはお客さまのライフスタイルに合わせた技術、地域の社会インフラの進捗状況に合わせた技術を提供することで、1人でも多くの方に使ってみよう、乗ってみようと思っていただき、市場に走る車の台数を増やしたいと考えてきました。
我々が内燃機関がいい、カーボンニュートラルな液体燃料がいいと考える理由はやはりエネルギー密度が高いことです。それに対して電気の密度はものすごく低く、車で使おうとすると現状ではやたらと大きなバッテリーが要る。ただこのバッテリーも技術革新の最中ですし、車のルーフで太陽光発電ができたり、道路から給電するシステムなど、いろいろな技術をいろいろな会社が開発していますから、こういったものが社会に実装されるに従い、ソリューションも変わっていく可能性がある。ですから、今日から電気自動車です、明日から水素自動車です、ということにはならない。今は黎明(れいめい)期ですから、いろいろな技術が長い時間をかけ、絶えず進化していかねばならない。当社では、人を幸せにできる技術、社会に貢献する技術、それを広く普及させる技術の3つの技術開発をしっかりとやっていきたいと思っています。
青木:そうしたなか、2017年にはトヨタと資本提携を結ばれました。これは自動運転や電気自動車の普及を見通した連携ですか。
毛籠:トヨタさんとは、電動化時代に欠かせない車載システムの開発を行うプラットフォームを一緒にやらせていただくというところが大きいです。業界として社会に貢献することはできるだけ一緒にやった方がいい、という考えですね。
国内の自動車メーカーの共創の分かりやすい事例としては、スーパー耐久レースで、トヨタさんとスバルさん、そして当社が同じカーボンニュートラル燃料を使い、レース結果のデータを交換しています。レースなので、基本的にはシークレットで行うべきところなのですが、それぞれのエンジンの形式によって同じ燃料でも出てくるものが違う。その原因を3社で究明することで、絶対見逃さないものが出てくる。それがカーボンニュートラル燃料の社会実装を早く、自信を持って進めることにつながると思っています。
ブランドも人間も、持って生まれたものは変わらず、磨かれると成長する
青木:一方で、御社の車はWorld Car of the YearやWorld Car Design of the Yearなど数々受賞され、欧州で暮らしていますと特に、“MAZDAデザイン”が高く評価されているのを実感します。国内でドメスティックに始まった企業がグローバル競争に揉(も)まれることで得た、マツダらしさや鍛えられた部分をどう感じていますか。
毛籠:学んだことはたくさんあります。かつて、国内で3番目のブランドになりたいといった気持ちもあり、やたらと車の種類を作って個性を失いかけていた時に、フォードが入ってきたことで(1979年に資本提携、その後解消)、やっぱり我々は走って気持ちの良い、スポーティーな車を得意としていることに気づくことができた。その流れが、2000年代になって、マツダブランドのコンセプトとして、『子どもの時に感じた、動くことへの感動』を表す『Zoom-Zoom(ズームズーム)』という言葉の世界観を打ち出すことにもつながっていきました。
この言葉は感情的な表現ですが、中心となるエッセンスは、やはり『走る歓び』です。ブランドも人間と同じで、持って生まれたものはあまり変わらない。ただいろいろと世の中に出て、磨かれるとブランドも成長する。車の技術も、クォリティも、見た目も変わってくる。それがうまく成長すると、いわゆるプレミアム的なところに到達することができるということだと思います。
青木:面白いですね。人と同じように成長するブランドという発想はあまりなかったので、非常に新鮮に感じます。
昨年発表された「2030 VISION」では、2030年に向けて強いメッセージを掲げ、『前向きに今日を生きる人の輪を広げる』というパーパスを策定されたことを基調講演でもお話しされていました。最後にもう一度、このビジョンとパーパスに込めた思いをお聞かせください。

|
毛籠:自動車産業がモビリティ産業へと大きく変貌していく時に、マツダって一体何をしている会社なのかということを、従業員をはじめステークホルダーに時間軸として分かっていただく必要があるということでビジョンを出しました。2030年には「『走る歓び』で移動体験の感動を量産するクルマ好きの会社になる。」わけですが、パーパスにはどこにも自動車という言葉が出てきません。
パーパスは約1年ほどかけ、何度もワークショップを開いて決めたのですが、非常にエキサイティングでした。我々のような昭和世代は、自動車という言葉がなかったら何をする会社か分からないと思ってしまうのですが、30代より下の世代になると、明らかに意識が違う。パーパスの文言の中に、車という言葉がなくても、普通に、「いいね」って思えるんです。所属するコミュニティが、自分のアイデンティティに近いと、ここで頑張りたいと、思ってくれる。でも50代60代に共感を持ってもらうためにも、ビジョンには「クルマ」という言葉を入れました。
『前向きに今日を生きる人の輪を広げる』という文言は、戦後の広島で1日1日復興に向けて頑張って、1日1日、いい日になって、笑顔が広がり、地域の輪が広がって、今日の平和都市へと歩みを進めてきた、そういう広島の先人たちの100年の生きざまとも重なる。当社にとって、非常にフィットしていると思っています。
青木:御社の歩んできた道、歩むべき道と、広島の復興の歴史が重なったときに、サステナビリティ目線でとても素敵なストーリーだなと聞かせていただきました。ありがとうございました。
文・廣末智子、写真・星屋征希(PATRONEFILM)