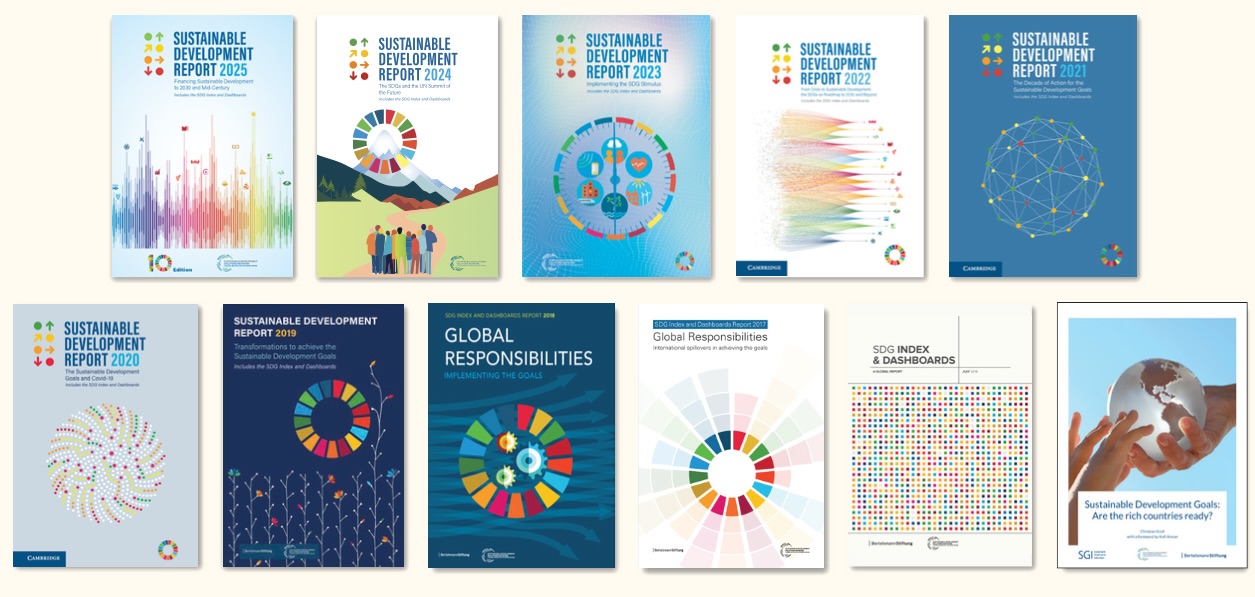「真の国際援助とは」と題したトークイベントが、6月27日に東京都内で開かれた。登壇したのは認定NPO法人「テラ・ルネッサンス」(京都市)のウガンダ駐在員で、初めての著作『荒野に果実が実るまで』(集英社)を発表した田畑勇樹氏だ。支援現場での実体験を振り返りながら、援助の在り方を問い直すセッションとなった。26歳の若き駐在員が見た、援助の現実と希望とは。田畑氏へのインタビュー内容も交えて再構成する。
1600人以上が飢餓で死亡
テラ・ルネッサンスはアジアやアフリカを中心に、元子ども兵や紛争被害者の自立支援を行っている。ウガンダでは、2005年から元子ども兵の社会復帰を支援。2023年からは北東部のカラモジャ地域で、灌漑(かんがい)農業を起点とした自立支援事業を展開している。

田畑氏が国際協力に関心を持ったのは高校時代。テレビ番組でアフリカに触れ、京都大学在学中にテラ・ルネッサンス主催のスタディツアーでウガンダを訪れた。さらにルワンダの大学に留学。その時、紛争被害を受けた友人たちが語った「自分の生まれ育った地域の平和のために働きたい」といった言葉に刺激を受け、「将来、アフリカで仕事がしたい」と決意した。2022年、大学卒業と同時にテラ・ルネッサンスに就職し、ウガンダに赴任。カラモジャ事務所長として、新規事業を立ち上げた。
カラモジャは半乾燥地帯に位置し、降雨量が少ないため農業生産が限られる。ウガンダ統計局のデータによると、貧困世帯比率は65.7%。ウガンダで最も貧困・飢餓が深刻な地域の一つだ。2022年には食料価格の高騰により、1年間で1600人以上が飢餓で死亡したという。背景には、気候変動による干ばつや治安の悪化、そして何より、ロシアのウクライナ侵攻によるインフレの影響があった。また、近くの南スーダンやケニアから銃が流入。若者が犯罪グループに加入し、家畜の窃盗や略奪・暴力など、貧困を起因とする負の連鎖に陥っている。
「援助依存」から脱する

深刻な飢えに苦しむ住民たちにとって、頼みの綱はNGOなどからの食料援助だった。田畑氏は緊急的な食料援助の必要性を理解しつつも、住民らの「援助依存」に疑問を感じていた。そんな時に出会ったのが、農業・自立への意思を持つ若者たちだった。「広大な土地はある。必要なのは水だ」――。そうして始まったのが、貯水池を起点とした、灌漑農業による自立支援プロジェクトだ。
「最初から、日当(現金)や食料は配らないと決めていた。農業を一緒に行う。それが唯一の支援」。田畑氏はそう振り返るが、何かにつけて日当を受け取るのを当然視する現地の政治家や行政からは、反発を招いた。「日当を払え」「日当がなければうまくいかない」といった声もあったという。それでも田畑氏は信念を貫いた。「日当があるからうまくいかないのではないか」との考えがあったからだ。

現地のスタッフは約15人で、日本人は田畑氏だけだ。プロジェクト開始に先立つ住民説明会では、「なぜ食料をくれないのか」「私たちを見捨てるのか」といった声も上がったが、プロジェクトの意義を繰り返し説明し、理解を求めた。その結果、150世帯、推定1000人以上の住民が参加。気まぐれな天候や政治家の妨害などに直面しながらも、サッカーコート一つ分ほどの大きさの貯水池を完成させた。
住民たちの力で荒野は農地に変わり、貯水池から水が送られた。プロジェクト開始から半年余り、ついに収穫の時を迎える。トウモロコシや豆、さらにその後、トマトやタマネギなど野菜の栽培にも成功。女性たちのはじけるような笑顔が広がり、喜びの歌声が響いた。

収穫物を販売し、初めて利益を分配すると、住民の言葉に変化が見られたという。「なぜ食料をくれないのか」と言っていた人が、「私たちのトマトを買ってくれ」と言うようになったのだ。プロジェクト開始前に「私には何もできない」と言っていた女性が、農業で収入が生まれたことで「これからは私が家族を支える」と笑顔で語った。その姿に田畑氏は「援助活動を続けてきて良かった、と思う瞬間。グッと来るものがあった」と述懐した。
住民の「地力」を育む支援
一方で課題もあるという。支援対象者のほとんどは初等教育を受けていない。識字率が低く、収支管理が難しい。田畑氏らは農場で週1回、読み書き・計算の授業を実施。また、日銭を稼ぐために日雇い労働を選ぶ人も多いが、田畑氏らは個別訪問や面談を通して、一人ひとりに寄り添った支援を続けている。
田畑氏は「『援助屋』に平和はつくれるのか」と、援助の本質を自らに問いかけてきた。その答えは「できる」だ。23歳でウガンダに赴任して、現地での活動も4年目に入った。構造的な格差や武器の流入、政治――。それらに直接手は届かなくても、住民が自立し、暴力や飢餓に陥らずに生きていける環境を支えることはできる。「平和が始まる場所」を、農業という営みの中に見ているのだ。

トークセッションの最後、田畑氏はこう語った。「私たちが去った後に、住民たちが自分の力で暮らしを立てられること。それが目指すべきゴールです。自らの手で命と暮らしを守ることができるように、『地力』を育む活動を続けたい」。7月中旬には、カラモジャに戻る予定だ。
8月20日から3日間の日程で、第9回アフリカ開発会議(TICAD9)が横浜で開かれる。日本での開催は6年ぶりで、アフリカの現状に注目が集まりそうだ。もっとも、政府レベルの議論だけでなく、田畑氏らのような民間の地道な取り組みにも、改めて脚光が当たってほしい。「希望の種」は、きょうも支援の現場でまかれている。
眞崎 裕史 (まっさき・ひろし)
サステナブル・ブランド ジャパン編集局 デスク・記者
地方紙記者として12年間、地域の話題などを取材。フリーランスのライター・編集者を経て、2025年春からサステナブル・ブランド ジャパン編集局に所属。「誰もが生きやすい社会へ」のテーマを胸に、幅広く取材活動を行う。