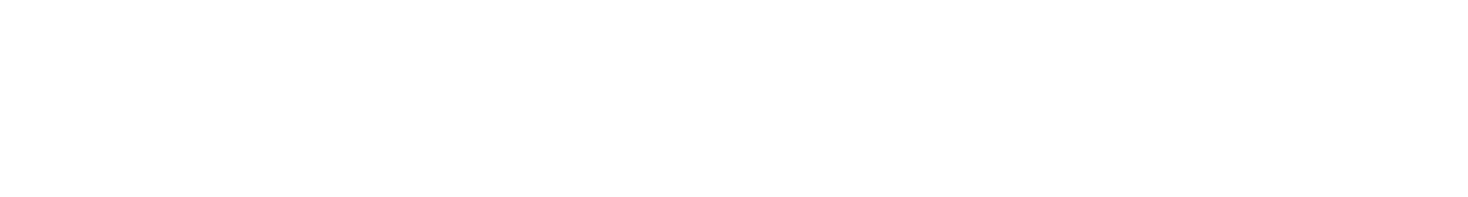|
「サステナブル・ブランド国際会議2024東京・丸の内」(2月21、22日、以下、SB2024東京・丸の内)がいよいよ来週に迫った。今年のテーマ「Regenerating Local(リジェネレイティング・ローカル)―ここから始める。未来をつくる。」の下に、50以上のセッションが展開される。前回は番外編としてSB本国のアメリカで会議の様子を報告したが、今回はヨーロッパでも広がっているRegenerate(再生する)について、その経緯を検証し、かつSB2024東京・丸の内でこれに触れそうなセッションを紹介しておきたい。
1.リジェネレイトって何?

工業化による広大な石灰採掘場跡地の自然回復を学ぶバイクツアー(写真はいずれもデンマーク、筆者撮影)
|
Regenerate(リジェネレイト)は辞書的には「Re(再び)+generate(生み出す)」で「再生」となるが、地球の生態系や資源を修復し、持続可能な状態に戻すことを言う。これが現在、ビジネス用語として入ってきたわけだが、そもそもサステナビリティとは何が違うのか?これまでにどんな議論がされてきたのかを整理したい。
そもそもこの言葉は、生態系の持続可能性を核としながら、環境科学や都市計画の中で古くから使われ、その考えが農業分野、さらにはビジネス分野へと移ってきた経緯がある。都市計画やコミュニティ開発などのコンサルティング会社、REGENESISの共同創業者のパメラ・マンとビル・リードの共著、Regenerative Development and Designによれば、“近代都市計画の祖”とされるエベネザー・ハワードが1880年代に著した『明日:社会改革への平和な道』が、1902年に『明日の庭園都市』として再版され、その中で、人類の定住と生態学的思考を結びつけた。それが、20世紀初頭の英国の田園都市構想につながったという。ちょうど工業発展に伴い、大気や水質、土壌の汚染が問題となり、環境破壊に対処する技術的なアプローチが重要視され始めた時期だ。
その後、1935年にアーサー・タンスリーは、生物と非生物の生息地における相互作用に注目し、生態系の回復と保全が新たなテーマとなった。さらに、20世紀中盤から後半にかけて、環境科学の視点はより広範囲に拡大し、生態系の研究や持続可能な資源管理の重要性が認識され、再生の概念がより重要になった。
現代の環境科学では、再生の概念は単なる環境の修復だけでなく、生態系の機能を回復し、持続可能な未来を築くための包括的なアプローチを意味し、生物多様性の保護、土壌と水の保全、再生可能エネルギーの利用などが含まれている。

|

|
私が住むデンマークのオールボーも20世紀に工業が発展する中で、都市部の周辺では、かつては石灰などの採掘が広大に行われていた。現在、その場所は広い草原、湿原、湖に再生している。供給公社、市、大学、民間企業の共同研究により、雨水、地下水、排水の適切なバランスを知るため、相互作用が調査され、市民にもデータ提供による参画が求められている。
また、生物多様性が戻った再生地を回る自転車ツアーや学校の林間学校も行われ、SDGs以前から自然学習が行われている。自転車専用道は街中を含めて市内で500キロメートルにも及ぶ。市民は再生地を散歩し、クリスマスに家族で湖を散歩する光景もよく見られる(「寒い冬になぜ湖に行くのか?」は未だに分からないが…)。
一方、港には風力発電のブレードが所狭しと積み上げられ、沖合や陸上では風力発電が建設されている。まさに包括的、すなわちリジェネラティブに街が面として変わっているのを感じる。
こうした動きはドイツやオーストリアも同様で、再エネの普及や環境保護への取り組みが進み、特に、気候変動への対策や生態系の保護、持続可能な農業の推進などに力を入れている。スウェーデンは、廃棄物のリサイクル率の高さや交通システムの改善により、持続可能な都市開発にも積極的である。
2.サステナビリティのための生態学的戦略
前述のパメラ・マンとビル・リードは、こうした取り組みを図表1のように表した。横軸が「人間の意識の統合度」として、左に寄るほど従来型の人間中心主義であり、「退化」だとし、右に寄るほどあらゆる生命の中心主義であり、「再生」と考える。彼らによれば(狭い意味での)サステナビリティは真ん中であり、資源の持続可能性に主に焦点が当たるのに対し、再生(リジェネラティブ)は環境や生態系の修復によって生態系や脱炭素にポジティブに働きかけていくことを言う。サステナビリティでは何も生産しない、消費しないことがいちばんとも考えられるが、再生では生産や消費をしながらも、生態系にはプラスへと向かうべきと考えるのだ。
図表1) サステナビリティのための生態学的戦略レベル

出典)Pamela Mang, Bill Reed(2012) “Regenerative Development and Design” Encyclopedia Sustainability Science & Technology
|
一方、縦軸は「パターン調和の規模」とされ、下は一つの有機体レベルから上は地球までの規模の違いがある。有機体の資源効率を上げていくのは(広い意味での)サステナビリティの初期段階であり、リジェネラティブになれば自ずとより広いエリアにおけるその他の要素との相互作用を考えることとなる。要は、ビル一つ、コミュニティ一つ、河川の流域を一つとっても、環境との相互作用をどう考えるか、が重要となる。
SB2024東京・丸の内 Day1のセッション、「Well-Being産業の創出に向けて、ワークライフバランスの生活動線をどう設計するのか」では、デンマークの企業で環境設備エンジニアとしてエネルギーデザインに携わり、“空気のエンジニア”と称される蒔田智則氏がファシリテーターとして登壇するので、こうした話も聞けるであろう。
3.リジェネラティブ・アグリカルチャー(農業の再生)とは?
農業分野では、持続可能な農業の実践や地域の食料生産システムの再生が重視されている。一方、農薬での土壌汚染やリンや窒素を肥料として使用することでの河川の富栄養化をもたらし、藻の異常繁殖にもつながっていると言われる。
そこで、有機栽培や自然農法などの方法論が再生の概念に基づいており、土壌の健康を回復し、生態系のバランスを取り戻すことを目指している。アルド・レオポルドは環境保護の先駆者であり、自然主義者として知られ、1949年の『A Sand County, Almanac』で「土地倫理(Land Ethic)」を訴え、持続可能な農業や土地管理の重要性を強調し、土地の再生と保全に焦点を当てた。
1980年代には日本でも、福岡正信が、世界的に知られる著書『「自然農法」わら一本の革命』(The One-Straw Revolution)などを通して自然農法を提唱し、土地の再生と生物多様性の保護を目指した。
ちなみに私がパリで受けたnature urbaineの農業ワークショップは、福岡が提唱した粘土団子をつくるものだった。この粘土団子は多種の種子を団子化し、水も肥料もやらずに地面に置くだけで、その土地に適した種子のみが成長するというもの。低コストで緑化ができ、植物の多様性がつくれるとして、インドやフィリピン、タンザニア、ギリシャなど各地で展開されている。
図表2) 農業の多様性とリジェネラティブ・アグリカルチャーの位置付け

|
筆者作成
図表2には農業の多様性と、その中でのリジェネラティブ・アグリカルチャーの位置付けを示した。横軸の左が化学肥料や農薬の使用を、右が土壌や微生物の力を利用する農法であり、左の縦軸は上にいくほど大量生産・流通を、下にいくほど少量生産・流通を表している。
とすると、日本での農法には4つの展開があるだろう。
一つは左の青の慣行農法であり、日本のほとんどの農家がこれに該当する。比較的大きな規模で生産を行うため、トラクター等で耕起し、化学肥料で単一品種を生産する農家である。これに対し、茶色で示した、不耕起、無肥料、無農薬、多品種という全く反対の自然農法がある。土壌やその中の微生物の力を最大限利用することで可能となり、前述の福岡正信などはこれを提唱していたし、最近でも一品種ではあるが、『奇跡のりんご』の木村秋則氏などはこの部類と考えられる。ただし、生産量の予測や確保が難しく、家庭菜園の域を出ないものも多い。緑に示したのはJAS有機などでも知られる、耕起、堆肥、無農薬、単一品種が基本の有機栽培や自然栽培と言われるものである。2017年の有機農地面積がスペインでは16.6%、イタリア15.2%、フランス13.9%に対して、日本では2021年で0.6%でしかない。高温多湿の日本の気候では欧州のようには簡単にはいかないことや作付け作物によって全く栽培方法が異なるためだ。例えば、ユズによる活性化で有名な高知県馬路村の有機農業の面積は81%にもなっている(関連記事)。
また、現在、トマトなどで日本でも展開され、園芸用施設の中でも伸びているのが、黄色で示したハウスによる養液栽培(ハイドロポニックス)である。完全にハウス内の温度管理をしながら、固形培地耕や水耕によって培養液を与えている。設備投資は莫大であるが、虫の発生も抑えるため農薬も不要であること、一年中の生産計画が立てられる、大量に仕入れる小売店の要求にまとめて出荷できるといったメリットがある。
一般に、持続可能な開発と設計には、技術的持続可能性と生態学的持続可能性の二つの流れがある。前者が技術とエンジニアリングに基づくのに対し、後者は生態学と生命システムの原則に基づく。そうすると、養液農法は前者寄り、自然農法は後者寄りとも言えよう。
つまり右の縦軸を見れば、上にいくほど外部環境に依存しないで育てる農法であり、下にいくほど自然や社会も含めた生態系と相互依存し合いながら育てる農法だ。私が図表2を作成した目的は、有機栽培 or 慣行農法という単純比較ではなく、収穫量とのバランスが重要であり、それぞれの事業目的や作物の種類、環境条件によって多様であることを伝えたいからだ。
SB2024東京・丸の内 Day2のセッション、「脱サラ、移住、そして農家へ、ビジネスパーソンが見たRegenerating Local」では慣行農法や有機農法を現場で実践する方々が登壇する。現在の課題や今後の見通しを語ってもらうなかで、日本の農業の行方をうかがい知ることができるだろう。
4.ビジネスをリジェネラティブに考えてみた
最後に社会経済のビジネス分野における、リジェネラティブとはどういうことかを考えてみた。それは、人々の社会的包摂や経済的活力の回復を意味するだろう。地域社会や経済の再生プロセスでは、具体的には雇用の創出や地域資源の活用、文化的資産の保護などが重要な要素となる。
図表3) 企業の多様性とRegenerative Businessの位置付け

|
筆者作成
企業について考える場合、先の農業のフレームワークを参考にしながら、横軸を左が金融資本(カネ)中心、右が社会関係資本(ヒト)中心として表してみた。左側の縦軸の上が大量生産・流通、下が少量生産・流通だ。産業革命以前は主として、茶色で示した中小企業がほとんどであったとすると、未上場、家族経営、ローカルに根ざしており、地域での少量生産・流通、大きくても国内市場が基本であった。特に日本においては稠密な人間関係や信頼がベースであり、社会関係資本(Social Capital)が重要であった。
一方、産業革命以降は蒸気機関による大量生産が可能となり、株によって大きな資本を集め、規模の経済性を発揮し、グローバルに市場展開する、青色の大企業が登場することとなる。
さらに1990年代からのIT革命によって起きたのが、GAFA(Google, Apple, Facebook, Amazon)やMicrosoftなどで知られる赤色のBig Techだ。それらの企業は、上場や買収によって規模を一挙に拡大し、利用者が相互に使用することで利便性が向上するネットワーク経済性を発揮。プラットフォーム化・グローバル寡占化していった。
2000年以降出てきたのは、さまざまなエンジェル投資を受けて上場し、インターネットにより市場を広げたり、投資を呼び込んでいる黄色のグローバルなニッチ市場(Hidden Champions)の企業だ。2002年の創業当時から動物実験や児童労働の禁止というサステナビリティ基準を公表していたタイのコスメやアロマのTHANN、2004年の倒産危機からデジタルとリアルの融合で復活したデンマークのLEGO、2005年創業の日本のサステナビリティ・ファースト、ミドリムシで知られるユーグレナなど、どれも個性を放ちながら急成長を遂げている。
そして今、面白いのは地方を拠点として新しい投資によってリノベーションを図ったり、地域資源や人を掘り起こして、新たな地域価値を創っている、緑色のGood Localな企業だ。光ファイバーでIT人材が集まった徳島県の神山町では民間出資の神山まるごと高専が始まったし、良品計画は千葉県鴨川市で古民家をリノベーションし、土着化しながら「感じの良いくらし」を作ろうとしている。ニッポニアは観光地としては知名度の低い地域でリノベーションを通した体験価値をつくりだしている。
SB2024東京・丸の内 Day1のセッション、「ソーシャル・キャピタルを活かすRegenerating Local」では、まさにそうした、Good Localな取り組みを聞くことができるだろう。
これまでの企業の経営戦略の中で当たり前のように、外部環境と保有する経営資源を切り分けて思考してきた。リジェネレイトとは、これ自体を否定する考え方でもある。むしろ外部環境を経営資源としてうまく引き込み、他の企業や組織とコラボレーションすることであり、その時の戦略主体は一つの有機体(企業)ではなく、生態系の中にある存在同士がつながった“有機化合物的な組織”となるのだと私は思う。その組織に最も重要なのは、多くの主体を惹(ひ)きつけるPurpose、つまりこの生態系の中で「なぜつながるのか?: Why」「どうあるべきか?: How」「何をするのか?: What」の存在意義なのであろう。