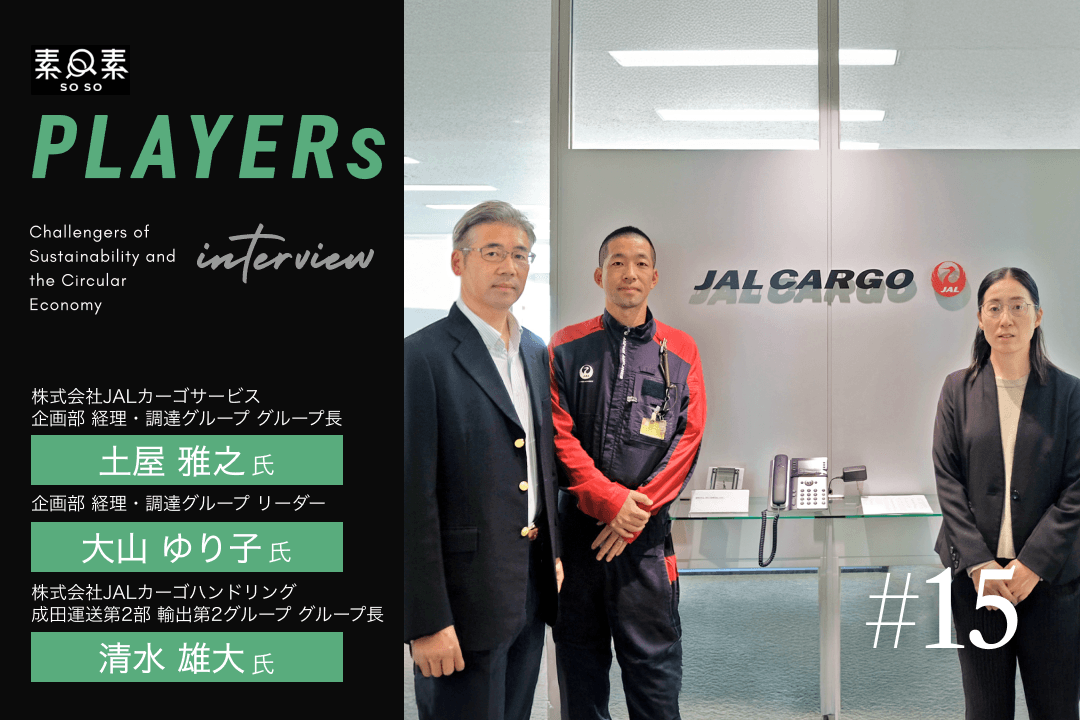「サステナブル・ブランド国際会議2025 東海シンポジウム(SB’25東海シンポジウム)」が2025年11月20日、名古屋市のSTATION Aiで開催された。東海地域でのサステナブル・ブランド国際会議の開催は2019年以来で、約130人が参加。東海地方ならではの、ものづくり・技術革新・地域の実装力といった強みを背景として、テーマは「Breakthrough in REGENERATION―信頼を築くESG情報開示とブランドコミュニケーションの最前線ー」に設定。ステークホルダーとの信頼を基盤とした価値の共創やイノベーションの創出、サステナビリティの在り方などを探求した。
「サステナビリティは“良いビジネスそのもの”」
冒頭、主催者を代表し、サステナブル・ブランド ジャパンの鈴木紳介カントリーディレクターが「この場が共創のスタートになることを目指しています。ぜひネットワーキングを促進して、次のサステナブルな取り組みのヒントを得ていただければ」とあいさつ。6年ぶりの開催へ期待を込めた。

最初の基調講演には、サステナブル・ブランド ジャパン総責任者兼ESGプロデューサー、Sinc代表取締役社長兼CEOの田中信康氏が「SBグローバルから見る価値共創の新潮流」と題して登壇。2025年10月に米国サンディエゴで開催されたSB国際会議のレポートを交え、サステナビリティを取り巻くグローバルな潮流を解説した。
田中氏は、米国で「ESGの観点からブランドを選ぶ」と答えた人が10年前の6%から32%に増加したという調査結果を紹介しつつ、「気候変動や脱炭素といった政治的に捉えられがちな言葉よりも、『健康』『自然』『信頼』といった普遍的なキーワードが共感を集めた」と指摘。その上で、サステナビリティは「Doing good(良いことをする)ではなくGood business(良いビジネスそのもの)」である、という認識がグローバルに広がりつつあると語った。
スタートアップが担う社会インフラの構築
次の基調講演には、Global Mobility Serviceの代表取締役社長CEOである中島徳至氏が登壇。3度の起業経験、その中での法的整理という困難を乗り越えてきた自身の歩みを振り返りながら、モビリティとフィンテックを掛け合わせる独自のビジネスモデルを紹介した。同社は、ローン審査に通らない人々が自動車を利用できるよう、フィリピンやインドネシアなどで、遠隔起動制御デバイスを活用した金融包摂型のフィンテックサービスを提供している。

モデレーターの田中氏から、前例のないビジネスモデルをゼロから構築する上での困難について問われると、中島氏は「無から有を生み出すのは大変。本当は行政やもっと力のある人たちに動いてもらいたいが、スタートアップがやらなければならない」と、社会インフラに近い仕組みをベンチャー企業が担うことの厳しさと覚悟を語った。社会課題の解決と経済合理性の両立という難題に挑み続ける姿勢が、会場の共感を呼んだ。
中島氏は、この事業が「自動車メーカー/販売店」「金融機関・投資家」「契約者」「国・地域」そして自社の「五方良し」を実現するモデルであると説明。「社会課題に向き合い、解決する中に経済合理性を創出する。それでこそ、真にサステナブルな仕組みとなり、社会に貢献できる」と強調した。最後に、来場者に向けて「諦めたら失敗なんでしょうけど、諦めなければ全部過程。成長の過程です」と熱いメッセージを送った。
エッセンシャルカンパニーへの進化とガバナンス改革
続いて「サステナビリティ経営がもたらす企業価値向上〜武蔵精密工業から見るバリュークリエーションとイノベーション〜」と題した基調講演とパネルディスカッションが行われた。登壇したのは、武蔵精密工業CIO(最高イノベーション責任者)の伊作猛氏と、同社社外取締役でエミネントグループ代表取締役社長CEOの小野塚惠美氏だ。

伊作氏は、同社の「テクノロジーへの情熱とイノベーションを生み出す知恵を合わせて、人と環境が調和した豊かな地球社会の実現に貢献する」というパーパスやビジョンを紹介し、「自動車部品メーカーの枠を超えて、テクノロジーで社会を支えるエッセンシャルカンパニーを目指している」と強調。特にアフリカでのe-Mobility事業に注力しており、単に電動バイクを供給するだけでなく、現地のスタートアップと協業し、交通インフラの整備、就業機会の創出、さらには再生可能エネルギーの普及といった社会課題の解決に取り組んでいると語った。
一方、小野塚氏は社外取締役の視点から、同社のガバナンス改革について解説。投資家との対話をきっかけに取締役会議長を社外取締役に変更した経緯や、新たに「ガバナンス委員会」を設置した狙いを説明した。また、企業価値向上における「エクイティストーリー」の重要性を説き、「エクイティストーリーを一言で言うと、『その企業の話を聞いてワクワクしますか?』という問いに答えられるかどうか」と述べ、投資家や従業員が未来に期待できる物語を構築することの必要性を訴えた。
ESG情報開示の実践と挑戦
シンポジウム後半は、2つのトラックに分かれてパネルディスカッションが展開された。ESG情報開示トラックの最初のセッションでは、「対応から価値へ:ESG情報開示の実践と挑戦」をテーマに議論が交わされた。

QUICK ESG研究所フェロー・ESGコンサルタントの山本高嗣氏は、情報開示の本質を「経営者とステークホルダーの情報格差を埋めるための手段」と定義。開示自体がゴールではなく、開示物を通じてステークホルダーと対話し、得られたフィードバックを経営に生かす「サステナビリティ・マネジメント・サイクル」を回すことの重要性を強調した。
イノアックコーポレーション執行役員広報部長の神谷秀幸氏は、非上場企業でありながらCSRレポートの発行を続ける理由について、「社員や求職者、取引先に対して、いかにエンゲージメントを持っていただくか」と説明。特に採用活動において、内定者の70%以上がCSRレポートを読んでおり、企業の姿勢を伝える重要なツールになっていると述べた。
ジェイテクト経営企画部サステナビリティ推進グループ長の西澤尚希氏は、上場企業としてグループ全体の非財務情報を収集・開示する上での課題に言及。「グループ会社からすると新しい仕事が生まれる形になるので、コストがかかってくるところをどう解決するかは経営課題」と述べ、データの正確性担保やレポートラインの整備の難しさを語った。
生物多様性の現場からの示唆
続いて、「生物多様性―企業は何が求められているのか、何ができるのか?」と題したセッションでは、情報開示の先にある「実践」に焦点が当てられた。ファシリテーターを務めたサステナブル・ブランド国際会議サステナビリティ・プロデューサーの足立直樹氏は、WWFジャパンのレポートを紹介しながら、多くの企業のTNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)レポートが「表面的な分析で、サプライチェーンの現場までカバーできていない」という課題を提示した。

この課題に対し、バイオーム代表取締役CEOの藤木庄五郎氏は、市民科学やAIを活用して生物の分布データを収集・可視化する独自のプラットフォームを紹介。生物多様性の状態をデータに基づいて把握し、企業の拠点ごとのリスク評価や保全活動の効果測定に活用できる技術がすでに存在することを示した。
速水林業代表の速水亨氏は、2000年に日本で初めてFSC(森林管理協議会)認証を取得し、環境管理型林業を実践してきた経験を共有。「放置していては豊かな森は再生しない」とし、適切な間伐によって林内に光を届け、下層植生を豊かにすることが生物多様性の向上につながると解説した。そして、「人の時間と木の時間をつなぐのが林業」と強調し、長期的な視点での森林経営の重要性を訴えた。
共感を生むカルチャーシフト

一方、マーケティング・コミュニケーショントラックでは、まず「情報開示は、企業のブランドムービーという新常識―共感を生むカルチャーシフトとは」と題したセッションが行われた。三井住友フィナンシャルグループ社会的価値創造企画部部長代理の片岡玲子氏と同部の呉怜實氏が登壇し、同グループのユニークな取り組みを紹介した。
同グループでは、経営の柱の一つである「社会的価値創造」を、社員発のアイデアで「シャカカチ」という愛称で推進。このインナー向けの活動を、統合報告書や特設ウェブサイト、さらにはブランドムービーを通じて社外にも積極的に発信している。片岡氏は、この取り組みが社員のモチベーション向上につながっていると語り、「社長賞を受賞した人は、表彰式の時に泣いて喜んでいた」というエピソードを披露。インナーブランディングが企業文化を醸成し、それがアウターブランディングにもつながるという、新しい情報開示の形を示した。
ビヨンドSDGsにおけるクリエイティブの役割とは

同トラックの最後を飾ったのは、グレートワークスによるセッション「ビヨンドSDGsにおけるクリエイティブの役割〜『伝える力』が未来をひらく〜」。代表取締役CEOの山下紘雅氏は、「伝える力が世界を動かすきっかけになる。企業価値を編集力で1本のストーリーに磨き上げよう」と語りかけ、ロジックとクリエイティブを往復する「戦略的着想」を用いて、クライアントの企業価値を可視化してきた事例を紹介した。
同社顧問で千葉商科大学客員教授の笹谷秀光氏は、SDGsの達成期限である2030年以降の枠組み「ビヨンドSDGs」の議論がすでに始まっていることに言及。これからの時代は「ウェルビーイング実現」が経営の中心的なテーマになると予測し、「日本の伝統的な価値観である“三方よし”を発信型に進化させ、SDGsをツールとして活用することが重要」と説いた。
新たな価値創造への挑戦――スタートアップピッチ
セッション終了後にはネットワーキングレセプションが行われ、会場となったSTATION Aiに入居するスタートアップ4社によるピッチが行われた。


KAMAMESHIは、製造業の設備保全部品を企業間で融通するプラットフォームを紹介。ZAIは、建設現場などで発生する余剰資材の再利用化を促進するアプリ「はざいっぽ」を提案した。はんぽさきは、圏外でも使え、70種類以上の専門地図を搭載した共有地図アプリ「LivMap」の活用事例を発表。エンサポートは、組織全体の営業力を底上げする教育DX「すぐすた」についてプレゼンテーションを行った。


東海地方では6年ぶりの開催で、熱のこもったセッションが展開されたSB’25東海シンポジウム。サステナビリティが事業の根幹を成すイノベーションの源泉であり、企業価値創造のドライバーであることを改めて示す場となった。
| <統合レポート・ライブラリー> 三井住友フィナンシャルグループ https://www.sustainablebrands.jp/report-library/1306030 イノアックコーポレーション https://www.sustainablebrands.jp/report-library/1306312/ ジェイテクト https://www.sustainablebrands.jp/report-library/1306326/ |
眞崎 裕史 (まっさき・ひろし)
サステナブル・ブランド ジャパン編集局 デスク・記者
地方紙記者として12年間、地域の話題などを取材。フリーランスのライター・編集者を経て、2025年春からサステナブル・ブランド ジャパン編集局に所属。「誰もが生きやすい社会へ」のテーマを胸に、幅広く取材活動を行う。