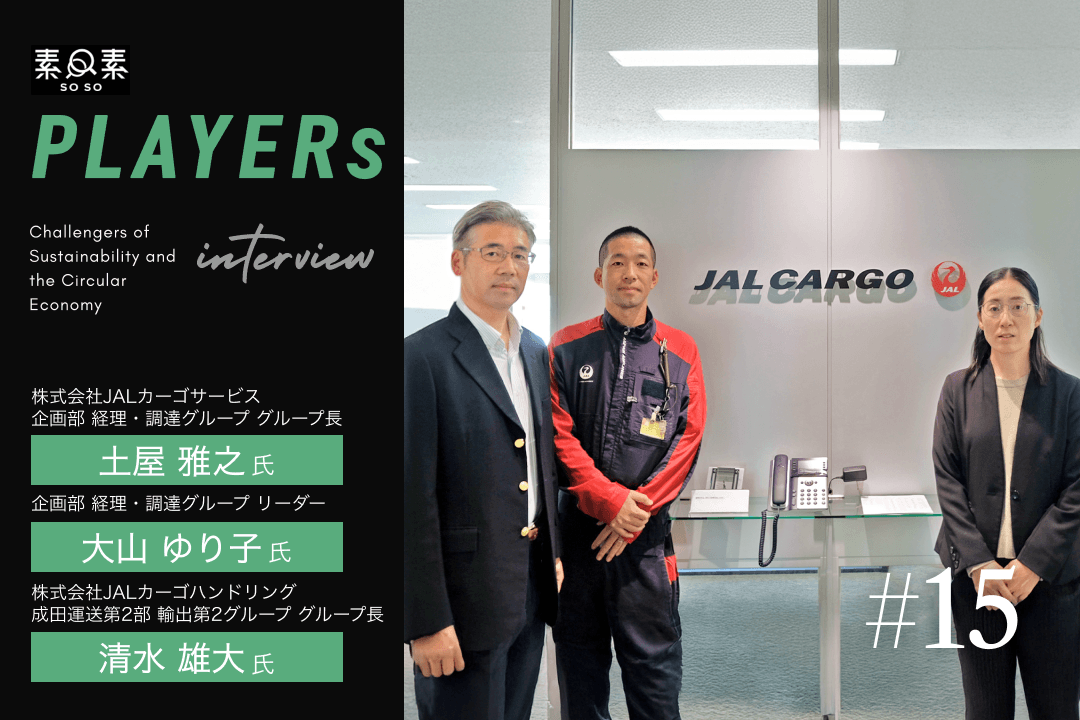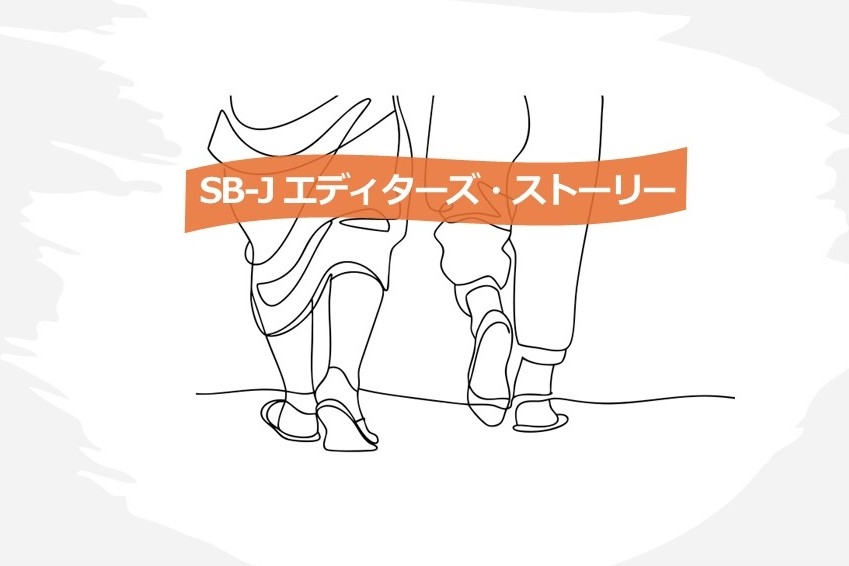
取材現場で心を動かされた言葉、記事にはならなかった小さな発見、そして、日常の中でふと感じたサステナビリティのヒント。本コラムでは、編集局メンバーの目を通したそんな「ストーリー」を、少し肩の力を抜いて、ゆるやかにつづっていきます。
今回の担当は廣末です。
異常気象に喘いでいるのは人間だけじゃない
9月を目前にして、全国で猛暑日が続いています。気象庁によると、今年7月の全国の平均気温は、1898年に統計を開始してから最も暑く、平年と比べて2.89度も高かったそうです。
この異常気象に喘(あえ)いでいるのは、私たち人間だけではありません。毎年のように酷暑や豪雨に見舞われ、すべての生き物が、生き残りをかけた試練に直面しています。植物であれば、多くの種が気候変動による何らかの影響を受け、少しでも生育しやすい場所を求めて分布を変えている、といったことも起きているのかもしれません。
市街地でも山間部でも、昔は見なかった花に遭遇
そうした植物の“生きざま”を、足元の草花から感じることがあります。私は人口約31万人の高知市に居住しながら、基本的にフルリモートでSB-Jの取材執筆や編集に携わっているのですが、近年、街中や山道で、明らかに昔は見られなかった草花に遭遇することが多いのです(広大な太平洋を両腕で包むようなロケーションにあるわが郷土、高知県の良いところは、何より、海にも山にも川にも、行こうと思えばすぐに行ける圧倒的な自然の近さにあると思っています)。
例えば、そもそも花の少ない夏場、これほどの猛暑の中で、アスファルトやコンクリートの隙間、道路脇の溝からしなやかな茎を伸ばし、薄紫色の花が風に揺れながらかたまりになって咲いている姿をよく見かけます。

この花はどうやら、「我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト」※1にも入っている、「ヤナギバルイバソウ」のようで、種子が勢いよく弾け飛ぶ性質から、全国で急速に広がっているようです。
また8月の最中に、涼を求めて山道をドライブした時には、棚田の石垣や、草の茂った斜面のあちこちに、背の高い、真っ白なユリが咲き誇っていました。最初はとても美しく感じたのですが、ほとんど数メートルごとに咲いているのを見るうちに、少し、異様に感じてきました。


| 高知県の山間部で、一つの茎から大輪の花を幾つも咲かせるタカサゴユリとみられる植物。花びら外側の赤茶色の縞が特徴とされる(2025年8月、香美市) |
これはおそらく、台湾原産の「タカサゴユリ」ではないかと思われ、やはり、「シンテッポウユリ(タカサゴユリ)」の名前で、前述の外来種リストや、国立環境研究所による「侵入生物データベース」※2に掲載されていることが分かりました。
身近な自然が外来種に置き換わる
外来種の植物と言えば、かつて花粉症の原因ではないかと言われたセイタカアワダチソウや、河川敷などで大群落が見られるオオキンケイギクなどが有名ですが、あらためてリストに載る花の画像を見てみると、ああ、あれも、これも!と思うものがたくさんあります。

例えば、トキワツユクサやヒメツルソバ、初夏に薄紫の小花をつけるマツバウンランなどがそうです。私は野に咲く草花が大好きなので、気が付きやすいのかもしれませんが、近所の空き地をはじめ、海沿いや、森の中に群生している姿がすぐに思い浮かぶ草花ばかり。身近な自然がいかに外来種に置き換わっているかを痛感させられます。
さらに思い返せば、今、ヤナギバルイバソウがかたまりになって咲く場所には、かつて、葉が赤いカタバミが一面に広がっていました。カタバミは貝原益軒の編さんによる「大和本草」(1709年)にも「葉ノ色青ト紫ト二種アリ」と記されているほど、古くから多様な種類が存在していたようですが、ここでは、ヤナギバルイバソウに居場所を奪われてしまったようです。
世界は進化に満ちている
こうした気付きの背景に、最近読んだ一冊があります。千葉大学大学院園芸学研究院准教授の深野祐也氏が今年6月に岩波書店から出版した『世界は進化に満ちている(岩波科学ライブラリー334)』がそれです。
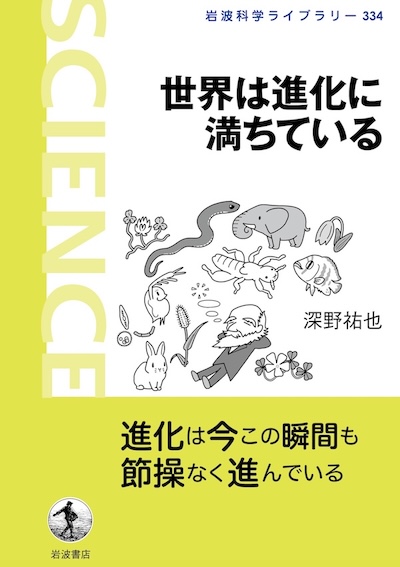
気鋭の進化学者である深野氏は、本の中で、「生物現象」としての進化が、いかに私たちの身近なところで短時間に起こっているかを、ダーウィンの『種の起源』の理論に基づきつつ、自身の研究エピソードを交えて語ります。
例えば、外来種のブタクサが日本で天敵がいない間にどんな進化を遂げたのかを調べるために、原産地の北米を横断して現地のブタクサと天敵の虫とを一緒に採集したり、散歩中に気付いた、都市には赤葉のカタバミが多い理由が「ヒートアイランド現象による自然選択の結果ではないか」と仮説を立てて検証したり――。読みながらワクワクし、早速、自分も足元の自然を観察したくなりました。
激化する気候変動によって植物の分布が変わることがあっても不思議ではなく、(そのせいかどうかは分かりませんが)赤葉のカタバミが、ヤナギバルイバソウと入れ替わった場所があることに思い至ったのも、本書の影響です。
“市民科学”に参加してみよう!
さらに、この本を通じてあらためて知ったのは、研究者でもなんでもない一市民であっても、生物の進化の研究に参加できる仕組みが身近にあることです。カタバミの葉色の研究では、自分の住む街では何色かを、スマホで撮った画像や、実物を採集して提供するプロジェクト※3が企画され、8月末現在、全国75地点から集まった1700点以上のカタバミの葉をもとに、研究チームが分析を行っているそうです。
AIが迅速にビッグデータの解析を行う時代、こうした研究のプロセスに市民が関わる “市民科学”(シチズンサイエンスやオープンサイエンスといった言葉で表されます)は、生物多様性のモニタリングや気象観測、海洋汚染調査といった分野で世界的に広がりを見せています。自分が関心を持って観察したデータが研究に活用されるかと思うと、面白さと可能性を感じ、私も参加してみたくなりました。
生物多様性保全の世界目標である「昆明・モントリオール生物多様性枠組」の中では、2030年までに陸域と水域のそれぞれ30%を健全な生態系として保全する「30by30(サーティ・バイ・サーティ)」と共に、「侵略的外来種の導入率及び定着率を50%以上削減する」という数値目標も掲げられています。
そうした大きな目標の達成に向け、日本では「ネイチャーポジティブ経済への移行」が叫ばれていますが、一人ひとりがまずは足元の変化に気づき、危機感を感じながらも、楽しみながら行動を起こすことで、世界は変わっていくのではないでしょうか?
仕事に追われる日々の中でも、「野の花が美しい」と思える気持ちを大切に、これからものんびり、空も海も山も川も近い高知で自然と付き合っていきたいと思います。
【用語注釈・参照サイト】
※1 我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト〈植物〉
https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list/fuka_plant.pdf
※2 国立環境研究所 侵入生物データベース(維管束植物)
https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/toc8_plants.html
※3 みんなでカタバミプロジェクト with かずさ〜あなたの街では何色ですか〜
https://sites.google.com/kazusa.or.jp/oxalis/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0
廣末 智子(ひろすえ・ともこ)
地方紙の記者として21年間、地域の生活に根差した取材活動を行う。2011年に退職し、フリーを経て、2022年から2025年までサステナブル・ブランド ジャパン編集局でデスク兼記者を務めた。