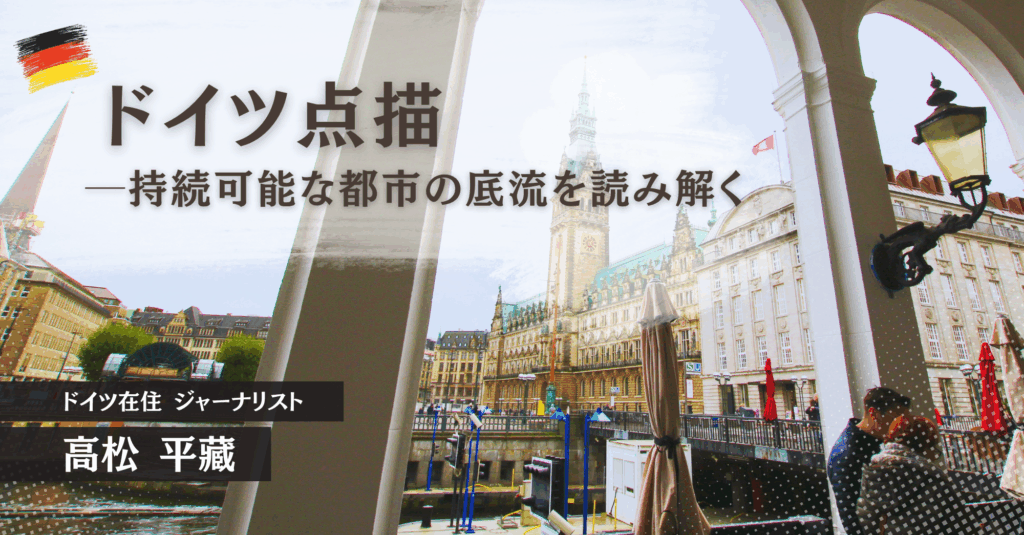
日本の選挙といえば、選挙カーの大音量や駅前での一方的な呼びかけが当たり前だろう。だが、私が暮らすドイツ南部の都市エアランゲンでは、そうした光景は見かけない。選挙期間になると、中心街の広場に各政党がカラフルなスタンドを出し、市民とじっくり話し合う姿が目立つ。今年2月には、移民排斥を掲げる極右政党のブースを市民たちが囲み、「なぜそんな主張をするのか」と静かに問いかける場面も目にした。そこに怒号や混乱はなく、冷静な対話が続く。
なぜドイツでは選挙カーが走らないのか?その理由は単純ではない。都市のつくり方、社会のルール、そして「みんなで話し合うこと」を大切にする文化など、いくつもの要素が重なっている。現場での体験をもとに、日本との違いを考えてみたい。
◾️ 歩行者ゾーンが「政治的対話」の空間に
私が初めてエアランゲンの中心市街地を訪れたのは1998年。石畳の広場と古い建物が並ぶヨーロッパらしい景色に、まず驚いた。何より印象的だったのは、車が見当たらない歩行者ゾーン。日本では珍しかったが、ここではすでに「当たり前」の空間だった。

その後この町に住み始め、土曜日の広場で政党のスタンドがずらりと並ぶ選挙期間の風景を目にした。赤・緑・青・黄色のパラソルが並び、パンフレットや風船、ひまわりの花が配られる。子どもたちや家族連れも多く、にぎやかな光景が広がっていた。だが、ただ「にぎわっている」のではなく、同時に党員や候補者が市民と立ち話をし、政治的な対話が自然に生まれているのだった。
10代の女の子がSPD(ドイツ社民党)のスタッフに「風船ちょうだい」と声をかけると、「僕たちの党のフルネーム知ってる?」と返され、「ドイツ・社会・民主党!」と答えて風船を受け取る。髪を立てたパンクルックの若者が党員と真剣に話し込む。どちらも日常の「一こま」で、「外国人」の私自身も、ここで市議や党のスタッフと知り合うきっかけになった。
日本の都市では、こうした光景はほとんど見かけない。都市計画の段階で「みんなが立ち止まって話せる場所」を意図的に作る発想が、そもそも希薄なのだと思う。
ドイツの都市では1970年代以降、中心市街地の歩行者ゾーン化が進み、車を排除して広場や通りを人々のものに戻してきた。こうした場所こそが、選挙期間になると政党スタンドが立ち並ぶ、対話の中心になっているのだ。
もちろん、ドイツに選挙カーがない理由は「歩行者ゾーン」だけではない。最近は、政策比較サイト(Wahl-O-Mat)やSNSも普及し、情報収集の手段は多様化している。日本でも見られる公民館などでの対話集会もある。
それにしても「選挙カーがない」と驚いているのは日本社会からの目線であり、おそらくドイツ社会では選挙カーは「想像もつかない方法」だ。
選挙カーが成り立たない理由としては、まず、法的に「連邦イミッション防止法」や各自治体の条例があり、公共の場での大音量の宣伝活動は規制されていることが挙げられる。つまり、「みんなが気持ちよく暮らす」ための静けさや秩序を守る仕組みが、法律や条例として明確に定められていることが前提にある。
それに対して、日本の駅前や通勤時間帯の「移動」に集中した空間では、立ち止まってじっくり話す余裕は生まれにくい。都市空間のつくり方次第で、政治や社会について話し合う「場」が生まれる、これはドイツの都市政策が示している大きなヒントだと思う。
◾️ 民主主義にはトレーニングがいる
そもそもドイツの歩行者ゾーンで上述したような対話が発生しやすいのは、そこが自治体の代表的な「みんなの空間(公共空間)」としてデザインされているからだ。またドイツには、「他の人の意見もちゃんと聞く」「みんなで話し合う」「相手を否定しない」というルールがあり、学校教育や文化事業でも民主主義的対話を身につけるようになっている。そうした「相互のコミュニケーション」という言論空間をつくる訓練が盛り込まれている社会なのだ。

冒頭で書いた極右政党のスタンドを市民が囲む場面でも、考えの違いはあっても、柵越しに冷静に意見を交わす姿が印象的だった。一部で報じられているように、極右の活動は、地域によっては過激なところもあるかもしれない。しかし、エアランゲンでの様子からは、思いのほか「言葉でぶつかり合う」こと、つまり民主主義の作法が守られていることが垣間見えた。
ドイツでは投票以上に、「誰もが自由に意見を述べ合い、人格を否定しない」ことが重視される。「外国人のくせに」「女のくせに」といった言葉は、ここでは通用しない。
一方、ドイツでも極右政党の支持が年々伸びている現実がある。実際、今年の総選挙では極右政党が大きく議席を伸ばした。しかし、それに対して多くの市民が「出自や背景で人を排除するのは違う」と声を上げ、街頭での対話や抗議を通じて自分たちの考えを表現している。
意見を言うのは簡単そうに見えるが、「どうやって自分の意見を作るか」「他の人とどう話し合うか」も、実は練習が必要だ。意見を出し合い、違う意見があれば調整し、できるだけ共通点を見つけていく。ドイツではこうした一連のプロセスを、地域の非営利組織やコミュニティ活動を通じて体験できる。そこはまさに「生きた民主主義」の現場だ。
立ち話を通じて知り合った市議の1人に「議会は賛成・反対がにぎやかで、物事を決めるのも時間がかかるよね?」と聞くと、「まあ、そうだね。でも決まるまでは誰がどんな意見を言ってもいい。ただ、決まった後はみんなで協力する。それがこの町の誇りだよ」と答えてくれた。
民主主義に対する理解と態度をトレーニングによっても強固なものとしているドイツ。民主主義が本当に生きたものになるかどうかは、選挙運動の「当たり前」を時に疑い、考え直すことから始まるのだろう。

高松 平藏 (たかまつ・へいぞう)
ドイツ在住ジャーナリスト
ドイツの地方都市エアランゲン市(バイエルン州)および周辺地域で定点観測的な取材を行い、日独の生活習慣や社会システムの比較をベースに地域社会のビジョンを探るような視点で執筆している。日本の大学や自治体などでの講義・講演活動も多い。またエアランゲン市内での研修プログラムを主宰している。 著書に『ドイツの地方都市はなぜクリエイティブなのか―質を高めるメカニズム』(学芸出版)をはじめ、スポーツで都市社会がどのように作られていくかに着目した「ドイツの学校には なぜ 『部活』 がないのか―非体育会系スポーツが生み出す文化、コミュニティ、そして豊かな時間」(晃洋書房)など多数。 高松平藏のウェブサイト「インターローカルジャーナル」













