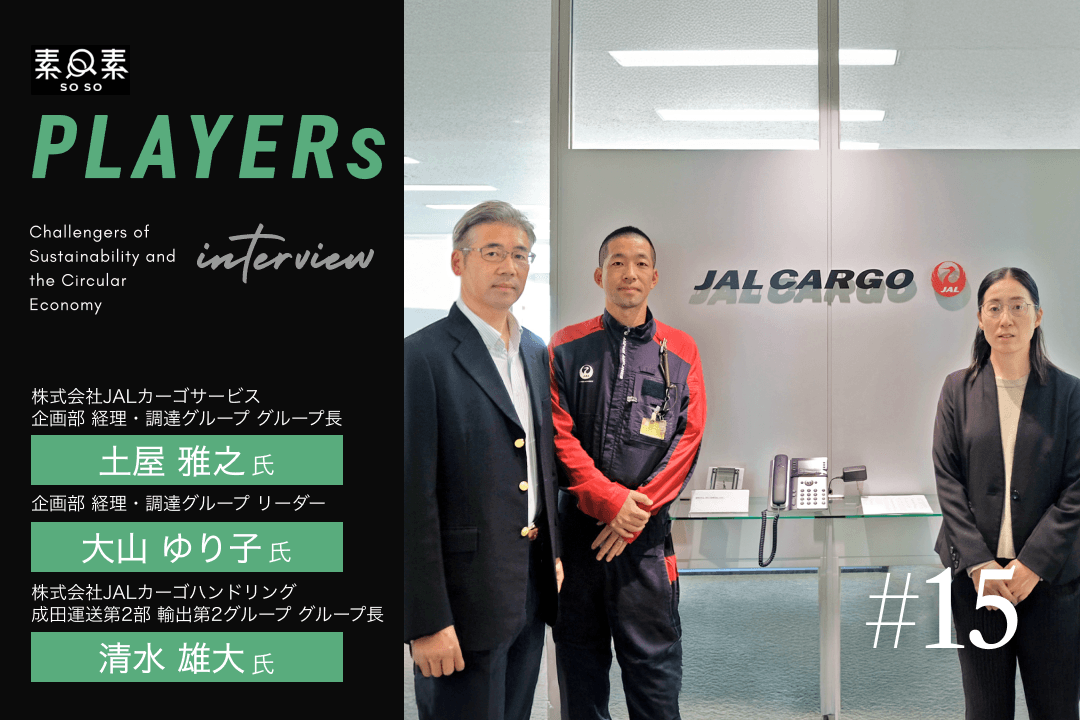関税政策によって先行きが不透明な米国の電子機器業界。国内での製造や、サプライヤーを本国に近づける「ニアショアリング」の必要性が高まる中、材料や部品をリサイクルし、循環させることの合理性も高まっている。しかし、電子機器の循環にあたっては、評価・推進に必要な業界の共通認識がないことなど、まだ解決すべき課題が多い。こうした状況を受け、国際エレクトロニクス協会(IPC)はこのほど、業界内の協働を促進するためのプログラムを発足した。(翻訳・編集=茂木澄花)

米国の新たな関税は、電子機器にも課せられるのか。ここ何週間か、さまざまな憶測が飛び交っている。当面の間、電子機器業界は難を逃れたようにも見えるが、大統領は「除外措置は一時的なものだ」という見解を示した。
電子機器業界は、材料と部品の製造、組み立て、流通を国外のサプライチェーンに頼っている。関税が保留される中、サプライヤー網を本国に近づける「ニアショアリング」に向けた圧力が高まる。だが、そもそも電子機器を米国内で製造することは可能なのだろうか。
現時点における米国の産業構造は、電子機器を含む消費者向け高性能製品の需要に対応できる仕組みを備えていない。しかし、関税の意図せぬ副作用によって産業のサーキュラリティ(循環性)が高まり、材料と部品のリサイクルが進めば、米国内で電子機器を製造できるようになる可能性がある。
コロナ禍で調達が不確実になり、価格変動が大きくなったときのように、現在の状況は、電子機器業界が循環性を高めてリスクを減らし、コストを安定させる契機になり得る。そして、その過程で環境と社会に与える悪影響を最少化できる可能性もあるのだ。
電子機器部品のリサイクルと転用を拡大し、必要な材料を賄えれば、米国の電子機器業界は国外のサプライチェーンへの依存を軽減できるだろう。材料や部品、使用済みの最終製品をごみにするのではなく、リサイクルや再利用、修理に回すことが、米国内で電子機器を製造するのに必要な材料を得ることにもつながる。
関税の思わぬ効果?
米政権で関税の議論が高まる中、「想定される価格高騰が起これば、電子機器の消費者需要は75%減少する」と予想された。iPhoneの価格は、2000ドルを超えて史上最高額になるとの推測もある。
こうした変動性は事業に悪影響を及ぼすため、国内製造のインセンティブとなり得る。そして、国内製造の実現可能性を高めるのが、材料や部品の循環だ。
循環型の電子機器業界においては、最終製品は使用後に分解できるよう設計されるはずだ。製品に使われる材料と、製品から取り出せる材料に関するデータが集められ、材料、部品、最終製品の需給動向を把握するために共有されるだろう。研究開発も盛んに行われ、テクノロジー、政策、経済といったさまざまな面でインセンティブが生じることで、活発な循環が起こる。
電子機器の循環を妨げる要因
しかし現在まで、米国内で循環型のサプライチェーンが大規模に実現するほど、テクノロジーや政策による後押しはなく、経済的インセンティブもなかった。
循環を実現しようとする業界のリーダーたちは、他にも壁に直面しているという。例えば、どのように製造過程に循環を取り入れれば良いかノウハウが得られないこと、意思決定と報告に必要なデータの種類があいまいなことなどがある。
さらに、電子機器業界にはまだ循環性の評価や解釈の手法に対する統一的な見解がない。全ての電子部品(基板など)の循環性を測って改善するのか、最終製品(ノートPCなど)の単位で測るのか、意見が割れている。循環性の進展を評価し、推進するには共通の認識が必要だ。
また、政府や研究機関における研究開発も危機に瀕している。一部の企業は、関税によって予算削減を迫られ、研究開発を断念することを検討している。こうした状況では、電子機器の循環をかなえるイノベーションはさらに遠のきかねない。
循環の経済合理性
サステナブルなイノベーションを費用削減と収益につなげられる企業こそが、不確実な現状を勝ち抜ける。年間約570億ドル分の鉄、銅、金が電子廃棄物として捨てられていると言われる現状を鑑みれば、これらを活用することは、明らかに経済的な利益につながるチャンスだ。
有名なのはアップルの例だ。同社の2025年環境進捗報告書によると、昨年、顧客に出荷された製品に含まれるアルミ、コバルト、レアアース、リチウムなどの素材の24%が、リサイクル素材またはリサイクル可能な素材だという。これは、同社が循環型の事業に野心的であることの現れであり、業界をリードする結果だ。
このように有望な成功事例やイノベーションはあるものの、高まる電子機器の需要に対応できるだけの規模での循環は、現時点では行われていない。おそらくこれまでは、どこで、どのように電子機器を製造するかを考え直す緊急性がなかったため、業界を循環型に移行する必要性が十分高まらなかったのだろう。現在、新関税が適用されるかどうかの瀬戸際に立たされている電子機器関連企業は、業界の継続的な成長軌道を支えるため、コストを安定させる手段を探ることを迫られている。循環が、この課題に対する解決策の1つになり得るのだ。
関税の脅威がある中でも、業界がサステナブルな方向に移行していることを示すデータがある。国際エレクトロニクス協会(IPC)が「Wired for Change」と題して最近発表した意向調査の結果によると、世界的な電子機器関連企業の多くがサステナビリティに取り組んでいるという。回答者の60%近くが、サステナビリティと循環性に取り組む主な原動力として、コスト削減と効率化を挙げた。
電子機器業界の循環型への移行を支援
世界の電子機器業界は、互いに依存し合っている。持続可能な業界への移行を進めるためには、互いに協力する必要がある。そのためIPCは、業界が共同体として行動できるよう、業界としての指針と情報を提供するプログラム「イボルブ(Evolve)」を発足した。電子機器業界の循環を支援するには、業界の成功事例を集めて共有することが不可欠だ。
特に大きな課題となっているのが、現時点で何が可能なのか、企業の認識を向上することだ。つまり、どういった材料、部品、最終製品がすでに循環可能なのかを共有しなければならない。自分の業界が循環性を取り入れられるとは知らず、ましてや、それに伴ってコストが削減できる可能性があるとは思ってもいない電子機器メーカーも多い。
電子機器業界が未来に関わる課題に直面する中、関係のない企業は1社もない。業界全体として取り組めば、製品のライフサイクル全体を考慮した循環型のデザインを実現し得る。持続可能でレジリエントな未来に向けて、団結して取り組めるのだ。
| ※編集部注:IPC「イボルブ」プログラム IPCは、電子機器製造の品質基準作成や認証、研修などを行う国際標準化団体で、プログラムやサービスの利用企業は世界で3000社を超える。IPCは2025年3月、電子機器業界のサステナビリティ向上を目指す「イボルブ」というプログラムを発足した。同プログラムのサイトではすでに、サステナビリティに関する業界の意向調査や、EUのCSRD(企業サステナビリティ報告指令)への対応指針などが発表されている。 今後は、サステナビリティに関する基準の作成や研修、ネットワーキング活動なども展開する見込み。今年中には、スコープ3排出量の報告に関するまとめと、EUのエコデザイン規則を解説した文書を発行する予定だという。 |