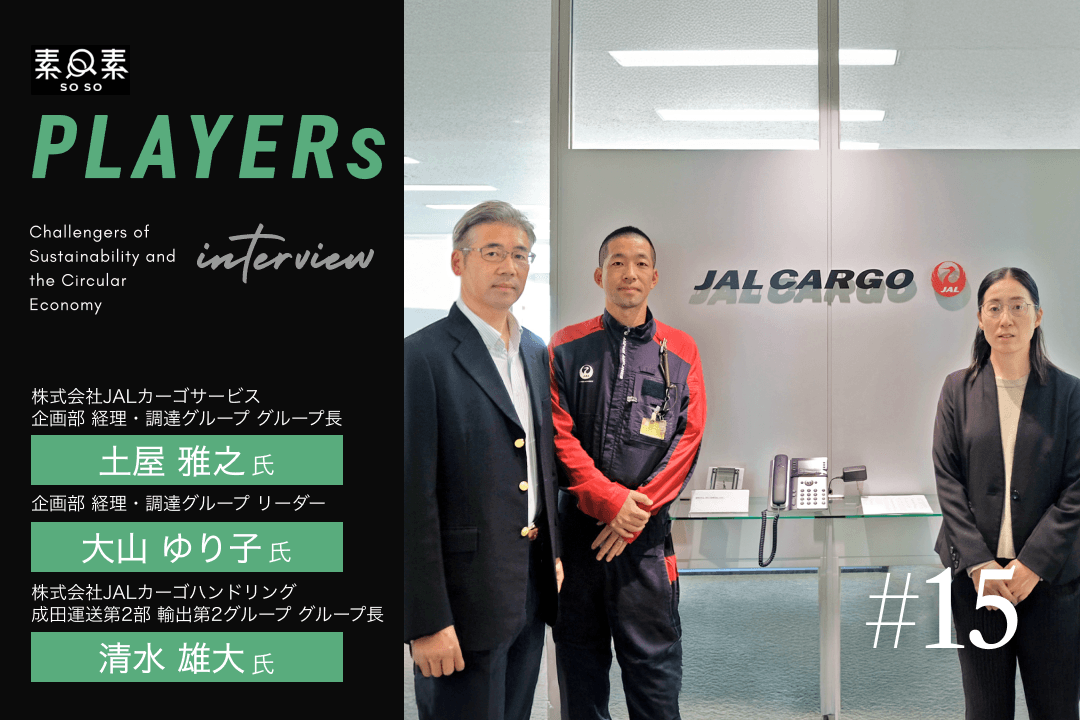SB 2018 Tokyo
 ファシリテーターの青木氏、神奈川県の脇氏、MATCHAの青木氏、電通の並河氏
|
地方創生をテーマにしたセッション「地方創生のカギとなる『ソーシャル・デザイン』をどう加速させるか」には、地方創生の現場で活躍する3人が登壇した。ファシリテーターは、サステナブル・ブランド国際会議東京 アカデミックプロデューサーの青木茂樹氏が務めた。(瀬戸内千代)
ウェブサイトを制作・運営するMATCHA (東京・台東区)の青木優社長は、外国籍の社員を積極的に雇い、日本語ネイティブではない旅行者や滞在者に便利な国内情報を多言語で発信している。日本の価値を分かりやすく海外に広めて旅行者を呼び込み、地域の魅力を未来に残す試みだ。自治体や企業との協働事例を示しながら、「ターゲットを絞ることが重要」と語る実践的な内容に、会場の企業人たちは真剣に聞き入った。
電通「新!ソーシャル・デザイン・エンジン」の並河進クリエーティブディレクターは、出向先の宮城県石巻市で「面白い人材」を発掘しては、都内イベントに講師として招くなど、彼らのユニークな企画や起業を後押ししてきた。東日本大震災被災地の石巻だからこそ生まれたという自由な発想の数々を紹介し、「彼らの知恵や行動力こそ地域資源だ」と語った。
脇雅昭氏は、現役の神奈川県職員(市町村課長)でありながら約5年前から休日を使って、全国47都道府県の公務員の交流イベント「よんなな会」を企画・運営している。活動で重視しているのは「わくわく感」から生じる自発性。ともすると顔を出す「ただ・けど病(駄目な理由を見つけて諦めてしまう傾向)」を克服するには、横につながるキカッケが必要だという。硬直した組織よりも思考停止とは無縁の「にゅるっとした組織」が理想と語って会場を沸かせた。

瀬戸内千代(せとうち・ちよ)
海洋ジャーナリスト。雑誌「オルタナ」編集委員、ウェブマガジン「greenz」シニアライター。
1997年筑波大学生物学類卒、理科実験器具メーカーを経て、2007年に環境ライターとして独立。自治体環境局メールマガジン、行政の自然エネルギーポータルサイトの取材記事など担当。2015年、東京都市大学環境学部編著「BLUE EARTH COLLEGE ようこそ、「地球経済大学」へ。」(東急エージェンシー)の編集に協力。