 |
サステナビリティ経営の重要性は議論されているが、それを実践し機能させている企業はまだ限られているだろう。サステナブル・ブランド国際会議2021横浜で行われたセッション「サステナビリティが中心にある企業経営」に登壇したのは、日本ロレアル、ベネッセ、大和証券グループ本社という持続可能性を経営の核に据える3社の現役トップたちだ。なぜ取り組みを推進し、それをどう実現しているのか。従業員の意識が変化することで企業が変化し、社会全体が持続可能性へ向かい、社会の中で生活する従業員がまた変化する――。セッションを通じて見えてきたのは、そんな好循環が起こるこれからの社会の全体像と、企業の姿だ。(サステナブル・ブランド ジャパン編集局)
パネリスト:
ジェローム ブリュア 日本ロレアル 代表取締役社長
田代 桂子 大和証券グループ本社 取締役 兼 執行役副社長
安達 保氏 ベネッセホールディングス 代表取締役社長 CEO
ファシリテーター:
足立 直樹 氏 サステナブル・ブランド国際会議 サステナビリティ・プロデューサー
レスポンスアビリティ 代表取締役
サステナブルビジネス・プロデューサー
国内で「サステナビリティ経営」が議論されるようになったのはパリ協定やSDGsの採択の後、2015年頃以降のことだ。しかし持続可能性という言葉が一般的でなかった頃から、CSRを超えて社会貢献の概念を経営理念に一体化して活動を続けてきた企業はある。現在明確に「サステナビリティ経営」を掲げ、実践する大企業の多くは、持続可能性に通じる経営方針を長年続け大きく成長した企業だとも言えるだろう。
ベネッセという社名はラテン語の造語で、「よく生きる」という企業理念を意味している。「『よく生きる』は英語で言うとWell Being。SDGsの目指す方向と一致している」と話すのは同社社長の安達氏。教育と介護の領域で事業を行う同社は、少子化や超高齢社会、教育の機会といった大きな課題に直面する企業でもある。同社が「サステナビリティ経営」を明確にしたのは2018年の初頭だという。そのきっかけを安達氏は次のように話す。
「2014年の個人情報漏洩問題により経営は厳しい状況だった。(安達氏が社長に就任した)2016年、最初にやったことは、社員の皆が納得できる新しい目標をシェアすること。それまでの『よく生きる』はお客様、あるいは社員にとっての言葉だった。ステップを進め、社会の『よく生きる』を考えるように定めた。社内でディスカッションをするうち、サステナビリティとは事業そのもので、事業をすることがサステナビリティに繋がっている、と会社全体が腹落ちした」
 |
世界最大の化粧品会社ロレアルも、サステナビリティへの取り組みは1979年に再生皮膚の研究に取り組み始めたことに端を発しているという。日本ロレアル社長のブリュア氏は「2006年、現CEO(ジャン-ポール・アゴン氏)の就任でサステナビリティの取り組みは加速した」と説明する。アゴン氏は経済的な側面だけでなく、社会にポジティブなインパクトを残せなければ企業の成功とは言えないと明確に打ち出した。2013年には環境負荷低減プログラム「Sharing Beauty With All」、そして2020年にはSDGsに沿った長期プログラム「ロレアル・フォー・ザ・フューチャー」を開始した。
「ロレアル・フォー・ザ・フューチャー」は2030年に向けて漠然とした目標でなく、プラネタリー・バウンダリー(地球の限界)を重要視して科学的にターゲットを定めたという。ブリュア氏は「(2006年から)ロレアルが企業活動の環境負荷を最小限にするだけでなく、環境にプラスのインパクトをもたらすことを考えていた。トップがまず社員に背中を見せた」と説明する。
大和証券グループ本社副社長の田代氏は2020年から同社の「SDGs担当」を務め、長期的視点で会社の方向性を考える立場になったという。同社もやはり「働き方改革」や「SDGs」という言葉が登場する以前から社会の課題を解決する取り組みを進めている。例えば2007年には19時前退社の励行をしており、2008年には日本で初めて個人の投資家向けにワクチン債を販売し始めた。
田代氏は「証券会社がSDGsに取り組む方法は2つあると考えている」と話す。ひとつは社員一人ひとり、そして会社の「自分ごと化」による取り組みだ。例えば社員が個人で再生可能エネルギーの関連投資を行ったり、SDGsを推進したり、定期預金を通じた社会貢献をしたりすること、そして「会社の自分ごと」として「働きがい改革」を推進し、早くから女性が活躍できる環境を整えてきたことなどだ。後者の例ではその結果、今では多くの女性が管理職として活躍しているという。
もうひとつの取り組み方法は事業を通じた社会課題の解決だ。現在策定中の2030年に向けたコーポレートビジョンでは「貯蓄からSDGsへ」というコンセプトで取り組みを進める。低金利や年金問題など、現在貯蓄のみでは資産形成をしにくい状況にある。投資による資産形成は証券会社にとって大きなビジネスチャンスでもある。田代氏は「お客さまが共感する投資先にお客様の資産が向かい、お客様の資産の成長とともにSDGsの実現につなげることができればと考えている」と話す。
サステナビリティはどのように社員に浸透したのか
3社のサステナビリティ経営を実践する経緯に共通するのは、社員、経営トップともに「腹落ち」「自分ごと化」が大きな原動力になっていることだ。とは言え、全社員にサステナビリティを浸透することは容易ではないだろう。ファシリテーターの足立氏は「実際に経営者としてどう社内コミュニケーションをしているか」を聞いた。
 |
大和証券グループ本社の田代氏は「収益状況、予算達成などを重視する部長クラスと、SDGsが大切だという若者や経営層のギャップをどう埋めるかが課題」と語る。特に仕事においても私生活においてもSDGsやサステナビリティを念頭に社会生活を送る若者から、会社組織としてどう声を汲み取るのか。田代氏は「トップが声を出せば役職者が少しずつ動く。若者は何も言わなくても自然と体が動く。そこまでトップからの声が浸透したとき、また若者から声が返ってきて組織が変化する、というのが今後の大きな動きでは」と展望する。
ベネッセでは社員一人ひとりの声、言葉の吸い上げを行ってきた実績がある。安達氏は「よく生きるという企業理念が浸透しているので、ボトムアップでできるだけ社員の声を掬い上げるということが結果的に(サステナビリティ経営の)浸透を促す上で良かった」と振り返る。またベネッセの創業日に行われる朝礼では、毎年「よく生きるとはどういうことか、会社として大切なことは何か」を話し合い、社員が自分の言葉で発表を行うという。そういった場を通じて、「サステナビリティ=よく生きる」という納得感が出てきたと安達氏は話す。
ブリュア氏は「ロレアルではトップから変化しようと(いう動きだった)。企業は社会、サステナビリティのために何ができるのかということで、まず社員の声を吸い上げた」と話す。
サステナビリティ通じたパートナーシップがビジネスにも生きる
社内で刺激し合うことに加え、サステナビリティへの取り組みの上では必ず、社外と連携する場面が出てくる。ファシリテーターの足立氏は「パートナーシップとは言っても、企業にとってはNGOや市民や行政とのパートナーシップは必ずしも得意領域ではない場合もあるのでは」と水を向けた。
ブリュア氏は「多くの小売業者の意識は高まっている」と実感を話した。ブランドとともに、消費者にサステナビリティの活動の紹介をしていこうという風潮は高まっているという。またロレアルが展開するブランド「キールズ」ではテラサイクルとの連携によるプラスチックの再利用プログラムや、NGOと連携した環境保護活動などを積極的に推進し、時には社会貢献のためだけのパートナーシップだけでなく、それがビジネス上の連携にも繋がっているという。
一方、ベネッセは瀬戸内海に浮かぶ直島で地域連携を深めている。現代アートの美術館を運営し、自然と建築、芸術を合わせて「よく生きる」とは何かを考える場所を醸成している。地域住民が観光ガイドを務め、生き生きとした姿を見せるなど地域活性に貢献しパートナーシップ活動を行う。また教育を事業領域とする同社にとって「学校の先生との連携が非常に重要だ」と安達氏は話す。生徒や学生たちに直接的に接する機会が多いのは学校の教員だからだ。
田代氏は証券業界のパートナーシップを紹介した。実は日本証券業協会は、早い段階からSDGsを取り上げて取り組みを進めている。協会が推進することで、地方の証券会社も一緒に活動できたという。「パートナーシップはベースを広げる上でも重要だと考えている」と田代氏は話す。そして「証券会社にとってNGOとの連携が非常に重要だ」と説明した。「タイムリーに、どこに、どういうかたちでお金を届けるのがベストかは私たちにはなかなかわからない。NGOとの繋がりが大切だ。パートナーシップがなければ思いがあっても適切にお金を届けることができない」という。
サステナビリティ経営で社員、企業、社会に変化は
では、サステナビリティ経営を推進することによって社員にはどのような変化があったのだろうか。SDGs推進室を設置した大和証券グループ本社では、「今までだと若手社員が『こんなこと言っても会社は反応しない』と思っていたが、「会社に伝えればもしかしたらやってくれるかも」と思い始めている」という。「この変化は大きくて貴重な変化だ」と田代氏は感慨を込めて話す。
これにブリュア氏も「コロナによって(社会は)打撃を受けたが、働き方は大きく変わったし、新しいやり方があって変化することができる、というように意識は大きく高まった。(社員も)会社に何かを変えてほしいときに自分の声がちゃんと届くという意識は高まっている」と同調した。
ファシリテーターの足立氏は「社員が変わり、それによって企業が変わり、企業の力で社会が変わる。その社会で生活する社員の意識がまた変化する、という好循環が生まれつつあるように感じる」と話した。この変化はビジネスそのものにとっても良い影響を与えそうだ。
ブリュア氏は「(サステナビリティ経営によって)生産性は上がっていると思っている。そして来年の業績の話ではなく、長期的視点で企業が変化し、声が届いていると社員も勇気づけられていると思っている。社員の活動が加速し、さらに会社に対しての意識を変えることによってビジネスも会社もより強くなる」と実感を込めた。
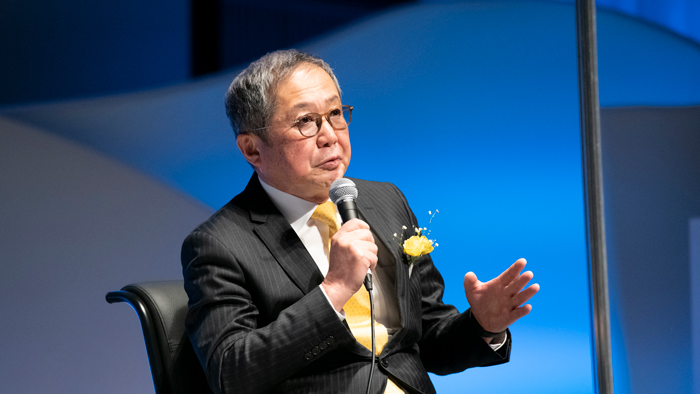 |
安達氏も「社会課題の解決をコアにすることによって事業に対する捉え方が広がったように思う。お客様のためにと考えていた社員のマインドセットが、社会のためにというふうに変化し、広がった」と話した「お客様だけでなく、社会の大きな意味での困りごとは何かという視点を皆が持つようになったのはサステナビリティ経営の大きな成果だと思っている」と力強く語った。
沖本 啓一(おきもと・けいいち)
フリーランス記者。2017年頃から持続可能性をテーマに各所で執筆。好きな食べ物は鯖の味噌煮。















