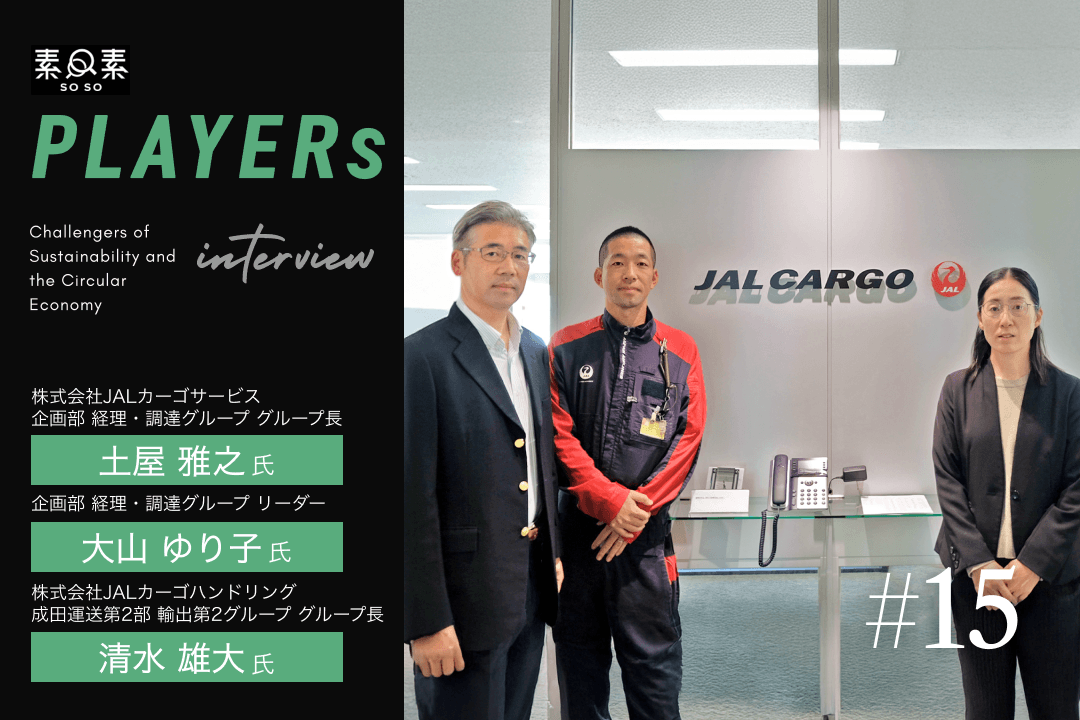|
東日本大震災から丸9年。特に原発事故のあった福島県は、経済活動も大きな苦境に立たされた。ところが、県産農産物の輸出量が2017年に震災前を越えて過去最高になり、それ以降も3年連続で更新し続けている。事業誘致も盛んだ。いま「FUKUSHIMA」に何が起きているのか。サステナブル・ブランド国際会議2020横浜では、福島県知事や地元ベンチャー企業社長らが登壇し、地域のブランド化について議論。全国の自治体が今後取り組まなければならない課題が浮き彫りにされた。(いからしひろき)
ファシリテーターは、関東学院大学経営学部 学部長の小山嚴也教授。パネリストは、福島県知事 内堀雅雄氏、特定非営利活動法人素材広場 理事長の横田純子氏、磐城高箸 代表取締役の高橋正行氏。4人はともに顔見知りということで、終始和やかな雰囲気で進んだ。
セッション冒頭、小山氏は「福島はおもしろい」と語った。地方創生はどこも上手く行っていない印象だが、「福島はすごい。色々な面白い動きがポンポン出ていて、福島での経験は日本のあらゆる場所のまちづくりや地域活性化のヒントになるだろう」と、今回のセッションの開催意図について語った。
それを受けて内堀知事から、福島県の現状についての説明があった。
 |
福島県は2011年以降「複合災害」に直面しているという。複合災害とは地震、津波、原発事故、風評被害、さらに丸9年という時間の経過による記憶の風化。昨年秋には台風9号(東日本台風)の災害にも遭い、地震と台風の二重、三重の被害に直面している。
特に県民にとって未だに重く難しい課題が原発事故の後遺症だ。避難者数はピーク時の約16万4000人より大幅に下がったものの、今も約4万人が県内外で避難生活を送っている。最近避難指示区域を解除された浪江町では居住率わずか8.2%、富岡町は12.9%、大熊町で31.4%と、簡単には故郷に戻れない状況が続く。
福島原発では廃炉対策が行われているが、一番問題なのは原子炉の中に溶けおちた燃料デブリ。その取り出しは世界に例がなく、30〜40年という長い時間がかかる見込みだ。
福島の農産物(桃、米、牛肉など)は9年たっても全国平均比で価格差がある。未だに福島県産をためらう人は国内にも一定数ある。
「こうした課題を解決したい」と内堀知事は話す。そのためにこれまで、どのような「挑戦」を行ってきたのか、その説明があった。
ひとつ目はもちろん「除染」である。2018年の春に全体的な「面」の除染は概ね完了。汚染土は大熊町と双葉町の中間貯蔵施設に運び込んでいる。その結果、福島県内の放射線量は大きく下がり、世界の主要都市の放射線量と変わらない水準となっている。避難指示区域の面積も2011年は県の面積の12.5%を占めたが、今は2.5%まで縮小された。
「一歩一歩故郷に帰れる環境づくりが進んでいる」(内堀知事)
農作物の安全対策も「一生懸命やってきた」とアピール。「世界標準と比べて極めて厳しい基準」でモニタリングを徹底し、玄米は4年連続、野菜、フルーツ、畜産物、栽培山菜・きのこは6年連続超過なし。海の魚、野生の山菜きのこもこの1年間で超過は0件。福島県産の農産物は安心して食べられることが立証されている。
県内農産物、「メイドイン・福島」の海外への輸出については、震災後はほぼゼロだ。しかし地道に輸出の機会を探り続け、2016年5月にはタイに桃を、2017年にはマレーシアに米を、ベトナムに梨を輸出できるようになった。その結果、県産農産物の輸出量は、2017年に震災前を越えて過去最高に。さらに2018年、2019年と3年連続過去最高を更新している。
2つ目の挑戦は「被災地発のイノベーション」だ。福島県のものづくりは震災後大きく落ち込んだが、現在は震災前の水準に戻っているという。しかし、特に被害の大きかった双葉郡は、震災前と比べ大きく落ち込んだまま。この地域を元気にするため、打ち出されたのが「福島イノベーションコースト構想」だ。これは、廃炉、ロボット、エネルギー等、最新鋭の研究をこの地で行うというもの。新たな産業、企業を集約する狙いだ。例えばエネルギー分野だと、浪江町で「福島水素エネルギー研究フィールド」を作っている。まもなく完成する予定で、世界最大の水素製造拠点となる見込みだ。ここで作られたCO2フリーかつオール再エネで作られた水素を、東京オリンピック・パラリンピックのエネルギーとして使用するプロジェクトも進んでいる(編集注:セッション開催時)。
内堀知事は、「他に11の重要プロジェクトを同時進行している。この挑戦を続けることが『チャレンジ県ふくしま』としての、これからの時代の大事な使命だ」と意気込んだ。
 |
続いて、他の2人のパネリストの自己紹介。
横田氏は、福島県に来た人々を「福島らしさ」でおもてなしするために、NPO法人を通じて地産地消に取り組む会員宿と連携し、地元素材を使った企画を実施。素材の情報収集・情報発信・受発注等を行っている「ふくしま人」だ。
仕事の一例が、昨年9月に行った「福島三大プライド鶏キャンペーン」のプロデュース。福島には「川俣シャモ」「会津地鶏」という二大地鶏に加え、歴史ある「伊達鶏」という銘柄ブランド鶏があるが、それぞれの鶏を使った料理を出す店が皿数を競いあい、一番多かったトリが「福島一番鶏」の名誉を得るというもの。参加店舗はトリごとに32店の計96店。4カ月間で合計5000食を越えたという。
そんな横田氏は、挨拶代わりに、震災の翌年に山口県で行われた「全国農林水産物直売所サミットin萩」で披露したスライド「ふくしまの、今」を紹介した。
横田氏は、「(このスライドを披露した)8年前と今はそんなに変わっていない。自分の中ではまだ農産物でも観光でも戻っていないという気持ちがある」と心情を吐露。「観光と農業、そして親の立場で今日は話をしたい」と抱負を語った。
 |
高橋氏が代表を務める磐城高箸はいわき市に工場を構え、周辺の山林の間伐材を100%使用した高級割り箸を、原木の仕入れから、皮をむく、割り、端材を燃やした熱での板の乾燥、成形、梱包にいたるまで、すべてワンストップで作っているメーカーだ。
特徴は高い品質とデザイン性。「希望のかけ箸」という商品はグッドデザイン賞を受賞した。この賞の受賞は、割り箸業界では後にも先にも同社だけという。
「しかし割り箸だけではきつい」と高橋氏。そこで、事業内容から外れない範囲内でさまざまな商品を開発する。例えば「眠り杉枕」。これは高級割り箸の強度検査の不合格品を5mm角刻んで中袋に500膳分入れたもので、こちらもグッドデザイン賞を受賞。昨年12月中旬にはシンガポールの投資会社と契約し、「KOMME」というブランド名で2月末にシンガポール、さらにASEAN諸国、香港、台湾、年末にはアメリカ、ドイツなどで販売される予定だ。
「木粉(こふん)さま」「おがべこ」は、杉のおが粉で作ったヌイグルミ。作業工程で出るおが粉は、通常は肉牛の敷き藁に使っており、ゴミは一切出ないが、一つの資材から少しでも利益を得ようと、こうした商品も作っている。
会社設立は震災の前年。昨年4月からは、1885年に開校し6〜7年前に廃校になった木造の「旧いわき市立田人第二小学校南大平分校」に会社の機能をすべて移設。そこで作りはじめたのが、ヒノキの間伐材を使った鉛筆、その名も「旧校鉛筆」。2019-20年度の「ふくしまベストデザインコンペティション」の「キャッチコピー・ネーミング部門」で最高賞を獲得したという。
外から見た福島県
 |
ファシリテーターの小山教授が問題提起したのは、「外部の視点」だ。内堀知事は長野県出身で、東京で国家公務員として働いた後、福島に出向して知事になった。高橋氏は横浜市出身。横田さんは地元出身だが、大手出版社で長らく旅行ガイドの旅行をしていた。つまり3人とも客観的視点を持っている。そうした視点で、福島の問題点をどう捉えているのか、小山教授は尋ねた。
3人とも口を揃えるのは、「福島県はブランド力が弱い」ということだ。内容的にはとても良いものを作っているのに、「福島県人はおだやかで優しい人が多いので、積極的に前に出ていかないことが問題」(内堀知事)だという。
横田氏は、「実は東京から福島までは新幹線で78分。この距離の近さをこれまでアピールしてこなかった」と観光のプロならではの観点で指摘した。
その点、高橋氏は「ブランド構築には相当力を入れている」と胸を張る。
まずは「ネーミング」。商品開発の半分以上の時間をかけているという。そして商品名が決まったら、一切変えない。例えば「旧校鉛筆」のロゴは3回変わっているが、ネーミングは一度も変わっていないという。
そして「ストーリー」づくり。廃校に会社機能を移したのもそれを狙ってのことだそう。割り箸は日本発祥で300年ほどの歴史があるが、それと1885年開校の小学校の歴史が「重なる」からだ。
ちなみに割り箸の材料は裏山の間伐材を使っているが、これは市場に出すと手数料や運送費もかかるため、それを引き受けることで少しでも林業家の負担を減らし、手元に残る金を増やしたいとの思いから。さらに皮は薪にして乾燥用に、おがくずは牧場で敷き藁にするなどゴミゼロの仕組みができ上がっている。こうした一つ一つの取り組みが、意図的ではないにしろ、「地域や環境に優しい」というストーリーを商品に与えている。
上手くブランディングすれば、市場で叩き売られる間伐材でも価値を生み出し、利益を出すことができる。まして、商品として最初から優れているものならばなおさらだ。その一例として、内堀知事が上げるのが福島の「地酒」だ。
福島は全国品種鑑評会で7年連続金賞受賞数日本一という記録を更新し続けている日本酒王国。しかもそれは、震災直後の風評被害を払拭するために県内の酒蔵が一致団結し、品質を上げてきた成果というストーリーがある。「しかしそれを知っている他県の人は少ない」と内堀知事は嘆く。
横田氏も、「そもそも福島県内の旅館で、福島の地酒を豊富にそろえている所が少ない。お酒は福島のキラーコンテンツ。“がつがつ”と売りたい」と意欲を示す。
そこで知事が取り組んでいるのが、福島=日本酒のイメージづくりだ。
震災後、東京・新橋で福島の地酒をふるまうイベント「ふくしまの酒まつり」を毎年行って来たが、年々人気が出て3万人を超える人出があっても、単に「美味しかった」で終わってしまっていた。つまりその酒と福島が結びつかないのだ。そこで2019年度からは県内で実施することにした。新潟県の「にいがた酒の陣」のように、県外から大勢の観光客が集まってくるような一大イベントに育てたいと考えているそうだ。
また、只見町の田園風景を残すために只見産米だけを使って蒸留された米焼酎「ねっか」も、他に類を見ないブランディングの成功例として注目されている。そこには補助金に頼らず、自分たちの手で故郷の風景を維持していこうという決意と力強さが垣間見える。
「(補助金に頼る事業は)補助金が切れると(事業が)終わってしまう。ある程度の経済性をもって自分たちで自立的に続けられるところまで持っていけるかどうかが、サステナブルかそうでないかの分かれ目だ」(内堀知事)
もう一つ、福島でいま注目を集めている取り組みが、「福島ロボットテストフィールド」だ。南相馬市と浪江町に整備されていたロボットの研究開発拠点で、このセッションの約1ヶ月後の3月31日に全面開所した。
内堀知事は、「これほど広いエリアは都心にはない」と胸を張る。ロボットの研究や操作の練習は、広く安全なエリアでないと行えない。ドローンはもちろん、「空飛ぶ車」の研究実験も今後行う予定で、「あと数年で当たり前になってくる」と期待を寄せる。最新の未来技術が福島から発信されようとしている。
小山教授は、この取り組みに「しっかりとニーズを把握している。勝手に工業団地を作って誘致するのではない。それに合わせた場を福島は提供できるというブランディングだし、相手目線に立っている。そういう取り組みを応援しようという雰囲気を福島では感じる」と評価した。
FUKUSHIMAのイメージが、被災地というネガティブなものから、「美味しいものがたくさんある」「最先端技術の生まれる場所」といったポジティブものに変わる日も近いかもしれない。いや、すでに変わりつつあるだろう。
しかし、福島の挑戦はこれで完結したわけではない。内堀知事も、「福島はまだ途上。まだいろいろな課題がある。これからの5年、10年、20年が大事。まだ現在進行系だ」と言う。
地域振興の抜本的な改革は、全国の自治体で取り組まなければならない問題だ。しかし「いつか……」と考えていても腰が重い自治体が多いのも事実だろう。小山教授はこう言う。
「福島は被災したことでその時期が早めに来てしまった。ならばその経験を学ぶことが、われわれがサステナブルになるための一つのヒントになる」
いからし ひろき
プロライター。2人の女児の父であることから育児や環境問題、DEIに関心。2023年にライターの労働環境改善やサステナビリティ向上を主目的とする「きいてかく合同会社」を設立、代表を務める。