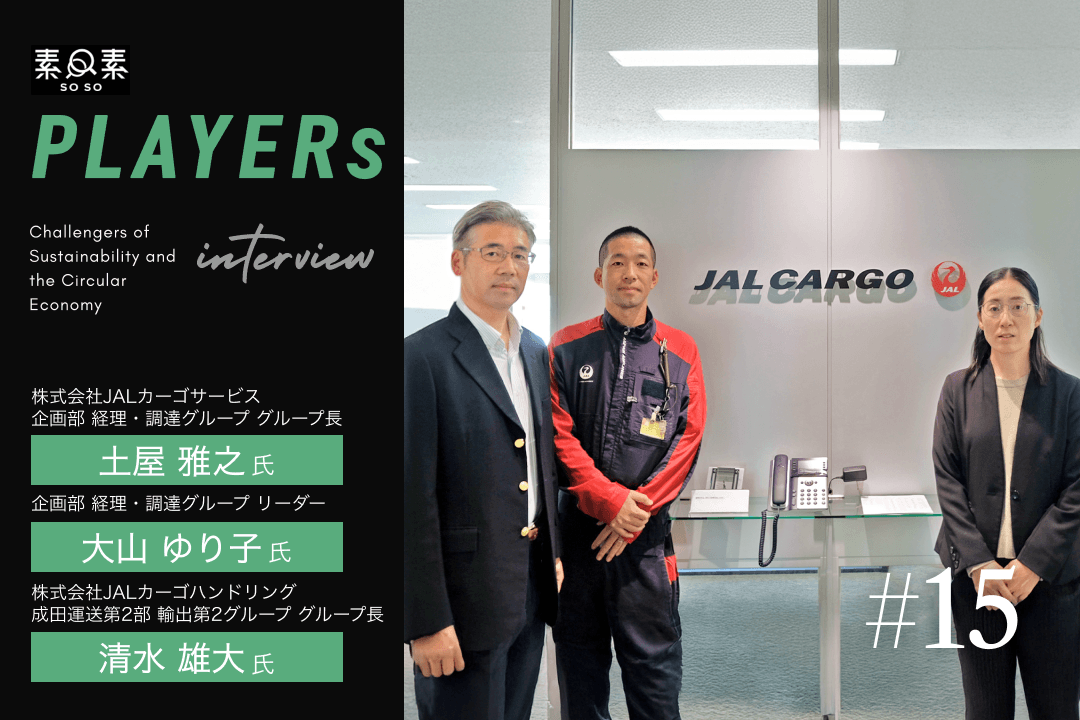サステナブル・ブランド国際会議の学生招待プログラム「第6回 SB Student Ambassador ブロック大会」の北海道大会が2025年11月9日、北海道大学札幌キャンパス(札幌市)で開催された。北海道内から24校138人の高校生が参加し、「地域の特性を生かした、北海道ならではの多面的な産業を考えよう」のテーマで実施。地場産業からダイバーシティ、環境保全まで、サステナビリティに関わる多彩な議論が交わされた。
「Boys, be ambitious」

オープニングでは、会場を提供した北海道大学のサステイナビリティ推進機構、総長特命参与の出村誠氏があいさつ。札幌農学校を前身とし、2026年に150周年を迎える同大学の歴史を紹介し、クラーク博士の「Boys, be ambitious(少年よ、大志を抱け)」の言葉が今も大学の理念として生きていると述べた。さらに、英国の高等教育専門誌による「THEインパクトランキング2025」で6年連続国内1位、世界44位にランクインした同大学のSDGsへの先進的な取り組みに触れ、高校生に向けて「失敗を恐れずに挑戦し、素晴らしい対話が成果につながることを信じている」とエールを送った。

続いて、地元・北海道総合政策部国際局長の小林靖幸氏が登壇し、「サステナブルな北海道にしていくためには、世界と関わっていくことがますます必要になる」とあいさつした。人口減少や高齢化が急速に進む一方、道内の在留外国人は2008年から2025年の間に、3倍以上の約6万9千人に増加。小林氏は「彼らがいないと、もはや産業が成り立たない。しかし今後、(労働力の)争奪戦になる」と指摘した上で、「彼らに選ばれるように、魅力ある、幸せに暮らせる社会にしていくことが重要」と強調した。
半導体で人々を幸せに

次に、次世代半導体の国産化を目指すRapidus(ラピダス)の品質保証部部長、内野美由紀氏が登壇。同社はかつて世界をリードした日本の半導体産業の復興を掲げ、2022年8月に設立された。北海道千歳市に最先端の2ナノメートルの半導体を製造する工場を建設中で、日本の半導体復興に情熱を燃やすベテラン技術者が全国から集まっていると紹介。「半導体を通して人々を幸せにし、豊かにし、人生を充実したものにする」という経営理念を掲げ、半導体の一大拠点「北海道バレー」の実現を目指していると語った。
内野氏は、AIや自動運転といった未来の技術に高性能な半導体が不可欠である一方、その消費電力の増大が大きな課題だと指摘。ラピダスは、高性能かつエネルギー効率の高い半導体を開発することで、持続可能な社会に貢献することを目指していると説明した。また、その実現には人材育成が鍵となるとし、国内外の大学や研究機関と連携して次世代の技術者を育てる重要性を強調。さらに、北海道の豊かな自然と共生するグリーンイノベーションの実現も、同社の重要なビジョンであると述べた。
「好き」に従って、社会を変える

基調講演には、Ezo Worm Japan代表で北海道大学水産学部3年の黒岩夕綺氏が「好きなことに向き合う」と題して登壇した。長崎市出身の黒岩氏は、幼少期からの魚への強い探究心が研究活動へと発展した自身の経歴を紹介。受験勉強に追われた中学時代に一度は情熱を失いかけたが、恩師の「好きなことがあるならやってみなよ」という言葉に背中を押され、水槽自動管理システムの開発や魚の行動心理の研究など、独自の探求を再開した。黒岩氏は当時を振り返り、「空気を読むのではなく、空気を描いてきた」と語り、自らの情熱に従うことの重要性を強調した。
その探究心は、やがて世界の食糧問題、特に養殖漁業が抱える魚粉(魚の餌)の課題へとつながった。魚粉は天然の魚を原料とするため、価格高騰や資源の乱獲、さらには生産国の食料安全保障を脅かすなど、サステナビリティに関わる複雑な問題だと指摘。北海道においても、本来食用となるはずのオスのニシンが安価で魚粉に加工されている現状に触れ、課題の根深さを解説した。

この課題に対し、黒岩氏は廃棄野菜などを利用して昆虫を育て、それを原料にした代替飼料でホシガレイを養殖するプロジェクトに現在取り組んでいるという。最後に「好きなことを好きだと言わないと、周りも助けようがない。大変なこともあると思うが、好きを叫びながら心に従って突き進んでほしい」と、自身の経験を踏まえて高校生に力強いメッセージを送った。
旅の未来を良い方向に動かす カンタス航空
午後の部では、3つのテーマに分かれてワークショップを実施。協賛企業による講演の後、高校生たちがグループディスカッションと発表に臨んだ。

テーマ1「共生社会の実現」では、カンタス航空の日本地区営業本部スーパーバイザーフィールドセールスの齊藤祥毅氏が登壇した。齊藤氏は、100年以上の歴史を持つオーストラリアのフラッグキャリアとして、同社が「Spirit of Australia(オーストラリアの精神)」という理念を掲げていることを紹介。その背景には、先住民であるアボリジナル・ピープルへの敬意を表す「Acknowledgement of Country」というオーストラリア特有の文化があると説明した。
また、機体のデザインにアボリジナル・アートを採用するプロジェクト「Flying Art Series」や、先住民コミュニティを支援する製品の機内提供など、文化の尊重と共生に向けた具体的な取り組みを解説した。これらの活動は、同社のサステナビリティ戦略の柱である「私たちの地球を大切にする」「人々を支援し活躍させる」「地域社会とお客さまをつなぐ」という方針に基づいている、と強調。その上で「旅の未来を少しでも良い方向に動かしてくれることを願いながら、アクションを積み重ねていきたい」と力を込めた。
講演を受け、高校生は「生活者が世界中の文化交流・文化尊重の重要性を理解し、サステナブルなフライトに参加したくなる体験アイデアを考えよう」というテーマで議論。各チームからは、機内でアボリジナル文化に関するクイズやアニメーションを体験することでマイルが貯まる「文化マイル」制度や、アメニティやチケットに伝統的なデザインを取り入れることで、乗客が文化に触れる機会を増やすといった多彩なアイデアが飛び出した。
宇宙産業を核に地域活性化 SPACE COTAN
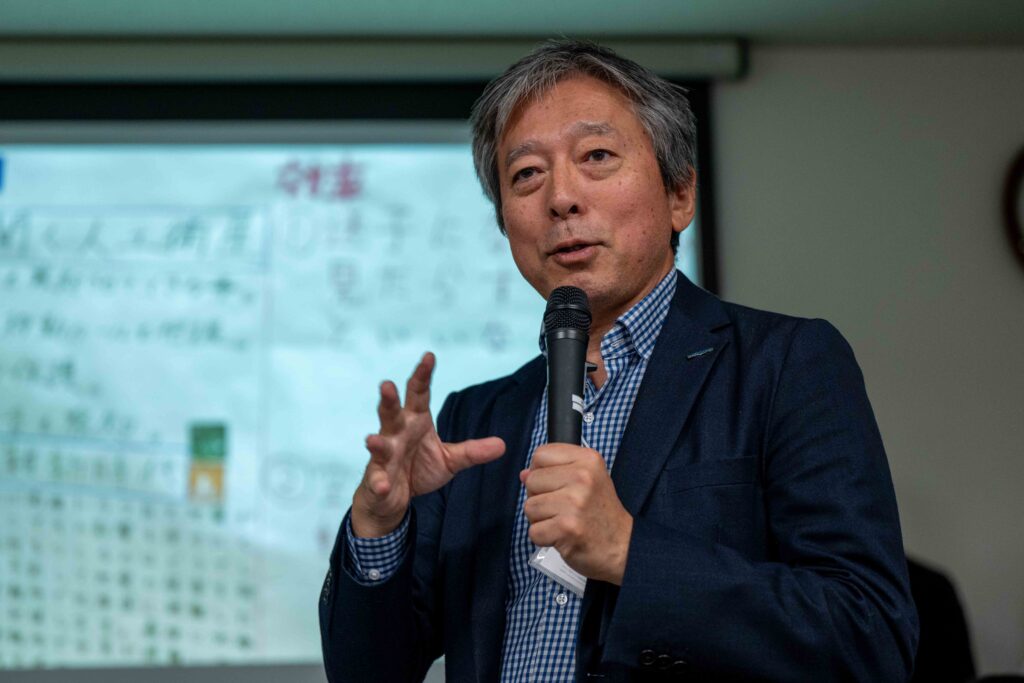
テーマ2「宇宙ビジネスの可能性」では、SPACE COTANの代表取締役社長兼CEOの小田切義憲氏が「北海道に、宇宙版シリコンバレーをつくる」と題して講演した。小田切氏は、北海道大樹町を拠点とする商業宇宙港「北海道スペースポート(HOSPO)」の事業を紹介。東と南が海に開けた地理的優位性や広大な土地といった「天然の良港」としての強みを生かし、国内外のロケット打上げを支援するアジアのハブ宇宙港を目指していると述べた。
また、空港ビジネスとの類似性を指摘し、ロケットを「輸送手段」、人工衛星を「荷物」と捉え、宇宙への輸送サービスをインフラとして展開するビジネスモデルを解説した。さらに、人工衛星がもたらすビッグデータは、農業や漁業、観光といった北海道の既存産業の発展に大きく寄与するポテンシャルを持つ、と指摘。既存産業の効率化や雇用創出・観光促進など、宇宙産業を核とした地域経済の活性化に期待を寄せた。
続いて高校生たちは、「北海道の人口は全国に先駆けて減少していきます。その中で社会や仕事、日々の暮らしで人工衛星を活用すれば便利になりそうなこと、効率的にできそうなことを考えてみよう」というテーマでディスカッション。クマなどの野生動物にGPSを取り付けて出没情報を共有し、人との遭遇を避ける安全対策や、雪の中で紛失した貴重品をGPSで探し出すアイデアが提案されるなど、活発な議論が展開された。また、衛星データで交通状況や店舗の混雑具合をリアルタイムに把握し、物流や人員配置を効率化することで、労働力不足に対応するアイデアも出された。

自然とエネルギーの調和 ピーエス工業

テーマ3「自然とエネルギーの調和」では、産業用加湿器などを開発・製造するピーエス工業の取締役工場長、後藤猛氏が登壇した。後藤氏は、同社が北広島市に構える札幌工場が「森の中の工場」であることを紹介。約50年前に創業者の夢から始まった植樹活動により、敷地の87%を緑地が占め、建物は13%だと語った。この森は、伐採した木を薪ボイラーの燃料として活用することで、工場の暖房エネルギーの一部を賄い、省エネとカーボンニュートラルに貢献している。
後藤氏は、こうした環境配慮の取り組みが、省エネだけでなく、ブランド価値の向上や社員の定着にもつながっていると説明した。また、同社が手掛ける冷暖房システムが、地中熱や地下水、温泉熱といった自然エネルギーとも親和性が高いことを紹介し、「顧客が満足するようなビジネス価値を提供しながら、環境配慮と省エネ活動を重ねて行動することが大事」と強調した。

講演後、高校生たちは「自然エネルギーを活用したこれからの冷暖房について考えよう」というテーマで議論を深めた。あるチームは、魔法瓶のように真空断熱構造を持つ住宅「お豆腐ハウス」を考案。夏は冬の間に貯蔵した雪を壁の空洞に入れて冷房し、冬は屋根に置いたレンズで太陽光を集めてサウナストーンを温め、雨水で蒸気を発生させて暖房にするというユニークなアイデアだ。また、家電などから出る排熱で屋根の雪を溶かし、その水流で小規模な水力発電を行って暖房の電力に充てるという提案もあった。
持続可能な地域社会へ、ユニークな提案相次ぐ
各ワークショップで選ばれた代表チームが、全体会場で成果を発表した。

テーマ1「共生社会の実現」の代表チームは、カンタス航空が計画する超長距離フライト「プロジェクトサンライズ」を想定し、乗客が20時間もの飛行時間を楽しく過ごせる体験型プログラム「ドリーミングフライト」を提案。五感を通してアボリジナル文化に触れる「アボリジナルセンス」や、先住民の文様を顔に塗って体験できる「トライブフェイスペイント」といったアイデアを発表し、知識だけでなく体感として文化に触れる機会の重要性を訴えた。

テーマ2「宇宙ビジネスの可能性」の代表チームは、災害時に人工衛星とAIを活用し、刻々と変化する状況に応じて安全な避難経路をスマートフォンなどに表示する「リアルタイムで変化するハザードマップアプリ」を提案した。これにより「自分の力ではどうにもできないアクシデントから命を守ることができる」と説明。さらに日常においても、緊急車両の接近をドライバーに知らせるなど、安全な交通社会の実現にも貢献できるとした。
テーマ3「自然とエネルギーの調和」の代表チームは、「身近な問題をエネルギーチェンジ」と題し、街中に溢れる落ち葉を発酵させて熱エネルギーを生み出し、温水式の床暖房に利用するアイデアを発表。ボランティア活動で落ち葉を集め、発酵後の腐葉土は農家に提供するなど、地域を巻き込んだ循環型の仕組みを提案した。駅のホームやバス停など公共空間での活用例も示し、身近な課題解決が地域の活性化につながる可能性を示した。メンバーは「チームのみんなといろんな視点から考えて、最高のアイデアが生まれた」と笑顔を見せた。
最後に、基調講演に登壇した黒岩氏が総評を述べ、「社会課題やSDGsは多角的に、多面的に見ないといけない」と指摘。広い視野を持つ重要性を高校生に伝えて、大会を締めくくった。

眞崎 裕史 (まっさき・ひろし)
サステナブル・ブランド ジャパン編集局 デスク・記者
地方紙記者として12年間、地域の話題などを取材。フリーランスのライター・編集者を経て、2025年春からサステナブル・ブランド ジャパン編集局に所属。「誰もが生きやすい社会へ」のテーマを胸に、幅広く取材活動を行う。