16~25歳の若者を対象に、サステナブル・ブランド ジャパンが運営するユースコミュニティ「nest」。現在活動中の第4期メンバーは、「自分らしい社会課題への関わり方を見つける」を共通テーマに、活発な議論を重ねてきた。
それぞれの関心領域によって6つのチームに分かれて探究してきたプロジェクトが、いよいよ具体的なアクション(「クエスト」)に入っていく。各チームがそれぞれの視点で課題と向き合い、イベントの開催やプロダクト開発、情報発信など、多彩なプロジェクトに挑戦する予定だ。本記事では、各チームの活動概要を紹介する。
AIボットで「勘違いサステナビリティ」に立ち向かう

メンバーから一言
私たちは、広く認知された環境行動が、実は効果的でない、または別の面で悪影響となる「勘違いサステナビリティ」の問題に取り組みます。例えば、コットン製エコバッグ1つを作る際に排出されるCO2量はレジ袋数千枚分に相当するとも言われています。勘違いサステナビリティの背景として、「環境に良いイメージのある行動や製品」がもたらす環境の多様な面への影響を、私たちが十分に考えずに受け入れてしまう傾向があると考えます。
そこで、9つのプラネタリー・バウンダリーを擬人化したキャラクター「プラバンちゃん」と対話ができるAIチャットボットをLINE上で設計。日常の中で「効果的な環境行動とは何か」を考える習慣を育てることを目指します。

企業の取り組みが生活者の購買意欲にどうつながるか?

メンバーから一言
私たちは、「サステナブルな商品が、良いものなのに選ばれにくい」という現状に注目し、その原因や課題について議論する中で、「自分の行動で社会が変わるのかがわからない」「購入後に満足できるか不安」「信頼できる根拠や仲間の存在が見えない」といった気持ちが、心理的なハードルになっているのではないかという仮説を立てました。
この仮説を検証するために、サステナブルな商品を扱う店舗にご協力いただき、商品に関する“伝え方”を一定期間ごとに変えながら、どの伝え方が購買意欲につながるかを観察する実証実験を企画しています。
本実験を通じて、サステナブルな商品や環境に配慮した企業の取り組みが生活者に伝わり、それらの商品や企業が選ばれる状態をつくるための糸口を見つけることを目指します。
地縁でつながる地域コミュニティのメカニズム

メンバーから一言
土地の縁によって結ばれた人たちから生まれる「おすそわけ」や「たすけあい」の精神に魅了された私たちは、地縁でつながる地域コミュニティの継続要因について議論を重ねてきました。特に、地域住民の感情や役割、意思決定の暗黙知といった、目に見えにくい要素がどのように関係しているのかに注目しています。
現在は、自治会や祭礼を長年支えてきた方々への聞き取りと場の観察を通して、地域コミュニティが持続するメカニズムの可視化に挑戦しています。最終的には、継続を支える関係の設計図と語りのアーカイブを作成し、地域に根ざした仕組みを明らかにするとともに、継続のカギとなる若年層の参加の入り口を明確にすることを目指します。
なぜ自分たちは社会課題に興味を持つのか?

メンバーから一言
私たちは『Compass for Action~自分らしい社会課題との向き合い方~』 をテーマに、社会課題に対する“アクションの輪”を広げる場づくりに取り組みます。
社会課題という大きなテーマを前に「関心層」と「無関心層」との間に見えない分断を感じ、「なぜ自分たちは社会課題に関心を持つのか」と問い直しました。話し合いの中で「関心がないことは悪ではない」と気付き、無関心層を変えるのではなく「関心を持ってから行動に至るまでの“間”にある迷いや距離感を埋めたい」という想いが生まれました。
社会課題に向き合うときに感じる孤独や不安をやわらげ、自分らしい方向(Compass)を見つけて行動へつなげる場を目指します。
親から子に伝わる、無意識のバイアス

メンバーから一言
私たちが今回取り組むテーマは「キャリア教育」です。これまで、キャリア教育を、海外の教育格差や、グローバル教育など、さまざまな視点から考えてきました。その中で私たちは、「自分のやりたいことに合った進路選択ができていない」「消極的な理由で進路を決めてしまっている」学生がいるという問題に注目し、その背景の一つに“親の影響”があるのではないかと考えました。
親御さんが無意識のうちに与えてしまっているかもしれないバイアスや考えは子供に大きく影響を及ぼしていると思い、それらを親御さんが認知することを目的とし、そのバイアスや考えが生まれた背景や自身の原体験を振り返ってもらうワークショップを行う予定です。

真の豊かさを考えるために

メンバーから一言
途上国開発、教育、環境問題に興味のある3人が集まったこのチームでは、“真の豊かさ“というテーマについて議論を重ねてきました。
メンバー全員が重視している問題は、人々の物質的充足の目的化により自然環境の破壊や心身の充足感の薄れが引き起こされている現代社会の状況です。物質的な充足に加えて、自然環境の充足や心身の充足感により幸せを感じられる人が増えていくためには、個々人が多様な豊かさの軸に気づいて行動を見直し、改善できるようになる過程が必要ではないかと考えるようになりました。
その第一歩として、“豊かさの価値観“の見直しと行動変容を促せるようなオンラインコンテンツの作成・発信を構想中です。
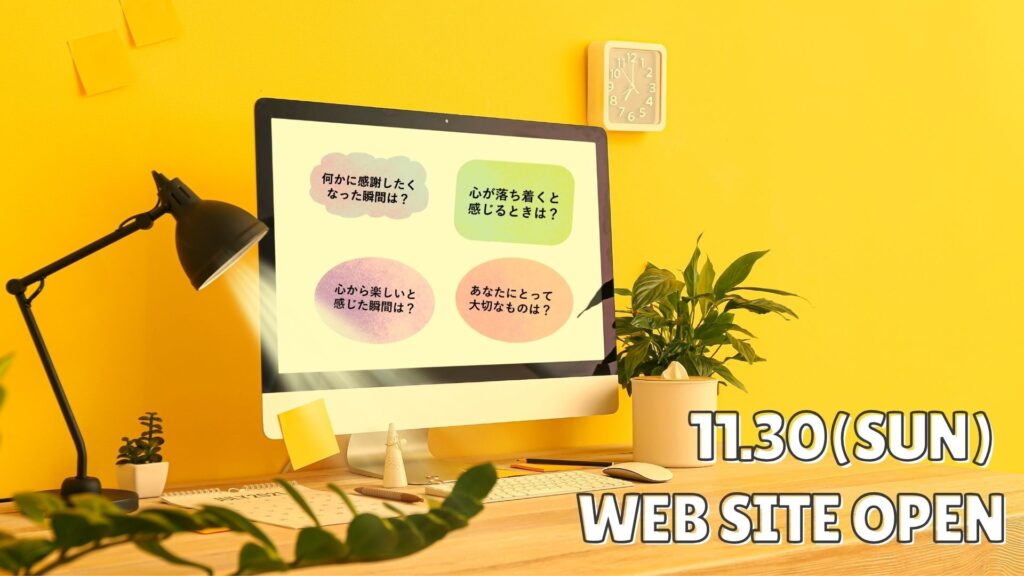
各チームの最新情報や詳細については、nestの公式instagramで確認できる。若きチェンジメーカーたちの「クエスト」に注目してほしい。
横田 伸治(よこた・しんじ)
サステナブル・ブランド ジャパン編集局 デスク・記者
東京都練馬区出身。毎日新聞社記者、認定NPO法人カタリバ職員を経て、現職。 関心領域は子どもの権利、若者の居場所づくり・社会参画、まちづくりなど。
















