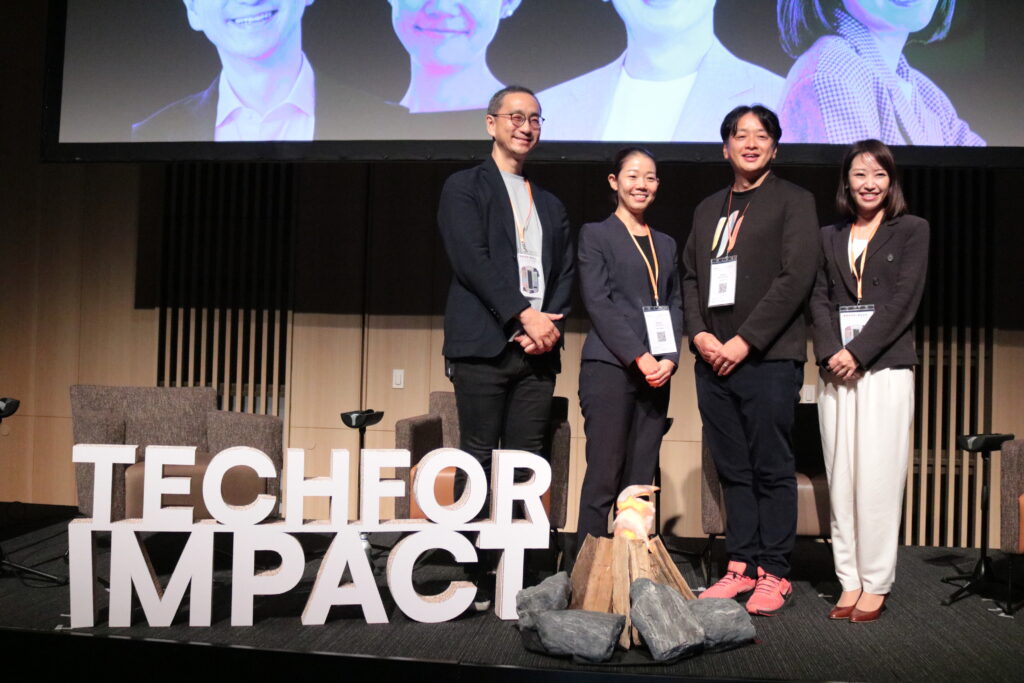
社会が直面する課題が複雑化・巨大化する一方で、国家による公的支援や従来の寄付モデルだけでは限界が見え始めている。年間4兆ドルとされるSDGsの資金ギャップは、その象徴だ。こうした中、社会貢献活動を活性化させるための新たな資金の流れをいかに生み出すか、世界的な模索が続いている。
このほど行われた「Tech for Impact Summit 2025」では、このテーマを深掘りする2つのセッションがあった。一つは、ブロックチェーンが自律的に生み出す財源をSDGs達成のために活用しようというグローバルな潮流。もう一つは、日本の寄付文化をアップデートし、「社会への投資」という新たな価値観を根付かせようという国内の動きだ。
両者に共通するのは、テクノロジー、新しい金融・経済の仕組みを駆使し、社会課題解決の担い手たちへ、より効果的で大きなインパクトを生む資金を届けようという意志だ。2つのセッションを振り返り、社会貢献を加速させる「フィランソロピー」(社会貢献活動に対する寄付や投融資)の未来を探る。
ブロックチェーンの巨大財源を「投票で活用」
「ブロックチェーンの財源でSDGsを拡大する」と題したセッションでは、ブロックチェーン「カルダノ」の開発を担うスイスの非営利団体「カルダノ財団」で、サステナビリティとイノベーションを率いるアレクサンドル・マーザ氏が登壇。ブロックチェーン技術が社会・環境課題解決の新たな資金源となる可能性について力強く語った。
マーザ氏はまず、SDGs達成に必要な資金が年間約4兆ドル不足しているという厳しい現実を提示。さらに、国連機関への資金提供も減少傾向にあり、資金ギャップだけでなく「オペレーションのギャップ」も拡大していると警鐘を鳴らす。
こうした状況の中でマーザ氏は、ブロックチェーンが果たせる役割として「オンチェーン・トレジャリー(ブロックチェーン上の金庫)」を挙げた。カルダノは、ネットワーク上で取引が行われるたびに手数料の一部がこの「金庫」に蓄積される仕組みを持つ。現在その残高は約14億ドルに上り、国家の基金にも近い財源を形成している。

この資金の使い道は、カルダノのトークン保有者による投票によって民主的に決定される。マーザ氏によれば、2022年から現在までに、この制度を通じて約1億5000万ドルが拠出され、そのうち約1000万ドルは150以上のSDGs関連プロジェクトに直接投じられたという。
国連開発計画(UNDP)との連携も進んでおり、カルダノが資金を拠出する形で「SDGブロックチェーン・アクセラレーター」を共同設立。世界中の課題とブロックチェーン技術を持つソリューションのマッチングを進めている。マーザ氏は「『金庫』は、持続可能な未来を支える新しい公的資金の形になる。ブロックチェーンの採用を広げるだけでなく、より良い社会の実現にも貢献できる」と講演を締めくくった。
日本の寄付文化は変えられるか?
テクノロジーが社会課題解決の新たな資金源となり得る一方、人々の寄付に対する意識や文化そのものも変革が求められている。セッション「日本の寄付文化は変えられるか?」では、日本のフィランソロピー業界をけん引する4氏が登壇。寄付を「かわいそうな人への施し」から「未来をつくるための投資」へと捉え直す、白熱した議論の模様を抜粋する。

| 【ファシリテーター】 鵜尾雅隆・日本ファンドレイジング協会代表理事 【登壇者】 小山有沙・ビル&メリンダ・ゲイツ財団 日本常駐代表 山本正喜・kubell代表取締役CEO 米良はるか・READYFOR代表取締役CEO |
鵜尾氏: まず、皆さんの自己紹介と、寄付にまつわる原体験をお聞かせください。
小山氏: ゲイツ財団では、世界中の人々が健康で生産的な生活を送れるように支援する活動をしています。私の寄付の原体験は、小学生の時に生徒会で赤い羽根募金を主催したことです。自分の持っているものを社会の大きなミッションにつなげる感覚を初めて覚えました。
大学院時代には、フィランソロピストが作った財団の理事として、NPOへの助成金配分評価などにも関わりました。さまざまな経験を経て、今、フィランソロピーのど真ん中で働いています。
山本氏: 正直に言うと、上場するまで寄付には全く興味がありませんでした。考えが変わったきっかけはエンジェル投資です。リスクを取って未来をつくろうとする起業家を応援する中で、「これと同じ感覚で応援できる社会貢献活動があるのではないか」と感じ始めました。
その後、政策提言を行うNPOに「政策のベンチャーキャピタル」のような形で寄付をする機会があり、社会を変えようと奮闘する人々の存在を知りました。これはまさに投資だと。そこから、同じ志を持つ上場企業の経営者たちと「フィランソロピー・サミット」を立ち上げるなど、仲間を巻き込みながら活動を広げています。

米良氏: 14年前、大学院在学中にクラウドファンディング「READYFOR」を創業しました。私にとっての大きな原体験は、29歳の時に悪性リンパ腫というがんにかかったことです。幸い標準治療で回復できましたが、一時は希少疾患の可能性も告げられました。その時、マーケットが小さいという理由で治療薬開発が進まない現実を知り、クラウドファンディングを通じて、こうした課題を解決したいと強く思いました。
クラウドファンディングの良さは、自分が見たい未来、手に入れたい社会を、自分の手で実現するために直接参加できる「手触り感」です。寄付は単なる施しではなく、自分にとって必要な社会を手に入れるための手段なのだと、自らの体験を通して実感しています。
寄付の概念を「社会への投資」へアップデート
鵜尾氏: 日本の寄付の現状と可能性をどう見ていますか?
山本氏: 日本の上場企業経営者は、エンジェル投資には積極的ですが、寄付となると途端に及び腰になります。リターンが金銭でないため「全損」という感覚が強い。でも、僕は寄付を「社会への投資」だと捉えています。
特に、政策提言のように一つのアクションが社会の仕組みを変え、何倍もの効果を生む「レバレッジ」が効く領域への寄付は、非常に投資対効果が高い。事業家は、自分がやる意味、つまりレバレッジを実感できれば動きます。エンジェル投資で原石を見つけて自慢できるように、NPO支援でも「あの団体を初期から支えた」という支援者が評価される文化が生まれれば、事業家の参画はもっと増えるはずです。
米良氏: まさに「社会への投資」という視点は重要です。社会課題が複雑化し、ベンチャーキャピタルが求める10年といった時間軸では解決できない問題が増えています。そうした領域には、リターンを求めない「Patient Capital(忍耐強い資本)」としての寄付が不可欠です。資本主義の枠組みではカバーしきれない領域に、長期的な視点で資金を投じる手段として寄付を捉える必要があります。

小山氏: アメリカを拠点とする財団から見ても、日本の文化に根差した寄付の形を考える必要性を感じます。お二人の話を聞いて確信しましたが、寄付を「資本の流れの中で最もリスク許容度が高い、スタート地点にある投資」と位置付ける考え方は、日本の皆さんにも受け入れられやすいのではないでしょうか。
誰かの課題解決を支援するだけでなく、そのインパクトや手触り感を重視するアプローチが、日本でフィランソロピーを根付かせる鍵だと思います。
変革の鍵は「エコシステムの構築」
鵜尾氏: では、日本の寄付文化を変革するための具体的な鍵は何でしょうか。
山本氏: 「拡大再生産するエコシステム」を作ることです。25年前、起業家はアウトローの集まりでしたが、今やスタートアップは国策となり、成功した起業家がエンジェル投資家となって次の世代を育てる循環が生まれています。
NPOやソーシャルセクターも、まさに初期のスタートアップ業界に雰囲気が似ています。志はあっても、資金も情報も仲間も足りない。ここに、スタートアップ・エコシステムと同じように、成功者が次の担い手を支え、それがまた循環していく仕組みを構築することができれば、大きく変わるはずです。
米良氏: そのためには、寄付の「商品設計」を磨く必要があります。山本さんのような方が求めるレバレッジ型の寄付もあれば、私のクラウドファンディングのように共感やコミュニティを軸にした寄付もある。寄付の出し手の多様なニーズに応える設計が重要です。
同時にNPO側も進化が必要で、目の前の人を救いたいという尊い動機から一歩進んで、「何を解決するために、いくらの資金で、どう社会を変化させるのか」という目標設計や事業計画を磨く必要があります。事業家の知見を借りながら、課題解決への道筋を明確にすることで、もっと大きな資金が流れ込むようになるはずです。
鵜尾氏: ありがとうございました。テクノロジーによる新たな資金創出と、投資マインドを持った担い手の増加。この2つの潮流が交わる時、日本の寄付文化は、そして社会課題解決のスピードは、飛躍的に進化するのではないでしょうか。
横田 伸治(よこた・しんじ)
サステナブル・ブランド ジャパン編集局 デスク・記者
東京都練馬区出身。毎日新聞社記者、認定NPO法人カタリバ職員を経て、現職。 関心領域は子どもの権利、若者の居場所づくり・社会参画、まちづくりなど。









