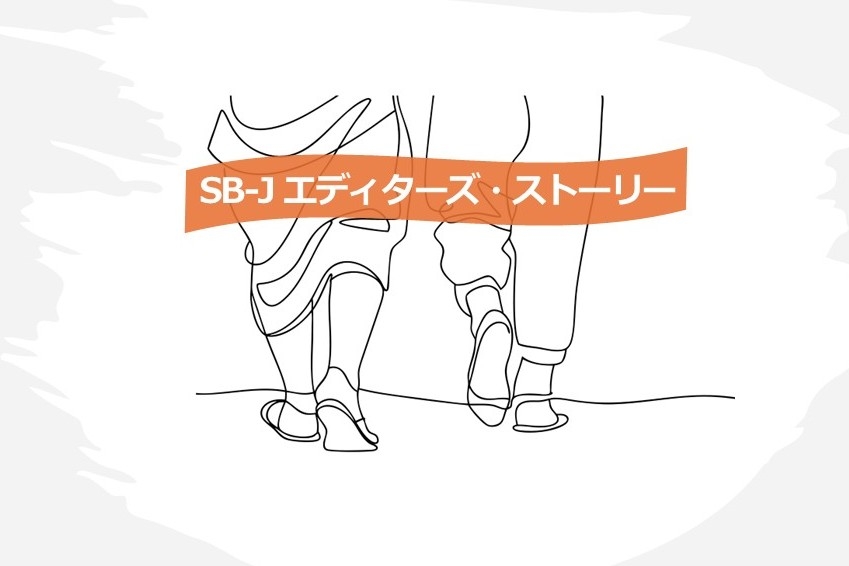
取材現場で心を動かされた言葉、記事にはならなかった小さな発見、そして、日常の中でふと感じたサステナビリティのヒント。本コラムでは、編集局メンバーの目を通したそんな「ストーリー」を、少し肩の力を抜いて、ゆるやかにつづっていきます。
今回の担当は山口です。

北海道で、クリエイティブな未来を創造する4日間
サステナブル・ブランド ジャパン インターンの山口です。今回は、北海道・札幌で開催された「NoMaps2025」について書いていこうと思います。
「NoMaps」とは、2016年にスタートしてから毎年開催されている、クリエイティブな発想や技術のための枠組み。世代や業種は関係なく、民間企業・官公庁・教育機関などが連携し、さまざまなカンファレンスやイベント、交流の場が提供されます。
イベントのカテゴリーも多様で、16種類に分かれています。カテゴリーの1つにある「TECH」では生成AIを使ったバトルゲームが体験できたり、「SPORTS」では札幌南高校ダンス部のダンスワークショップを受けられたり。どの日も見どころが盛りだくさんで、カメラスタッフの方々が走り回る様子もSNSに掲載されていました。
このうち、教育の未来を考える「EDU」は、文科省の担当者から高校生まで、教育に関わる多様な人が集まり、これからの教育について考えるプログラムです。 私は今回、その中のセッション「高校での探究的な学びを踏まえた、これからの大学生活の在り方を考える」に、現役大学生ゲストとして参加しました。

学生が地域食材で作ったお弁当に感動
札幌に到着したのは9月13日、土曜日の朝。残暑の東京と違う、心地よい風を感じながら向かったのは、NoMaps内のカテゴリー「Food」のセッションです。
参加したのは、「未来の一膳 by さっぽろフードクリエーションズ」。学生たちが、ほたてや今金男しゃくなど北海道が誇るブランド食材を使った料理を開発。参加者は学生たちが開発したお弁当を食べられるほか、学生自らのプレゼンテーションや生産者・関係者とのディスカッションが行われました。
最初は「無料でお昼が食べられる!」という言葉に乗せられて参加したセッションでしたが、同世代の学生たちが地域や食について深く考え、料理や言葉として表現する様子にとても感動しました。生産者からのうれしい言葉もその場で聞くことができ、多様な人々が密に連携し地域を豊かにする様子がとても新鮮で、いただいたお弁当も最高においしく感じました。

海外大学にいながら、日本で過ごす意味
おいしいお昼ご飯で幸せになった後は、いよいよセッション本番。
一緒にお話しさせていただいたのは、ZEN大学の社会連携プログラムを担当する出雲路敬行さんと、「さとのば大学」を経営するアスノオト取締役の黒井理恵さん。モデレーターを務めてくださったのは、コエルワ共同代表COOの嶋本勇介さんでした。
ZEN大学もさとのば大学も、いわゆる「ちょっと変わった学校」。デジタル技術を活用してオンラインを中心に学んだり、日本中を回りながらの大学生活を送ったりします。私が通う「ミネルバ大学」と似つつも少しずつ違う学校で、教育者として携わる方々と話せることにワクワクを感じていました。
事前ミーティングの時に話題に上がっていた「日本で学ぶ意味とは?」という問い。偶然、直前のセッションでも学生から挙がり、本番のセッション中にも議論されたこの質問が印象に残っています。
ミネルバ大学は、アメリカをはじめ、アルゼンチンやドイツ、インドなどに拠点を持っており、半年ごとに滞在する国を変えながら、学生生活を送ります。今年は初めて日本が拠点として立ちあがり、現在は東京で過ごしている身として、「海外大学生として、日本で学ぶ意味はどこにあるんだろう」と、個人的にもよく考えるようになった問いでした。
特に印象に残っているのは、さとのば大学の黒井さんがおっしゃっていたこと。「日本の強みは、自然と精神性をどちらも兼ね合わせているところ。自然災害が多い日本だからこそ、自然を尊敬する気持ちや、共に生きる精神性が育まれる」というコメントに、強く共感しました。
確かに、東京での学生生活が始まって、大学で最初に教わったのは、日本が持つ「禅」の考え方についてでした。自然災害とともに発達した農業や建築の技術について学んだり、お寺に1泊して住職の方にお話を聞いたり。「自然と共存する」「共に生きる」という考えは、これからのサステナビリティはもちろん、多様な人々や環境と生きていく上で重要な一つになると思うのです。

そして、それを学ぶ形もさまざま。ミネルバ大学のように、世界の多様な人々を身近に巻き込みながら学ぶ方法や、さとのば大学やZEN大学のように、日本国内の様々な地域や団体と連携して理解を深める方法。どの道も、すごく魅力的で、これからキャリアや自分軸を築く学生にとって、とても有意義な経験になると思います。
改めて考える「日本」にいる価値
私は正直、米国の大学に在籍しながら日本で学ぶことに当初「もったいなさ」を感じていました。日本の住み慣れた環境より、新しい生活や場所を経験したいという気持ちがあったのも事実です。ですが、このセッションを通して、「あえて日本で学ぶからこそ改めて気付ける日本の魅力や未来があるのでは?」と期待がさらに大きくなりました。
これからも、今ある自然、環境に感謝しながら、共に生きる心を持って歩みを進めること。
この気づきを忘れぬよう、常に「日本」の価値を、日本人としても、時にはミネルバでの学びを通した客観的な目線でも、考えていきたいです。
山口 笑愛(やまぐち・えな)
サステナブル・ブランド ジャパン編集局 インターン
ミネルバ大学在籍中。ユースコミュニティ「nest」に参加したのがきっかけで、高校1年生からSBに関わる。今はファッションと教育を主軸に、商品制作、メディア、イベント企画を通して発信活動中。















