
2030年までに「ネイチャーポジティブ」を達成する世界目標に向け、失われた自然を積極的に増やす、担い手としての企業の役割が注目されている。生態系の劣化は災害の激甚化に密接に関わり、グリーンインフラを増やしていくことはレジリエントな社会を構築していく上でも欠かせない視点だ。本セッションでは「企業が拓(ひら)く生態系再生の時代」をテーマに、国内で先進的に取り組む2社と、環境NGOによるグローバルな事例の紹介を通して、そのビジネスとしての可能性と、現状の課題について議論がなされた。
| DAY2 ブレイクアウト ファシリテーター 足立直樹・SB国際会議サステナビリティ・プロデューサー パネリスト 井阪由紀・積水ハウス ESG経営推進本部 環境推進部 環境推進部長 兼 環境マネジメント室長 浦嶋裕子・MS&ADインシュアランス グループホールディングス サステナビリティ推進部 上席スペシャリスト 東梅貞義・公益財団法人世界自然保護基金ジャパン 事務局長 |
2000万本の「5本の樹」効果を検証——積水ハウス
積水ハウスは2001年から、住宅建築時に地域の気候や風土に合った在来樹種を庭木として植栽する造園事業を行ってきた。「3本は鳥のために、2本は蝶(ちょう)のために」という意味合いを込めた「『5本の樹』計画」で、これまでの累積植栽本数は2000万本を超える。
その膨大なデータから2021年、琉球大学発のスタートアップ企業と共同で、各地域での樹木と生態系の相関関係を数値化し、生物多様性保全活動の効果を定量評価できる仕組みを構築。さらに東京大学との共同研究で、生物多様性の豊かな庭が人間のウェルビーイング向上に果たす効果の検証を進め、うつ症状を発症するリスクが減ったり、環境への意識が高まったりするといった傾向が分かってきているという。

同社の井阪由紀氏は、「5本の樹」計画がここまで広がったことを「住まう方の幸せと、生き物が自然に増えていくことがうまく合わさったからだと思う」と表現。今後は、植栽の組み合わせによってどんな生物多様性が生まれるかを可視化するツールの活用などを通じて、「企業としての生物多様性への取り組みと、お客さまに提供するサービスとの間をつなぎ、ストーリーを設計していくことが重要になる」と語った。
自然資本の回復とレジリエンス強化に注力——MS&AD

MS&ADインシュアランスグループホールディングスの浦嶋裕子氏は、2013年度に約500億ドルだった自然災害による世界の保険損害金が2023年には1000億ドルを超えるなど、保険業界が直面する自然災害リスクの増大に言及。各地で激甚化している自然災害は「自然のもたらす、生態系サービスの劣化が密接に関わっている」という考えから、自然資本の回復とレジリエンス強化を両立させる「グリーンアースプロジェクト」に注力していることが紹介された。
具体的には、2020年7月の豪雨で甚大な被害が発生した熊本県球磨川流域での湿地の復元や、千葉県印旛沼流域での谷津の保全などに取り組み、研究機関との連携も両エリアで進めている。千葉では国立環境研究所などの知見を得ながら、「開発と環境をどう共存させるか」という視点に立った議論を進める。半導体関連産業の集積が進む熊本では、地元の肥後銀行や熊本大学、熊本県立大学などと連携し、グリーンインフラによって地下水を保全しながら、地域の経済を回す新たな仕組みづくりを構想中という。
浦嶋氏は企業の生物多様性への取り組みが本格化していくかどうかについて、「公益と私益のバランスをどう組み合わせていくのか、世界的にもまだ分かりやすい解がない。1社では賄いきれないコストを社会がどう分担していくかが最大の課題だ」と述べた。
洪水の教訓から始まったパキスタンの事業とは——WWF
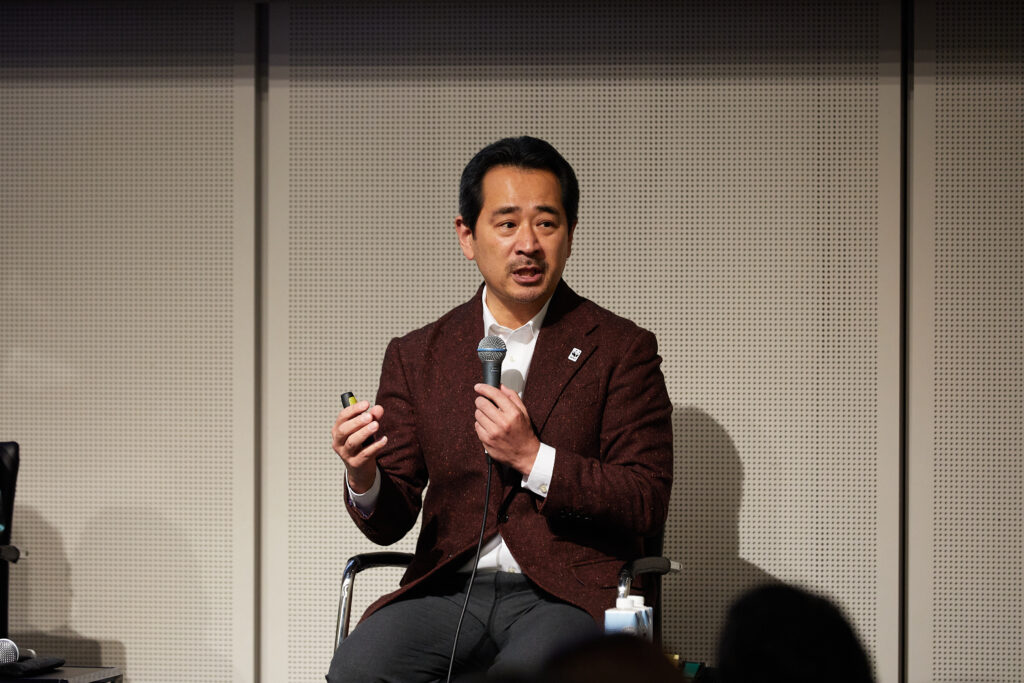
WWF(世界自然保護基金)ジャパンの東梅貞義氏は、ネイチャーポジティブの実現に向けた世界の潮流を、自然を生かした社会課題解決「ネイチャーベースドソリューション」の実践例などに基づいて解説。この中で、2023年にパキスタンのインダス川流域で約3300万人が被災した大洪水を教訓に、パキスタン政府が進める「リチャージパキスタン」プロジェクトの詳細を語った。
プロジェクトは、インダス川流域の約1万4200ヘクタールにも広がる森林と湿地を再生し、今後起きる水害に計画的に備えるもので、約7年をかけて取り組む。開発途上国の温室効果ガス削減と、気候変動の影響への対処を支援する「グリーンクライメート・ファンド(GCF、緑の気候基金)」による約120億円の拠出も決まっているという。
東梅氏は、このプロジェクトが「国の防災基本計画に取り入れる目的」で行われると同時に、「流域で農業や養殖業を行う人たちの生計の向上にもつなげる」計画とされている点を高く評価。「これは政府のプロジェクトであり、公共調達だ。世界で災害リスクが高まる中、将来的に、同様のアプローチが日本やアジアの各地で取り入れられた時、企業にとってのビジネスチャンスにもなるのではないか」と会場に呼びかけた。
課題は顧客への伝え方と財源調達
後半のクロストークは、ファシリテーターの足立直樹氏が「近い将来、生態系再生と地域の恩恵の両立を目指す取り組みの費用対効果が証明されるのではないか」と提起することから始まった。「企業と投資家がタッグを組みながら実証するステージに入っている」とする東梅氏の見方を受けたものだ。

これに対しMS&ADの浦嶋氏は「例えば、透水性の高い道路を作れば、水の流出をこれだけ抑制でき、水災を防ぐことができるといったことが定量化できれば、それは単なるグリーンボンドではなく、インパクトボンド(の投資対象)になっていく」と、価値を可視化することで資金の流れをも変えていく可能性を指摘。
一方、東梅氏は「世界中で認証された森林や魚が増えても、その商品を選んで買う人は自動的には増えないと感じている」とした上で、「顧客にとっての価値は何かを見定めるプロセスが社会にないと、(仕組みとの間に)ギャップが生じる。効果を提示するだけでなく、住民がその価値を実感できるところまで持っていけるかどうかが鍵」と述べた。
積水ハウスの井阪氏も、「5本の樹」計画は「環境に良いから」広がったのではなく、家や土地に合った庭木を提案したことが結果的に生物多様性保全につながったものだとして、「それぞれの顧客にとって実質的にどういうメリットがあるかを、ストーリーにして伝えることでうまく流れをつくっていけるのでは」と話した。
最後は、足立氏が「企業は、生態系を壊さないようにするというだけでなく、今まで以上に生態系を増やしていくことに直接関わっていける」と強調。さらに「日本でも、グリーンインフラが公共調達として予算がつけば、大きなマーケットになる。企業とNGOが一緒に、投資家にも声をかけて取り組んでいくのが良いのではないか」と国の方向性についても示唆する形でセッションを終えた。
世界目標である2030年のネイチャーポジティブ達成に向け、日本企業がビジネスチャンスをものにすることができるかどうかが今、問われている——。
廣末 智子(ひろすえ・ともこ)
地方紙の記者として21年間、地域の生活に根差した取材活動を行う。2011年に退職し、フリーを経て、2022年から2025年までサステナブル・ブランド ジャパン編集局でデスク兼記者を務めた。
















