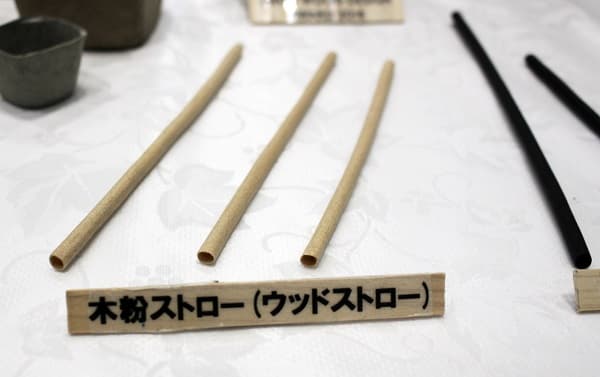プラスチックごみは今や世界中の喫緊の課題だ。現行のリサイクル手法は多大なエネルギーと化学薬品を要するなど問題が多いため、新しいリサイクル技術が求められている。そこで、米国の2大学が先ごろ発表したリサイクル新技術に関する研究論文を2回に渡って紹介しよう。1回目は、身近なプラスチックPETを空気中の水分で分解してモノマーに変換するという、米ノースウェスタン大学の新技術だ。(翻訳・編集=遠藤康子)

ノースウェスタン大学の化学者チームが先ごろ、最も普及しているプラスチックPET(ポリエチレンテレフタレート)の廃棄物を分解する技術を新たに開発した。空気中に含まれる水分を利用する手法で、毒性がなく、資源効率に優れ、溶剤は不要である。
同大チームが開発した新技術は至ってシンプルだ。PETの化学結合を安価な触媒を用いて分解し、ただ空気にさらす。すると、空気中に含まれるごく微量の水分の働きで、分解されたPETがモノマー(単量体。プラスチックを構成する最小単位の重要な物質)に変換されるという。このモノマーを再利用すれば、新たなPET製品や、より価値のある他素材を生産できるのではないかと研究者は期待している。
PETごみをアップサイクルできる実用的技術
2025年2月に化学系ジャーナル『グリーンケミストリー』で発表された研究論文によると、このプラスチックリサイクルの新技術は現行手法より安全性と持続可能性に優れ、よりクリーンでより安いため、プラスチックの循環型経済の実現に大きく近づくことができる。
「米国は1人当たりのプラスチック廃棄量が世界最大です。ところが、リサイクルされている割合は5%にすぎません」と話すのは、同論文の共同責任著者で、ノースウェスタン大学ウェインバーグ人文科学カレッジの化学研究助教ヨシ・クラティッシュ氏だ。
「各種プラスチックの廃棄物を処理できる、より高度な技術が今すぐ必要です。現行の処理法はペットボトルを溶解して質の劣る製品へとダウンサイクルするものばかりですから。今回の研究が特に有望なのは、空気中に含まれる水分を使ってプラスチックを分解するという、格段にクリーンで対象を絞り込んだプロセスが可能である点です。PETを構成する基本物質のモノマーを取り出せば、リサイクルできるばかりか、価値のより高い素材にアップサイクルすることも可能になります」
「私たちがこの研究で開発したのは、プラスチック廃棄物という最も急を要する環境課題の1つを持続可能かつ効率的なやり方で解決できる技術です」。論文筆頭著者ナビーン・マリク氏はそう語る。「従来のリサイクル手法は廃棄塩といった有害な副産物が発生することが多い上に、大量のエネルギーと化学物質が必要です。これに対し、私たちが開発した手法は溶剤の代わりに空気中に含まれる微量の水分を利用します。環境に優しいだけでなく、現場でも応用可能な非常に実用的手法でもあるわけです」
研究論文の共同責任著者には、マリク氏とクラティッシュ氏に加え、同大教授のトビン・J・マークス氏が名を連ねる。研究実施時、マークス氏率いる研究グループに所属するポスドク特別研究員だったマリク氏は現在、インドにあるSRM理工科大学の研究助教だ。
PETリサイクルに伴う難点
PETは食品パッケージや飲料ボトルなどに用いられている一般的なプラスチックで、全世界に出回っているプラスチックの12%を占めている。難分解性であるため、プラスチック汚染の大きな要因だ。使用後は、埋立地行きになるか、時間とともに細かくなってマイクロプラスチック(直径5mm未満)やナノプラスチック(直径1マイクロメートル未満)となり、その多くは河川や水路に流れ着く。
研究者にとって、プラスチックの新しいリサイクル手法を解明することは一大関心事だ。現行の手法では、プラスチックの分解時に何かと問題が付きまとう。例えば、高温燃焼や溶剤には大量のエネルギーが必要で、有害な副産物も発生する。化学反応用の触媒(例 : プラチナとパラディウム)はたいてい高価であったり毒性を有したりして、さらに有害な廃棄物も発生する。後工程ではリサイクル素材と溶剤を分離しなければならず、そのプロセスもまた多大な時間とエネルギーを要する。
マークス氏率いるノースウェスタン大学研究グループは以前にも、溶剤を使用しない触媒工程の開発に初めて成功している。そして、この度の新研究で考案したのも溶剤を使わないプロセスだ。
「溶剤を使用する工程には欠点が多数あります」とクラティッシュ氏は話す。「溶剤は高価で、高温まで熱する必要があります。その後、化学反応が起きると材料が入り混じった液体となるので、そこからモノマーを選別して取り出さなくてはなりません。そこで私たちは、溶剤を使わず、空気中に含まれる水蒸気を利用することにしました。この方がずっと洗練された方法でプラスチックのリサイクル問題に対処できます」
「洗練された」リサイクル手法
この新しい手法を実施するに当たって研究チームが用いたのは、触媒作用を持つモリブデンと活性炭だ。いずれも豊富に存在するので安く入手でき、毒性もない。工程ではまず、化学結合でつながった高分子化合物のPETを触媒ならびに活性炭と混ぜて熱した結果、化学結合がすぐに分解された。
研究チームは次に、分解された物質を空気にさらした。すると、空気中に含まれているごく微量の水分によって、物質はテレフタル酸(貴重なポリエステルの前駆体)へと変化した。この過程で生じた副産物はアセトアルデヒドという、除去が容易で有用な工業用薬品だ。
「空気は多くの水分を含んでおり、どこにでもあり、化学反応に使える持続可能な資源です」とマリク氏は話す。「比較的乾燥した環境でも、大気中には平均して約1万から1万5000立方キロメートルの水分が含まれています。大気中の水分の力を借りることで、大量の溶剤と強度の化学薬品を使わず、エネルギー投入量を減らすことができました。こうして、よりクリーンで環境に優しいプロセスが実現したのです」
「余分な水を追加したら反応が止まってしまいました。とても微妙なバランスで成り立っているプロセスなのです」とクラティッシュ氏は話す。「空気中に含まれる水分量が最適だということです」
リサイクルに伴う複数の問題を解決
こうしてたどり着いた手法は時間がかからず効果的で、テレフタル酸の潜在的含有量の94%をわずか4時間で回収することができた。また、触媒は耐久性があって再利用もでき、繰り返し使用しても効力は失われない。この手法は合成プラスチックにも有効で、ポリエステルのみを抜き出してリサイクルすることができる。回収対象を絞り込めるので、触媒の使用前にプラスチックを選別する作業は不要だ。これはリサイクル業界にとって大きな経済的利点となる。
研究チームは、プラスチックボトルやシャツ、合成プラスチック廃棄物など実際のプラスチック素材でこの工程を試し、同様に効果があることを証明した。着色されたプラスチックでも、純粋で無色透明なテレフタル酸に分解されたという。
研究チームは、産業利用に向けて工程の規模拡大を計画している。大規模な用途向けに工程を最適化し、大量のプラスチックごみを処理できるようにするのが目標だ。
「私たちが開発した技術は、プラスチック汚染を大幅に減らし、プラスチックの環境フットプリントを低減し、循環型経済への歩みを後押しする可能性があります。素材を捨てずに再利用する循環型の未来がかなうかもしれません」とマリク氏は話す。「この技術は、よりクリーンな未来に向けた具体的な一歩であり、革新的化学と自然が足並みをそろえた形で世界的課題に立ち向かえる証しでもあります」
第2回では、同じく一般的なプラスチックである高密度ポリエチレンのリサイクルを促進する先端的な機械学習モデルを紹介する。