
地方創生とウェルビーイングを軸に、地域社会の持続可能な発展と幸福を追求するコミュニティ・プラットフォーム「未来まちづくりフォーラム」。7回目を迎えた今回は、「ポストSDGs時代の稼ぐ力と新たな価値創造」をテーマに、「サステナブル・ブランド国際会議2025東京・丸の内」と同時開催された。
フォーラムの幕開けを飾ったオープニング・トークやキーノート・トークでは、山梨県や岡山市が取り組む先進的な事例が紹介されたほか、京都先端科学大学・名和高司教授による「エシックス経営」にまつわる講演などがあった。地域資源を生かした持続可能なビジネスモデルを構築し、地域社会の経済的自立や成長を実現するためのヒントを探った。
| オープニング・トーク 岸田里佳子・内閣府 地方創生推進事務局 内閣審議官 長崎幸太郎・山梨県 知事 キーノート・トーク 大森雅夫・岡山市 市長 笹谷秀光・未来まちづくりフォーラム 実行委員長 名和高司・京都先端科学大学教授 一橋大学ビジネススクール客員教授 |
「地方創生2.0」に向けて政府が協働を推進

フォーラムの冒頭、内閣府地方創生推進事務局の岸田里佳子内閣審議官が登壇。政府が設置している「地方創生SDGs官民連携プラットフォーム」を取り上げ、「既に7800を超える民間企業や地方自治体が参加し、SDGsを活用しながら地域の課題解決に取り組んでいる。国内で最大規模のプラットフォームで、政府としても引き続き力を入れていきたい」と強調。
続けて2025年1月、石破茂首相が国会の施政方針演説において「楽しい日本」を目指すと表明したことと、その政策の核心である「地方創生2.0」に言及。「政府は、『令和の日本列島改造』というキャッチフレーズのもと、『産官学金労言』※のステークホルダーの皆様と政策を磨き上げながら、地方創生を強力に推し進める」とし、「持続可能なまちづくりの実現に向けて多様な方が協働し、新たな価値を生み出す場である『まちづくりフォーラム』に敬意を表するとともに、このような取り組みが全国に広がることを期待している」と述べた。
※「産官学」に金融界、労働界、言論界(マスコミ)を加えたもの
国内外と連携し水素社会実現を目指す山梨県

山梨県の長崎幸太郎知事は、県が推進する水素社会の実現について講演。「脱炭素社会のキーテクノロジーは、CO2を排出しないグリーン水素技術に基づくエネルギーシステムの実現だ」と訴えた。
山梨県は、再生可能エネルギーの余剰電力で水素を製造し、貯蔵・利用する「Power to Gas(P2G)システム」を構築。長期間の貯蔵や輸送が可能な水素の特性を生かし、再生可能エネルギーの発電量安定化に資する技術として期待されている。製造されたグリーン水素は、地域のスーパーマーケットチェーンや東京ビッグサイトなどで熱源として使用されており、インド、スコットランドでも同システムの導入が進められているという。
こうした実績を踏まえ県は、「富士ハイドロジェンバレー・コンソーシアム」を組成。水素を燃料とする新しいモビリティ製造やカーボンフリー農業を目指すほか、水素社会のビジョン策定に意気込む。海外との連携も着々と進み、インドのウッタル・プラデーシュ州やブラジルのミナス・ジェライス州と連携協定を締結したほか、グローバル化に向けたコミュニティやシンクタンクを立ち上げ、国内外の機関との共同プロジェクト創出を目指しているという。
2026年3月には、富士五湖地域で「富士ハイドロジェン・サミット2026」が開催される。「持続可能な社会づくりは、どの国で誰が政権を取っても必要。山梨県はグリーン水素を活用し、世の中に貢献していきたい」と表明した。
岡山市の総合力をさらに高める教育の力

恵まれた自然環境と充実した交通網に加え、都市機能が集積し、暮らしやすいという岡山市。近年は、政令指定都市の中でも市内総生産や民間投資などの伸び率が高く、大森雅夫市長は「稼ぐ力が相当上がっている」と明かす。
経済的成長や子育て支援に力を入れるだけでなく、岡山市は10年以上前からESD (Education for Sustainable Development)=持続可能な開発のための教育に力を入れている。2014年には、ESDに関するユネスコ世界会議を日本で初めて開催。2015年には国内外の優れたESDの取り組みを顕彰する「ESD岡山アワード」を設立した。さらに2024年、OECDによる世界各国の首長ネットワーク「チャンピオンメイヤーズ」に大森市長が選出され、基調講演を行った。
2025年10月には、ESDに関する地域拠点(=RCE)の関係者が集まる「グローバルRCE会議」が、岡山市で開催される。2014年に続き2回目で、同一都市での複数開催は史上初だという。大森市長は、「世界を動かすのは人の力。誇りを持って岡山で、子どもも大人もネットワークを持ちながら、世界や社会に貢献する。そんな意識を持った都市にしていきたい」と展望を語った。
ポストSDGsに向けて、パルス的な取り組み脱却を
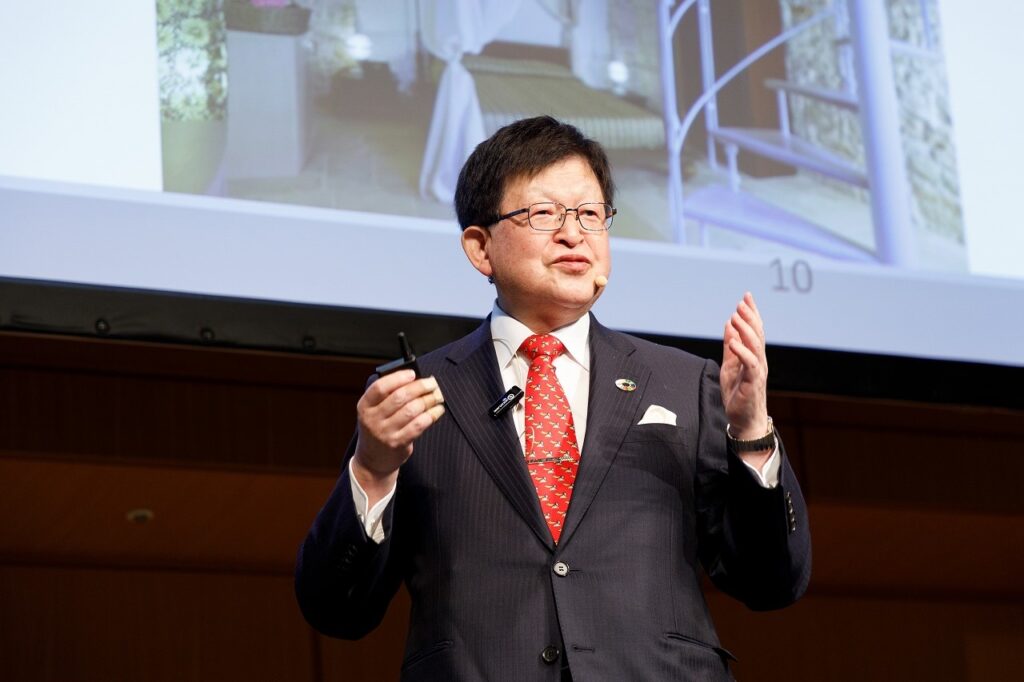
笹谷秀光・未来まちづくりフォーラム実行委員長は、「ポストSDGs時代のウェルビーイングと地方活性化」と題し講演。まちづくりの3つのポイントとして、①官民連携でその場所を特別だと感じさせる「センス・オブ・プレイス」、②経済・環境・社会の三位一体で「稼ぐ力」、③都市に対する誇りや愛着「シビック・プライド」を挙げ、このために連携・協働で新たな価値を生み出す「協創力」の重要性を語った。
日本政府によるSDGs 実施方針は2027年、最後の改定を迎える。笹谷氏は「日本は今年、国全体の進捗状況のまとめに入る。ポストSDGsの検討開始に合わせ、日本らしい提案が出せるよう、我々は加速して活動すべき。今からでも遅くはない」と明言した。そのために、取り組みを一時的な盛り上がり(=「パルス的」)にしないことや、取り組みの内容を発信する重要性を指摘。企業担当者の人事異動で取り組みが途切れてしまう仕組みにも危機感を募らせ、「CSRからCSVへの変化など、サステナビリティの全体像を頭に置いておかないといけない。また、ターゲット同士の結びつきや取り組みの担当部署を明らかにして、しっかり進めていかないといけない」と呼びかけた。
ポストSDGsに向けて、笹谷氏は最後に各ステークホルダーが活用・参照すべき機会や枠組みを挙げた。政府なら自発的国家レビューを、自治体はSDGs未来都市を、メディアはメディアコンパクトを、そして企業は「18番目の目標」である自由演技集を、自らの取り組みの推進力とすることができる。笹谷氏は「従来のSDGsターゲットに加え、ウェルビーイングの概念を取り入れていくこともポストSDGsには必要。本フォーラムを通じて、取り組みのヒントを見つけてほしい」と訴えた。
日本の強みを世界に届ける「エシックス経営」
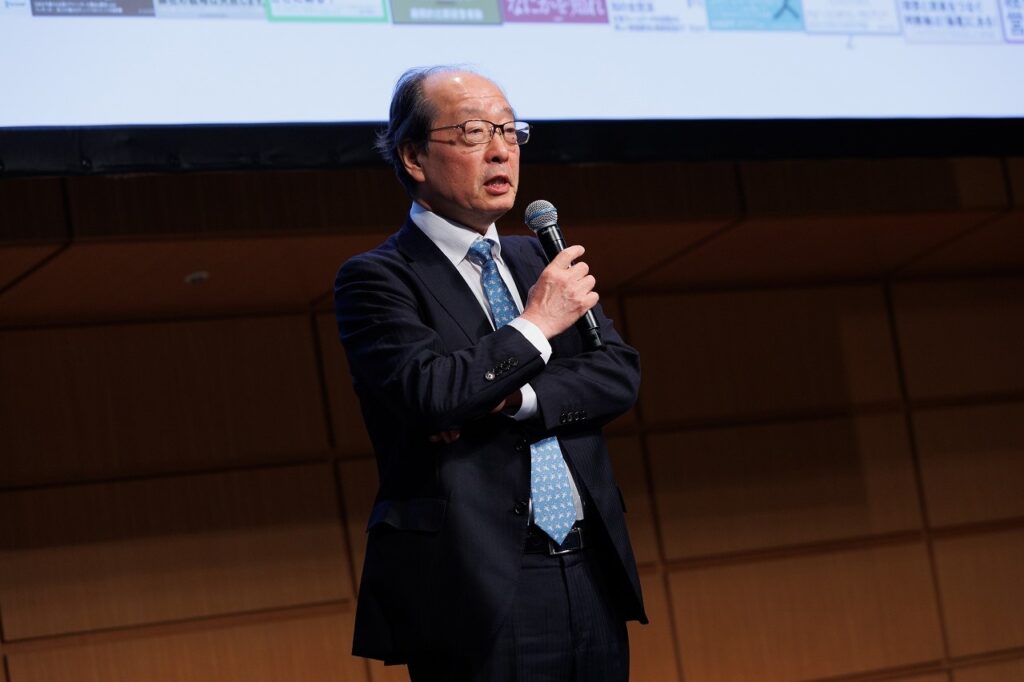
一橋大学ビジネススクール客員教授の名和高司氏は、「エシックス(倫理)」の視点から経営にまつわるトークを展開。「悪いことをしない制度」であるコンプライアンスではなく、「良いことをする態度」で企業の在り方を考えることがエシックス経営だといい、「マネタイズにとらわれず、倫理観が人々に根づいている日本は『倫理資本主義』のメッカだ」と主張した。
以前は「パーパス」をキーワードに企業経営を分析してきたという名和氏だが、「きれいごとだけでなく、社員一人ひとりが自分ごととして実践しなければ意味がない」と「パーパスからプラクティスへ」の転換を訴えた。名和氏は「ありたい姿」であるパーパス、「やるべきこと」であるプラクティス、行動原理である「プリンシプル」を置く「エシックス経営のシン三位一体」の図を披露し、これらの根底にエシックスがあるべきだと説明した。プリンシプルを明確にしている例としては、「京セラフィロソフィ」とウォルトディズニーの「THE 5 KEYS」を挙げ、「プリンシプルを明確な言葉に落とし込み、社員に浸透させ、行動の優先順位を判断する基準とすることが重要だ」と補足した。
また名和氏は、「シン日本流」経営という概念を提唱。異質性を軸に、個を重視する欧米流や、同質性が高かった従来の日本流とは異なり、異質なものが異質なままで共存する価値観だ。名和氏は「お互いを敬い、インクルーシブに交わることが日本は得意なはず。この日本的な精神を世界に発信して、新しい資本主義の形、『和』を構築していけるのではないか」と未来への希望を示した。
清家 直子(せいけ・なおこ)















