|
参加者はJAMSTECで無人探査機を見せていただいた
|
23人の高校生が“異分野融合”の視点で研究を行うプログラム「IHRP(Interdisciplinary High School Research Program)2024」は、8月にキックオフキャンプを終えました。その後3ヶ月間はインプット期としています。今期のテーマである「巡り、繋がる、地球のいろ。」に関連したさまざまな分野の研究者や専門家の先生方のご協力のもと、各大学の研究室に配属させていただくなどして学びを深めてきました。また今年度のプログラムでは、昨年度とは異なり、コミュニティを意識したプログラムにしているため、対面で交流できる機会として、11月に対面でのワークショップを開催しました。(本文寄稿・IHRP=森垣穂香)
IHRPのプログラムのインプット期では、高校生それぞれが複数の学問分野の視点を身に付けながら、自分の研究テーマを模索することを目的としています。週に1回、さまざまな専門の先生のワークショップをオンラインで受講する他、希望する高校生は、実際にIHRPが提携している研究室に配属し、研究のために必要な知識や考え方を身に付けることができます。こうしたプログラムを通じて自分自身の関心分野の知識を深めながら、さまざまな分野に触れることで、興味の幅を広げ、新たな問いを見つけている高校生もいるようです。
また11月16日と17日には、社会科学の研究をしたいと考えていたり、また海洋研究に関心がある高校生たちが、IHRPをご後援いただいている聖心女子大学グローバル共生研究所と、海洋研究開発機構(JAMSTEC)を訪れました。聖心女子大学グローバル共生研究所のワークショップでは、対面で9人、オンラインで3人の高校生が「子どもと戦争」をテーマに子どもの権利条約について知り、子どもが不条理な状況に置かれるとはどういうことか、私たちの権利が守られているのかなどを学びました。参加者の中には、今回初めて子どもの権利を知ったメンバーも多く、ワークショップ後には「『子ども』という視点を今後の研究に加えてみたい」「研究対象を『子ども』に変えることを検討したい」などの声が挙がり、とても充実した時間となりました。
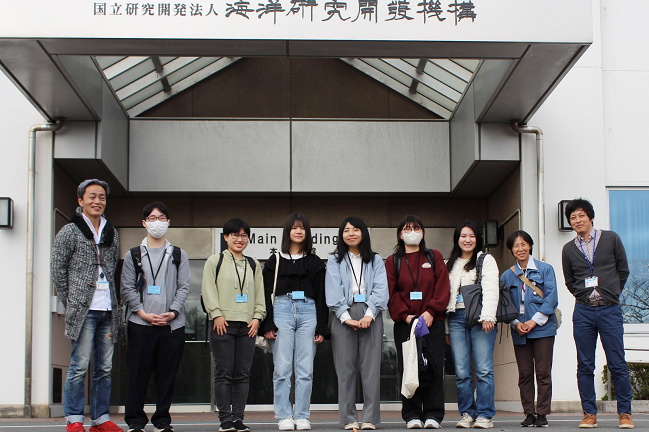 海洋研究開発機構(JAMSTEC)を訪問しました
|
聖心女子大学グローバル共生研究所でのワークショップの様子
|
また、JAMSTECでは、高校生5人が海洋研究に関する最前線の現場を見学し、研究者の先生方から、海洋に限らず“学問を学ぶ”ということについて、学びとは「私たち、自分自身が認識している関心領域は小さなもので、まだ自分が認識していない自分を楽しませること」だと話されていてとても印象的でした。またプラスチック問題に関して、先生方が海洋研究で深海に潜る中で実際に発見したごみを拝見させていただき、海洋に流れ出ているごみが私たちの生活に、また環境にどのような影響を与えているのかについてレクチャーを受けました。そして、科学的な知見が実社会にどのように活用されるのかを学びました。参加者たちは、研究者がいかにして課題を発見し解決に向かうのか、その姿勢やプロセスをじかに学び、多くの刺激を受けていました。
実際に研究所を訪れ、対面のワークショップなどでの学びを通して、参加者は多様な分野の視点や知見を自分の研究にどう取り入れていけるか、異分野融合の意義を改めて感じ取ることができたようです。
一方で、対面形式の活動はどうしても首都圏に暮らす高校生が参加しやすい環境となるため、IHRPでは基本的にオンライン活動を中心にプログラムを構成しています。その中でも、今年のインプット期で特に印象的だったのは、高校生たちが主体的に研究機関や企業に連絡を取っていた姿です。忙しい高校生活の中でIHRPというプログラムに参加し、さらに自ら学びを求めて行動する姿に、同世代として感動を覚えました。
こうしたオンライン・対面でのワークショップや専門分野ごとの研究室配属を通して、彼らの学びはさらに深まり、アウトプット期への大きなモチベーションとなったようです。
高校生たちの研究紹介
■江川陸翔 (えがわ・りくと、IHRP4期生、広尾学園高等学校1年生)
私は現在、「インスリンの血糖低下機序と中枢作用、およびその障害機構の解明」という研究を進めていらっしゃる千葉大学 大学院医学研究院の小野 啓准教授のもとで研究に携わらせていただく準備を進めています。
私には長年糖尿病を患っている祖母がおり、糖尿病は私にとって常に身近な疾患でした。祖母は糖尿病を発端とした白内障を発症し膵臓(すいぞう)にも障がいが出ており、祖母のように苦しんでいる糖尿病患者を助けたいという思いが年々強くなりました。糖尿病の治療を目的としたミトコンドリアの研究をしたいと思ったことがきっかけで、IHRPに応募しました。
しかし、実際にこのような研究を1人で実行することは難しく、高校生がマウスを使った研究等もできないということを知り、幾つかの大学や研究室に連絡を取ったのですが、断られてしまいました。高校1年生が研究するにはまだ難しいのかと思っていたのですが、粘り強く連絡を取り続けた結果、小野准教授が受け入れてくれました。多くの人の助けがなければ研究に取り掛かることすらできないということを、今回、身をもって実感しました。研究に携わらせていただけるよう、取り計らってくださった千葉大学大学院の先生方には大変感謝しています。
またインプット期には、北海道大学大学院工学研究院の佐藤 久教授に、論文の探し方や研究の進め方について多くのアドバイスをいただき、とても有意義な時間を過ごすことができました。今後研究を進めていく中で、さらに多くの研究者の方々と関わり、知識や技術を深めて、近い将来、新たな糖尿病の治療法を見つけたいと思っています。
■アガルワラ ラチト(IHRP4期生、K.インターナショナルスクール東京 高校2年生)
私の研究テーマは「関東地域における大気汚染レベルがアルツハイマー病リスクに与える影響の比較」です。日本は世界有数の高齢化社会であり、アルツハイマー病の増加は避けられない課題です。しかし、どのような環境要因がこのリスクに関わるのかは、未だ十分に解明されていません。特に大気汚染は、単なる健康被害を超え、脳の認知機能や疾患発症リスクに潜在的な影響を与える可能性があるとされています。この未知の領域を探ることは、社会全体に寄与する科学的解決策を生み出す鍵になると信じています。
IHRPに参加したのは、自分の研究を深めるだけでなく、その研究を実社会でどのように役立てられるかを探るためです。また、同じ情熱を持つ仲間と視野を広げる機会を得たいという強い思いもありました。夏キャンプでは、多彩な背景を持つ同年代の仲間たちや企業の方々と交流し、理論や視点だけでなく、自分の研究を進めるための実践的なアプローチを学びました。この経験は、私がコンフォートゾーン(自分自身の居心地の良い環境)を超え、自分のアイデアをより明確かつ革新的にするきっかけとなりました。
今後の研究では、関東地域内で大気汚染の異なる地域を比較し、そのデータがアルツハイマー病のリスクにどのように影響を与えるのかを統計的に分析する予定です。また、この研究を通じて得た知見を基に、大気汚染の削減や健康的な環境づくりを考えています。私の最終目標は、この研究が単なるデータ分析にとどまらず、持続可能で健康的な社会の実現に寄与することです。アルツハイマー病のリスクを軽減し、高齢者一人ひとりがより豊かで安心した生活を送れる未来を築くことです。
現在、インプット期を終えアウトプット期に入った高校生たちは、12月末に行われる冬キャンプでの中間発表に向けて、それぞれの学びを深めています。アンケート調査をしている高校生や配属先の研究室で実験の準備をしている高校生など、この3カ月での学びを生かしてアクションを起こしています。半年間という短い期間の中で、1つのプロジェクトを進めるのはとても大変ですが、小さなものでも実際に何かアウトプットすることで、さらに新たな学びを得られることを期待しています。

IHRP(Interdisciplinary High School Research Program)
IHRP(Interdisciplinary Highschool Research Program)は、世界各地で活動する大学生が、高校生の異分野融合の研究を支援する、特定非営利活動法人です。「社会課題解決のための研究」「異分野融合」「多様な高校生にチャンスを」をコンセプトに、高校生同士、高校生と研究者・企業の“新結合“をもって、社会問題へ斬新な解決策を創造することを目標にしています。










