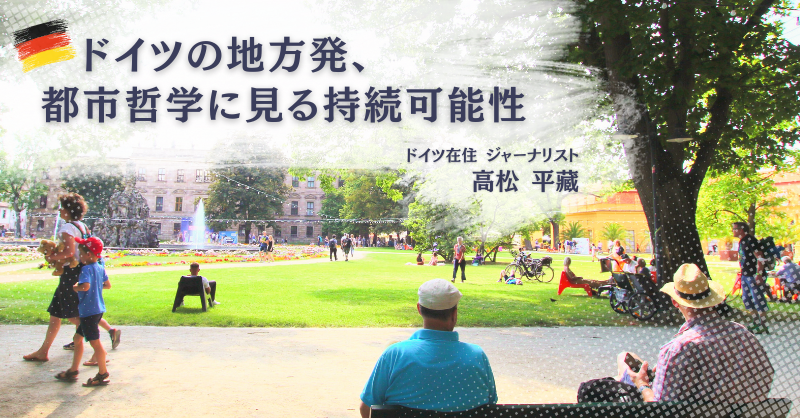 |
「ドイツの夏って涼しくていいですよね」
初夏を迎えると、日本の仕事関係の方とのメールの「ちょっとした近況のやり取り」で出てくる言葉だ。確かにサウナのような日本の気候に比べると、湿度が低く、影に入れば涼しい。「そうですね、一般家庭にまずクーラーはありませんから」と常とう句のように返していた。
しかし昨年、家を新築したドイツの友人が、「エアコンもつけた」と少し自慢げに話してくれた。確かに比較ポータルVERIVOXの調査(2023年7月)によると、ドイツで13%の人が自宅で空調を使用している。またここ数年、個人用のエアコンが欧州市場でじわじわと増加、企業的視点から見ると、これからますます需要が増える見込みだ。
これは30度を超える「暑い夏」が増えてきていることに関連している。この数年、森林火災の予防が強調され、水不足が毎年懸念されている。近所に大きな芝生の余暇空間があるが、真夏にはその芝生が枯れる様子を目にする。
現在のところ、自宅に空調設備を持っている人は少ないが、ヒートアイランド現象が進む可能性もある。このような問題に効果的なのが「緑」だ。
■グリーンシティ化が進められている
都市の緑化は近年の重要な課題であり、多くの自治体が取り組んでいる。私が住む人口約12万人のエアランゲン市(バイエルン州)は、経済的にも強い都市だが、環境問題に先駆的に取り組み、1990年代初頭に「環境首都」の称号を2度得ている。市の周りは森に囲まれ、余暇緑地も多く、土地利用の観点から言えば30%程度の「緑」がある。また個人宅で胴回り80センチ以上の木を切る場合は、代わりの木の植樹を義務付けるなど、緑化率にかなり気を遣っている。
公共空間には約4万本の樹木があり、行政がそのメンテナンスを含め、毎年積極的に植樹をしている。最近であれば市街中心地および、その中核になる空間の歩行者ゾーンの植樹プログラムを立案し、今年4月には、このプロジェクトに対して連邦政府からの資金調達も行った。
 エアランゲン市の歩行者ゾーン。木々が空間の価値を高めている(筆者撮影)
|
これらの木々は、特に市街地でどのような役割を果たしているのだろうか?
デザイン的にも重要な要素であり、街の景観を向上させる。人々が快適さを感じるのに役立っており、生活の質の「底上げ」につながっている形だ。また、都市の樹木は装飾的な要素だけではない。環境と健康にも重要な役割を果たしている。樹木は二酸化炭素を吸収し、酸素を放出する。空気中の微細なほこりなどをろ過し、気温を下げてくれる。
■人工空間の緑の肺
このように見ていくと樹木は都市の公共空間における「緑の肺」であり、多くの「サービス」を提供してくれる装置といっても過言ではないだろう。自然をコントロールし、活用する考え方が定着しているのがうかがえるが、言い換えると、都市とはあくまでも人工空間であることが強調されていることを意味している。
とりわけドイツを見ると、中世時代の都市は市壁で囲まれ、その中で多数の市民が生活できるようにつくられてきた。そのため物理的に人工空間としての都市のリアリティが人々の間にあったと考えられる。
もちろん、こうした市壁で囲む構造は19世紀の工業化で崩れることもあった。それにしても歴史的にみると、都市では「使える人工空間」を継続的に運営・発展させる感性や実際の法制度などが練られてきた。現在の言葉に置き換えるならば、まさに「持続可能性」だ。
■「文明と自然」を対比する時代ではない
エアランゲン市は植樹を毎年行い、緑化率を高めていることを書いたが、そこには一見、ばかばかしく感じられるような構造もある。なぜなら都市計画では道路の拡張などのために伐採される木もそこそこあるからだ。例えば2012年から2017年にかけて1300本の木が伐採されている。それで、「伐採される以上に植樹を」ということになり、実行に移している。
植樹の際に問題になるのが、「どこに植えるか」ということだ。木の根の成長も考えなければならず、思いのほか難しい。そして、市街地では、建物と道路などとのアンサンブルの最適化という課題は常にある。
それから、当然のことながら、木のケアのみならず植樹にもコストがかかる。例えば木の大きさにもよるが1本当たり、植えるだけで1000〜1200ユーロかかる。日本円の物価感覚で言えば10〜12万円程度、円安の折である1ユーロ=160円で計算すると16万円〜20万円ほど。「緑の肺」を公共空間に実装するには予算がいるのだ。
このように見ていくと、木々は都市計画の範ちゅうにあり、都市インフラであることがよく分かる。樹木は都市という人工空間のクオリティを高めるツールとしての自然なのだ。そして、緑化とは極めて社会的な課題でもある。したがって、植樹のプロセスにも市民参加が大切になってくる。
まとめると、緑化には社会的・生態的・空間的な観点があり、万人に対する公平な機能が期待されている。都市における緑とは「共通善」なのだ。このような考え方は2020年に欧州連合(EU)の加盟国の都市開発担当大臣らによって採択された持続可能な都市開発のための重要な政策文書「新ライプツィヒ憲章」でも強調されている。
共通善とは聞きなれない言葉だがギリシャ時代にまでさかのぼる。多くの議論があるが、ここではドイツ・バイエルン州の憲法から、次のように定義する。すなわち人間の尊厳を伴った、全ての人々の生存を保証すること、全ての人々の生活水準が段階的に向上すること、これが共通善である。
都市の問題は伝統的に「文明と自然」の対立と見なされることが多かった。また昨今はグリーンウォッシュという観点からの批判的議論もある。しかし、都市において西洋的な「自然をコントロールし、活用する」という考え方が行き着いたのは、緑を共通善として位置付けることであると言えよう。

高松 平藏 (たかまつ・へいぞう)
ドイツ在住ジャーナリスト
ドイツの地方都市エアランゲン市(バイエルン州)および周辺地域で定点観測的な取材を行い、日独の生活習慣や社会システムの比較をベースに地域社会のビジョンを探るような視点で執筆している。日本の大学や自治体などでの講義・講演活動も多い。またエアランゲン市内での研修プログラムを主宰している。 著書に『ドイツの地方都市はなぜクリエイティブなのか―質を高めるメカニズム』(学芸出版)をはじめ、スポーツで都市社会がどのように作られていくかに着目した「ドイツの学校には なぜ 『部活』 がないのか―非体育会系スポーツが生み出す文化、コミュニティ、そして豊かな時間」(晃洋書房)など多数。 高松平藏のウェブサイト「インターローカルジャーナル」














