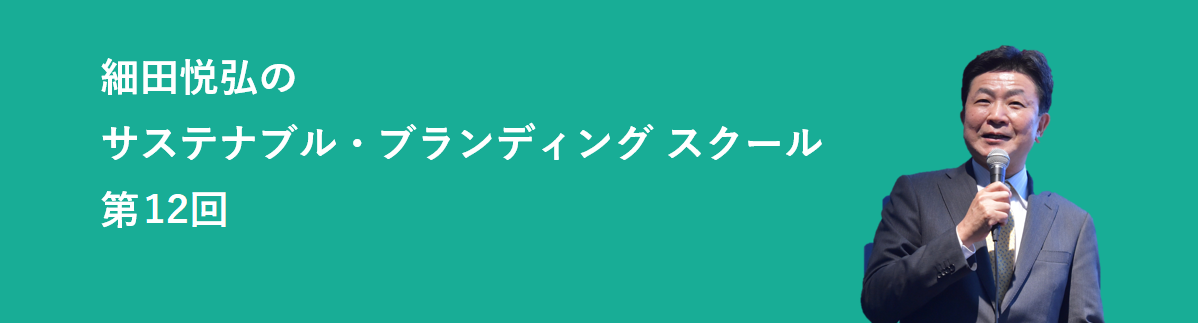 |
営業部門の方から、「ブランドが大事と言われても、直面する数字(売上目標)との兼ね合いがピンとこない」という声をよく耳にします。たしかに目先の利益は大事です。でも、目先の利益を続けていきたいのなら、「ブランド」が肝心です。今回より、営業パーソンに向けた「サステナブル・ブランド講座」を開講(執筆)します。
企業ブランド重視の時代
「ブランド」というと、これまで、ラグジュアリーブランドと呼ばれるヨーロッパなどの高級品、商品そのもの、商品品質、ロゴマークや商標、広告・キャンペーンで作られるものなどと捉えられる傾向が強くありました。いわば、プロダクトブランド(商品ブランド)を中心に、顧客を対象としたマーケティングや広告といった限られた分野において、マーケターの手に委ねられていた時代といえます。
ブランドやブランディングという言葉は、長らく「かっこいいCF(commercial film)=かっこいいブランド=いいブランド」という考え方がまかり通っており、広告キャンペーン主導型でした。いきおい「ブランド」というよりは、「ブランドイメージ」という言い方がよくされていました。今でも、しばしば「ブランド戦略=広告宣伝戦略」のように語られることがあります。よって、営業部門は直接関与する必要がない、ましてやBtoB企業や中小企業には関係ないといった風潮もありました。
それが近年、経営層において企業価値やコーポレートブランドへの関心が高まり、企業経営の根幹に関わるテーマとして議論されるようになってきました。商品だけでなく、「企業」もブランドとなります。マーケティング分野だけでなく、経営戦略としても「ブランド」が論じられるようになりました。したがって、事業戦略・営業戦略における位置づけも高まっています。
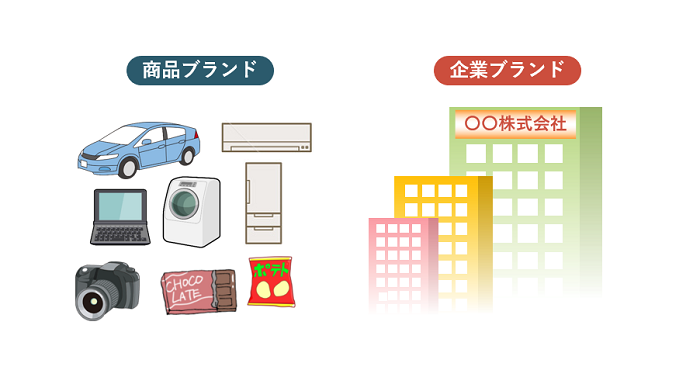 |
企業不祥事が多発すると、企業への不信感の高まりとともに消費者の目は格段に厳しくなっています。さらには、市場が成熟化し、商品の明瞭な差別化が困難でコモディティ化し、商品などの情報が氾濫し、労力や時間などの選択コストが高くつくとなると、消費者や顧客は「企業ブランド」で選ぶ傾向が顕著になってきました。企業が提供する製品・サービスの品質、機能、デザインなどの安全性や有用性もさることながら、事業における環境への取り組みや社会課題の解決など、「サステナビリティ」に根差した企業経営全体に目を向けるようになってきています。このことは、消費者・顧客からのブランド評価の対象が、プロダクトブランドそのものから企業全体のコーポレートブランドへと目線が拡張してきていることを意味します。
「企業ブランド」のエンドースメント効果
ブランディングは、「商品・サービス」の競争力を高めるだけではありません。顧客は、商品がコモディティ化(一定の質に収まった標準化された商品で、「いくらでも代わりがある」という状態)する中で、その企業の想いや姿勢を評価します。
すると次の段階では、「商品が同じようなものであれば、この企業のものを買おう」と、個別商品だけでなく、その企業の商品全般を支持するようになり得ます。「このブランドだけは特別」と思わせる力であり、企業サイドからみると、戦わずして他社よりも一歩生活者に近づくことができる強力な武器となります。これこそが「企業ブランド力」の真骨頂であり、「エンドースメント効果」といいます。エンドースメントとは、企業ブランド(親ブランド)が商品ブランド(子ブランド)に対する保証を与えるという意味です。「同じような商品なら、この会社のだったら間違いない」という判断をしてもらえるということです。ブランドがエンドーサーとなり、保証機能を果たしてくれます。ブランド力の本質は、顧客などのステークホルダーが、企業や製品・サービスを選択・購買する際に象徴的に表れます。
ブランドは、営業活動における「シード権」
今日の社会の価値観において、顧客をはじめとするステークホルダーからの要請や期待を集約したコーポレートブランドは、信頼と愛着の旗印として、持続的な競争優位の源泉となります。企業ブランドが高まれば、顧客だけでなく、取引先、投資家、従業員、地域社会といったステークホルダーの信頼と支持を獲得できます。「あの会社は金儲けだけではなく、世のため人のために経営されていたのだ」ということが理解されると、いよいよ強力なブランド力を発揮し始めます。今この時代だからこそ「社会性」を備えることが、ブランドに一段と磨きをかけます。顧客を惹きつけ、その他のステークホルダーも共鳴して集まってきます。今日、ブランディングの核心に位置付けられるのが「サステナビリティ」の概念といえます。
 |
BtoBビジネスにおいても高いブランド価値は、商談に際して「オープン・ザ・ドア効果(顧客の営業活動への心理的抵抗をやわらげ、門戸を開きやすくする効果)」を発揮します。たとえば、新規開拓をする場合にしても、社名を知られている会社の営業パーソンは、そうでない会社よりも会って話を聞いてもらえる確率は高まるはずです。
ブランドは、「営業活動におけるシード権」です。目先の利益は大事、ただし目先の利益を続けていきたいのなら、「ブランド」が持続可能なビジネスの生命線といえるでしょう。

細田 悦弘 (ほそだ・えつひろ)
公益社団法人 日本マーケティング協会 「サステナブル・ブランディング講座」 講師 一般社団法人日本能率協会 主任講師
1982年 中央大学法学部卒業後、キヤノン販売(現キヤノンマーケティングジャパン) 入社。営業からマーケティング部門を経て、宣伝部及びブランドマネジメントを担当後、CSR推進部長を経験。現在は、企業や教育・研修機関等での講演・講義と共に、企業ブランディングやサステナビリティ分野のコンサルティングに携わる。ブランドやサステナビリティに関する社内啓発活動や社内外でのセミナー講師の実績豊富。 聴き手の心に響く、楽しく奥深い「細田語録」を持ち味とし、理論や実践手法のわかりやすい解説・指導法に定評がある。 Sustainable Brands Japan(SB-J) コラムニスト、経営品質協議会認定セルフアセッサー、一般社団法人日本能率協会「新しい経営のあり方研究会」メンバー、土木学会「土木広報大賞」 選定委員。社内外のブランディング・CSR・サステナビリティのセミナー講師の実績多数。 ◎専門分野:サステナビリティ、ブランディング、コミュニケーション、メディア史 ◎著書 等: 「選ばれ続ける会社とは―サステナビリティ時代の企業ブランディング」(産業編集センター刊)、「企業ブランディングを実現するCSR」(産業編集センター刊)共著、公益社団法人日本監査役協会「月刊監査役」(2023年8月号) / 東洋経済・臨時増刊「CSR特集」(2008.2.20号)、一般社団法人日本能率協会「JMAマネジメント」(2013.10月号) / (2021.4月号)、環境会議「CSRコミュニケーション」(2010年秋号)、東洋経済・就職情報誌「GOTO」(2010年度版)、日経ブランディング(2006年12月号) 、 一般社団法人企業研究会「Business Research」(2019年7/8月号)、ウェブサイト「Sustainable Brands Japan」:連載コラム(2016.6~)など。














