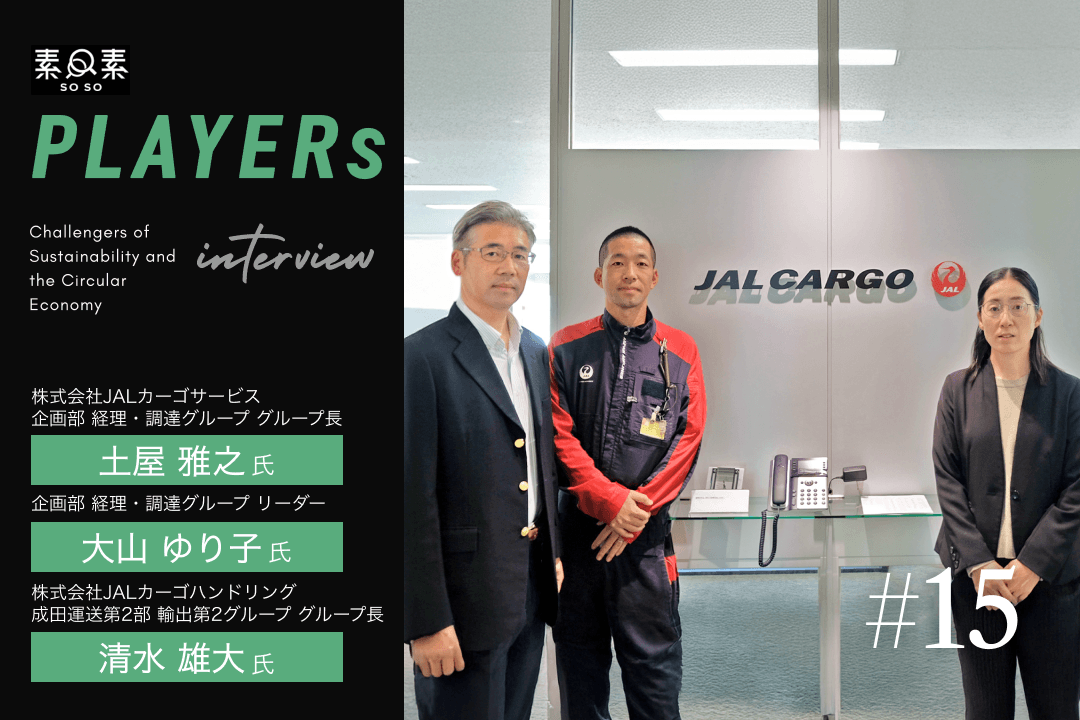曽根氏、杉浦氏、三輪氏、下田屋氏 (左上から時計まわり)
|
気候変動やフードロス問題などの社会課題の解決に向け、「食」にかかわる多様なアクターが今取り組んでいる行動とは――。2月に開かれたサステナブル・ブランド国際会議2022横浜で、ヴィーガン料理の第一人者として世界的に活躍するレストランのシェフや、これまで廃棄されていた食材のアップサイクルに取り組む食品会社の担当者らが、それぞれの実践にかける思いを語るセッションがあった。今回の国際会議のテーマでもあった「リジェネレーション(再生)」を食べることから考えることにもつながる議論を紹介する。(廣末智子)
ファシリテーター:
内藤真未・YUIDEA Branding & Sustainable Planning サステナブル・ブランディング事業推進責任者
パネリスト:
下田屋毅・日本サステイナブル・レストラン協会 代表理事
杉浦仁志・ONODERA GROUPグループ エグゼクティブシェフ 執行役員
曽根清子・料理通信社 編集部 編集長
三輪千晴・オイシックス・ラ・大地 経営企画本部 新規事業開発準備室 Upcycle by Oisix ブランドマネージャー
料理人はもっとさまざまな分野で人を幸せにすることができる
「どうしてレストランがサステナビリティを推進していかねばならないのか。シェフがどういった食材を調達するかによって地球の未来が変わっていくからだ」
最初に登壇した日本サステイナブル・レストラン協会(東京・渋谷)代表理事の下田屋毅氏は、気候変動や森林破壊、漁業資源と種の絶滅、強制労働や児童労働といった社会環境問題が、食を巡るサプライチェーンにおいて知らず知らずに深刻化している現状を示し、フードシステムを変革する必要性を訴えた。同協会は、飲食店の食材調達や運営のサステナビリティを格付けする英国発NPOの日本組織として世界的なレストランやシェフとも連携する。
その協会が定める国際指標のアドバイザーシェフとしても活躍するのが、日本でのヴィーガン料理の第一人者とされる、ONODERA GROUP(東京・千代田)エグゼクティブシェフの杉浦仁志氏だ。シェフとしての立場を軸に、杉浦氏はフードテックや企業コンサル、地方創生、食育や医師と連携した食事療法の研究など、幅広い活動を手掛ける。その根底にあるのは、「料理人はもっとさまざまな分野で人を幸せにすることができるのではないか」という思いだ。
食の課題と最新のテクノロジーを掛け合わせた分野では、大学や企業との連携で、水耕栽培野菜や、農薬を使用しない堆肥から育つ果実の研究開発などに力を入れる。ダイナミックな取り組みとしては、旬の食材の産地に太陽光発電機や瞬間凍結機を搭載したトレーラーを運び込み、その場で瞬時冷凍した規格外品を消費地に輸送して販売する“トランスフォーマーロジスティクス”の実証実験も進めているという。
大根の皮やナスのヘタを使ったチップスなど、廃棄食材のアップサイクル商品を発売
一方、食材が畑から食卓に運ばれるまでのサプライチェーン全体でのフードロスを目指すのがオイシックス・ラ・大地(東京・品川)だ。全国約4000の生産者や加工メーカーと提携し、同社独自の基準に基づいた食品を、消費者からの発注を受けて届けるサブスクリプション型のプラットフォームを提供する。
昨年度からは見た目や形が不揃いで流通に乗らない野菜や、加工食品の現場でこれまでは廃棄されていた食材をアップサイクルした商品のブランド化に着手。三輪千晴氏によると、具体的には漬物工場で出る大根の皮や、ナスのヘタを加工したチップス、バナナの皮で作ったジャムといった商品が生まれているという。
「活用手段が分からず捨てられてしまっていたり、食べる文化がなかったりするものをより美味しく食べられる形に付加価値を付けている。産地や加工メーカーと直接つながっているからこそ、どんな工夫やアレンジが効くかが分かり、それを生活者のニーズとつなげるチャレンジだ。フードロスを身近な生活の工夫からなくす世界をつくっていきたい」
コロナ禍が食材の作り手と使い手、食べ手を近づけるきっかけに
セッションには、2006年に月刊誌としてスタートし、現在はウェブメディアとして食と暮らしの在り方を発信する『料理通信』の編集長である曽根清子氏も登壇。「食材の作り手(生産者)と使い手(料理人)、食べ手(生活者)の循環を回す」視点から取材を続けるなかで、「コロナ禍が3者を近づけるきっかけとなったのではないかと感じる」と話した。
なぜなら、時短営業を経験したことで飲食店が働き方を見直したり、生産者も生鮮食品の加工に力を入れるようになったり、市民農園に参加する人が増えるなど、互いの距離が近づいているからだ。コロナ禍を経てどう食と向き合うかを探る連載では、生産者から「地域で循環する小さな経済が大切」や「農業をアート、文化活動と捉える」といった、リジェネレーションを考える上でのキーワードが多く聞かれたという。
「流通の発達により、生きていく上で欠かせない食べ物が自然の恵みであることを実感しにくくなっている。これからは誰もが食材の作り手であり、使い手であり、食べ手であることを大切に、自分でやってみることで新しい回路が開けるのではないか」
この曽根氏の提言に対し、セッションのファシリテーターを務め、サステナブル・ブランディング事業を推進するYUIDEA(東京・文京)でオウンドメディアの運営に携わる内藤真未氏は、「作り手と使い手、食べ手が役割を固定せず、まずはいろいろな実践をしてみるところから新たな気づきが生まれ、その気づきの集積が大きな変化になっていく」と同じメディアの立場としての共感を表明した。
地産地消、サーキュラーエコノミー、食料自給率向上に貢献を
 |
セッションの後半は、食と暮らしを巡るさまざまな連携について議論が進み、杉浦氏は、小学生新聞の紙面で、健康や環境に配慮したプラントベースの食事の大切さを家庭で簡単に作れるレシピとともに紹介していることなどを報告。「なぜ今、地球温暖化が進んでいるのかといったことを料理を通じて子どもたちに伝え、日常の食から親子の会話が生まれるような働きかけが大事なフェーズに入っている」と述べた。
このほか、三輪氏は「日本や、世界全体では、ブラックボックス化されている食品廃棄の現状を変えたい。メディアやレストランとも協力し、横のつながりを強めることで救える野菜を増やし、もっと美味しく食べられるものを届けたい」、曽根氏は「世の中の動きとして認知される前の現場の意識や価値観の変化を言語化していくことで、進むべき方向や未来の兆しを示したい。その上で実際に行動変容を起こしていくための仕組みを、行政や企業と一緒につくっていく」とそれぞれにできることを強調。
最後に下田屋氏が、「われわれがハブとなって、地産地消やサーキュラーエコノミーの推進、食料自給率の向上に貢献したい。いろんなアクターを呼んできて、レストランのサステナビリティを推進し、横のつながりや仕組みをつくっていきたい」と抱負を語り、セッションを終えた。
廣末 智子(ひろすえ・ともこ)
地方紙の記者として21年間、地域の生活に根差した取材活動を行う。2011年に退職し、フリーを経て、2022年から2025年までサステナブル・ブランド ジャパン編集局でデスク兼記者を務めた。