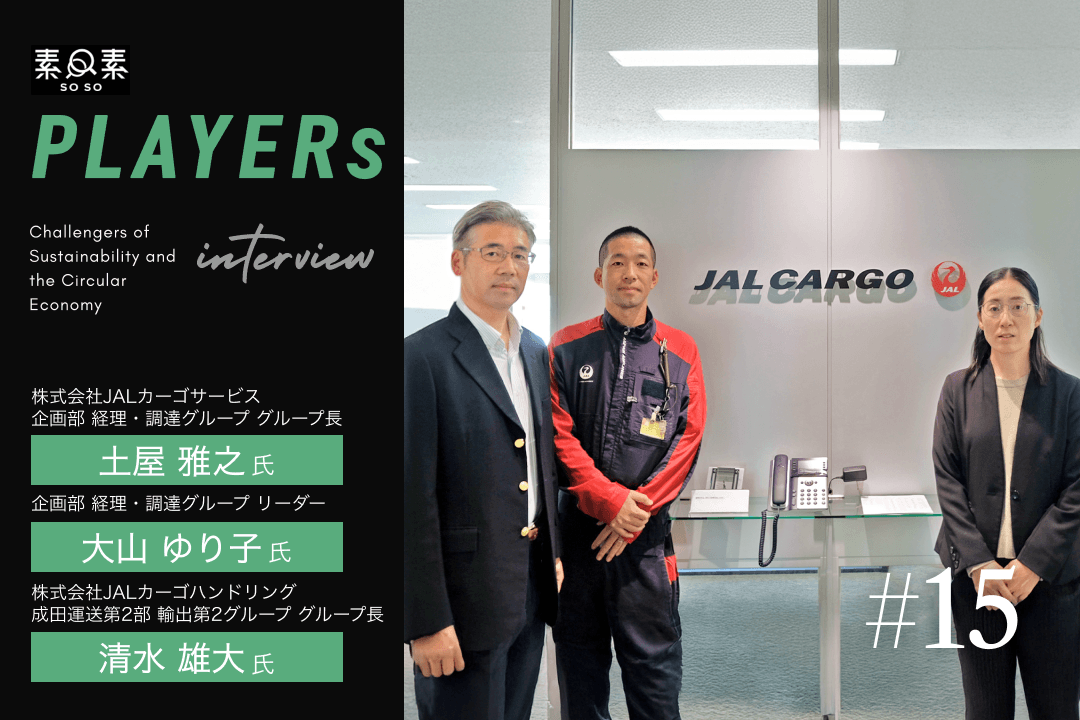右上から時計まわりに、小山氏、秋鹿氏、牛島氏、小和田氏
|
「サステナビリティは、余裕があるならやればいい」――。日本企業内で、持続可能なビジネスづくりに取り組む部署への理解はいまだに十分ではない。サステナブル・ブランド国際会議2021横浜では、従来の企業イメージにとらわれず、先進的な新事業を打ち出す各社の担当者らが集い、社内外にサステナビリティの考えを浸透させるために行っている工夫や、自社の再定義に踏み切る重要性の提言などを通して、これからの日本企業の在り方について議論した。(横田伸治)
ファシリテーター
小山 嚴也 関東学院大学 経営学部 学部長・教授(当時・現同大学学長)
パネリスト
牛島 慶一 EY Japan 気候変動・サステナビリティサービス パートナー
秋鹿 正敬 日揮ホールディングス サステナビリティ協創部 常務執行役員 / サステナビリティ協創部長
小和田 みどり ライオン サステナビリティ推進部 部長
「持続可能な社会へ社員一丸となって未来構築を進める企業は、一体何が違うのか?」と問いかけたこのセッション。参加したのは、日揮ホールディングスの秋鹿正敬・サステナビリティ協創部 常務執行役員、ライオンの小和田みどり・サステナビリティ推進部長、そしてコンサルティングを通して各社の取り組みを支援しているEY Japan気候変動・サステナビリティサービス パートナーの牛島慶一氏。ファシリテーターは関東学院大学の小山嚴也教授が務めた。
日揮ホールディングスは石油精製や天然ガス処理のプラント製造で知られるが、プラントで発生するガスから二酸化炭素を回収する低炭素・脱炭素化技術や、生ごみ・排水からメタンガスを取り出して発電などに利用するバイオガス技術の開発など、環境に配慮した事業サイクルを打ち出しているという。秋鹿氏は「日揮だけなく、大学や他社、政府、スタートアップのみなさんと協働することで持続可能な社会を目指す」と決意を語った。
一方のライオンは、「より良い習慣づくりで、人々の毎日に貢献する(ReDesign)」というパーパスを全社で共有し、日用品の提供だけでなく、消費者の生活を健やかにすることを目指している。具体的には、歯磨き嫌いの子ども向けに、アプリと連動して楽しみながら歯磨き習慣を身に着けられる商品や、困窮家庭で育った子どもを対象に、楽しいオーラルケア経験を提供するワークショップを実施し、自立支援にもつなげていく試みを行っている。こうした取り組みについて、小和田氏は「この部署に来るまでは『サステナビリティは、余裕があれば取り組むもの』と思っていた」と明かした上で、「サステナビリティを一部の部署だけの活動にしないためにも、社内外に発信し、経営者をはじめ社内の意識を変えていくことが非常に重要。事業の発展との両輪で進めなければならない」と強調した。さらに同じ日用品メーカーの花王と、洗剤の詰め替え用パウチを共同でリサイクルする実証実験を開始したことについて、「社会課題の解決は、競争や競合でなく、秋鹿さんが協創とおっしゃった通り、いろんなところと組んでやることが早道」と語った。
牛島氏は「株主の利益を最大化するのではなく、パーパスに応じて多様なステークホルダーに価値を届ける」という近年の企業のあり方を説明。ESGやサステナビリティなど「非財務情報」が企業の価値に影響する時代であることを強調した。その上で、自らが「何屋」であるかを再定義するパーパスの変更、パーパスを追求するために人材を確保・育成する新たなケイパビリティの獲得、「自社が社会にどのようなインパクトを与えているか」を可視化してステークホルダーに訴求する――といった経営の見直しが日本企業に求められており、そうした変革こそが日本企業が世界にアピールしていくために必要だと指摘した。
秋鹿、小和田の両氏に小山教授は、サステナビリティを推進する部署が立ち上がるプロセスについて問いを投げた。秋鹿氏は「脱炭素の分野で、社会に生かせる技術を持っている人材は研究所にいたが、ビジネス化には手が届いていなかった。そこで、社会貢献が企業の価値になることを認識し、技術陣とビジネス陣の合同で部署を作った」と、2019年10月に2人でスタートしたサステナビリティ協創部が、約1年3カ月で研究職約20人を擁する約60人の部署へと成長した経緯を説明。「既存事業とのバランスを取りながら、若手社員にも社会貢献の意義を伝えてきた」と社内の意識改革についても触れた。小和田氏も「サステナビリティ推進部の業務は多岐にわたっていたが、他部署の人間は内容を把握していない、というくらい閉じた部署だった」と自身の着任時を振り返り、「経営陣を含めて勉強会を開催したり、各部署に業務内容を説明したりするなど、社内の意識を変えてきた」と続けた。
こうした企業の実情に、牛島氏が「サステナビリティやCSRなどの言葉は、コンテクストが受け手によって大きく異なる。用語を、実際の業務に合わせてどう意味づけるかが難しい」と指摘すると、小和田氏も「部署に来た当時は、英単語ばかりで何を言っているのかわかりづらく、まずは言葉の定義から始めた」と頷いた。
一方、社外に向けての発信の話題に移ると、小和田氏はライオンの広報戦略に触れ「商品競争には限界がある。スペックよりも、ブランドの存在意義をストーリー化して伝えなくてはならない。そこで、ブランド開発をパーパスに基づいて行ってきた」と説明。習慣をリ・デザインするというパーパスについては「社内ビジョンとは別にパーパスを設定したことで、社内では腹落ちが難しかった。だがコロナ禍で、『人のためになる商品を作っているんだ』と自信を持つことができ、納得度も高まったのでは」と、社員の意識統一の難しさを語った。
小山教授が一般的な企業理念とパーパスを比較し「パーパスには、本業についての記述が無く簡潔なことが多い。そこが、社会的価値と経済的価値を結びつけやすくする秘訣では」と投げかけると、牛島氏が「なぜパーパスが必要かと言うと、不確定な時代かつ人材が多様化していく中で、社員に会社に所属している誇りを持たせるために、シンプルな言葉が重要になってくる」と同意した。
牛島氏はさらに、「無形資産が必ずしも経済的価値に結びつくわけではない。成長する企業は、自社の強みのどこを生かすかを考え、過去の無形資産の上に新たな無形資産を構築している」と、安易にESG評価を経済的価値と関連付けることの危うさを指摘した上で、「ライオンは歯ブラシをただ売るのではなく、人の習慣に目を付けて価値を作り出した。日揮も、廃棄物が資源になる技術で社会と企業のWin-Winが実現できる。そこに着眼したのは素晴らしい」と、両社が自社の再定義を進めている姿勢を評価した。
横田 伸治(よこた・しんじ)
サステナブル・ブランド ジャパン編集局 デスク・記者
東京都練馬区出身。毎日新聞社記者、認定NPO法人カタリバ職員を経て、現職。 関心領域は子どもの権利、若者の居場所づくり・社会参画、まちづくりなど。