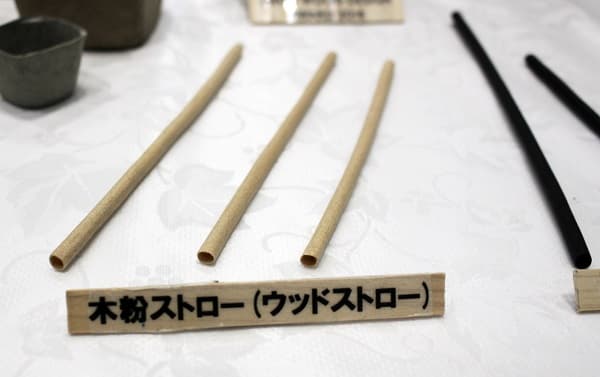|
積水化学工業は、高機能プラスチック製品のパイオニアとして、まさにその時代時代に本業を通じて、社会的課題の解決に貢献してきた企業だ。サステナブル・ブランド国際会議2021横浜の基調講演で、同社の取締役 専務執行役員の上脇太氏は、2030年に向けた長期ビジョンにおいて掲げるステートメント「Innovation for the Earth」のEarthには、「地球と、地球上に住んでいる人々、という2つの意味を持たせている」と語り、1947年創業の同社が、革新的な製品やサービスを通じて、人々の暮らしや環境にどう貢献してきたか、また未来に向けてどんなサステナビリティ戦略を描いているのかを語った。(廣末智子)
社会的課題を解決するプラスチック製品に注力
2006年から「サステナビリティ貢献製品」制度導入
1947年にプラスチックの総合的事業化に取り組み、48年には日本初の「プラスチック自動射出成形」を、さらに50年にはセロハンテープ、52年には塩化ビニル管の開発・・・。創業以来の取り組みを紹介する動画に、次々とその時代を象徴するような事業のテロップが映し出される。戦後の高度経済成長の波に乗り、高機能プラスチック事業を拡大していった同社は、60年代には、その開発商品であるプラスチックごみ箱「ポリぺール」によって、「日本のまちを美しくした」。当時の人々にとっては画期的な出来事であったのだろう。
その後も、プラスチック製品のパイオニアとして、同社の本業を通じた社会的課題の解決は続き、2006年からは、当時は「環境貢献製品」と呼んでいた、今でいう「サステナビリティ貢献製品」に関する制度ができた。その製品の社会的課題解決力はもちろん、ガバナンスや顧客満足度、あるいはサプライチェーンの健全性や収益性について、社内だけではなく、研究者やNPO法人の代表、環境メディアや消費者の代表らでつくる社外のアドバイザーによるトータルな評価に基づき、該当製品を認定するものだ。上脇氏によると、現在、売上高ベースで、このサステナビリティ貢献製品が60%ほどの比率であるのを、80%以上にする目標を立てている。そのために、非常に社会的課題の解決力が高く、且つ、収益性が高い商品を生む努力に邁進しており、それにはやはり技術力をベースとしたイノベーションが不可欠だという。
現在、同社は社内カンパニー制を採っており、住宅、環境・ライフライン、高機能プラスチックの3つに加え、新分野としてのメディカル、あるいはエネルギー分野も手掛けている。昨年策定した2030年を見据えたビジョンの中でも、レジデンシャル(住まい)とアドバンストライフライン(社会インフラ)、イノベーティブモビリティ(エレクトロニクス/移動体)、ライフサイエンス(健康・医療)の4分野での企業価値や目標を描いており、さらにその中には、プラスチックスの成形技術や住宅の工法技術といった28項目に細分化されたプラットフォームがある。これについて上脇氏は「こうした一つひとつの技術を磨き、且つ、それらを融合させてイノベーションを推進していくことが、サステナビリティ貢献製品の基本なのです。逆に言うと、このプラットフォームから外れたものはやりません。そこの範囲の中で技術を深めていくことを徹底しています」と強調する。
目に見えないインフラの維持に貢献
プラスチックごみ再生事業検証へ
そして、その具体例について、一つひとつ説明。まず戸建て住宅については、工場で80%作れるような工法を採っていることが特徴であり、その結果、現在供給している約85%が、屋根一面にソーラーパネルを敷き詰めることで大容量の発電機能を持った、いわゆる“ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)”と呼ばれる住宅であると報告。CO2の削減だけでなく、災害などで停電が長引いた時にも自然エネルギーで暮らしていけるといった社会価値を提供している。またこういった住宅が並ぶ住宅地の地下に、ゲリラ豪雨や台風による水害を防ぐための、廃プラから作ったインフラを埋め込むことで、安心して暮らせる街づくりへの貢献にもつなげているという。
地下のインフラということで言えば、日本全国の地面の下にはつなぎ合わせると約42万キロにもなる下水管が眠っており、そのほとんどが前の東京オリンピックの頃に作られたもので老朽化が激しく、道路の陥没などの事故を引き起こす懸念もある。同社はこうした下水管の内側に、ロボットを使ってプラスチック製の帯を被覆していく工法で、古い下水管を更生させる事業も手掛けている。つまり、地面を掘削せずに済むだけでなく、廃棄物も出ない、下水を止める必要もないので住民に影響を与えないというメリットの多い工法で、「普段は目に見えない、大事なインフラの維持というところに貢献していきたい」と語った。
このほかインフラ面では、ガラス繊維にウレタンを含ませ、発砲させて作る「合成木材」が、老朽化した鉄道の枕木の更新材として特に欧州などで注目されている。合成木材は腐ることがないため、普通の木材と比べて耐久性があるだけでなく、軽くて丈夫という特性がある。欧州では木材に塗る防腐剤が環境規制に抵触することからもその代替材として引き合いがあり、上脇氏は「鉄道という大事なインフラを守る、という意味でも全世界の課題に貢献している」と胸を張った。
さらに、自動車の分野では、事故発生時のドライバーの安全性の面から開発したフロントガラス用の中間膜が、今後、電気自動車が普及した際には、その遮熱性の高さから、バッテリーの負荷を下げるとともに、ナビや速度の情報などをガラスに映り込むようにすることで、運転時の安全性を高めることにもつながる。
また最後に、上脇氏は、「今、われわれが手掛けている未来技術」として、焼却場に運ばれるごみをガス化し、微生物の力でプラスチックの原料となるエタノールに再生していく技術の検証を来年度から行う計画であることを表明。「私どもはプラスチックで事業をさせてもらっています。ですので、このプラスチックが混じったごみからもう一度プラスチックを作り、サーキュラーエコノミー(循環型経済)を回していくという社会的課題の解決になんとしても貢献していきたい」。そう力強く決意を語った。
廣末 智子(ひろすえ・ともこ)
地方紙の記者として21年間、地域の生活に根差した取材活動を行う。2011年に退職し、フリーを経て、2022年から2025年までサステナブル・ブランド ジャパン編集局でデスク兼記者を務めた。