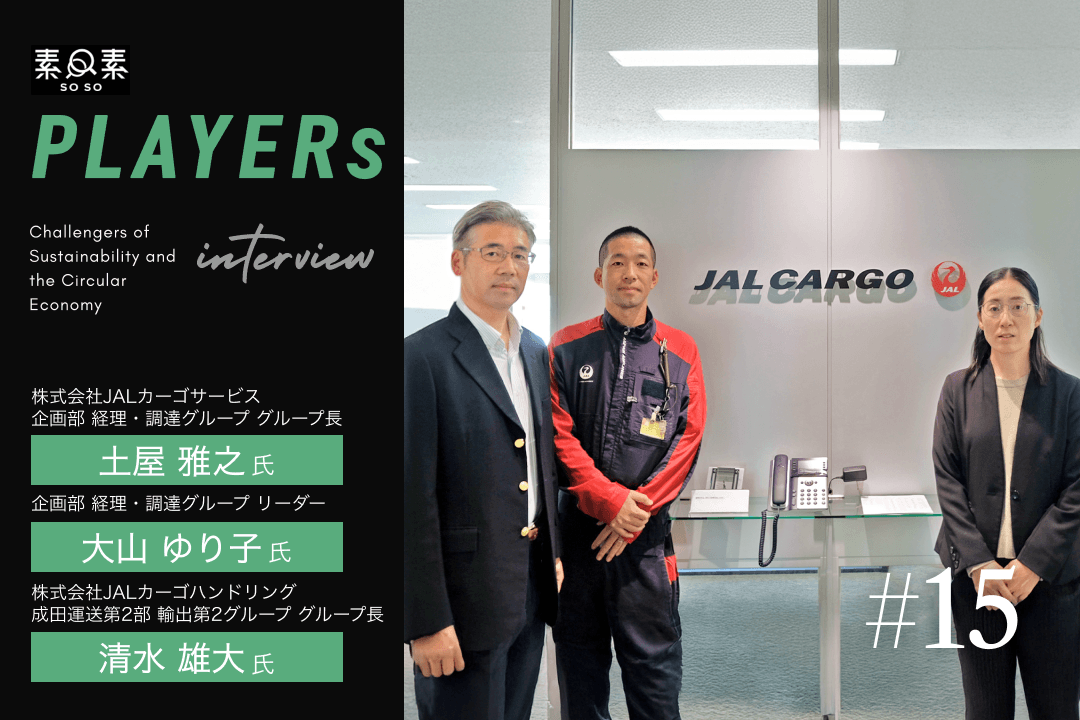稲作で大量に発生する稲わら。メコン川流域では年間1億トン近く、日本では約800万トン出るという。メコン地域では多くが焼却処理されており、大気汚染や気候変動への影響が問題視されている。このほどベトナムでは、メコン地域の5カ国から代表者が集まり、稲わらを回収して有効活用するための取り組みを議論するワークショップが開かれた。一方日本では、稲わらは農地にすき込んで土づくりに活用される場合が多いが、メタンガスの発生といった問題もある。畜産用の飼料としての活用拡大や、バイオ燃料や肥料への加工が模索されている。
稲わらは廃棄物ではなく貴重な資源
世界有数の稲作地域であるメコン川流域では、年間1億トン近くの稲わらが出るという。それらの多くは野焼きで焼却処理されており、大気汚染や炭素排出が問題になっている。しかし近年、稲わらを貴重なバイオマス資源と見なして回収・活用する取り組みが、ベトナムを中心に広がっている。
2025年11月19日、ベトナムのカントー市で、稲わらの活用について話し合うワークショップ「稲わらのバリューチェーン:政策と投資の機会」が開かれた。会場には、ベトナム、ラオス、カンボジア、ミャンマー、タイから100人を超える代表者が集まった。同ワークショップは、国際稲研究所(IRRI)、ベトナムの協同組合農村開発局(DCRD)、ベトナム米穀協会(VIETRISA)が共同開催したもの。IRRIは、1960年代後半に高収量な稲の品種を開発して「緑の革命」に貢献したとして知られる国際機関で、日本も資金拠出に加え、人材派遣や技術協力などで長年協力している。

IRRIは、メコンデルタと近隣諸国で持続可能な稲わら管理を推進するため、2023年から「ライス・エコ・プロジェクト」を実施してきた。韓国政府が資金を拠出するメコン・韓国協力基金の支援を受けたプロジェクトで、循環型の稲わら管理技術の開発・実証などを行っている。今回のワークショップでは、同プロジェクトの成果も披露された。
その一つが、ライス・エコ・プロジェクトが一部出資して開発した「イージーファーム」というアプリケーションだ。農家を、機械で稲わらをロール状にするサービスや稲わら買取市場と直接つなぎ、稲わらの回収を促す仕組みで、すでに2000軒以上の農家で試験導入されている。こうした取り組みによって稲わらを資源として活用することで、水田にすき込んで処理した場合と比べても、1ヘクタール当たり最大3トンものCO2排出を抑えられることが分かったという。
メリットはCO2排出削減だけではない。稲わらで作られた有機肥料を使用したところ、稲の収量が10~15%増加したという。また、稲わらの売却が農家の新たな収入源になり、その地位を守ることにつながる可能性にも注目が集まる。
ワークショップで発表したカントー大学のグエン・ホン・ティン博士によれば、現在最も多くの利益を生み出している稲わらの活用方法は、キノコ栽培で菌床の材料として使う方法だという。他にも、有機肥料、バイオ炭、バイオマスペレット、バイオプラスチックなどに加工する事例への言及があった。しかし、グエン博士によれば、明確な品質基準がないこと、物流基盤がぜい弱なこと、正式な取引市場がないことが課題だという。
メコン地域における稲わら活用3つの課題
DCRD局長のレ・ドゥック・ティン氏は、稲わらの有効活用が、ベトナムのグリーン成長に向けた鍵になると語る。その上で、今後さらに稲わらの有効活用を進めるためには次の3つのことが必要だと主張した。
①法制度の整備
稲わらを廃棄物ではなくバイオマス資源だと認める制度設計を行うこと。持続可能な稲わら市場を構築するために、収集、保管、輸送、再利用に関する基準が必要。
②バリューチェーン再編
機械で稲わらをロール状にするサービスや、収集拠点の整備などについて、協同組合が中心的な役割を果たすべき。また協同組合には、稲わらを有機肥料、バイオ炭、バイオマスペレットなどに加工する企業と農家をつなぐ「架け橋」としての役割も期待される。
③資金調達と炭素市場との連動
民間投資、政府開発援助(ODA)、融資など、さまざまな資金源を動員することが必要。また、稲わらに関する測定・報告・検証(MRV)のシステムを確立し、炭素クレジットの仕組みに組み込むことも重要。
中国から稲わらを輸入する日本
今回のワークショップに日本からの参加はなかったと見られるが、日本でも稲わらの活用は大きな課題だ。農林水産省によると、国内で発生する稲わらは年間約800万トンで、大半は農地にすき込まれている。全体の1割弱に当たる約70万トンは牛などの餌として活用されているものの、国産の稲わらだけでは需要を満たせず、中国から年間約20万トンを飼料用として輸入している。さらに、年度ごとの推移を見ても、国産稲わらの活用量は微減傾向だ。
需要があるにもかかわらず活用が進まない現状に対し、農林水産省は飼料としての稲わら活用を推進する施策を進めてきた。例えば、稲わらの購入を希望している畜産農家のリストをウェブサイトに掲載して農家とのマッチングを行っている。また稲わら収集に必要な機械や倉庫、飼料の流通に必要な保管施設の整備を支援する補助金も設定した。
稲わらの活用拡大を支援する地方自治体もある。例えば山梨県北杜市は、農協と協働し、稲わらを循環させる仕組みを作ったという。稲わらをロール状にする機械の導入を市が補助し、米農家で稲わらロールを作れるようにした。それを農協が管理する倉庫などに保管し、畜産農家に分配。米農家には、家畜の糞尿からできる堆肥を還元するという仕組みだ。
国内でもバイオ燃料化や圧縮の技術開発進む
日本の各地方自治体のウェブサイトには、すき込みによって稲わらを土づくりに活用するよう呼び掛ける記載が多く見られる。確かにすき込まれた稲わらは肥料になるが、温室効果がCO2の28倍ともいわれるメタンガスが多く発生するという課題もある。農家にとっては無料で使える肥料とも言える稲わらだが、気候変動対策の観点からは対策が求められている。
こうした要請に応えるため、新技術の開発が進む。農業機械などを手掛けるクボタは、京都大学や早稲田大学と連携して、稲わらからバイオ燃料や肥料を製造し、地域で資源を循環する仕組みを作る研究を進めている。すでに秋田県で実証実験施設が稼働しているという。
稲わらはかさばるため、輸送や貯蔵の難しさも課題だ。これに対しては、農業に関する研究開発を行う国の機関である農研機構と石灰メーカーの足立石灰工業が連携し、石灰処理を施した上で稲わらを圧縮する仕組みを開発した。石灰処理を施してから圧縮した稲わらは、石灰処理を施さずに圧縮した稲わらに比べて、密度が高く、かさばらない。またバイオ燃料への加工もしやすくなるため、原料としての稲わらの価値向上も期待できるという。
同じ「稲わらの活用」という課題でも、メコン地域と日本では現状が大きく異なっている。農業の慣行や法規制、畜産業など稲作以外の産業との関連性、協同組合の影響力や物流システムなど、さまざまな要因が絡み合う複雑な課題だ。とはいえ、環境負荷の少ない肥料への加工や、協同組合が主導する資源循環の仕組みなど、共通して生かせるノウハウもある。各地域での取り組みの進展が、互いに良い影響をもたらすことを期待したい。
茂木 澄花 (もぎ・すみか)
フリーランス翻訳者(英⇔日)、ライター。 ビジネスとサステナビリティ分野が専門で、ビジネス文書やウェブ記事、出版物などの翻訳やその周辺業務を手掛ける。