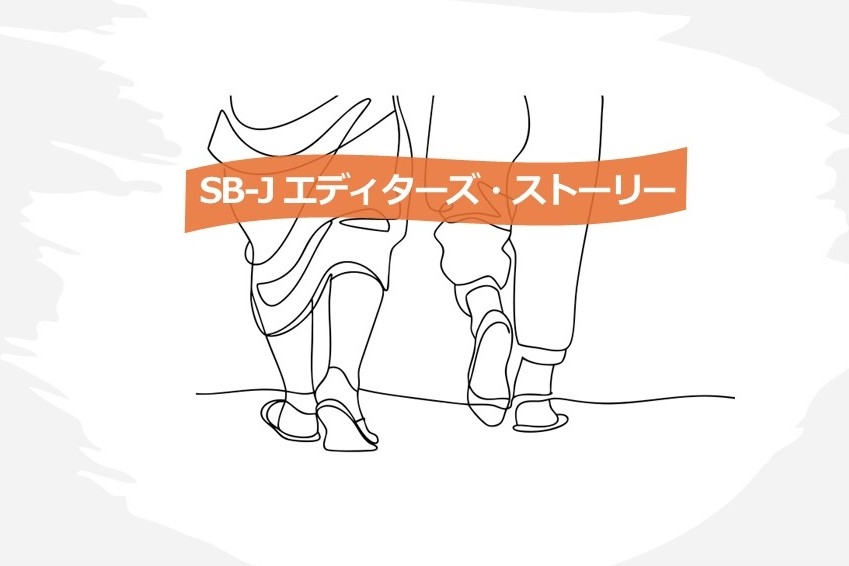
取材現場で心を動かされた言葉、記事にはならなかった小さな発見、そして、日常の中でふと感じたサステナビリティのヒント。本コラムでは、編集局メンバーの目を通したそんな「ストーリー」を、少し肩の力を抜いて、ゆるやかにつづっていきます。
今回の担当は松浦です。
始まりはクラウドファンディング

突然ですが、先日、ネパールに行きました。世界遺産観光? エベレスト登山? 違います。
「コーヒーの木の植樹」をしに行ってきました。その経験がとても記憶に残るものになったので、ご紹介したいと思います。
私が参加したのは、「BIKAS COFFEE(ビカスコーヒー) 植樹ツアー」。ビカスコーヒーは、東京都の江戸川橋に本店を置く、ネパール産の豆を取り扱うコーヒーショップです。クラウドファンディングで「自分のコーヒーの木のオーナーになる」というプログラムを見つけたことから始まりました。
そのクラウドファンディングは、「自分の木」を購入すると、その木がネパールの村の農園に植えられて、3年後に収穫された500gのコーヒー豆が届く、というもの。
もちろん支援だけして、3年後を楽しみに待つのも良いのですが、「せっかく自分の木が植えられるチャンスなら!」と思い、ツアーに参加することを決めました。
ネパール到着、第二の名を授かる!
ビカスコーヒーのオーナーの菅勇輝さんは、学生時代から途上国支援の活動をしており、卒業後はネパール出身のゴクールさんとNPO法人で活動。その後、2019年にネパール産コーヒー豆の流通をつくり、現地の雇用支援や地域開発につなげることを目的にビカスコーヒーをオープンしました。
ネパールではもともとコーヒーの栽培が盛んではありませんでしたが、気候変動の影響で、多様な食物を栽培していく「アグロフォレストリー(森林農業)」を進めたいという思いから、ハルパン村での植樹支援をスタートしたそうです。ハルパン村での栽培は順調に5年目を迎えており、今回のツアーは初めて、ゴクールさんの生まれ育った「ダリンボット村」で植樹を行うものでした。
飛行機の遅延で遅れて到着したわれわれを迎えてくれたビカスメンバー。ネパール式の歓迎でカタ(スカーフ)を首にかけてもらい、ネパールでの名前を授かりました。植樹ツアーなど、ゴクールさんとネパールに訪れると全員、「ネパールネーム」を命名してもらえるそうです。
私の名前は、『prakriti (プラクリティ)』。ネパール語で「自然」という意味です。(「みどりこ」という日本名ではなく、最初に会った印象からつけているそう。すてきな名前で、とても嬉しかったです!)

ツアーは、ゴクールさんの案内の下、カトマンズの世界遺産を巡るところから始まります。仏教とヒンドゥー教が入り交じるネパールで、初めて見る儀式やしきたりも教わります。(このツアーも学びの深いものでしたが、今回は植樹を中心に)
ゴクールさんの生まれ故郷、ダリンボット村へ

標高1200mのカトマンズから、さらに標高が高い地域へ。舗装されていない道を東にガタガタと進むこと2時間半。標高1500mに位置するのが、人口700人ほどのダリンボット村です。
山の斜面の緑の木々の中に家が点々と建っています。斜面を滑るように歩いて下り、ゴクールさんの「実家」に到着。そこでは、たくさんの村の方が迎えてくれました。
この村では、ゴクールさんの兄アルジュンダイさんを中心に、約30人の村の方がコーヒーの栽培を始めています。皆さん、トウモロコシや唐辛子などたくさんの作物を栽培していますが、複数の収入源の確保のため、そして日本の消費者のためにコーヒーの栽培も始めてくださっているそうです。

ダリンボット村からすると、初めての植樹体験ツアー参加者の訪問。お互いにそわそわしながら、Google翻訳を使ってなんとか身振り手振りで村の皆さんと交流をします。

歓迎に、ダルバード(ネパールの代表的な家庭料理)をおなかいっぱいいただいたら、植樹の時間です。コーヒーに適した斜面、日陰になる場所を探しながら、コーヒーの苗を一つひとつ手で植えていきます。
「村を支える力になってほしい」
着いてから改めて気づきましたが、ここはトラクターも入れない山の斜面。「植えるところ」と「歩くところ」が整備されているわけでもなく、野生の木もたくさん。トウモロコシのエリアと、コーヒーのエリアが分かれているわけでもありません。
背の高いトウモロコシの間にコーヒーを植えることで、トウモロコシの日陰がコーヒーにとってちょうど良い環境になる――。そんな農業が行われていました。

「アグロフォレストリー」という言葉はもちろん知っていたものの、日本にあるような整備された畑しかイメージが無かった私は、これが自然との共生というものか、と生で見たアグロフォレストリー農法に関心しながらも、「ちょっと服装間違えたかも」と思いました。
多様な植物が生い茂る斜面をかき分け、滑りそうになりながら、植えられそうなところを探して自分の選んだ苗を植えます。
コーヒーは、2年目から実がなり、3年目から収穫できるようになるそうです。この、自分の手で植えた苗が、いつか大きくなり自分の手元に届くのかぁと思うと、とても感慨深いものです。(ワイルドに手で穴を掘り、手で埋めるスタイルです)

コーヒーの木には、「みどりこ prakriti」と書いたプレートをつけました。自然の一部であるような自分の本名もとても気に入っていますし、名付けてもらった「自然ーprakritiー」も自分の人生の大切にしているものに通じるようで、大切な名前になったからです。

クラウドファンディングとしては3年で一度終わる予定ですが、この自然とともにこのコーヒーの木が、何年も村を支える力になってほしいと思い、プレートを書きました。
価値ある瞬間に立ち会う
それぞれ自分の木を植樹した後は、他のコーヒーの木の植樹と畑の整備のお手伝い。

「それは雑草!抜いて!それは唐辛子!抜いちゃダメ!」とゴクールさんの指示の下、子どもたちも一緒に雑草を素手で引っこ抜いては投げ捨てながら、新しい苗を植えていきます。
どこまでいっても山。でもこの環境が水切れの良さだったり、多様な植物同士で影と日当たりを作り、朽ちた葉が養分になってコーヒーが育つんだ、と自然の力強さを感じずにはいられませんでした。
夜は、みんなでたき火を囲みながら交流。ゴクールさんの兄弟もみんな集まり、ネパールビールを片手に、日本のことや村のこと、ビカスコーヒーのこれからのことなどをみんなで語り合いました。
ゴクールさんは5人兄弟。長男のアルジュンダイさんが、この村でのコーヒー栽培のリーダーです。今年、アルジュンダイさんを中心に植えたコーヒーの木はなんと2400本! 全て、自分が経験した手作業だと思うと気が遠くなる量です。
来年以降もどんどんコーヒーの木を植えて、収穫して村の収入にしていきたいと意気込むアルジュンダイさんの目はキラキラしていて、この地に、このタイミングで来れて本当に良かったとかみ締めました。

もともとは「自分だけのコーヒーが届く!」というところに面白みを感じていましたが、このコーヒーが今後はダリンボット村の一部として、自然の中に溶け込み、生物多様性を育み、毎年コーヒーの実をつけて、村の収益になっていく。そんな未来を想像すると、とても価値のある瞬間に立ち会えたように感じました。
究極の「生産者が見える」
ちなみに、ネパールは断トツで「紅茶文化」。朝は、ホテルでも村でも「チヤ」と呼ばれるミルクティーを出してくれます。(インドのチャイとは違い、スパイスは入っていません)

菅さんが 「育てるコーヒーがどんな味か知ってほしい」と、その場でコーヒーをドリップして淹(い)れてくれましたが、みんな飲み慣れないブラックのドリップコーヒーに渋い顔。コーヒーを好きになるにはまだ時間がかかりそうですが、きっと村の方たちが育てた豆で淹れたコーヒーは格別においしいはず。

生産者の孫まで見えちゃったもん。この環境を守りたいって、心底思いました。コーヒー豆が届くのは、3年後の2028年の春。そのころ、村は、村の人たちはどうなっているんだろう。ダリンボット村が、私が植えた木と、一緒にビカス(ネパール語で発展)できることを願っています。
松浦 緑子
サステナブル・ブランド ジャパン編集局 パートナー
2020年〜2025年までSB JAPANのイベントディレクターとして携わる。現在は、イベント会社の広報に携わる傍ら、SB-Jのほか、サステナビリティ・エシカルを軸に活動中。アウトドアが趣味。















