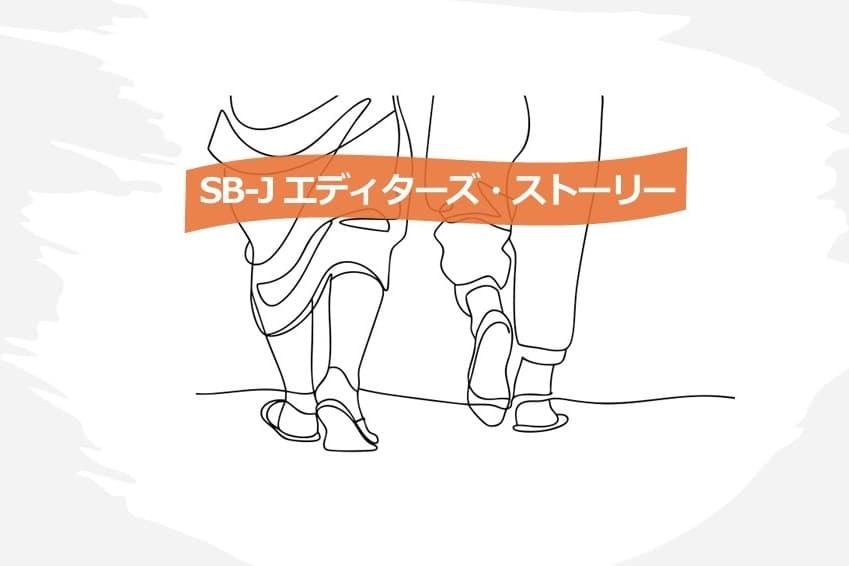「服を着ていないCEOがいる組織を想像してみてください」──今では古典となったエリザベス. W. モリソンとフランシス. J. ミリケンの論文「Organisational Silence: A Barrier to Change and Development in a Pluralistic World」(訳:組織的沈黙:多元的世界における変革と発展の障壁)にそう書かれています。さらに、論文はこう続けます。「従業員は誰もそのこと(CEOが服を着ていないこと)を口にしません。なかには、CEOの服装をほめる人さえいます」。
これは非常に的確な比喩です。職場での沈黙、そしてそれが静かに信頼をむしばむ様子を、これほど鮮明に描き出すイメージはありません。なぜなら、すべてのESGデータの背後には人間の物語があり、時には誰も口にできない真実が隠されているからです。
簡単に数値化できないものを忘れてしまうリスク
私たちは、サステナビリティ報告がかつてないほど進化した時代に生きています。EUの企業サステナビリティ報告指令(CSRD)や新しい欧州サステナビリティ報告基準(ESRS)は、企業が人や地球に与える影響を測る方法を大きく変えつつあります。従業員の離職率やジェンダーバランスから、メンタルヘルス休暇や内部告発制度に至るまで、あらゆる指標が用意されるようになりました。しかし、測定すればするほど、簡単には数値化できないもの――人々の声や主体性、幸福――を忘れてしまうリスクも高まります。
データは「何が起きたか」を示します。人の声は「なぜ起きたか」を説明します。

近年、欧州の企業は、サステナビリティのこの“人間的側面”を再発見しつつあります。それは単なるソフトデータではなく、長期的な価値の基盤として位置付けられています。
例えばオランダに本拠を置く金融サービスのINGは、メンタルウェルビーイングをサステナビリティ戦略に組み込み、マネージャーに早期のストレス兆候を認識させる研修を行い、バーンアウト予防をESGのパフォーマンスの一部として扱っています。
テクノロジー企業のシーメンスは、ドイツの長い伝統である「Mitbestimmung(共同決定制度)」を継続的に適用し、従業員代表が監督委員会に直接参加することで、労働者の声が人事政策だけでなくサステナビリティ目標にも反映される仕組みを作っています。
そして北欧では、通信サービスのテリアがデジタル製品設計において人権やメンタルヘルスを考慮し、単にデータをどう収集するかではなく、それが人々の自律性やプライバシー感覚にどのように影響するかを問う取り組みを行っています。 これらの事例には共通点があります。それは、ESGを単なる測定の作業から、『働くうえでの人間らしさを問いかける対話』へと変えている点です。これらの企業が私たちに教えてくれるのは、企業の最大のサステナビリティ上の課題は、もしかするとカーボンフットプリントではなく、いかに人の声に耳を傾けるか、という「聞く力のギャップ」かもしれないということです。
組織的沈黙は伝染する
人々が実際に経験していることと、リーダーが耳にすることの間にあるこのギャップこそ、研究者が「組織的沈黙(organisational silence)」と呼ぶものです。それは、学習やイノベーション、信頼を阻む見えない障壁です。
沈黙は、階層が強く、フィードバックが安全に行えず、懸念を表明すると「それはあなたの仕事ではない」と言われる文化の中で繁殖します。私たちは、残念ながらキャリアのどこかで必ず一度はそんな経験をしており、このパターンがいかに有害かを知っています。時間が経つにつれて沈黙は習慣となり、人々は声を上げなくなります。それは関心がないからではなく、自分の声が何かを変えるとは信じられなくなるからです。
皮肉なことに、沈黙は伝染します。リーダーは問題を耳にしないため、すべてが順調だと思い込み、従業員はその静けさを無関心だと受け取ります。こうして組織は前に進み続けます──裸のまま、しかもとても称賛されていると感じながら。

欧州では、この沈黙に対して実践的に取り組む動きがいくつか見られます。オランダやイギリスでは、従来のコンプライアンスチェックに加え、職場文化や心理的安全性を評価するウェルビーイング監査が増えています。フランスの「つながらない権利」法は、勤務時間外の業務連絡から従業員を守り、個人の時間を特権ではなく尊重として取り戻すことを目的としています。
さらに北欧諸国では、経営陣と従業員の間で定期的・構造的に行う協議や対話(ソーシャルダイアログ)が、ガバナンスのDNAに組み込まれています。これらは極端なアイデアではなく、真実を安全に伝えられる仕組みです。
ESGの未来を切り開くのは、データと声を融合させる企業
日本に限らず、多くの組織にとって、これは難しい課題のように思えるかもしれません。階層構造はコミュニケーションを形づくり、文化的・企業的な調和は時に正直さを犠牲にすることがあります。しかし、正直さのない調和は脆いものです。ESGへの期待が世界的に広がるなかで、企業は単に報告するだけでなく、従業員の声にどう耳を傾けているかを示すことがますます求められるでしょう。
ESGの未来を切り開くのは、データと声を融合させる企業です。人を単なるデータポイントとしてではなく、持続可能なビジネスを共に形作るパートナーとして扱う企業です。数字は私たちがどれだけうまくやっているかを教えてくれますが、声だけが、私たちがどのような存在になろうとしているのかを示してくれます。

ベッティーナ・メレンデス
戦略立案、マーケティング、ビジネスデザインを専門に国際的に活躍。オランダ領キュラソー島政府観光局やベルリンのスタートアップで経験を積み、10代の頃からNGO活動に携わるなど、社会貢献にも積極的に取り組み、サステナビリティに関する幅広い知見を持つ。2021年に顧客体験を重視した幅広いデザインを提供するニューロマジックに参画。2024年からはニューロマジックアムステルダムのCEOおよび東京本社の取締役CSO(Chief Sustainability Officer)に就任し、持続可能な未来の実現に取り組む。 現在はオランダ・アムステルダムを拠点に活動中。社会・環境・経済のバランスを考慮したビジネスの推進に尽力している。