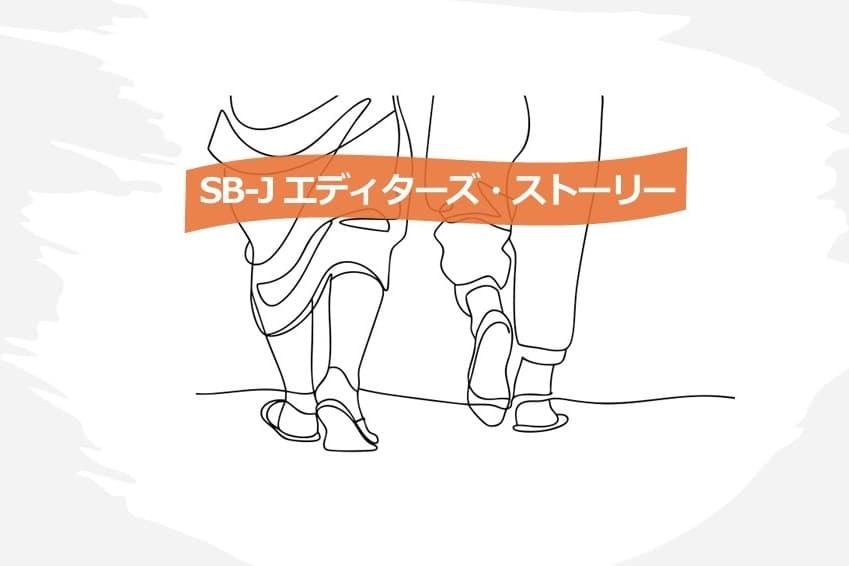Sponsored by UL Solutions

欧州のCSRD(企業サステナビリティ報告指令)や国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)の基準公表など、非財務情報の透明性を求める動きが急速に広がっている。投資家や規制当局だけでなく、顧客や取引先もESG情報を重要視し、サプライチェーン全体にまで開示要請が及ぶケースも増加。効率的かつ信頼性の高いデジタル基盤の重要性が高まる中、UL Solutionsが提供するESGマネジメントプラットフォーム「UL 360」に注目が集まっている。どのような特徴があり、日本企業にとっての導入意義は何か――。UL Japan環境サプライチェーン事業部 サステナビリティグループ・マネージャーの織戸香里氏に聞いた。
UL Japan環境サプライチェーン事業部 サステナビリティグループ・マネージャー
UL Solutionsの歩みと日本法人の役割
――まずは御社全体の概要から伺いたいと思います。御社は「製品の安全認証」で世界的に知られていますが、最近ではESG領域のサービスも拡大されています。
織戸香里(以下、織戸) UL Solutionsは1894年に米国シカゴで設立されました。「より安全な世界を目指して(Working for a safer world)」をミッションに掲げ、130年以上にわたり安全科学をリードしてきました。多くの方には「ULマーク」でおなじみの製品安全試験・認証のイメージが強いと思いますが、現在はそれにとどまらず、環境試験や規制対応、さらにはデジタルソフトウェアやアドバイザリーまで領域を広げています。
製品の安全認証などを手掛ける一方で、ESG(環境・社会・ガバナンス)情報の開示を支援する「UL 360」の提供など、ソフトウェア分野にも注力しています。
安全概念の拡大とESG領域への進出
――UL Solutionsといえば「安全」の代名詞ともいえる存在ですが、なぜESGソフトウェアという新しい領域に踏み込んだのでしょうか。
織戸 背景には「安全」概念の拡大・発展があります。創業期には電気製品の火災リスクが焦点でしたが、今では環境汚染や気候変動、労働安全、ガバナンスといった要素が「安全で持続可能な社会」に不可欠です。つまり、サステナビリティなくして真の安全は実現できない、という考え方です。こうした「安全の定義の広がり」に合わせてサービスを進化させ、製品の安全認証や環境試験で培った知見を生かしたソフトウェア事業として、ESG領域に参入しました。
ESGデータを一元管理する「UL 360」
――具体的に「UL 360」とはどのようなプラットフォームなのでしょうか。
織戸 UL 360は、企業が持つ多様なESGデータを一元的に収集・管理し、国際的な基準に沿った開示(レポーティング)や継続的な改善に向けたデータ活用までを支援するソフトウェアです。二層構造が特徴で、まず自社グループ内のデータを集約する「ベースシステム」があります。そしてもう一つが、サプライヤーからの情報を収集する「サプライチェーンシステム」です。これによって温室効果ガス排出量やエネルギー使用量、労働安全指標など幅広いESGデータを効率的に集めることが可能で、社内外の必要データを一つの基盤に集約できます。

また、データ品質の信頼性確保や各種報告基準への迅速な対応を重視して設計しています。 CDP(気候変動などに関する情報開示の国際的枠組み)、GRI(グローバル・レポーティング・イニシアチブ)はもちろん、最新のCSRDの開示項目にも対応。あらかじめ用意された質問に沿って入力するだけで、報告書やCDP回答を効率的に作成できます。すでにシステム上にあるデータは自動でマッピングされるため、重複入力の手間も削減できます。基礎データをUL 360に蓄積しておけば、CSRDやISSB/SSBJで新たな開示要求が生じても速やかに対応可能です。
UL 360はグローバルで多くの企業に導入いただいており、製造業や金融、サービス業など幅広い業界で活用されています。導入形態は3種類あり、標準機能をすぐ使いたい企業には「パッケージ製品」を、標準機能に一部設定を加えたい場合は「パッケージ製品プラス」を、より複雑で大規模な要件を持つ場合には「テーラーメイド」を提供しています。企業規模やニーズに応じて段階的に選択できるのは、大きな強みです。
スコープ3対応を支える機能
――ESGデータの中でも、特に難しいのがスコープ3だとよく言われます。UL 360はこの領域をどうカバーしているのでしょうか。
織戸 本当にその通りで、多くの企業が最も苦労しているのがスコープ3です。UL 360にはサプライチェーン専用のデータ収集システムがあり、取引先に入力を依頼してデータを集約・分析できます。例えば購入した原材料や部品ごとのCO2排出量をサプライヤーに入力してもらい、自動で集計するといったことが可能です。
導入に当たっては「まずは主要な一次取引先(Tier 1)のうち影響の大きい10社から」といった現実的な範囲を設定し、段階的に対象を広げていきます。「自社だけではサプライチェーン全体のCO2排出量が把握できない」という企業でも、UL 360を通じて、取引先を巻き込みながらデータ精度を高めることができます。
柔軟なモジュール設計とUL Solutionsならではの強み
――ここ数年、ESGデータ管理やサステナビリティ情報の開示を支援するソフトウェアが続々とローンチされています。競合が多い中で、UL 360のユニークさはどこにあるのでしょうか。
織戸 一つは、高度な柔軟性と拡張性です。UL 360はモジュール式の構造を採用しており、企業の状況に合わせて機能を拡張できます。標準機能から使い始め、必要に応じて機能を追加していけるため、導入規模や段階に応じた柔軟な展開が可能です。
もう一つは、UL Solutionsが安全科学や環境分野で培った知見を反映している点です。グローバル標準への先進対応も特長で、規制動向を常にモニタリングし、製品設計に組み込んでいることは大きな強みです。UL 360は最初からGRIやISSB/SSBJ基準に沿った項目や管理機能が備わっており、基準の改定があれば、ソフトウェア側でアップデートを迅速に提供します。国際的な独立調査会社Verdantixの評価でも、UL 360は「リーダー」に選ばれています。機能性や柔軟性、ユーザーからの評価が総合的に認められた結果です。
導入プロセスと支援
――新しいシステム導入には不安も伴います。実際のプロジェクトはどのように進むのでしょうか。
織戸 テーラーメイドの一例をご紹介すると、プロジェクトの立ち上げ、詳細設計、構築、テスト・受入、トレーニング、システム稼働といった流れになります。テーラーメイド型の大規模プロジェクトの場合、稼働まで1年以上かかるケースもありますが、限られた範囲でまず導入するパッケージ型であれば、最短6週間ほどで稼働した実績もあります。このように、導入スコープや企業の体制に応じて柔軟に期間・規模を調整できるのも特徴です。
サポート体制については、弊社の導入チームがお客様のプロジェクトメンバーと共同で進める伴走型支援が基本です。

システム周辺の業務プロセス設計や運用フローの構築も含めて、丁寧にお手伝いしています。例えば、「どの部門にどのデータ入力を任せるか」「社内のどの承認フローに組み込むか」といったポイントも含め、一緒に検討し設定を進めます。
また、開発から運営まで一貫した管理がUL 360の強みの一つですが、外部パートナーとの連携も進めています。システム構築に強みを持つ企業やESG動向に強みを持つ企業などと協業し、UL 360の導入支援体制を拡充する考えです。こうしたネットワークを通じて、大規模プロジェクトからスピード重視の導入まで、幅広く対応できるのがUL 360の強みです。
日本企業特有の課題に寄り添う
――日本企業特有の課題について伺います。業務の属人化や社内調整の難しさが指摘されます。
織戸 多くの企業では長年エクセルでデータを管理してきましたが、ファイルが複雑化して担当者しか中身を理解していない、担当者が異動・退職すると引き継ぎが困難になる、といった問題があります。UL 360は一元的に管理できるため、人によるばらつきやミスが減り、共通のプラットフォームを使うことで組織的なナレッジの蓄積も可能になります。実際、「担当者が1人で抱えていたCDP報告作業をチームで分担できるようになった」「データ更新の履歴が残るので監査対応の不安が減った」といった声も聞かれます。
日本企業は現場ユーザーの負担や合意形成に細心の注意を払う傾向があります。この点を弊社も十分理解しており、グローバル標準の実装方法をそのまま持ち込むのではなく、日本のお客様に合った進め方を意識しています。例えばシステム導入時も、各部署の担当者を巻き込みながら少しずつ範囲を広げるアプローチを取り、「使ってもらいながら定着させる」ことを重視します。ユーザーに寄り添ったサポートを提供することで、結果的にデータ入力率や精度の向上につなげています。
サステナビリティ経営の基盤に
――今後の展開についても教えてください。

織戸 UL 360は常に機能強化と進化を続けています。直近では、製品ごとのカーボンフットプリント(PCF)算定機能をリリースする予定です。製造業を中心に「製品単位でのCO2排出量を見える化したい」という声が強まっており、それに応えるものです。この機能の追加により、企業単位の削減目標だけでなく製品レベルでの環境インパクト評価も一貫して行えるようになります。製造業など製品別の環境性能を競争力と捉える業界にとって、大きな武器になると考えています。
今後もグローバルでの規制動向に合わせたアップデートは続きます。ISSB/SSBJや各国のサステナビリティ基準が更新・拡充されれば迅速にソフトウェアへ反映し、ユーザー企業が常に最先端の対応を取れるよう支援していきます。また、お客様からのフィードバックを元に「この機能が欲しい」という声を拾い上げ、UL Solutionsの開発チームがスピーディーに具現化するサイクルを維持します。われわれの原点である「より安全な世界を目指して」というミッションの下、サステナビリティ経営の基盤になる仕組みづくりに尽力してまいります。
| UL 360の詳細・お問い合わせはこちら |
眞崎 裕史 (まっさき・ひろし)
サステナブル・ブランド ジャパン編集局 デスク・記者
地方紙記者として12年間、地域の話題などを取材。フリーランスのライター・編集者を経て、2025年春からサステナブル・ブランド ジャパン編集局に所属。「誰もが生きやすい社会へ」のテーマを胸に、幅広く取材活動を行う。