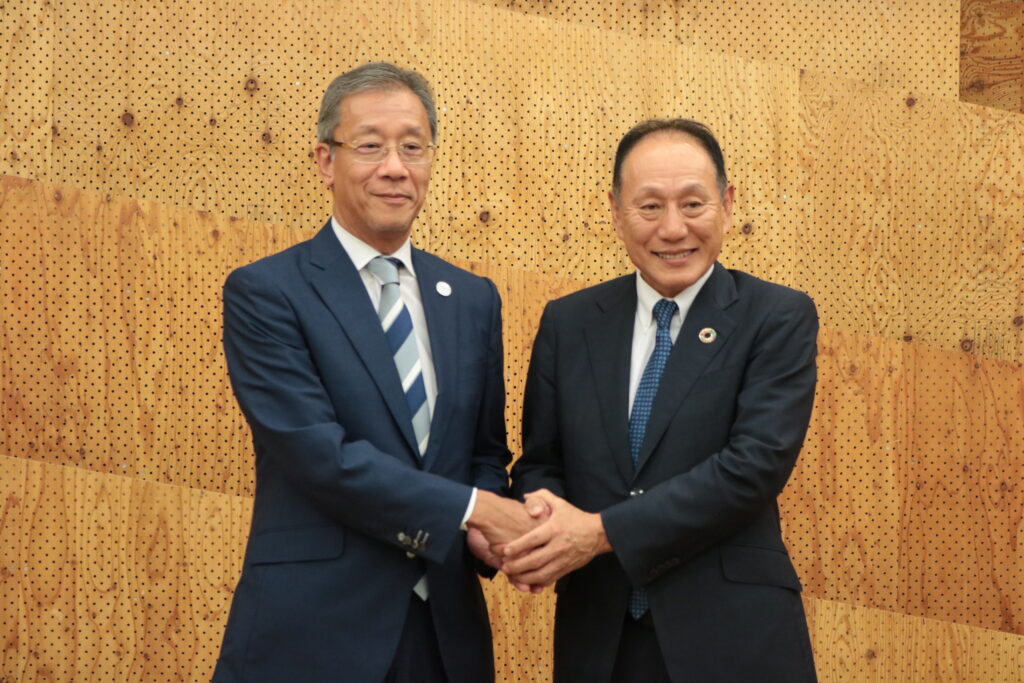
東京大学と大和ハウス工業は2025年10月1日、大和ハウス工業からの10億円の寄付を基に、エンダウメント(大学独自基金)型の研究組織として「東京大学住宅都市再生研究センター」を新設した。気候変動や少子高齢化など、複雑に絡み合う社会課題の解決に向け、住宅・都市の再生という観点から分野横断的な研究を、寄付金の運用益を使うことで「恒久的に」推進するという。産業界とアカデミアががっちりと手を組んだ、持続可能な社会の実現に向けた新たな知の拠点として注目が集まりそうだ。
複合的課題に、運用益を財源として恒久的に挑む
新設されるセンターの最大の特徴は、大和ハウス工業からの10億円の寄付金を元手にした「エンダウメント型研究組織」である点だ。これは、寄付金を大学独自の基金として運用し、その運用益を恒久的な財源とする仕組みを指す。従来の数年単位で運営される寄付講座とは異なり、長期にわたって安定的に研究を推進できるため、腰を据えた研究活動が可能となる。東京大学の藤井輝夫総長は「このような組織は、本学における未来志向の知の創出を支える重要な柱」とその意義を強調。この形態は、東京大学では個人寄付による「応用資本市場研究センター」、いすゞ自動車からの寄付を受けた「トランスポートイノベーション研究センター」に続く3例目となり、大学の本気度がうかがえる。

センターが挑むのは、現代社会が直面する複合的な課題群だ。気候変動への適応と緩和、少子高齢化社会における新たなコミュニティ形成、生物多様性の保全、大都市における住宅価格の高騰問題、そして人口減少下での既存建築ストック(空き家など)の有効活用。これら個別の課題に個別に対処するのではなく、「住宅・都市の再生」という包括的な視点から解決の糸口を探る。さらに、センター長に就任する小泉秀樹教授(東京大学大学院工学系研究科)は、「『職場と家庭以外に居場所がない』といった現代日本のウェルビーイングに関わる課題も、都市の構造と密接に関係している」と指摘しており、研究の射程は広い。
そのアプローチは、学内にとどまらない。情報技術、気候変動、社会科学など、学内の多様な研究組織と連携するほか、国内外の大学やUN-Habitat(国連人間居住計画)のような国際機関、国の省庁や自治体、そしてスタートアップから大企業まで多様な産業界のプレイヤーとの連携を視野に入れる。アカデミックな研究成果を、実社会で機能する技術革新や具体的な政策・制度の設計・提言へとつなげ、社会実装させることを最終的な目標としている。
「理念の共鳴」と「作った責任」
センター新設についての記者発表会は、2014年に大和ハウス工業が寄贈した東京大学本郷キャンパス内の「ダイワユビキタス学術研究館」で実施。登壇者からは、それぞれの立場での強い思いが語られた。
東京大学の藤井総長は、大和ハウス工業の創業者・石橋信夫氏の「何をやったらもうかるかではなく、どういった事業が世の中の役に立つかを考えるべき」という理念に言及。「この理念は、公共性に奉仕するという私たちの使命とも深く共鳴するもの。志を同じくする大和ハウス工業さまと手を取り合い、社会に資する研究に共に挑戦できる」と述べ、今回の連携が資金提供を超え、理念を共有したパートナーシップであることを強調した。
一方、大和ハウス工業の芳井敬一代表取締役会長は、今回の寄付に至る長年の取り組みを語った。同社は1962年以降、全国で大規模戸建て住宅団地「ネオポリス」を開発してきたが、その多くが近年、少子高齢化や空き家の増加といった課題に直面している。これに対し、同社は「作った責任」を果たすべく、2015年から住民や行政を巻き込んだ団地再生事業に着手。さらに、2024年には住民や行政、専門家を招いた「ネオポリスサミット」を開催するなど、産官学民連携のプラットフォーム構築に注力してきた。
同社の目的は、こうした自社の団地再生事業で得た知見や課題意識を社会全体に還元することだ。「当社の団地のことだけではなく、広く多くの方に知見を共有すること、それが我々の創業者の考えです」と芳井会長は語る。東京大学という研究拠点がハブとなることで、より普遍的な社会課題を解決することに期待を寄せた。

センターでの研究をけん引する小泉教授は、「新しい都市の在り方を構想し、制度として定着させるには5年、10年といった長いスパンの仕事になる」と長期的なビジョンを語り、エンダウメントという仕組みがそれを支えることの重要性を指摘した。
一企業の「作った責任」を果たすという意志が、大学の「公共性への奉仕」という使命と交わり、社会の未来を構想する新たな拠点が生まれる。この産学連携が、持続可能な都市の実現に向けた確かな一歩となることが期待される。
横田 伸治(よこた・しんじ)
サステナブル・ブランド ジャパン編集局 デスク・記者
東京都練馬区出身。毎日新聞社記者、認定NPO法人カタリバ職員を経て、現職。 関心領域は子どもの権利、若者の居場所づくり・社会参画、まちづくりなど。










