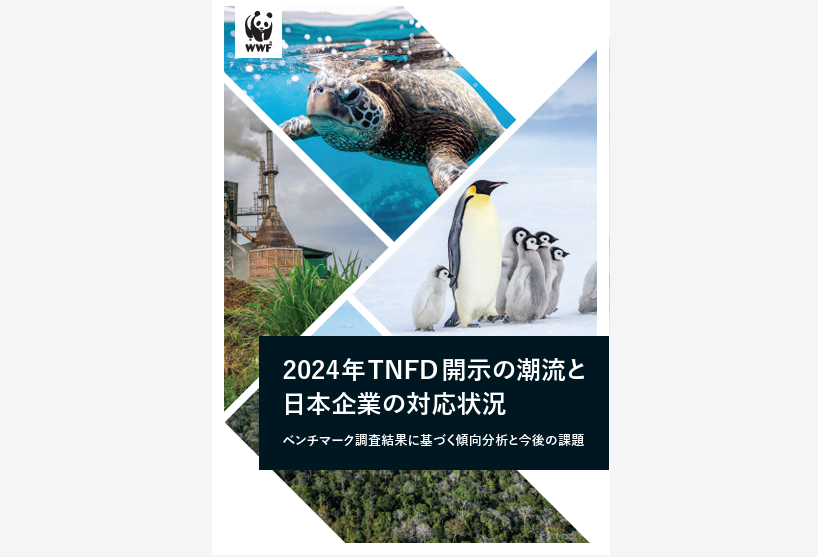
TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)への対応において、日本企業は世界をけん引する「優等生」とされる。環境省によると、2024年と2025年の会計年度においてTNFD開示を公表予定として登録した企業は、全562社中、日本は154社で世界最多。しかし、その開示の質は、本当に世界をリードしているのだろうか。
WWFジャパンは2025年8月、日本企業65社を対象とした調査報告書「2024年TNFD開示の潮流と日本企業の対応状況」を公表。2024年における企業の取り組み状況を分析したこの報告書は、積極的な開示姿勢を評価する一方で、真の自然共生型事業への転換に向けた課題も浮き彫りにしている。
マテリアリティ・アプローチへの基本理解に課題
報告書は、アサヒグループホールディングス、花王、ソニーグループなど、多様な業種の主要企業計65社を対象に、各社のTNFD開示が自然への依存・影響関係をどれだけ的確に捉え、事業変革につなげようとしているかを独自の「キーポイント」に基づき評価・分析したもの。
報告書によると、2024年のTNFD開示における最も基本的な課題としては、マテリアリティ・アプローチの理解不足が挙げられた。TNFDでは財務マテリアリティの採用が「必須」とされた上で、自然への包括的な影響を分析するインパクトマテリアリティを含めたダブルマテリアリティ・アプローチが「推奨」されている。企業側にはどのアプローチを選択・採用したかの明示が求められているが、調査対象65社のうち、採用した方法を明示していた企業はわずか13社(20%)だった。
「直接操業」と「バリューチェーン」の明暗
事業活動の「何の要素が」「どこで」「どのように」自然に依存、影響しているのかを分析する「自然関連課題の特定・評価」では、直接操業(自社拠点)とバリューチェーンで明暗が分かれた。直接操業分析では40%の企業が高評価を獲得し、比較的進展している。住友林業は優良事例として、自社操業とサプライチェーンの拠点を地図上に示し、重要地域の特定プロセスまで開示している。
バリューチェーン分析は大きく遅れ、高評価はわずか19%だった。43%の企業が汎用(はんよう)分析ツールによる業界一般の分析に留まり、原材料のトレーサビリティ確保が最大の課題となっている。コーセーは「水」への依存を特定・開示したが、「周辺の生態系に関する情報が不足しているため、十分に影響の分析ができていない」とも記載。報告書は、情報ギャップがどこにあるか特定されたことで、今後情報収集のためのパートナーシップやデータツールの開発に寄与する可能性を指摘した。
戦略の実効性に疑問も
自然へのマイナスインパクトの回避・軽減に取り組む「ミティゲーション・ヒエラルキー」については、一定程度の理解が進んでいるものの、実効性のある戦略構築には課題が残るとされた。過半数の企業が何らかのマイナスインパクト回避・軽減の取り組みを示したが、全体の18%はスポット的な事例紹介に留まり、体系的な計画に基づかない状況が確認された。
直接操業では「節水」が最も多く取り組まれており、コスト削減との親和性が高かったことが指摘されている。バリューチェーンでは「森林破壊ゼロ方針」や「責任ある鉱物調達」を掲げる企業が多いものの、方針から実際の運用段階への移行が今後の重要課題となっている。
王子ホールディングスは、包括的な取り組み事例として注目される。同社は「持続可能な森林管理方針」と「森林破壊・転換ゼロコミットメント」を策定し、生物多様性、土壌、水資源保全のモニタリング体制を構築している。さらに森林の再生・回復に向けた測定指標とターゲットを設定し、回避・軽減から再生・回復まで一貫したミティゲーション・ヒエラルキーに沿った戦略を展開している。
ただし、多くの企業でコミットメントの質、時間軸、測定指標の適切性、進捗開示において課題が残る。森林破壊ゼロを宣言しながら、森林破壊ゼロを保証しない認証品の調達率を指標とする例や、30年後のような長期すぎる目標設定など、実効性に疑問が残る開示も散見された。
先住民族・地域社会との関係構築では革新的事例も
IPLC(先住民族と地域社会)との関係構築は最も遅れている分野となった。自然関連課題とIPLCを関連づけた認識は十分に広がっておらず、高評価とされる「星3つ」に到達した企業はわずか3社だった。全65社が国際的な人権規範への賛同を表明していたものの、人権デューデリジェンスの範囲に地域住民や先住民族を含め、誰もがアクセス可能な苦情処理窓口を設けている企業は28%に留まった。
一方で、革新的な取り組みも紹介されている。花王はパーム油調達において、インドネシアの独立小規模農家からの苦情や問い合わせを直接受け付ける仕組みを構築した。言語や認知面でのアクセシビリティに配慮し、対象農園数、問い合わせ件数、対応状況まで透明性をもって開示している。この事例は、困難とされるバリューチェーン上流でのステークホルダーエンゲージメントが実現可能であることを示している。
義務化が進む中で、率直かつ積極的な開示を
欧州では企業サステナビリティ報告指令(CSRD)により、大企業に自然関連情報を含むサステナビリティ開示が義務化されており、日本企業の欧州子会社も対象となる。国内では、サステナビリティ基準委員会(SSBJ)が自然関連開示基準の検討を進めており、TNFDを参考とした基準策定により任意開示が段階的に義務化される可能性もある。
こうした制度化の流れは、企業にとって競争優位性を築く機会でもある。例えばコーセーのように、現在TNFD開示で「分からないこと」を率直に開示している企業の姿勢は、社会全体の知見蓄積に貢献している。企業の積極的な開示により先例が蓄積され、分析手法の改善が進むことで、全体的な開示品質向上が期待される。自然と共存する事業モデルへの変革は始まったばかりだが、透明性の高い開示を通じて実効性のある取り組みを推進する企業が、持続可能な未来をつくる原動力となるだろう。
| WWFジャパンの報告書「2024年TNFD開示の潮流と日本企業の対応状況」はこちらから |
横田 伸治(よこた・しんじ)
サステナブル・ブランド ジャパン編集局 デスク・記者
東京都練馬区出身。毎日新聞社記者、認定NPO法人カタリバ職員を経て、現職。 関心領域は子どもの権利、若者の居場所づくり・社会参画、まちづくりなど。











