
2025年3月、SSBJ(サステナビリティ基準委員会)は日本独自の「企業のサステナビリティ情報の開示基準」を公開した。これにより上場企業には2027年3月期以降、Scope1、2、3の排出量を含めた、より具体的な情報開示が求められるようになる見通しだ。これを背景に「Scope3への取り組みをどう進めるか」が今、企業の大きな課題となっている。このセッションでは、国を挙げて脱炭素の道筋を示している環境省や、Scope3への対応を先行して進めている日清食品、アストラゼネカ、第一三共からパネリストを招き、「これからのバリューチェーン全体の情報開示」についてディスカッションした。
| DAY1 ブレイクアウト ファシリテーター 山吹善彦・Sinc 統合思考研究所 副所長 上席研究員 パネリスト 杉井威夫・環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 脱炭素ビジネス推進室 室長 横山之雄・日清食品ホールディングス 取締役・CSO 兼 常務執行役員 長町井須美・アストラゼネカ 財務本部 購買部長 有馬覚・第一三共 サステナビリティ部企画グループ 主幹 |
義務開示が迫るScope3 取り組みのヒントは
セッション冒頭、ファシリテーターの山吹善彦氏は超満員の会場に向けて、「情報開示、Scope3対応への関心の高さが伺える。自社だけが売上を上げればいいという時代ではなく、バリューチェーン全体で共通の目標を持たなければ事業は成立しない」と強調した。
環境省の杉井威夫氏は、日本が掲げる「2050年ネットゼロ実現」に向け、次期NDC(温室効果ガス削減目標)で「2035年60%、2040年73%の削減」と示されたことについて、「野心的な目標だが、ネットゼロを実現しないことには未来はない」と表現。政府もバリューチェーン全体での脱炭素化促進を重要課題としており、「さまざまな施策集の提供やモデル事業認定などを進め、事業会社およびサプライヤー、業界単位での取り組み支援を引き続きしていきたい」と語った。

こうした国の推進方針の下、各企業はどのように取り組みを進めているのか。日清食品の横山之雄(ゆきお)氏は同社の環境戦略「EARTH FOOD CHALLENGE 2030」について紹介。「Scope1+2で42%減、Scope3で25%減(ともに2020年比)を目標にするなど、具体的な数値、定量目標を掲げて達成を目指している」と語った。
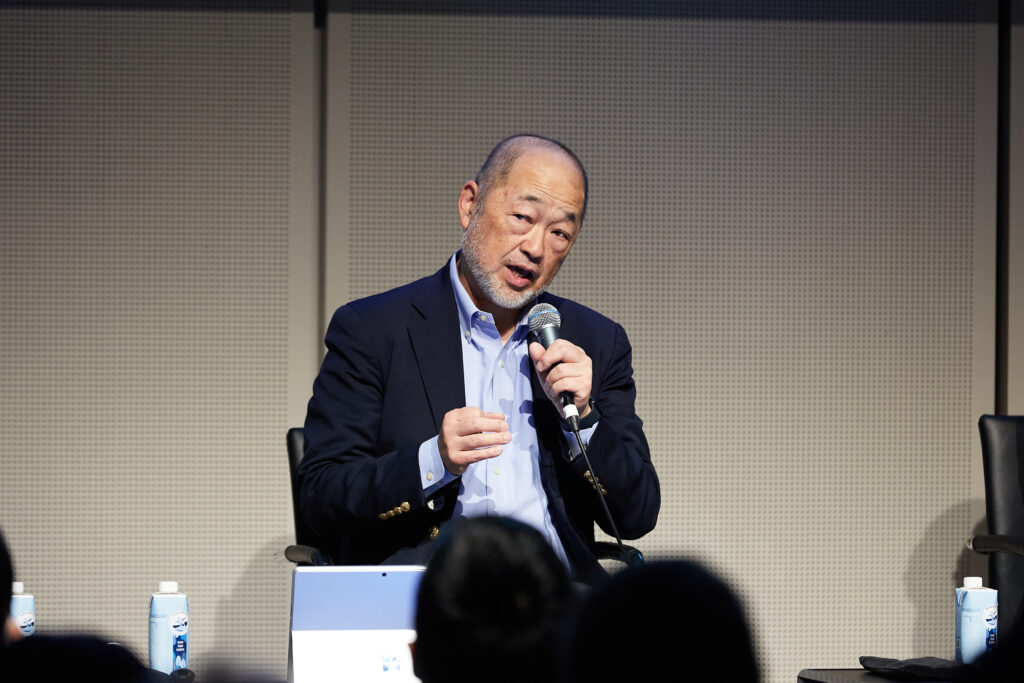
Scope3への取り組みとしては「2030年までに環境や人権に配慮したパーム油を100%調達する」と設定。この達成について、横山氏は「RSPO認証(持続可能な方法で生産されたパーム油であることを証明する国際的な認証制度)にのみ頼るのではなく、衛星や現地訪問により、森林破壊や労働環境などのモニタリングを実施、生産者とのエンゲージメントにも力を注ぎながら進めている」と説明した。

アストラゼネカの長町井須美氏は、同社のネットゼロ達成への計画を解説した。同社は、グローバル全体で「2026年までにScope1、2で98%削減(2015年比)」、「2030年までにバリューチェーン全体で50%、2045年までに90%削減(2019年比)」を行い、これをもって全排出量のネットゼロ達成を目指す。全排出量のうち95%以上をScope3が占めているといい、長町氏は「取引先に対し、SBT(企業が設定する温室効果ガス排出削減目標)に基づく目標設定と認証取得、またCDP(英国発の国際的環境非営利組織)を通した情報開示も同時にお願いしている」とサプライチェーン全体での取り組みを強力に推進していることを語った。
同社は日本製薬工業協会(製薬協)や環境省とも協力して取り組みを加速しており、長町氏は「地球の健康と人々の健康を、企業の垣根を越えてどう実現していくべきか、常に考えながら進めている」と力を込めた。
業界全体、異業種の連携が動き出している
後半のディスカッションでは、各社のScope3対応における企業の枠を越えた取り組み事例に注目が集まった。

アストラゼネカの長町氏が先に述べた製薬業界全体での動きについては、製薬協の有馬覚氏(第一三共)から内容が詳しく補足された。有馬氏は「まずはなぜ脱炭素への取り組みが必要なのかを会員企業に伝えることが重要。健康のために薬を作る私たちが、健康を害する環境を作るわけにはいかない」と語り、「医薬品業界全体で脱炭素に関する表彰制度をつくり、製薬メーカーが持つ環境負荷低減技術を広く拡散していく予定だ。技術共有、環境レジリエンス向上を、業界、個社、取引先のトリプルウィンで進めていこうとしている」と協会の動きを紹介した。
一方日清食品の横山氏が紹介したのは、物流ネットワークの構築による脱炭素への取り組みだ。異業種連携による重量物と軽量物の「混載輸送」や、輸送車両が往路と復路の両方で積荷を運ぶ「ラウンド輸送」といった事例について、横山氏は「輸送ニーズの増加、物流人員の減少などが課題の物流市場。酒類・飲料メーカーやJAと連携し、軽い即席めんと重い飲料、コメなどを組み合わせてトラックに積載すれば、効率よく重量と空間を満たすことができる」とメリットを強調し、すでに輸送におけるトラック使用台数20%削減、CO2の17%削減などの結果を出していると説明した。
これらの動きに対しファシリテーターの山吹氏は「同業での活動は、類似課題を他社も抱えているからこそ情報共有しやすい。こと脱炭素化などの社会課題解決においては、他社と同じ目的を目指して動く方が、効率がいい。それにより物流課題など他の課題解決も可能になる。そのことに多くの方が気付くことで、脱炭素化への可能性は広がっていくはずだ」と言及。こうした取り組みの拡大に期待を寄せた。

そのほか山吹氏は、アストラゼネカが、本来コスト削減を主眼に置きがちな調達部門を中心にScope3への取り組みを進めていることにも注目。「サステナビリティと調達でどうバランスを取りつつ進めているのか」と長町氏に疑問を投げかけた。
長町氏は「取引先からも『重視するのはコスト削減ですか? 脱炭素ですか?』という質問をいただく。しかしこれは天秤(てんびん)にかける話ではない。『選択するのではなく、一緒にやっていきましょう』という考え方で、勉強会や情報共有の場を作りながらサポートしている」と回答。また社内も同様に、「調達部門だけではなく社員一人一人がやるべきこと」とメッセージを送って、経営層を含めた全社員のミッションとして捉えてもらうよう働きかけているという。「どちらも苦労も多かったが、少しずつ理解を広げてきた」と長町氏は振り返った。
自社の成長のためにも、他社と協働すべき

各社の取り組みを聞いて、環境省の杉井氏は「すばらしい先行事例だ。個社それぞれ状況が違う中でも 、『脱炭素のためではあるが、自社の今後の取引や成長のためにも重要な取り組みだ』 と伝えていくことの大切さを感じた」と語った。そして政府もさまざまな取り組み事例を「グリーン・バリューチェーン・プラットフォーム」で開示しているとし、「ぜひ利用を」とメッセージを送った。
最後に、「すでに過酷な状況にある地球環境をこれ以上悪化させないためには、全ての人々の協力が必要不可欠だ。サポートを惜しまず続けていくので、ぜひ、皆で一歩一歩を進めていこう」と呼びかけ、セッションは幕を閉じた。
笠井 美春(かさい・みはる)
愛媛県今治市出身。大学にて文芸を専修。卒業後、株式会社博展において秘書、採用、人材育成、広報に携わったのち、2011年からフリーライターへ。企業誌や雑誌で幅広く取材、インタビュー原稿に携わり、2019年からは中学道徳教科書において創作文も執筆中。











