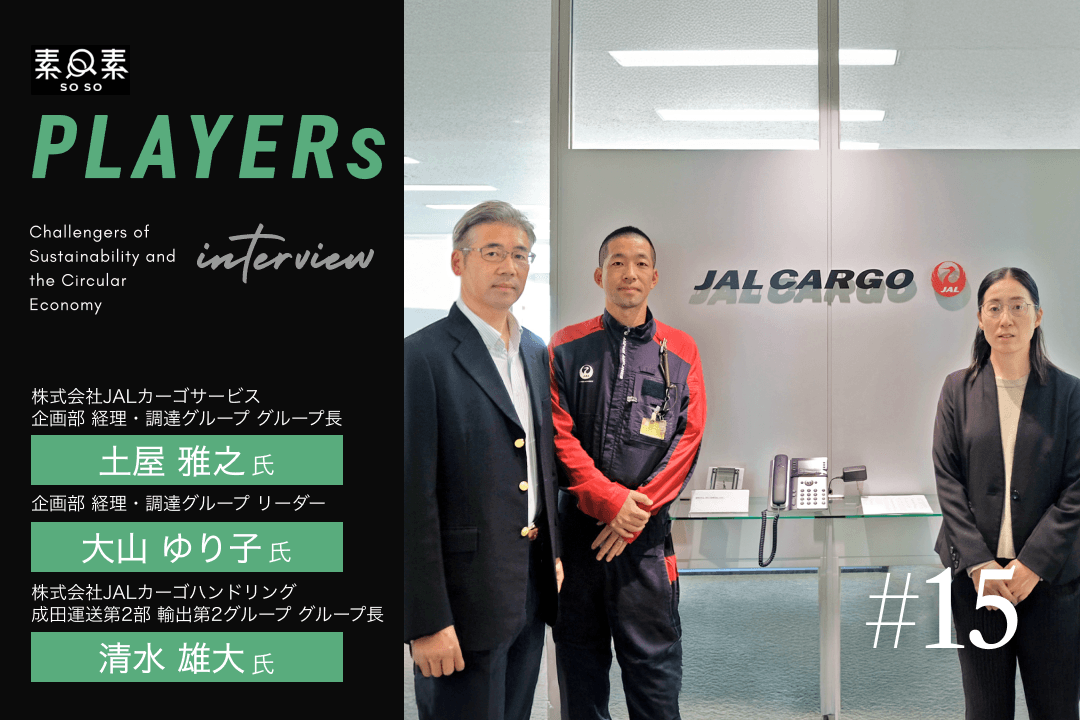現代社会は、急速な人口減少と高齢化、それに伴う地域経済の衰退といった深刻な課題に直面している。特に地方においては、後継者不足や農地の維持などの問題が顕著であり、都市部との間には価値観や消費行動のギャップも存在する。一方で、環境問題や持続可能な社会への関心は高まっており、倫理的な消費行動、すなわちエシカル消費が注目を集めている。「エシカルが変える生活と地域」と題した本セッションでは、地域が抱える課題に対してエシカル消費をどのように結びつけ、持続可能な地域社会へ変革できるかを巡り、3人のパネリストが議論を交わした。
| Day2 ブレイクアウト ファシリテーター 青木茂樹・サステナブル・ブランド国際会議 アカデミックプロデューサー/駒澤大学 経営学部 市場戦略学科 教授 パネリスト 石津大輔・針江のんきぃふぁーむ 代表 小泉篤・花王 グローバルコンシューマーケア部門 特命フェロー/一般社団法人グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン 理事 村上清幸・インテージリサーチ 代表取締役社長 |
セッションの冒頭、ファシリテーターを務めた青木茂樹氏は「個人の商品選択行動が、いかに地域や暮らしを変えていくのか」という問題提起から議論をスタートさせた。個々の消費者の倫理的な選択が地域全体の変革につながる可能性について、多様な視点からの議論を促す意図が示された。
有機農業と地域資源で育む共創のまちづくり

滋賀県高島市で農業を営む針江のんきぃふぁーむ代表の石津大輔氏は、年間降雨量が多く日照時間が短い地理的特性に加え、人口が毎年1%ずつ減少しているという厳しい地方の現状を伝えた。その中で、先代から引き継いだ米農家を有機農業主体へと転換し、地域の豊かな水資源を活用した具体的な取り組みを紹介した。
湧水が豊富であるという地域特性を生かし、川掃除などの地域インフラの維持活動を通じて住民の協力体制を育んでいる。また、農業と他分野との関係性に着目した「農◯(のうまる)」という独自の言葉を提唱。地域ならではの「農」に根差した事業を行う石津氏は「都市の消費者にも、農を感じてもらう切り口がたくさんあるはずだ」と語った。
企業パーパスから広がる地域連携

花王のグローバルコンシューマーケア部門特命フェローの小泉篤氏は、「豊かな共生世界の実現」という企業パーパスの下、エシカル消費の促進に向けた同社の取り組みについて説明。特に、奈良県生駒市での実証実験では、詰め替え製品の利用促進によるCO2排出量削減効果や、移動販売・詰め替えステーションの設置といった具体策が紹介された。
このプロジェクトは、同社の新規事業の一環として若手社員が主体となって推進しており、地域社会との連携を通じて「サーキュラー社会」の実現や地域活性化、自治体との共創を目指している。小泉氏は、そのために地域住民が主体となってプロジェクトを自走させることが何より大事だと強調。将来的には、他地域への展開も視野に入れているという。
社会的データ利活用が導く、ウェルビーイング視点のまちづくり

インテージリサーチ代表取締役社長の村上清幸氏は、同社が持つ多様なデータと分析ノウハウを生かし、地域ごとの多様性を理解した上での、データに基づく施策立案の重要性を強調。地域住民の幸福度について、経済指標に加え、24項目から成る住民のウェルビーイング指標の意義について語った。
同社が実施した消費者のサステナブル行動に関する調査によると、消費が社会にもたらすメリットよりも個人のメリットを重視する傾向があり、エシカル消費の伸び悩みが見られたと説明。また、SDGsに対する意識もダウン傾向が見られるという。さらに、女性の方が家計や子育てを通じて地域に関わりが深く、食品の安全や環境問題への意識が高まりやすい傾向があることも指摘。「人を育てるのは地域だ」と述べ、民間企業と行政が連携して地域課題の解決に取り組む意義を訴えた。
地域をつなぐ共通言語としてのデータと対話
各社の事例発表後、議論はデータ活用へと移った。村上氏は、人口減少や地域間連携の課題に対し、共通言語としてのデータの重要性を指摘。総務省が提供する「地域経済分析システム」(RESAS)がバージョンアップし、地域ごとの詳細な経済データやウェルビーイング指標が容易に利用できるようになったことを紹介し、客観的なデータに基づく議論と課題解決の重要性を訴えた。これにより、地域の実情を正確に把握し、多様な関係者が共通認識を持つことが可能となる。
地域活性化には、多様な主体の連携が不可欠だ。ファシリテーターの青木氏は、教育機関との連携や若年層への啓発活動を訴えた。小泉氏も、地域に根差した企業のリーダーシップの重要性を改めて強調。石津氏は、地域の特性を深く理解し、それに根差した取り組みを継続することの大切さを語った。村上氏は、地域ごとにウェルビーイング指標が異なる例を挙げ、画一的な視点ではなく、多様な価値観を理解することが活性化の鍵であると指摘した。
また、都市部と地方の意識のギャップや、世代間の価値観の違いも議論され、それぞれの地域や住民の特性に合わせたアプローチの必要性が確認された。
セッション全体を通して、エシカル消費は単なる消費行動にとどまらず、地域社会の持続可能性を高めるための重要な要素であることが再確認された。青木氏は「サステナビリティがなかなか進まない現実がある中で、客観的に地域そのものを見つめ直す必要がある」と指摘。データ分析による現状把握、多様な主体の連携、そして何よりも地域への深い愛情と理解が、持続可能な地域社会の実現には不可欠であるという強いメッセージを発信し、セッションは幕を閉じた。
井上 美羽(いのうえ・みう)
愛媛県松野町在住フリーライター。地方で農を実践しながら、地方での食の魅力化に取り組む。 食、環境、地方を専門として、主に取材・インタビュー記事の執筆を手掛ける。 日本サステイナブル・レストラン協会や日本スローフード協会の事務局として、食にまつわるイベントプロデュース、コーディネーターなどを担当している。