Sponsored by 原田産業
 |
企業が環境・社会・経済の持続可能性を保つ「サステナビリティ経営」の重要性が叫ばれるようになって久しいが、資金や人的リソースが限られる中小・中堅企業が、全社的なサステナブル・アクションを実行するのは容易ではない。
そうした中、主要な商品のカーボンフットプリント(CFP)を社員自らが海外の工場を訪問して算定し、その結果を踏まえた各商品の環境負荷の大きさについて特設サイトで紹介するなど、社内外のステークホルダーに向け、総力を挙げてサステナビリティを実践する企業がある。半導体や液晶、造船、食品など幅広い業界向けに商品やサービスをグローバルに展開する、1923年創業の老舗総合商社、原田産業(大阪・中央)だ。
創業初期に建てられた本社ビルは有形文化財に指定されるなど、歴史と伝統を守り抜く一方、事業を通じて革新的な挑戦を続けてきた同社が今、なぜ、サステナビリティに重きを置き、加速させるのか――。「サステナビリティ推進プロジェクト」のコアメンバー3人に、その背景や今後の展望を聞いた。
インタビュイー
澤田順次・原田産業取締役執行役員
李駿也・同社クリーンテクノロジーチーム LCAエキスパート
杉本知輝・同社機械チーム
CFP算定を通してサプライチェーン全体の意識改革を狙う
大阪市に本社を置く原田産業は社員約200人の老舗総合商社だ。その事業は「造船・海洋」「建設・インフラ」「エレクトロニクス」「ヘルスケア・ライフサイエンス」「食」「生活」の6分野にまたがり、国外にも事業所や関連会社を含めて10拠点を展開。業界と商材に特化した営業チームがさまざまな商品やサービスを開発・展開している。
そんな同社が2021年4月、取締役会・執行役員会の直下に、役員らでつくる「サステナビリティ推進会議」を設置した。そのいちばんの理由を、取締役の澤田順次氏は「本気で環境配慮に取り組むなら、大企業だけがアクションを起こすのではなく、すべての人の環境意識が変わっていく必要がある。我々が率先して取り組みを進めることで、他の中小企業や、取引のある個人店も考え方が変わっていくはずだからだ」と話す。
 澤田氏
|
社内的には推進会議を設置して以降、アパレルや機械、医療など営業部門の13チームに加え、人事総務や経理財務など間接部門も含めた全チームが、毎年のアクションプランと2030年の目標を設定。例えば半導体や電子部品製造工程のクリーンルーム現場で使われる手袋などを扱うクリーンテクノロジーチームでは、2030年までに環境負荷の低い「サステナブル素材」を使った商品比率を50%以上とすることを定めた。
中でも同社が、すべてのステークホルダーへの発信を意識して力を入れるのが、取り扱い商品の原材料調達から製造・輸送・使用・廃棄までの全段階で発生するCO2排出量を数値化して開示するCFP算定だ。そこには、同社の売り上げの約4割を産業・医療用などの手袋やガウンといった消耗品が占める中で、「顧客企業の商品の選定基準に、“環境負荷の大きさ”を加えることで、ビジネスを通してサプライチェーン全体で環境負荷を低減していきたい」(澤田氏)という商社としての強い思いがある。
商品の環境負荷低減を特設サイトで紹介し、ビジネスの成功とSDGs達成を支援
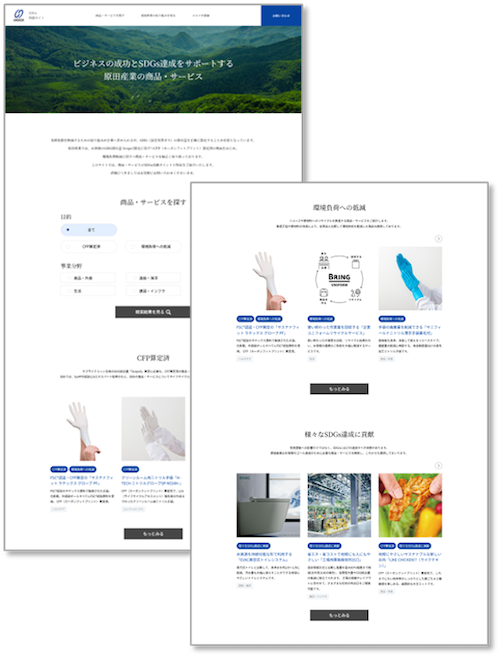 CFPの算定結果も踏まえ、取り扱い商品の環境負荷低減のポイントなどを紹介する原田産業の特設サイト
|
その思いが表出しているのが、同社が、「ビジネスの成功とSDGs達成をサポートする原田産業の商品・サービス」と銘打って2024年10月に開設した特設サイトだ。ここでは 6つの事業分野にわたる同社の取り扱い商品を、CFP算定完了の結果や、環境負担を減らすために開発された商材、環境以外のSDGsゴール達成に貢献できる商材という3つの観点から紹介されている。
CFPの算定は、専門コンサルタントの支援を受けノウハウを学んだ社員らが、専用のシステムを活用して実施する。その際、机上で計算するのではなく、社員らは国内外の製品製造ラインに直接足を運び、原材料だけでなく工場の運営形態なども確認しながら各製品のCO2排出量をデータベース化することもあるという。こうしたCFP算定の中心を担うのが、「LCAエキスパート(ライフサイクルアセスメントの評価・算定の妥当性判断に関する資格)」の資格を有する、李駿也氏だ。
 李氏
|
李氏は、取り組みを始めた2022年当初の状況を「電気や水道の消費量、ごみ処理の現状など工場側としては開示したくないと感じる情報も引き出さなくてはならない。初めてマレーシアの手袋工場に行った際は、会社を代表してCFP算定モデルを確立する立場であったため、正直大きなプレッシャーがあった」と振り返る。それでもひるまなかったのは、「まずはCFPに取り組む価値、重要性を取引先の担当者に直接伝える必要があった」からだ。
 |
「実際に欧米企業では、CFP算定済みの手袋でないと使わないところも出てきており、ビジネスの持続可能性にも直結し始めている。そうしたことを伝え続け、最終的には工場の担当者も理解してくれました」。苦労が報われ、同社としては第一弾となる手袋製品のCFP算定を実現した。特設サイトでは、取引先向けにCFP算定の結果を公開している。李氏が算定を手掛けた手袋では、1枚当たりのCO2排出量が78.2グラムであることに加え、「お客さまの工場からの廃棄物の中でも消費量が多いからこそ、CFP算定済み商品を使うことで温室効果ガスのスコープ3の削減にもつながり、課題解決に寄与する」といった担当者によるポイントの後に、商品の詳細情報が掲載されている。
これを機に同社のCFP算定は軌道に乗り、現在は10事業部で算定に着手、今後もより多くの商品に拡大していく予定だ。澤田氏は「『CFPは企業活動として当たり前』という状態にしていきたい。価格と同じようにCFPが製品の指標の一つとなっていけば、消費者も含めて社会の意識が変わっていくはず」と期待を込めて語る。
全社員がSDGs目標を持ち、柔軟に新規事業を提案できる組織に
CFPの算定だけではもちろんない。同社ではほかにも、工場からの使用済み作業服回収・リサイクルサービスなど、サステナビリティに関する多様なアクション・新規ビジネスを打ち出している。それを可能にしているのが、取締役会直下の「サステナビリティ推進会議」を中心に、全社的なサステナブル・アクションを推奨する各種制度が整備されていることだ。
同社では社員の意識改革にも力を入れる。全部門がSDGsに関する業務目標を持ち、それぞれの業務において、どのようにSDGsに貢献できるかを考える仕組みを構築。「サステナビリティ推進会議」は各事業部の目標進捗の管理やフォローだけでなく、社員向けに定期的な研修会や勉強会を開催し、社員一人ひとりが、サステナビリティに対する当事者意識を持つように促す。またSDGs目標達成に向けた新規開発や活動には、社内で特別予算を設定しており、通常稟議より簡略化した決裁だけで活用できる制度も導入している。
イノベーションを生むための制度としては、スタートアップ企業との独自の事業共創プログラム「HARADA ACCELERATOR PROGRAM」も展開している。毎年、原田産業の事業テーマごとに国内外の複数のスタートアップを採択し、その顧客開拓などをサポートするもので、すでに具体的な新規事業案も動き出している段階だ。
こうした取り組みを支える企業精神は、新たに入社する人材にも伝播(でんぱ)している。入社2年目の杉本知輝氏は、大学・大学院で環境負荷の低い材料の開発設計を研究していた経歴を持ち、入社後は、船舶部品などの販売を手掛ける機械チームに配属された。その一方で、今年10月には、15人の社員からなる「サステナビリティ推進プロジェクト」のコアメンバーに抜擢され、特にCFP算定や特設サイト制作において他部署の社員らとの連携を図る窓口を担う。
 杉本氏
|
杉本氏は「もともと環境問題や環境負荷の低い材料について学んできた事もあり、そういった背景を活かした持続可能なビジネスを模索していきたいと思っていた」と意欲をにじませ、澤田氏も「こうしたスペシャリストが加わってくれたことはとても大きなポイントになる」と評価する。入社2年目の社員に、サステナビリティ推進の鍵となるポジションで活躍する場が用意されていること自体、規模が大き過ぎない中堅商社だからこその柔軟性と言えるかもしれない。
創業以来の「社会貢献」意識と、次の100年
 |
同社が全方位でサステナブル・アクションを推進する背景には何があるのか――。この問いについて、澤田氏は、同社が100年を超える歴史の中で、戦争や災害など幾つもの苦難に遭いながらも、そうした非常時の社会状況や需要に寄り添いながらビジネスを展開してきた経緯が大きいという。「もともと原田産業は関東大震災後の復興特需に合わせ、ガラス輸入を通して社会の復旧とともに成長してきた会社。生産能力を自社で持たない分、商社は社会課題の解決こそをビジネスにするべきで、経営理念にも社会貢献を明記している」と、澤田氏は力説する。
老舗総合商社としての歩みを踏まえ、同社は今後もサステナビリティをますます重視する姿勢を崩さない。現在は、海外拠点や関連会社も含めたGHG総排出量を整理・算出しており、2025年中にはパリ協定に基づいた温室効果ガス排出削減目標を掲げるSBT認証の取得も目指す。「CFPをビジネスの指標とし、各商品取引の意思決定に活用できるように進展させる」「サステナビリティに関する専門知識を持つ人材を社内でさらに育成する」「関係企業と連携することで、サプライチェーン全体でのサステナビリティレベルの向上を目指す」――と、3人はそれぞれに意気込む。
澤田氏は「サステナビリティを社員一人ひとりの目標にまで落とし込み、制度も充実させて多面的に活動できていることは、中堅企業ならではの強みを生かせているから。現時点で、我々と同等の規模の企業でここまで取り組んでいるところは無いと思っている」と強調する。その上で、「SDGsの達成と、ビジネスの成功を両軸で捉え、顧客企業と共に、その両方を達成できるように展開していきたい。SDGsへのアクションを通してビジネスをより強固にしていきたい。会社と社員をしっかり守りながら、社会全体も継続可能な形で未来につなげていく」と、「次の100年」への決意を力強く語った。
文:横田伸治 写真:藤岡修平
SDGs関連商品・サービス特設サイト https://www.haradacorp.co.jp/sdgs/













