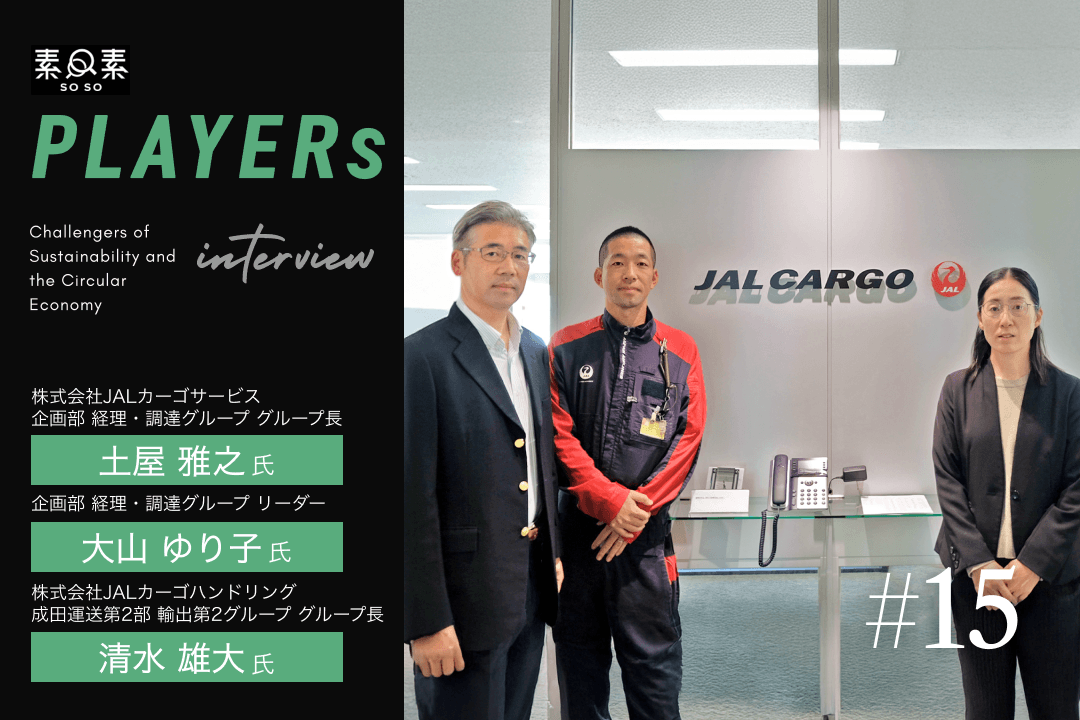Sponsored by SUSCOM
 タイのコーヒー産地を訪れたJosé. 川島良彰氏
|
気候変動の影響が分かりやすく起きている産業の一つに「コーヒーの2050年問題」を抱えるコーヒーがある。原料となるコーヒー豆が現在の適作地でとれなくなることによる供給不足の問題はもちろん、そもそも生産から消費に至るまでが長く、バリューチェーンが多岐に広がっていることによって、さまざまな課題が山積しているのだ。
ここでは一杯のコーヒーを通じて、消費者と生産者の双方が幸せになることを目指し、世界中の農園を巡りながら全力でサステナビリティ課題に向き合う、“コーヒーハンター”こと、ミカフェートを主宰する、José. 川島良彰氏の仕事を紹介する。
ミカフェート https://www.mi-cafeto.com/
コーヒーハンターJosé. 川島 良彰 https://www.mi-cafeto.com/aboutus/top_message/
世界中の生産者とコーヒーを愛する人々を結ぶ、価値ある一杯を
José. 川島氏は18歳でエルサルバドルに留学。国立コーヒー研究所にてコーヒーの研究を重ね、栽培・精選を習得した。1981年、大手コーヒー会社に入社、世界中で農園開発に携わるうち、「本当においしいコーヒーをつくる」ためには、気候変動や生産地の労働環境などさまざまな課題に向き合う必要があることを痛感したという。2008年ミカフェートを設立し、JALコーヒーディレクター、タイ王室 コーヒーアドバイザーなどを歴任。コーヒーを通じて世界をサステナブルに変える活動を展開している。
 |
|
そうした多岐に及ぶ活動の根幹にあるのは、豆の生産現場から、一杯のコーヒーを提供するに至るまでのすべてのプロセスに一切の妥協なく向き合う姿勢だ。「コーヒーで世界を変える」ために、いかにして生産国と消費国の間の架け橋となるか――。自らをコーヒーハンターと名乗る川島氏が行き着いた考えは、自然環境と人権の両方を守りながら、おいしいコーヒーづくりに励む生産者の市場を作り、価値を高めていくことだった。
世界初、航空会社が取り組むサステナブルなコーヒーの意義
あくまでコーヒーの価値を高めるため、José. 川島氏が行なっている仕事の中でも、特筆すべきものをここで紹介したい。それは、日本航空(JAL)が全線で導入する、「JAL CAFE LINES」と呼ばれる機内サービスだ。「機内で本当においしいコーヒーを」というコンセプトを掲げるこのサービスは、単に機内で提供するコーヒーを豆の品質にこだわったおいしいものへと変えただけではない。JALから川島氏に届いたオファーは、コーヒーを巡るサステナビリティにとことんこだわりたいという、「ある意味画期的なもの」であり、非常に取り組みがいのある仕事だった。
そのオファーが来たときの思いを川島氏はこう振り返る。
「うれしかったのは、それぞれのクラスで違うコーヒーを出してくださいと言われたことです。ビジネスクラスと、エコノミーと、お客さまが席に対する対価を支払っている中で、食事もお酒も違う。だから、コーヒーも違って当たり前なのですが、これまでは目を向けてこられなかった。そこに初めて切り込むことができるという意味で画期的なサービスだと感じました」
 |
現在、3年目となるこのサービスは、実際にファーストとビジネス、エコノミーでそれぞれ違うグレードのコーヒーを使い、そのどれもがおいしいコーヒーを提供している。もちろん、コーヒー豆の持続可能性に配慮することは絶対条件で、ビジネスもエコノミーも、すべてがいわゆるサステナブルな活動をしている農園の豆を使っている。
そもそもJALのコーヒーは、エコノミーであっても人と自然を守る団体レインフォレスト・アライアンス(RA)の認証コーヒーを使っており、ニューヨークにあるRAの本部には“JALのコーヒー”が飾ってあるほど。同サービスでも100%が認証コーヒーであり、中には、タイ北部の少数民族がアヘン栽培から脱却し、自活するために栽培しているコーヒー豆を使用する銘柄もある。つまり、そのサービスは日本航空という企業のサステナビリティへの取り組みと思いを利用者に伝えると同時に、ミカフェートがビジネスで目指す未来に向けた一つの道しるべとなっていると言える。
本当の意味での持続可能なコーヒーをつくりあげていくために必要なこととは
最後に、本当の意味でのサステナブルなコーヒーをつくりあげていくことについての川島氏の思いを改めて伝えたい。
 |
 |
世界中で飲まれ、土地ごとに独自の文化を広げてきたコーヒーは、関わる人の数において世界最大級の産業の一つですが、多くの課題を抱えてもいます。例えば、地球温暖化により2050年には今までの生産地が他地域に移動したり、栽培適地が半減するともいわれる問題があります。また温暖化によるコーヒー樹の病害も深刻ですが、これまで50年間、さまざまな課題と共存してきた歴史を見れば、きちんと資金を出し、栽培に関する正しい教育とあわせて実行すれば、一定の対応も可能なはずです。では、なぜできないのか? それは、コーヒー自体の価値が正当に評価されていないから。この50年間に賃金も上がり、農薬など経費も上がっている、けれどコーヒーの国際取引価格は横ばいで、生産者にしわ寄せがいく。つまり、本当にやらなければならないのはコーヒー自体の価値を上げることです。
ミカフェートはそのために設立した会社です。明確な基準による品質のピラミッドをつくり、最高グレード=コーヒーのロマネコンティのようなコーヒーを作ることで、全体の価値を引き上げる。生産者にきちんとした対価を払う。生産者も責任を持って、安全で安心して飲める品質のものを作る。そして、クオリティに見合った取引が成立するマーケットができることで生産者は継続して収入を得られるようになる。コーヒー自体の価値を高めることで初めて、サステナブルなコーヒーが実現するのです。