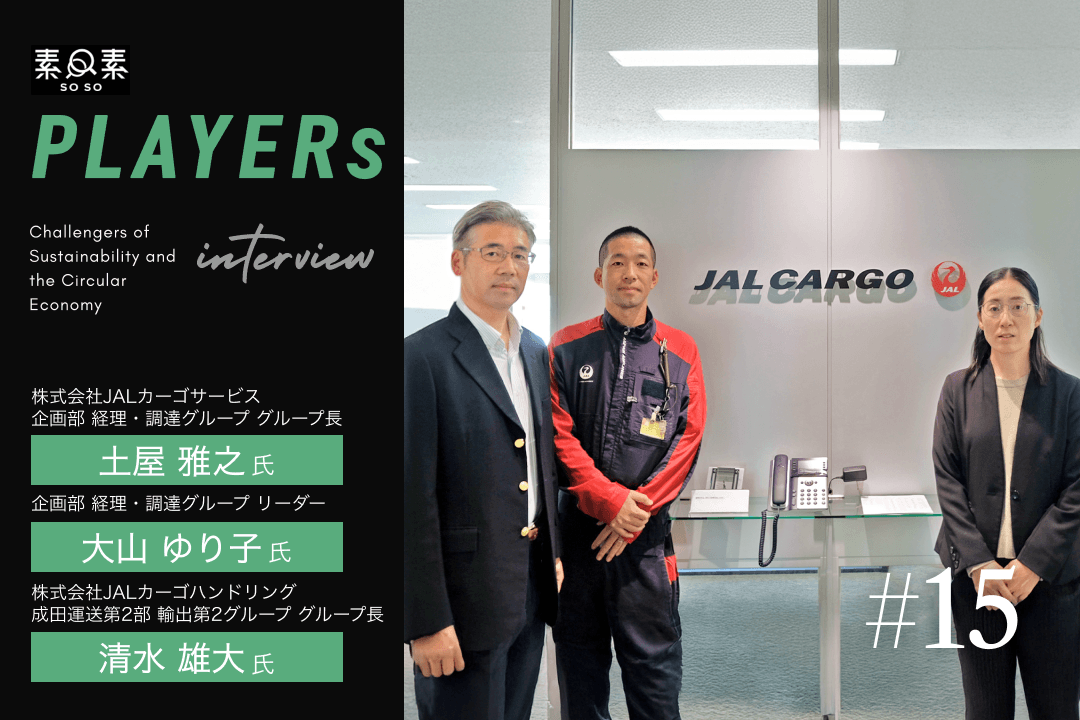4月15日に「脱原発」が実現したドイツ(Photo by Arnold Middelkoop on Unsplash)
|
今後の日本のエネルギー政策を決める重要な法案である「GX(グリーントランスフォーメーション)推進法」が国会で5月12日に成立した。脱炭素社会の実現に向けた考え方や具体的方策を示したものだが、「再生可能エネルギーの主力電源化」を標ぼうしながらも、原子力や火力発電を重視し、それを国の責務で行うことを明確に示したものとなった。150兆円という巨額の資金が動く脱炭素への道筋だが、その処方箋を間違えると日本が世界の潮流から取り残され、脱炭素そのものの実現にも黄信号が灯りかねない。GX関連法案は本当にグリーンなエネルギーへの移行を加速させるのか、有識者に聞いた。(環境ライター 箕輪弥生)
原発を国の責務で推進
GX関連法案は、脱炭素を進めるための「GX推進法」と電源に関する5つの法案を束ねた「GX脱炭素電源法」の2つがある。複雑でわかりにくいが、どちらの法案も今年2月に閣議決定されたGX基本方針を実現するための枠組みを定めたものだ。
このGX基本方針には、省エネや再エネの導入拡大と合わせて、原発の再稼働や、次世代革新炉の開発、水素やアンモニアの需要拡大支援などが示されている。
「GX推進法」は、10年間で20兆円のGX経済移行債の発行や、CO2の排出に課金する「カーボンプライシング」をはじめ、150兆円を超える官民のGX投資を促進することなど、基本方針を実現するための経済的な方策について示している。
一方、「GX脱炭素電源法」は原子力基本法、原子炉等規制法、電気事業法、再処理法、再エネ特措法の改正案5つを束ねたものだ。国の責務で原発を活用し、現行の原発の運転期間を原則40年にするという規定を廃し、60年を超えた原発も経済産業省の認可で稼働できることを盛り込んでいる。
これにより、日本は東日本大震災後から示してきた「可能な限り原発依存度を低減する」という原則を改め、既存の原子力発電所の延命をはかり、原子炉の新増設を推進する原発回帰の方向性が明確化したことになる。
重要な法案であるにもかかわらず、決定までのプロセスの透明性がないこと、関係省庁や環境団体、企業などとの協議もなく経産省主導で進んだ事実に関しても、環境NGOなどから問題提起されている。
原発への過剰投資が生む脱炭素の遅れ
今回の関連法案で示されたように原子力発電を、国を挙げて支援するのは果たして日本にとって持続可能なエネルギー政策なのだろうか。
原発の新増設については「次世代革新炉」の開発をいくつかのメニューをあげて示しているが、ほとんどが実験的な実証炉であり、唯一商用炉とする「革新軽水炉」も2040年代の運転を予定している。昨年のG7サミットでは2035年の電源の脱炭素化が合意されたが、それにはこれらは全く間に合わない。
原発にかかる電力コストについても非常に高価なものとなっている。これについて、NPO法人 原子力資料情報室の松久保肇事務局長は、「動かない原発につぎ込んできた維持費用が大きくかさんでいる」と解説する。
松久保氏によると、「ここ10年で原発維持費や政策経費を加味すると、少なく見積もっても23.5兆円に達し、原発による発電単価は59.5 円/kWhにはね上がっている」。太陽光や風力といった再エネの発電単価が数分の一と大きく下がっているのとは対照的だ。
原発の維持費も、再エネが「FIT賦課金」という形で電気料金に明記されているのに対して、原発は発電原価に含まれて実際には負担しているものの消費者には見えないという。
今後は新たな原発の開発費にも国の資金が投下される。GX投資のうち、 少なくとも1兆円は高温ガス炉・高速炉原発の開発や建設に支出される予定だ。
松久保氏は「費用対効果が考えられていない。原発への過剰投資は、他の電源への投資を抑制し、結果として日本のエネルギートランジションを遅らせる」と警鐘を鳴らす。
もちろん、世界の2割の地震発生を占める日本の自然災害の多さや、核廃棄物の処分方法などの問題は顕在化したままだ。
排出量削減のインセンティブとしては不十分な炭素価格
今回成立した「GX推進法」では初めて「カーボンプライシング」を2028年から導入することを明らかにした。しかし、「導入時期が遅く、炭素価格は他の先進国の10分の1以下で排出量削減のインセンティブとしては不十分」と松久保氏は指摘する。
さらに脱炭素電源のもう一つのオプションとして政府が力を入れているのがゼロエミッション火力と呼ばれる水素、アンモニア、CCS(二酸化炭素回収・貯留技術)の利用だが、これらもすぐに実用化できる技術ではなく、できたとしても非常に高価なものになると予想される。
水素・アンモニア発電は、国のエネルギー基本計画でも2030年の総発電量の1%しか見込まれていない。水素・アンモニアの石炭火力への混焼発電は、石炭火力の延命策として、欧州からも批判を受けているほどだ。
国際基準から乖離しつつある日本のエネルギー政策
環境エネルギー政策研究所(ISEP)の飯田哲也所長は「日本のエネルギー輸入額は昨年、35兆円と過去最高となった。今後円安が進み貿易収支が経常赤字になると、高価なグリーン水素やアンモニアなどを購入する余裕はなくなるのではないか」と危惧する。
日本の自然エネルギーのポテンシャルは環境省の試算でも、電力供給量の2倍はあるとされる。「再エネは一番安い上に、純国産エネルギーで、早く使えて気候危機にもエネルギー安全保障にも寄与する。再エネを最大限活用することが世界のコンセンサスになっている」(飯田氏)。
実際に、ドイツはすべての原発を停止し、今年は5割を再エネで発電する。デンマークでも昨年は電源の80%、来年は100%を再エネで賄う可能性がはっきり見えてきた。
どちらの国も再エネの導入は1990年代には日本より低く、3~4%を担うのみだった。そこから再エネに移行するエネルギー政策を強化してきた結果が大きな差を生んでいる。
しかし、日本は今なお約2割を再エネで発電するのみだ。「日本が目指す2030年に再エネ36~38%、原子力20~22%の電源構成も今のままだと実現性に乏しい。結果、足りない分を化石燃料で補うことになる」(同)。
日本は、グリーンエネルギーへの移行を本当に実現できるのか。飯田氏は「論理とファクトとデータに基づく政策形成をしないと、日本は世界から何周も遅れていく」と危機感を露わにした。
国のGX基本方針の冒頭には、『GX に向けた脱炭素投資の成否が、企業・国家の競争力を左右する時代に突入している』とするメッセージが示されている。これはまさに正論だ。しかし、その処方箋を一歩間違うと、企業や国の競争力を半減させることにもつながる恐れを含んでいる。
箕輪 弥生 (みのわ・やよい)
環境ライター・ジャーナリスト、NPO法人「そらべあ基金」理事。
東京の下町生まれ、立教大学卒。広告代理店を経てマーケティングプランナーとして独立。その後、持続可能なビジネスや社会の仕組み、生態系への関心がつのり環境分野へシフト。自然エネルギーや循環型ライフスタイルなどを中心に、幅広く環境関連の記事や書籍の執筆、編集を行う。 著書に「地球のために今日から始めるエコシフト15」(文化出版局)「エネルギーシフトに向けて 節電・省エネの知恵123」「環境生活のススメ」(飛鳥新社)「LOHASで行こう!」(ソニーマガジンズ)ほか。自身も雨水や太陽熱、自然素材を使ったエコハウスに住む。JFEJ(日本環境ジャーナリストの会)会員。 http://gogreen.hippy.jp/