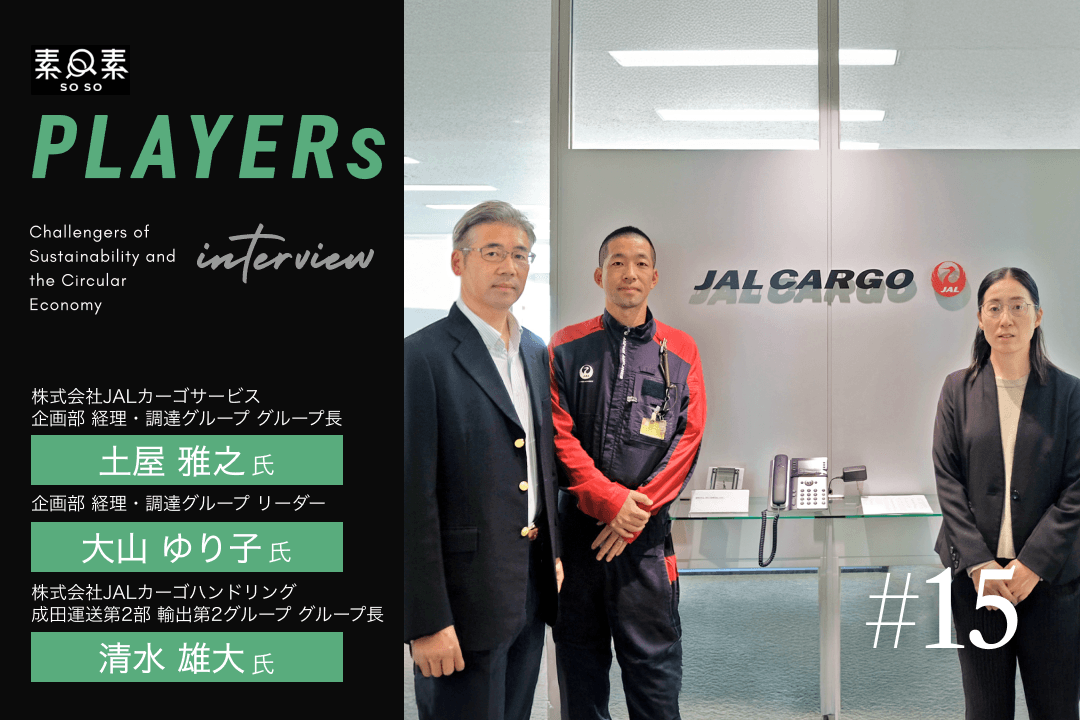|
脱炭素は、検討から実施の段階に大きく移っている。
多くの企業や自治体がカーボンニュートラルの取り組みを急ぐ一方で、そこに潜むリスクに気づいていないケースが散見される。今回のコラムでは、中でも最も陥りやすい、「グリーンウォッシュ」を取り上げたい。
グリーンウォッシュとは、「環境に配慮しているように装っているものの、実際の行動や活動が伴っていない」ことである。「偽装グリーン」とも呼ばれる。
それは、脱炭素に消極的な企業という程度の評価にとどまらず、強くネガティブな意味合いを持つ。せっかく脱炭素を進めているのに、一転して強烈な非難にさらされる危険がそこにある。
広がるグリーンウォッシュの領域
カーボンニュートラルの主たる取り組みは、CO2など温室効果ガスの排出を削減することにある。例えば、化石燃料から再生エネルギーへの切り替えを進めるなど、環境に配慮した行動をとること、つまり、多くの活動をグリーンに転換することが基本となる。
その際、2つのカテゴリーでの嘘が、グリーンウォッシュと指摘される可能性が出てくる。
一つは、企業活動全般に関する環境配慮で、具体的には、原料、製造過程などできちんとした環境に対するケアがなされていない場合、嘘=グリーンウォッシュと認定される。製造過程などには、そこで働く人たちの人権も含まれる。人権侵害が行われているとされる中国・新疆ウイグル自治区で作られる太陽光パネルを使うことについて、グリーンより広い定義のSDGsウォッシュの扱いが取りざたされたことは記憶に新しい。
もう一つは、表現の問題である。
後で詳しく述べるが、一般的な再生エネ発電施設でも、環境配慮が欠けていることから、つくられた電力が再生エネと認められないケースがある。そういった電力を、再生エネによる電気と称したり、脱炭素に貢献する電力を導入しているという表現を行ったりした場合、即、グリーンウォッシュになってしまう。
環境への配慮が欠けているとは、「持続的でない発電方法や災害の原因となる発電施設」などのことをいう。
エネルギーではないが、ブームとなっている大豆ミートの国内最大手の不二製油グループは、大豆調達網の点検を行う。自らが使用している大豆が、森林破壊につながる耕地で生産されていないかのチェックを進めているのである。グリーンウォッシュを事前に防ぐことは、もはや企業活動の基本となった。
使ってはいけない再生エネ電源の見分け方
カーボンニュートラルへの道筋の基本は再生エネ電力の確保である。
例えば、再生エネの発電施設との契約を結ぶときには、その施設がどうやって作られたか、どういった燃料を使っているかを調べておく必要がある。前述した「持続的でない発電方法や災害の原因となる発電施設」のチェックのことである。
後者の、災害の原因となる発電施設の例はわかりやすい。山の斜面に多くの森林を伐採して建設される太陽光発電は、一見して災害の危険があると想像される。この発電所からの電力は、再生エネ扱いされず、脱炭素にカウントされない。それどころか、その電気の使用で「脱炭素に貢献」「カーボンニュートラルを目指す」などの表現を使うと、嘘つき、ぎまん、偽装、と最大級の非難を浴びることになる。
確認しておくが、“知らなかった”は通用しない。そこまで調べたうえで利用するのが企業としての当然の責任だとされているからである。
前段の、持続的でない発電方法には頭を悩ませられる。
RE100などの国際イニシアティブやそれぞれの企業は独自に基準を定めていて、メガソーラーはダメとか、大型水力発電の場合、新設は認めないなどのばらつきもある。
最近、特に厳しい目で見られるようになってきたのが、木質バイオマスの発電施設である。欧州委員会は、すでに多様性の高い原生林からの木材は認めるべきではないとして、発電能力5MWを超える木質バイオマスの発電施設は、グリーンでないと変更した。また、アメリカの銀行大手シティグループのアナリストは、基本的にバイオマスを持続可能なエネルギー源とはみなさないとまで言っている。
私見ではあるが、遠くない将来に木質バイオマス専焼で一定規模以上の発電施設からの電力は、再生エネ電源とは認められなくなると考える。特に日本のように輸入材を使っているものは厳しい。現地の状況を把握することは現在でも必須だが、巨大な費用で建設された大型発電施設からの電力が、再生エネでなくなるリスクが今後も常に付きまとうことになる。
ドイツではついに事件が発生 「エコ」や「環境にやさしい」もグリーンウォッシュに
環境先進国といわれるドイツで5月、グリーンウォッシュに絡む疑惑でドイツ銀行に検察と金融当局の捜索が入った。ESG(環境・社会・企業統治)投資に関してうわべだけ環境に配慮しているように装っていると内部告発した投資責任者を、銀行が解雇したことがきっかけとなった。
事件は極端な例だが、特に宣伝分野では、グリーンウォッシュを排除するための基準作りが世界で進められている。特定の広告がグリーンウォッシュと指摘され、告発されるケースが相次いでいるからである。
イギリスの競争・市場庁(CMA)によるウェブサイトの世界的調査で、環境に関する情報発信のうちおよそ4割が消費者の誤解を招き、法令に触れる可能性があるとの結果が出た。
イタリアでは、「グリーンディーゼル」を謳うイタリア炭化水素公社(ENI)が、罰金およそ6億5000万円を受け、宣伝活動も中止となった。イタリアの競争・市場庁(AGCM)がグリーンとは言えず、消費者を欺いたと認定したのである。
日本のサイトなどでも、「グリーン」「エコ」「環境にやさしい」などの表現が、ごく当たり前に使われている。しかし、それぞれ非常にあいまいで、根拠が示されていないケースがほとんどである。今後は、データや他者による検証なしでは、これらの言葉は使えなくなるであろう。グリーンウォッシュの指摘に耐えられないPR表現は、リスクでしかない。
グリーンウォッシュ対策は、徹底的な情報開示
グリーンウォッシュを回避する決定的な対策は、情報開示である。
情報開示は、単に知っていることを表に出すことではない。
例えば、再生エネ発電施設がどうやって作られ、どういう形で使われているかを、徹底的に調べ、そのすべてを公にすることである。開示を前提とすれば、甘い調査は行うことができない。自ら知ることで、結果としてリスクを避けることができるという理屈でもある。世界の金融機関でつくるTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)が、脱炭素実現のために企業に厳しい情報開示を求めているのは、ここに強い理由がある。
北村 和也(きたむら・かずや)
日本再生可能エネルギー総合研究所代表、日本再生エネリンク代表取締役、埼玉大学社会変革研究センター・脱炭素推進部門 客員教授
民放テレビ局で報道取材、環境関連番組などを制作した後、1998年にドイツに留学。帰国後、バイオマス関係のベンチャービジネスなどに携わる。2011年に日本再生可能エネルギー総合研究所、2013年に日本再生エネリンクを設立。2019年、地域活性エネルギーリンク協議会の代表理事に就任。エネルギージャーナリストとして講演や執筆、エネルギー関係のテレビ番組の構成、制作を手がけ、再生エネ普及のための情報収集と発信を行う。また再生エネや脱炭素化に関する民間企業へのコンサルティングや自治体のアドバイザーとなるほか、地域や自治体新電力の設立や事業支援など地域活性化のサポートを行う。