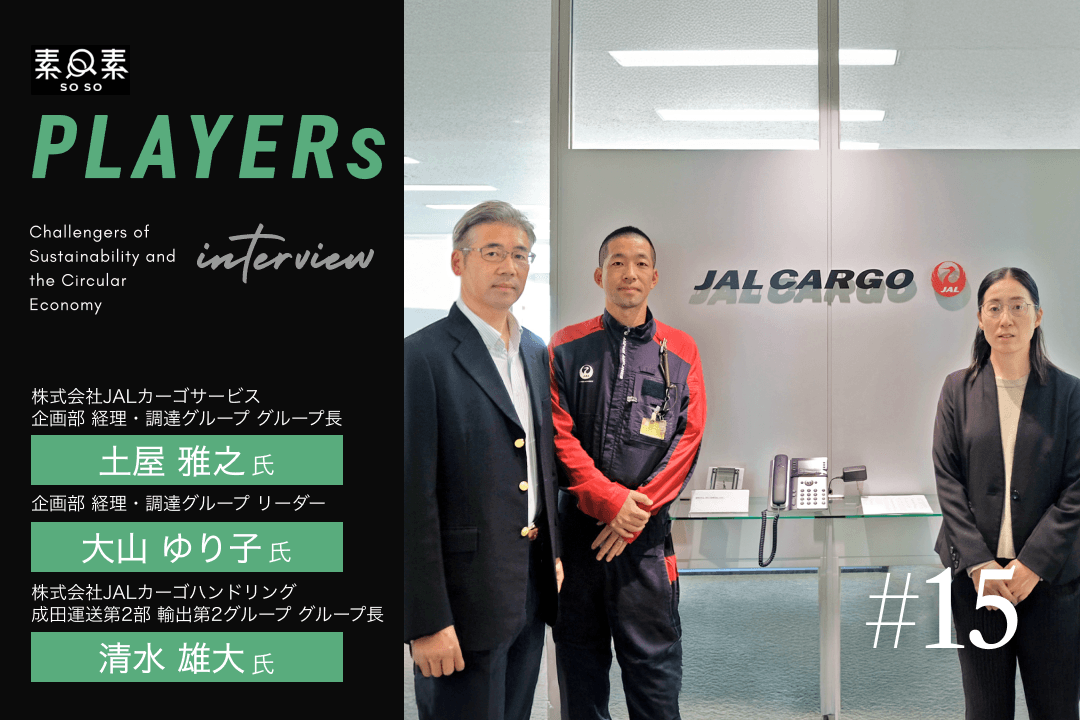Photo by Shinichi Takahashi
|
ガーナの首都・アクラ郊外に、「アグボグブロシー」と呼ばれる地区がある。世界最大の電子廃棄物の不法投棄場所と言われ、別名「電子ごみの墓場」。美術家の長坂真護(まご)さんは2017年、初めて現地を訪れ、広大な投棄場所に衝撃を受けた。「自分ができることを通して、この電子ごみの墓場をなくしたい」――。電子ごみを素材にした絵画を描き、その収益を蓄積・投入して、150億円の大規模なリサイクル施設を現地に建設する壮大な構想を温める。「課題解決の活動は、まるで地球を経営するようなもの」と、長坂さんは喝破する。(サステナブル・ブランド ジャパン集局=沖本啓一)
「誰かが転んだら、ハンカチを出す」
 Photo by Fukuda Hideyo
|
地平線まで届くかと思えるほどに広がる、捨てられた電子部品の山。レアメタルなどを取り出しわずかな収入を得るために、現地の若者がごみを燃やし、極めて有毒な煙がそこかしこから立ち昇っている。彼らのほとんどは劣悪な環境のため、30代で死亡するという。アフリカ西部、ガーナのアグボグブロシー地区。「電子ごみの墓場」を2017年、初めて訪れた長坂真護さんは、想像を絶する光景に衝撃を受けたという。困っている人が目の前にいた。自分には何ができるのか――。
「ポケットにハンカチがあって、目の前で誰かが転んでひざを擦りむいたら、ハンカチを出す。ただそれだけだったんです。僕は10年間、絵を描くことしかしてこなかった。だから絵画で、どうやってこの光景を変えられるのか。それだけの行動です」
現地から持ち帰った電子ごみを「絵の具」にして、絵を描いた。売れた収益は「電子ごみの墓場」で困っている人たちに還元する。これまでに無償の学校をつくり、50年分の運営費用も確保した。有毒ガスに晒されながら電子ごみの墓場から収益を得て生活している人たちのために、400個以上のガスマスクも寄贈した。根本的な解決を目指し、大規模なリサイクル工場施設の建設を想定する。プラスチックのリサイクルを手がける日本環境設計(東京・千代田)とも協力し、10年後に建設費用150億円を芸術活動から捻出することが現在の目標だ。
 Photo by Fukuda Hideyo
|
芸術の持つ「役割」
「いろんな方向性があると思います。例えば、寄付を募ったり、アートと結びつけず単にクラウドファンディングにしたり。でも、僕は彼ら(現地の人たち)と目線を合わせて、共通価値を創造して、共有していきます。彼らは僕のモデルです。モデルとして、売れた収益をリターンする。それって資本主義の中で当たり前のことじゃないですか」
今では1000万円以上で売れる絵もある。現地のネガティブな風景そのものをアートとして価値に転換し、大きな社会課題の解決を目指す。美術家として、アートに社会的な役割を与えることに違和感はなく、アートの産業の中でアートを売ろうという考えは一切なかった。
 |
「アートって、もともと社会にとって必要なもので、人を救うためにあるんです。太古の壁画は、今起きていることを伝えるために描かれたものです。情報共有のツールです。僕はアート界では無名ですが、経済紙やテレビで取り上げられています。それこそアートの役割としては真実ではないかと思っています」
長坂さんの作品を購入したある経営者は「作品を見れば、自分が置かれている状況、会社の状況、自分がどれだけ幸福か、何に対して生きなければいけないかを、一発で思い出せる」と話したという。
展開するのは「サステナブル・キャピタリズム」
 Photo by Shinichi Takahashi
|
学校を設立し、ガスマスクを寄贈し、最終的にはプラントを建設する。長坂さんの取り組みは他にもある。現地に「ミュージアム」を設立し、世界中から訪れるジャーナリストなどから入場料をとり、これもすべて現地の人たちの生活向上の資金にするというものだ。
「アグボグブロシーを訪れるジャーナリストたちは現地の若者を撮影し、風景を撮影し、大きなメディアに売るんです。その収益は現地に還元しません。現地の人たちはジャーナリストたちに対して怒っています。だから、ミュージアムをつくり正当な対価を払ってもらいたいです」
「例えば父親の仕事がタイヤを焼くことであれば、自身もタイヤを焼く仕事に就き、子どものころから有毒ガスを吸い続け30代で亡くなる。彼らにはそれしかありません。小さな経済活動と環境を壊す活動がセットになったことしかできない。そこに環境保全の機能を持ったミュージアムをつくり、スラム街に文化を組み込む。それによって彼らの生活がどう変わるか、アートで証明したいんです」
 |
構想に着目したハリウッドの映画監督からは、2カ月間の密着取材でドキュメンタリー映画を撮影するという依頼が舞い込んだ。自身の書籍から名称を取った法人「Still A “BLACK”STAR」を立ち上げ、ドキュメンタリーを観た観客が「Still A “BLACK”STAR」のライセンス商品を購入すれば、収益が現地に還元されることで観客自身も活動に参加できる――「最高のビジネス・モデルでしょう?」と長坂さんは笑顔で話す。このような経済活動を「サステナブル・キャピタリズム」、長坂さん自身の訳によれば「循環型競争原理資本主義社会」と呼び、「地球を経営するようなものです」と説明した。
「サステナブル」の概念を捉える
「リーズナブルという言葉に対して、ほとんどの人は精神的にスッと理解できると思います。それと同じ感覚で『サステナブル』という言葉も使えるようになるといいと思います」と長坂さんは語る。環境にいいことをしている、ボランティアをしている、だから「サステナブルだ」ということではないという。経済活動や地域のコミュニティ、文化、背景にあることを全て含め、「Sustainableの意味を根本的に理解して、『それってサステナブルだね』って感覚として言えることが大事かなと思います」
しかし意外なことに「SDGsについてはあまり知らない」という。「17項目のアイコンを見ても『こんなにできるわけないな』って思ってしまいます。僕がやっていることを思い返して、学校ができた、ミュージアムができる、雇用が生まれた――あ、何項目かクリアしてた、という感じです。サステナブルにディベロップメントが紐づいても、誤解を招くだけじゃないですか? サステナブルの意味を理解していれば自然とSDGsの達成になります」
「ただ、サステナブルの概念を絶対に取り入れるべきだということでもありません。地球を汚したいという人はほぼいないと思います。そこに、自分ができることは何ですか、と問いかけることをしたいんです」
時代の価値観
「一昔前、ごみ拾いをしている人が『格好いい』なんて言われることはありませんでした。『不良』が格好いいと言われていたこともあります。今、僕が150億円でやりたいことは清掃業です。日本の若い子が僕を見て『カッコいい』と目を輝かせます。そんな時代が来ています。地球という母なる大地への反抗期は、もう終わったんです。あとは恩返しをする。それができるのが、僕たち人間だと思います」
美術家・長坂真護さんの活動は、芸術が持続可能性へ向き合う先進的な一例だろう。10年後、リサイクル・プラントが建設された「持続可能なアグボグブロシー」の光景を見られるかもしれない。
 Photo by Shinichi Takahashi
|
長坂真護さんの作品をモチーフとしたグッズはこちらのHPから
沖本 啓一(おきもと・けいいち)
フリーランス記者。2017年頃から持続可能性をテーマに各所で執筆。好きな食べ物は鯖の味噌煮。