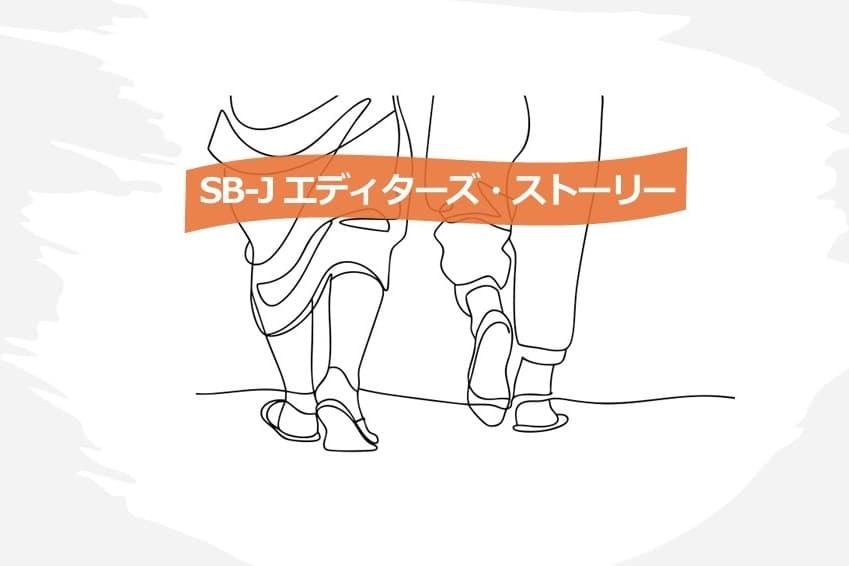環境や社会の課題を解決する取り組みで、Z世代の存在感が高まっている。消費者としてのZ世代は、製品の持続可能性を考慮して購入を決めることも多い。さらに仕事を選ぶ際にもその価値観は重要であり、気候変動などの課題に対する解決策を提示しようと自ら起業する例も増えている。本記事では、Z世代の起業家であるベン・リチャードソンとジョージ・ウェイドが同世代の起業事例を紹介し、あらゆる世代のビジネスリーダーに向けてアドバイスを送る。(翻訳・編集=茂木澄花)
Z世代に属する私たちにとって、気候危機は子どもの頃から生活の背後にあるものだった。だから私たちは、その脅威が憶測でも遠く離れた場所で起きていることでもないと知っている。山火事、洪水、極端な気温、海岸線の浸食は、今や「新常態(ニューノーマル)」の一部だ。
多くのZ世代は、自分が関わる企業を決める際、企業が持続可能性のためにどんな責任を果たしているかを参考にする。米サステナブル・ブランズと世界的なマーケティングリサーチ会社イプソスによる2025年の社会文化トレンド調査でも、そのことが浮き彫りになった。調査対象となったZ世代の59%が、なじみのない製品を購入する際、成り行きでよく知っているブランドを購入するのではなく、持続可能な選択肢のあるブランドを選ぶと答えたのだ。さらに、Z世代の回答者の49%は、よく購入していたブランドから、環境や社会に対して責任を果たしているブランドに最近乗り換えたと回答している。
このように、Z世代の多くはすでに、自らの環境負荷を軽減するため、購買行動を変えている。責任ある行動を取っている企業、取り組みの内容をオープンに発信している企業を支持しているのだ。これと同じ原動力から、より良いビジネスを推し進めるリーダーになったり、自ら起業したりするZ世代も多い。
この傾向は、若いイノベーターたちがテクノロジー、代替素材、データなどを使った次世代の解決策を発表していることにも表れている。持続可能性のための取り組みを、単なるマーケティング施策を超えるものに押し上げているのだ。Z世代は歴代屈指の起業家精神を持つ世代だ。考え方の近い者同士が協働して実現性のある解決策を打ち出し、すでに良い影響をもたらしている例は増えている。
世界中にいるZ世代の起業家たちは、若い視点と決断力で実社会の問題に取り組み、効果的で規模拡大や再現が見込める、持続可能な解決策の開発を進めている。その中からごく一部を紹介する。
- 英国のアナヒタ・ラブラックとキアラン・ダウズは、オーシェン(Oshen)という企業を立ち上げ、リアルタイムでの海洋データ収集を目的とした、自律型の小型ロボット船を開発した。この小型船は、ブイや大型船よりも安全で環境に優しいという。同社は、ロボット同士のネットワーク構築という新しいアプローチで、重要な海洋データを集めるための頑丈でコスト効率の良い手段を創出している。
- Z世代の中でも特に若い起業家が、16歳でカーボンゼロ・エコ(CarbonZero.eco)を立ち上げたハーパー・モスだ。シリコンバレーを拠点としたスタートアップである同社は、バイオ炭を使って環境再生型農業の拡大を支援している。バイオマスを加熱して作られるバイオ炭は、農家が土壌の健康と作物の収量を改善するのに役立つとともに、大気からCO2を吸収する。
- ヌハ・シディキとクリティカ・ティヤギはトロントを拠点にアートス(erthos)を創業した。同社の高機能な生物由来素材は、問題の多いプラスチックの代替品として、生産システムに円滑に組み込むことができる。
- ジェイク・バーバーとディンジエ・タンは、シンガポールを拠点にプリファー(Prefer)というスタートアップを起業した。同社は気候変動に弱い作物であるコーヒーを今後も飲み続けられるようにするため「コーヒー豆を使わないコーヒー」を作っている。
筆者たちも「持続可能性に関して企業が直面する最大の課題に、現実的な解決策を提供する」という共通の決意のもと、ゼベロ(Zevero)という会社を始めた。私たちはどちらも持続可能性の大切さを理解している企業で働いていたが、複雑なせいで見過ごされていることがいかに多いか、気付いてもいた。特に、サプライチェーン、ベンダーの決定、包装の選択などに伴う間接的な排出量、つまりスコープ3排出量の割合が大きいことが気がかりだった。
そこで私たちは、排出量のデータを包括的で実利的な情報にするため、AIを活用したプラットフォームを開発した。これにより、企業は表面的な取り組みにとどまらず、管理が難しいバリューチェーン排出量を削減するための具体的で測定可能な手順を、迅速に実行できるようになる。バリューチェーン排出量は、企業の温室効果ガス排出量合計の約75%に上るとも言われている。
特に長続きして影響力を持つことのできる持続可能性の取り組みは、日々の企業活動から見つかる。これが、私たちがこれまで学んできたことだ。どこから始めるべきか迷っているあらゆる世代のビジネスリーダーに、「データを共有し、全員を巻き込み、持続可能性を全社的な取り組みにする」という方針を勧めたい。持続可能性に関する取り組みを企業のミッションの中心に位置付けることは、将来にわたるレジリエンス(強じん性)と機会を築くことにつながる。私たちZ世代の起業家がそのことを示している。