
畑の土の健康状態を評価・開示することで、消費者はおいしい野菜を選んで買うことができ、生産者は環境クレジットによる収益向上を見込める――。そんな新たなフードシステムが動き始めている。農業ベンチャーBG(東京都目黒区)が進めるプロジェクト「Next Green Revolution」は、生産者と消費者をつなぎ、「土」を起点に食、農、環境の好循環を生み出す壮大な挑戦だ。
従来の農法では「土が弱る」
日本の農業の99%を占めるとされる慣行農業(化学肥料や農薬を使い、効率的な生産を目指す一般的な農法)は、収量の安定維持によって戦後の食料安定供給を支えてきた。しかし、土を介さず直接的に野菜へ栄養を与えるこの方法は、土本来が持つ多様な微生物の生態系を崩し、その力を弱らせてしまったと指摘されている。BGが挑むのは、自然に近い生態系の土で野菜を生産し、そのおいしさをブランド化して消費者に届けること、そしてその環境的価値を経済的価値につなげていくことだ。
BG取締役の久保田龍星氏は「通常、スーパーの野菜売り場では、産地や有機JAS認証といった基準はあっても、『良い土』で野菜を選ぶことはできない。もっとおいしい野菜を食べたいという欲求に選択肢を作ることが、結果的に環境にも良い」と目を付けた。実際に、自然に近い生態系を持つ土は水や栄養の浸透力・保持力が高いことで、野菜が水や栄養を吸収しやすく、畑の栄養流出による環境汚染も起こさない。さらに、水はけもよく、豪雨などの災害にも強いという。
「食べる革命」と「つくる革命」の両輪

同社の「Next Green Revolution」が目指すのは、「食べる革命」と「つくる革命」という2つの事業を両輪に、生産者と消費者をつなげるフードシステム。食べる革命「Next Green Vegetables」は、「土で野菜を選ぶ」という新しい文化を創造するブランドだ。BGは、国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研)や複数の大学との取り組みを通じて、独自の評価指標「Agri LCA+」を開発。これにより、土壌の生態系、炭素貯留などの環境への貢献度、野菜がおいしく育つ微生物環境などを多角的に評価し、「土の価値」を可視化する。基準を満たした土で育った野菜を選定し、「Next Green Vegetables」ブランドとしてスーパーマーケットなどに展開していく構想だ。
健康な土で育った野菜は、味わいにも違いが出るという。久保田氏は「化学肥料に偏ると、えぐみが野菜に残りやすくなる。一方で、多様な微生物が共生する豊かな土で育った野菜は、野菜本来の風味があり雑味のないクリアな味わいになる」と強調。実際、取材時にキュウリやオクラを食べ比べたところ、一般販売されている野菜に感じる青臭さが、「Next Green Vegetables」にはない。代わりに、みずみずしさと爽やかな風味が口の中に広がった。
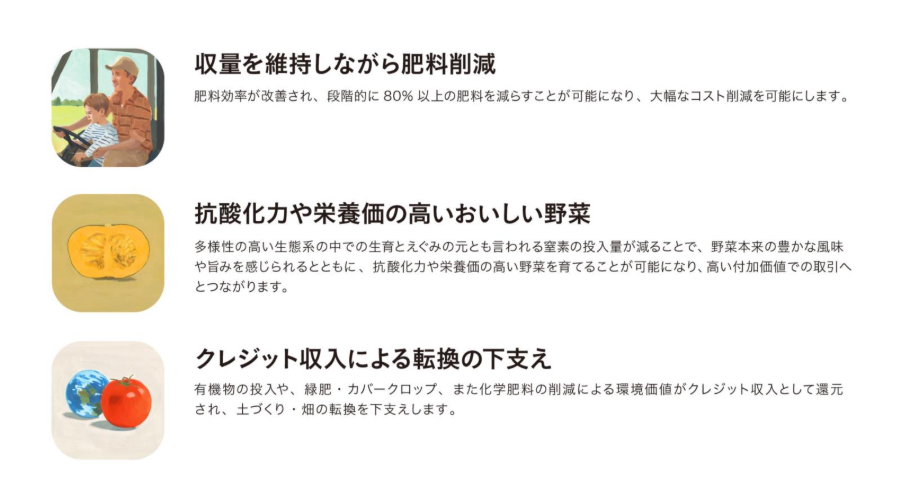
一方、つくる革命「Next Green Method」は、生産者が持続可能な土づくりへ転換する際の「資材」「評価」「資金」という3つの課題をワンストップで解決するソリューションだ。まず、地域で未利用となっている食品工場残渣(さ)や家畜糞尿、伐採木など多様な有機物を集めて発酵させた独自のオールインワン有機発酵資材「Soil Next」を生産者に提供。これにより、自然界の多様な生態系を畑に再現し、微生物の力で土を豊かにする。次に、その土づくりの取り組みを「Agri LCA+」で客観的に評価、消費者にも情報開示する。
そして、土壌改善による環境価値を「Next Green Credit」として企業などに販売することで、生産者は野菜の販売代金に加え、クレジットによる新たな収入源を確保できる。この3つの仕組みにより、生産者は収量を維持しながら化学肥料や農薬を削減し、収益を高めつつ持続可能な農業へと移行できるという。
企業の参加が資金面の循環を生む
取り組みの背景には、現代のフードシステムが抱える課題がある。現在の流通システムでは、手間暇をかけて土づくりに励んでも、その価値が価格に反映されず、生産者の努力は消費者に届かない。「この分断が、生産者の土づくりへの意欲をそぎ、土壌劣化を加速させる一因となってきた」と久保田氏は話す。

BGの取り組みは、生産者と消費者、企業と生産者をつなぎ、新たな価値共創を実現するプラットフォームとなりつつある。例えばヤンマーとは、同社のコンポスター(生ごみ処理機)の環境影響評価を「Agri LCA+」を用いて実施する形で連携。食品廃棄物の資源循環がもたらす環境価値を定量的に示し、企業のサステナビリティ活動を後押ししている。
デベロッパーの日鉄興和不動産との連携では、開発で発生する伐採木を「Soil Next」の原料として再資源化し、「Next Green Credit」を創出。また東京建物は「Next Green Vegetables」ブランドの野菜を社員食堂で提供する。企業側は環境クレジットを購入することで企業活動による環境負荷をオフセットでき、結果として生産者の収入にも貢献するといった資金面の循環が生まれる。
誰もがいつでも参画できる「船」に
BGは、2030年までに「Next Green Vegetables」の取り扱いを全国のスーパー300店舗に拡大するという目標を掲げる。「食べる革命」が消費者の意識を変え、市場の需要を喚起する。その需要が「つくる革命」を支え、生産者の持続可能な農法への転換を加速させる。そして、企業の参加が資金と資源の循環を生み出す。
久保田氏は「この革命は、僕たちだけでは成し遂げられない。生産者、消費者、企業、誰もが乗れる『船』として、この仕組みを大きくしていきたい」と展望を語る。おいしさとサステナビリティの両立に向けて、土のイノベーションが進む。
横田 伸治(よこた・しんじ)
サステナブル・ブランド ジャパン編集局 デスク・記者
東京都練馬区出身。毎日新聞社記者、認定NPO法人カタリバ職員を経て、現職。 関心領域は子どもの権利、若者の居場所づくり・社会参画、まちづくりなど。










