
気候変動と少子高齢化が加速度的に進行する今、国を挙げて地方自治体のDXとGXを推進し、地域活性化を目指す動きが活発だ。国の制度を活用し、脱炭素に関するスキルを備えた専門人材が地方に常駐しながら自治体に伴走する──そんな、新たな連携モデルも動き始めている。その一例として、今春、社内に「自治体GXセンター」を立ち上げたメンバーズ(東京・中央区)の山形県長井市での支援を、現場で奮闘を始めたばかりの若手社員の日常を通じて追った。
国の派遣制度を民間企業が活用
同社は、企業のサステナビリティ経営を「実行フェーズ」で支援。2023年からは、脱炭素に関する知見とデジタルスキルを併せ持つ人材による「脱炭素DXソリューション」を展開するほか、2024年には「地域脱炭素DXセンター」を、今年4月には「自治体GXセンター」を社内に設置し、自治体支援に乗り出している。
背景には、政府が2030年までに100カ所以上の「脱炭素先行地域」の創出を掲げて地方創生を積極推進する一方で、その担い手となる自治体では、財源やノウハウの不足が脱炭素化のハードルとなっている実情がある。このため内閣府や総務省は、民間の専門人材を自治体に派遣する制度を設けており、同社もこれを活用して、社員が地方に常駐する新プロジェクトを実現。その第1弾となる舞台の一つが、山形県南部の人口約2万5000人のまち、長井市だ。
“生きた情報”に触れられるのは大きな価値
「常駐して初めて、市長の教育にかける熱意を直接聞き、戦略の方向性を考える上で欠かせない、現場の空気を感じることができました。ネット上の資料では得られない“生きた情報”に触れられるのは大きな価値です」
そう語るのは、入社3年目で、今年5月から長井市に暮らす、メンバーズ CSV本部 自治体GXセンターの武田大輝氏。もう一人のベテラン社員と共に、市の「総合政策課 環境政策推進室」にデスクを構え、発見と学びの日々を過ごしている。
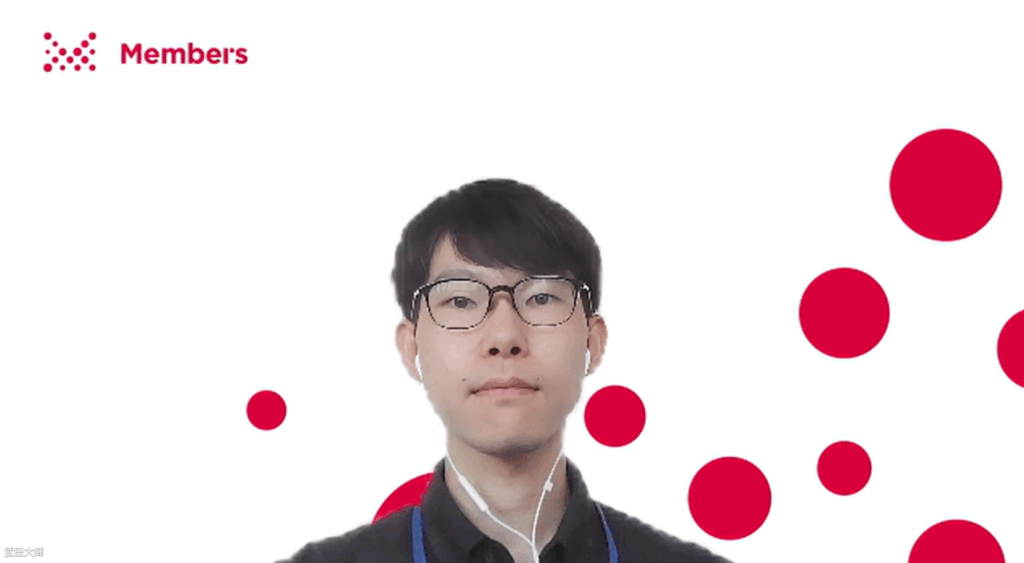
広島県呉市の出身で、長井市とはこれまで縁もゆかりもなかった。もともと、エネルギー産業が大きな転換期を迎える中で、脱炭素の動きが地方の経済や社会に与える影響に強い関心を持ち、メンバーズに入社。環境への貢献と地域活性化を両立させる新たなビジネスモデルの創出に、現場で挑戦したいと考えていた。今回の自治体常駐プロジェクトが社内で公募された際、迷わず手を挙げたという。
子どもたちの学びから、持続可能な未来づくりを
長井市は、環境省の「脱炭素重点対策実施地域」に選定されており、現場では学校給食の再生可能エネルギー100%を図る「RE100給食」や「バイオガス発電を起点とした循環型地域づくり」といった先進的なプランが進められていた。
メンバーズは、これらの取り組みを①学校給食のRE100化を起点とする脱炭素ムーブメントの創出、②森林や農地におけるJ-クレジット制度の活用、③再エネの「自家消費」モデルの確立に向けた支援、④地域通貨(ながいコイン)と連動したインセンティブ設計、という4つの戦略として体系化し、それらを相互に連携させることで地域内に好循環を生み出す仕組みを提案した。
中でも鍵になるのは、①の事業と、③の事業の組み合わせだ。「給食のRE100化」という脱炭素化の象徴的な取り組みによって、まずは子どもたちのエネルギーへの興味関心を高め、親世代にまで共感を広げる。さらにそこから、地元の事業者による各家庭への再エネ導入へと、波及効果をつなげる狙いがある。
暮らしの脱炭素化と地域経済の活性化を両立させるこのモデルは、「子どもたちの学びから、持続可能な未来づくりを始める」という長井市独自の連携モデルであり、現在、武田氏はモデルを波及させるための最初の実行フェーズを支援しているところだ。
7月には夏休みの自由研究用に、家庭の消費電力について調べることを提案するプリントを市内の6小学校に配布した。「長井市は豪雪地帯なので、冬場は特に消費電力が多くなる。そうした地域での暮らしとエネルギーを結びつけて考えるきっかけになれば」と武田氏。今後は出前授業なども積極的に行い、子どもの探究心を引き出す丁寧な発信を通じて、脱炭素化をムーブメントとして広げる考えだ。
市の総合政策課 環境政策推進室の一員として、地域にどっぷりと浸かり、「密度の濃い経験を通じて自分自身も成長していきたい」と語る武田氏の声からは、新たな連携モデルの担い手としての確かな一歩が感じられた。
持続可能な支援の在り方を探っていく
走り始めたメンバーズ社員による地方常駐型のGX支援プロジェクト。事業を統括するメンバーズ 専務執行役員 兼 脱炭素DXカンパニー社長の西澤直樹氏は、現在、長井市に加え、北海道沼田町にも若手2人が常駐し、サーキュラーエコノミーの構築に向けた支援に着手していることを、「幸いにも2つの自治体とご縁をいただいた。気候変動と人口減少による地方の衰退という課題をビジネスで解決するというミッションを掲げる当社にとって大きな前進だ」と話す。
今回、地方常駐プロジェクトに参入したのは、脱炭素リテラシーとデジタルスキルを兼ね備えた人材による支援対象を、東京を中心とした企業から、全国各地の企業へと広げる中で、「自治体を巻き込んだ包括的なGX支援の必要性」を強く感じたことがきっかけだった。
現在は、内閣府や総務省による制度を活用しており、「将来的には、自治体支援を通じて当社自身が新たな収益モデルを構築していくことにも挑戦したい。自治体ごとの課題に耳を傾け、お互いにとってのビジネスチャンスを見つけながら、持続可能な支援の在り方を探っていきたい」と展望を語る。
専門人材と自治体職員が「チーム」に
IMG_2923-1024x743.jpeg)
脱炭素化と地域活性化への強い思いを胸に長井市にやってきた武田氏らを、「チームの一員」として迎え入れた市側はどのような思いで見ているのか──。
長井市総合政策課 環境政策推進室 主査の斯波(しば)優美子氏は「地域脱炭素という大きなテーマに対して、専門的な視点を持つ人材が現場に常駐し、職員と日々やりとりをしながら共に考えてくれるのは、職員にとっても刺激になり、心強い。『子どもたちの学びから、持続可能な未来づくりを始める』という目標のもと、一緒になって、市民の意識啓発に力を入れていきたい」と語り、信頼と期待の大きさをにじませる。
2050年のカーボンニュートラルに向け、全国の自治体が脱炭素化を急ぐ中、専門人材が常駐し、その地域固有の課題に向き合いながら伴走するメンバーズのビジネスモデルは、行政と民間が協働で進めるGXの可能性を大きく広げていきそうだ。
廣末 智子(ひろすえ・ともこ)
地方紙の記者として21年間、地域の生活に根差した取材活動を行う。2011年に退職し、フリーを経て、2022年から2025年までサステナブル・ブランド ジャパン編集局でデスク兼記者を務めた。















