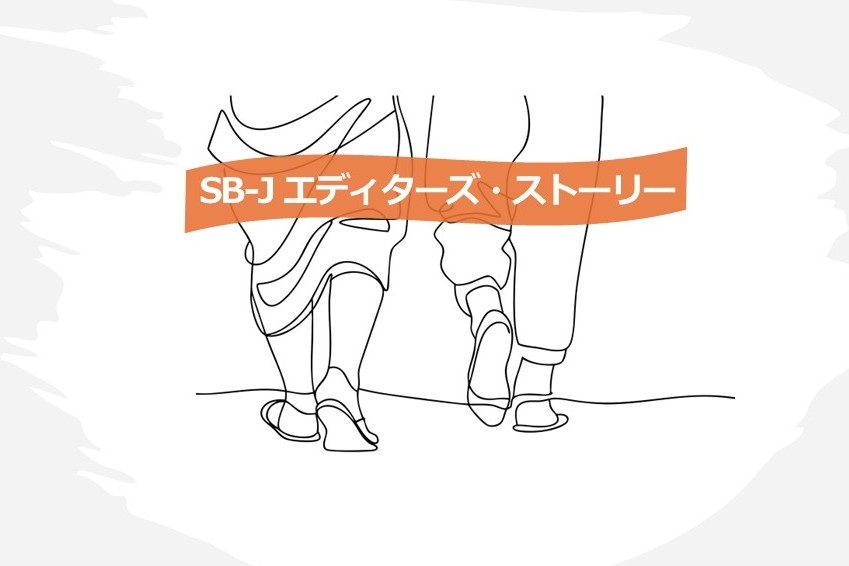
取材現場で心を動かされた言葉、記事にはならなかった小さな発見、そして、日常の中でふと感じたサステナビリティのヒント。本コラムでは、編集局メンバーの目を通したそんな「ストーリー」を、少し肩の力を抜いて、ゆるやかにつづっていきます。
今回の担当は山口です。
万博の「テーマウィーク」登壇をきっかけに
こんにちは!サステナブル・ブランド ジャパン インターンの山口です。

今、世界中から人々が集まり開催されている「大阪・関西万博」。万博には、「テーマウィーク」が設けられているのをご存じでしょうか。
週ごとに、「人権」や「生物多様性」などのテーマが定められ、それに対して解決策を話し合う「対話プログラム」や新しいアクションを促進する「ビジネス交流」が開催されています。10月13日の閉幕まで、さまざまなテーマに基づく期間限定の企画が催されるので、今後訪れる予定のある方々は一度チェックしてみてくださいね。
今回私は、とても光栄なことに、テーマの一つである「健康とウェルビーイング」内で、対話プログラムのセッションに登壇者として参加しました。
そこで今回のコラムでは、セッションでの対話はもちろん、セッション前日に巡ったパビリオンから感じた文化やウェルビーイングの可能性、そして個人的な思い出を書いていこうと思います。
万博は、まるで「世界旅行」
万博での経験全体を表現するとしたら、「超格安な世界旅行」です。マルタ、ベルギー、ブラジルなど、さまざまな国で活躍している方と話し合えたり、大屋根リングの下ですれ違ったりすることができました。各パビリオンも、国の文化や自国愛に溢れていて、旅行に行かなくても世界のいろいろな文化や人々をちょっと身近に感じられる、そんな場だなと思いました。
ちなみに、SNSなどでよく、「パビリオン ベスト●●」みたいな情報が流れてきます。私も、そういった投稿をよく見ていましたが、実際には、偶然ふらっと入ったパビリオンが印象に残ることも多かったです。パビリオンのクオリティや「口コミ」は関係なく、純粋に自分が行ってみたいと思う国のパビリオンを選んで訪れるのがよいかもしれません。
そんな中でも、今回は特に日本館について紹介していきます。
あえて日本を選んだ理由は、「国の文化を尊重し、それを活用しながら技術・経済成長を導く」という将来がクリアに見えた気がしたからです。また日本が、将来のサステナビリティをけん引していく可能性を大いに秘めているのでは?という期待も込めています。
循環する日本館
国内パビリオン「日本館」のコンセプトは、「小さな循環」。

まず目に入ってきたのは、小さな木の板が集まった外観でした。建物というより、「木の集合体」と表現する方がしっくりくる感じ。 調べてみると、木の間から中をのぞけるような設計と「中と外、展示と建築の連続」によって、日本人が大切にする「間」の価値観を意識できるように作られているそうです。実際に、木の板同士の間にある空間や、豪華に飾り付けず自然と調和したようなシンプルな造りは、日本の自然観や美意識を見事に表現していると感じました。
中に入ると、藻類が培養されている様子を実際に観察できたり、ものづくりで意識される「やわらかく作る」という価値観が最先端技術とともに紹介されていたり。また、藻類を原料の一部として使用したスツールの制作過程も実演されています。
海に囲まれている日本にとって重要な資源となる「藻」や、伝統的に引き継がれる価値観を、最先端技術と掛け合わせて活用している取り組みを知ることができたのは、純粋にとても新鮮で、未来的な体験でした。また、少しかしこまった言い方ですが、日本が担うサステナビリティへの可能性を感じ取るきっかけにもなりました。
その「サステナビリティの可能性」とは、今、日本だけにとどまらず、世界に足りていない、自然への「敬意」や「愛」だと思うのです。
日本がけん引していくサステナビリティ
サステナビリティといえば「欧州」というイメージを持つ人も多いのではないでしょうか。実際SDGs達成度ランキングなどを見ると、上位はほとんどヨーロッパの国々が占めています。でも私は、日本が古くから持つ「自然との調和」や「八百万(やおよろず)の神」などの価値観が、世界の、環境や動物のウェルビーイングをバランスよく保つためには必要だと思うのです。自然環境を、人間が支配しコントロールできるものではなく、尊重するべき、私たちを守ってくれる、そして私たちも守るような存在として捉えること。
それを、日本パビリオンで表現されている、自然をうまく生かした生活の工夫や循環技術で再確認できたような気がしています。
少しパーソナルな話になりますが、私は今、ミネルバ大学という、世界中から学生が集まる学校に通っています。
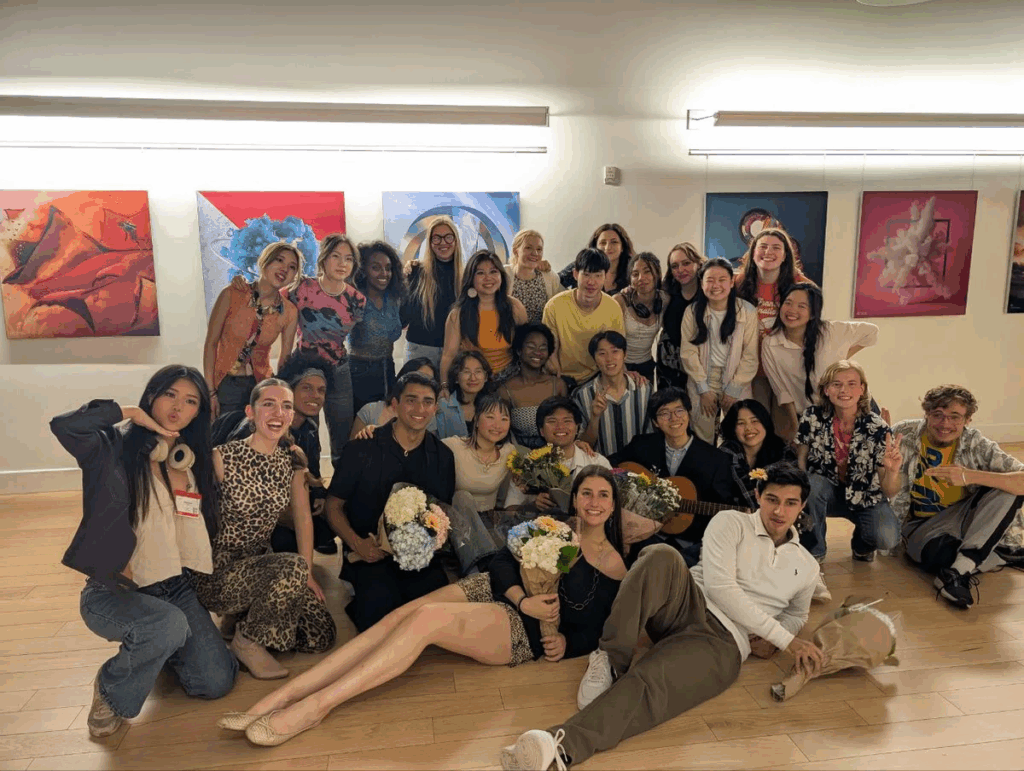
そこでは、お互いが生まれ住んでいた国についての会話をすることも多く、私自身も常に、「日本とは?」「日本人であることとは?」ということを考えさせられます。
今回、世界中のパビリオンが集まる中で日本館を体験できたことは、さまざまな国の状況や成長がある中で、「日本」がどうあるべきなのか、これまでどうだったのかを考える貴重な機会になりました。日本が、欧州などの他国を「追う」のではなく、未来をけん引するようなビジョンを描けた気がしています。
それを現実にかなえるためには、他国の人々や自然との調和、多様な背景や立場の人々を尊重することが、絶対に欠かせないと思います。とても大きく曖昧なビジョンですが、それは選挙であったり普段の選択であったり、小さな意識が重なって達成できることなのではないでしょうか。
自分や日本が、他者や地球のためにどんな将来を描きたいのか。そしてそのためにどんな選択をするのか。もう一度深く考える体験となりました。
登壇者としてウェルビーイングを議論

そして迎えた万博2日目。「Well-being 経営・教育」というテーマの対話セッションに、登壇者の1人として参加しました。多大な影響力を持つ方々と対話できる場はとても緊張しましたが、本当に、貴重な時間でした。特に印象に残っているのは、「AIの能力が爆発的に伸びている中、人間の仕事やウェルビーイングの形がどのように変化していくのか」という質問。先が読めない中で、結果よりもプロセスを重視すること、相手へ愛を持って接することなど、名だたるリーダーの方々が語るマインドセットの在り方はとっても印象的で説得力のあるものでした。
これらの価値観は、私が普段身を置いている教育の現場でも、大切にされるべきだと感じます。例えば課題や学習に「AIを使ったか、使っていないのか」という結果だけに焦点を当てるのではなく、「AIを使った/使わなかった間、何を学んだのか」というプロセスの部分にも目を向けること。AIを使う=悪 ではなく、自分なりに最も学びを得られる過程を意識して選択することが、学ぶ方法の選択肢が増えていく中で重要になってくると思います。そしてそれが結果的に、私たちのウェルビーイングにも貢献していくと思うのです。
万博の魅力は人にあり
世界中の文化や人々が集まる万博。 そんな万博が日本で開催され、そしてテーマウィークの関係者として関われたことは、とても光栄に思います。
私は万博の最も大きな魅力は「人」にあると感じました。
パビリオンを回るのももちろんとっても楽しいですが、例えばそこで働いている方に質問をしたり、セッションを聞きに行ったり。世界から集まる人々の生の声が、日本の大阪で聞けることは、本当に貴重な機会だと思います。
長くなりましたが、万博での経験は私にとって一生ものになった気がしています。
そしてこの機会が、多くの日本人にとって、国内外の人たちの最もウェルビーイングな将来を考えるきっかけとなりますように。
山口 笑愛(やまぐち・えな)
サステナブル・ブランド ジャパン編集局 インターン
ミネルバ大学在籍中。ユースコミュニティ「nest」に参加したのがきっかけで、高校1年生からSBに関わる。今はファッションと教育を主軸に、商品制作、メディア、イベント企画を通して発信活動中。















