
プラスチックごみの増加や気候変動が深刻化する中、大阪・関西万博の北欧パビリオンで6月、日本テトラパック主催の特別イベント「資源循環の未来:共創が生み出す新たな価値と可能性」が開催された。基調講演やパネルディスカッションを通して、欧州の先進事例などを共有。製紙メーカーやリサイクル事業者らが「共創」を軸とした連携モデルを議論し、古紙の資源循環の方向性を示した。熱気に満ちたイベントの様子を報告する。

イベント冒頭、日本テトラパック代表取締役社長のニルス・ホウゴー氏がステージに立ち、「日本政府が掲げている2050年までのカーボンニュートラル達成の実現には、脱炭素に資する循環型経済の推進が必要」と力説。そのためには「産業界、行政、学術界、消費者の幅広い連携が不可欠だ。パネルディスカッションなどを通じて共創の可能性を探っていきたい」とあいさつした。
「譲歩」しながら全体の「最適化」を

初めに、欧州製紙連合会事務局長のヨリ・リングマン氏が「資源循環の未来の形成」と題して基調講演を行った。欧州では同連合会がハブとなり、「4evergreen」というアライアンスが発足。紙繊維由来の容器のバリューチェーン企業100社以上が参加し、2030年までに紙繊維由来の容器のリサイクル率を90%に引き上げることを目標に活動している。
その野心的な目標の達成に向けて、4evergreenは「紙繊維由来の容器リサイクル可能性評価のプロトコル」「循環型を前提とした設計のガイドライン」「回収と分別を改善するガイダンス」を策定した。ヨリ氏はEUの包装・包装廃棄物規則(PPWR)への対応も念頭に、「循環型経済の実現には、素材メーカーである製紙業者からリサイクル事業者まで、バリューチェーン全体の協力が不可欠だ」と強調。時には互いに「譲歩」しながら、全体システムの「最適化」を図ることが重要だと主張した。
循環性はデザインから始まる

基調講演に続いて、テトラパックのサステナビリティ部門副社長、キンガ・シェラゾン氏が登壇した。キンガ氏はまず、世界の温室効果ガス排出量のおよそ3分の1を食品産業が占め、2050年までに70%増加するという厳しい統計を提示。食品・飲料業界における循環型経済への移行の重要性を訴えた。具体的には、「循環性はデザインから始まる」として、紙容器の設計段階からリサイクル性を高める「デザイン・フォー・リサイクリング」の実践を紹介。これは4evergreenが策定した設計ガイドラインに則ったもので、業界横断の協働事例となる。
さらにキンガ氏は、紙容器の「回収率の低さ」を課題として説明。AIを活用して回収・追跡を行う英国のスーパーや、メーカー主導で回収・再利用を推進するネスレなどの事例を紹介し、バリューチェーン全体での連携が必要と強調した。最後にキンガ氏は「良いニュース」として、日本ではミルクパックなどからの繊維がティッシュペーパーや多くの日用品に再利用されていることに触れ、「循環型経済を実現させる共通の目標に向かって、一緒に前に進みましょう」と呼びかけた。
アルミ付き紙容器を段ボールの原料に

続いて登壇した製紙業界最大手、王子ホールディングスのリサイクル推進部長、島谷啓二氏は、包装資材の脱プラスチック化で紙素材の存在感が高まっている、と指摘した。他方、日本では紙・板紙の生産量の減少に伴い、古紙発生量も減少。古紙回収率は81.7%、利用率も66.6%(いずれも2024年時点)と横ばい状況が続いている。特にアルミ付き紙容器の回収率は3.6%と極めて低く、焼却処分される例が大半であることが大きな課題という。
島谷氏はこの状況を打破すべく、複合素材も含めた全ての未利用古紙をリサイクル可能にする取り組みが重要と強調。そこで日本テトラパックと共同で開発した、アルミ付き紙容器を段ボールの原料として再資源化する国内初のリサイクルフローを紹介した。また、古紙資源のリサイクル促進には、技術革新と法制度の整備、さらには行政・企業・消費者の連携が必要と力説。最後に「リサイクルといえば王子」とブランディングも意識した表現で、循環型社会の実現へ強い決意を語った。
共創が生み出す価値と可能性
イベント後半はパネルディスカッションが行われ、製紙会社、リサイクル事業者、容器メーカー、自治体に関わる一般社団法人から、パネリスト4氏が登壇。「官民連携を通した紙製容器包装の循環型社会の実現」をテーマに、資源循環の現状と課題、そして今後の展望について議論を深めた。ファシリテーターは、サステナブル・ブランド ジャパン総責任者(Sinc 代表取締役社長兼CEO)の田中信康が務めた。
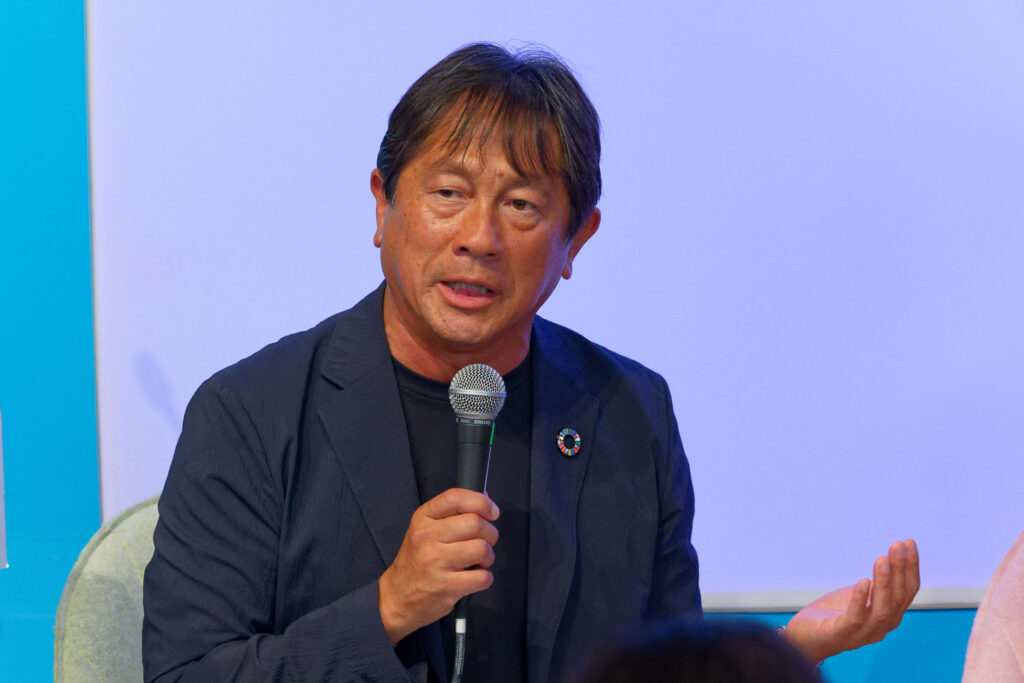
冒頭、田中は「共創」と「サーキュラリティー(循環)」の2つのキーワードから、イベント前半の基調講演などを振り返った。その上で「ここで交わされた多様な視点からの議論を、各企業・自治体が自らの地域・組織に落とし込み、実際のアクションに移してほしい。このセッションが、そんなきっかけ作りになれば」と述べ、まずは「現状把握」からパネルディスカッションをスタートさせた。

一般社団法人イクレイ日本は、会員自治体の活動をサポートし、国際的な都市間連携を推進している。イクレイ日本事務局長の内田東吾氏は、日本には約1000の焼却施設が存在することを紹介。「日本では紙ごみの多くが可燃ごみとして処理され、自治体ごとに収集方法が異なるためリサイクルが進みにくい」と指摘した。続いてイベント前半にも登壇した王子ホールディングスの島谷氏が、製紙メーカーの立場から「限られた地域でしかリサイクルが行われていない」とし、リサイクルを容易にする技術革新がメーカーの役割と語った。
大本紙料代表取締役の大本知昭氏は、来年に創業70年を迎える関西拠点のリサイクル企業として、「古紙の発生量減少で回収ネットワークの維持が困難になっている。市民の啓発や新たな再生品の開発が重要」との認識を示し、回収量確保の苦労を明かした。日本テトラパックのサステナビリティディレクター、大森悠子氏は容器メーカーの視点から「古紙不足の状況で、燃えるごみの3〜4割を占める紙類の資源化が鍵になる。未利用資源としての活用を推進している」と述べた。

続いて「課題」では、内田氏が「自治体ごとの対応は細分化しており、行政の採算性や取り組みのスピード感に課題がある」と指摘。焼却施設の更新には長期的計画と安定的な収集量が不可欠なため、新たな分別フローの導入が容易ではない自治体の現状を解説した。島谷氏は「経済合理性を保ちながら、個社だけでなく関係者が分担して取り組む必要がある」と強調し、製造業者と回収業者、行政の連携強化を求めた。
大本氏は「利便性の高い回収手段の提供が求められる」とし、都合の良い時に出せる「リサイクルステーション」のような収集モデルの構築を訴えた。大森氏はスーパーや回収業者への声掛けを重ね、西日本で約400カ所に回収拠点を拡大した事例を挙げつつ、「消費者の認知はまだ低い。小売やブランドオーナーとともに消費者コミュニケーションに取り組んでいる」と課題を共有した。

最後に「今後の展望」として、大本氏は「既存のインフラを活用したことで、アルミ付き紙容器の回収がスピーディーに拡大した。今後もこの事例を生かして、回収の効率化を目指す」と意欲を示した。島谷氏は「通常の古紙と同様にリサイクルできる技術確立が進めば、回収のしやすさにつながる。紙パルプ業界全体で課題解決と技術進歩に向けた連携が重要だ」と展望を語った。
内田氏は「地域ごとの事情を踏まえた最適な資源循環モデルが必要。自治体と民間が互いの特性を理解して、対話しながら進めることが大切だ」と提言した。大森氏は「持続可能な社会の実現には、成功事例を共有し、業界の縦割りを超えた柔軟な連携が不可欠」とまとめ、バリューチェーンを横断した共創を訴えた。
パネリスト4氏の議論を踏まえて田中は「丁寧な対話と、地に足をつけて地道にやっていくことが大事。勇気の出るディスカッションになった」と手応えを語り、セッションを締めくくった。

共創が生み出す価値と可能性を探った、今回のイベント。欧州と日本の最新事例の共有から、多角的な視点による議論まで、「資源循環の未来」を考える上で示唆に富む内容となった。自社だけでは成し得ない循環型経済の実現には、業界も国境も超えた共創こそが欠かせない――。参加者はあらためて、そのように実感したに違いない。
眞崎 裕史 (まっさき・ひろし)
サステナブル・ブランド ジャパン編集局 デスク・記者
地方紙記者として12年間、地域の話題などを取材。フリーランスのライター・編集者を経て、2025年春からサステナブル・ブランド ジャパン編集局に所属。「誰もが生きやすい社会へ」のテーマを胸に、幅広く取材活動を行う。















