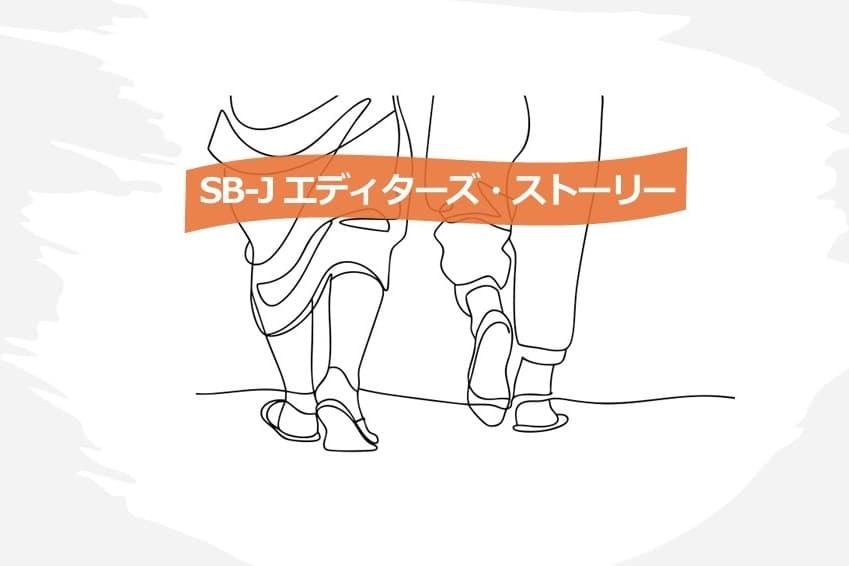「仕草がかわいい」「癒される」と、近年、珍しい爬虫(はちゅう)類などのペットをSNS上でもよく見かける。しかし、その生き物は違法取引によって日本に持ち込まれたものかもしれず、本来の生息地では絶滅の危機に瀕(ひん)しているかもしれない。
今年11月にワシントン条約の第20回締約国会議(CITES CoP20)を控え、WWFジャパンはこのほど、日本で人気の爬虫類9種に関する国際取引の実態をまとめ、「問われる日本の責任」と題したレポートを発表した。調査では、合法的な輸入記録のない種や、生息国の規制をかいくぐったロンダリング(合法的に輸出可能な繁殖個体と偽った取引)が行われている疑いが確認されたという。
世界有数のペット大国日本で、爬虫類をペットとして飼うことは、遠く離れた自然や生き物の命とどうつながっているのか──。
人気爬虫類9種の取引実態を多面分析
WWFジャパンによると、爬虫類は現在、世界で最も商業利用されている脊椎動物の一群とされ、国際市場の規模は数十億ドルに達する。日本では近年、犬や猫以外の多様な生き物をペットとする流れの中で、「生きた爬虫類」の輸入量が増加。2022年には世界第2位の輸入国となっている。
こうした状況を受け、今回の調査では、すでにワシントン条約の附属書に掲載され、取引が規制されている種に加え、今後CITES附属書への掲載提案がなされる可能性のある種にも焦点を当てた。
対象となったのは、コバルトツリーモニターやクロヨロイトカゲ、トッケイヤモリなどの9種。2000〜2023年の国際取引データや、2025年3月に行った、41のウェブサイトと、出展業者90以上の即売会でのスポット調査などをもとに、取引の合法性と持続可能性を多面的に分析した。
合法性、持続可能性ともにレッドフラグ


爬虫類展示即売会で、トッケイヤモリや、アカメカブトトカゲが販売されている様子©WWF-Japan
調査の結果、見えてきたのは、違法に捕獲された野生の爬虫類が、飼育下で繁殖されたものと偽って日本に輸入された疑いのあるケースが多く存在する実態だ。
例えば、クロヨロイトカゲは、種としての合法的な輸入記録が一切なかった。またインドネシアの固有種でオオトカゲの絶滅危惧種、コバルトツリーモニターは、生息国インドネシアで野生個体の輸出が禁止されているにもかかわらず、「野生捕獲」と記載された個体が流通。全体として、合法性と持続可能性の両面でレッドフラグが上がる種が目立った。
一方、動物愛護管理法上、事業者には原産地などの記載義務があるのに反して、多くの個体が原産地の記載がないままに販売されていた。さらに、ワシントン条約で未規制のアカメカブトトカゲとモトイカブトトカゲについても、多くの個体が安価に販売され、持続可能性が懸念される状態にあることが明らかになった。
日本の市場拡大が違法取引を助長する
レポートはそうした実態を踏まえた上で、「日本の爬虫類ペット市場の拡大が、野生動物の過剰で違法な取引を助長し、種や生態系への影響が強く懸念される」と警鐘を鳴らす。世界第2位の輸入国として、日本が国際的な爬虫類取引において責任を持ち、合法で、持続可能な市場へと変容することを求める内容だ。
具体的には、ワシントン条約における管理当局(経済産業省)と科学当局(環境省)に対し、輸入確認の強化やロンダリング防止のためのサイズ制限、全ての輸入爬虫類に関する詳細なデータベースの構築と、監視体制の強化などを提言。
事業者や消費者に対しては、生きた爬虫類の市場を自主的に規制し、「取引が野生の個体群に悪影響を及ぼす恐れのある種や、ロンダリングが疑われる個体の販売や購入を拒否するべき」としている。
野生動物のペット化が取り返しのつかないリスクに
WWFジャパンは、過剰な利用と違法取引によって絶滅の危機にさらされる野生動物をゼロにすることを目標に、2022年から「野生動物を安易にペットにしない」ことを訴えるプロジェクトを展開。野生動物のペット利用自体を一律に否定するものではないが、需要の高まりが違法取引を助長し、種の絶滅や、輸入された動物が日本の在来種に悪影響を与えるリスクにつながること、また本来、人と暮らすこと自体が強いストレスとなる種も少なくないことを、さまざまなアプローチで消費者に伝え、行動変容を促してきた。
ペットとして輸入されたアライグマが野生化し、特定外来種として駆除対象となっている例や、日本で人気を博したコツメカワウソが密輸の横行によって絶滅危惧種となり、ワシントン条約で国際取引が禁止された経緯などは、そのリスクを如実に示している。
「生きた動物のトレーサビリティが全くない日本」
今回の調査で改めて浮かび上がった、日本の爬虫類ペットを巡る実態は、何を物語っているのか――。長年日本の爬虫類ペット市場を調査してきたWWFジャパン 自然保護室 野生生物グループの若尾慶子氏は、「依然として合法性や持続可能性に疑問のある取引がなされ、しかも市場が拡大していることは甚だ遺憾だ」と受け止める。
ペットの過剰利用を食い止めるためには、日本の当局による積極的な働きかけが求められるが、若尾氏には「その前に、事業者が、適正で持続可能な取引を行うよう、自主的なコントロールを通じて市場が変化してほしい」という思いが強い。
現状では、「生きた動物のトレーサビリティが全くなく、入国してしまったらそれ以降のことは分からない。特に消費者からは一切見えない」ことが大きな課題だ。
そうした状況を踏まえた上で、若尾氏は、日本の消費者に対して、「由来が明らかでない個体は購入しないようにしてほしい。本来、生き物が大好きなはずの方に、野生動物をペットとすることの意味を今一度考えてほしい」と語る。
11月のCITES CoP20では規制強化が議論されるが、法制度を待つだけでなく、日本の市場と消費者自身の意識の変革が問われている。
| 【参照サイト】 ・WWFジャパン『問われる日本の責任~日本市場で人気の9種の爬虫類に関する取引調査』レポート https://www.wwf.or.jp/activities/data/WWF_report-tracking-the-trade-jp.pdf ・「好きだからこそ。〜違法な取引から野生動物を守りたい〜」 https://www.wwf.or.jp/campaign/da_2019ws/ |
廣末 智子(ひろすえ・ともこ)
地方紙の記者として21年間、地域の生活に根差した取材活動を行う。2011年に退職し、フリーを経て、2022年から2025年までサステナブル・ブランド ジャパン編集局でデスク兼記者を務めた。