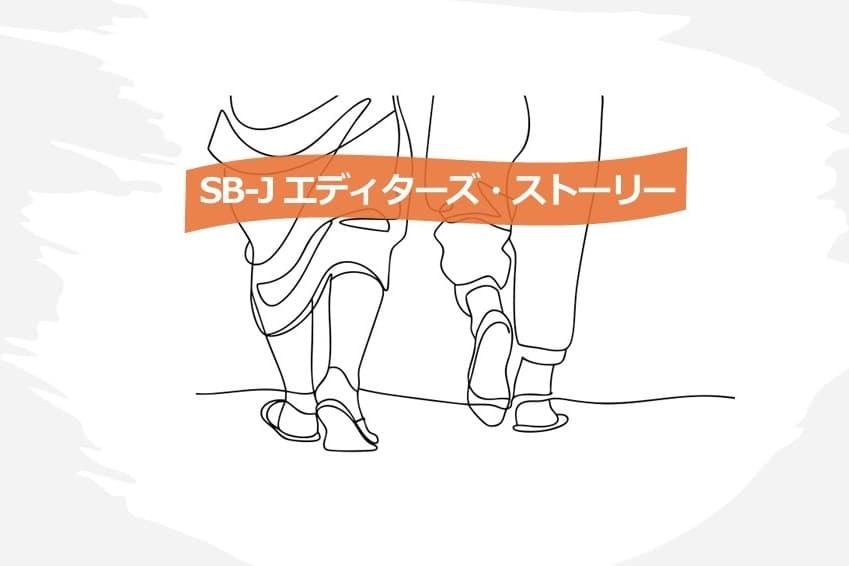恐ろしいことに、魚の重量を上回るほど多くのプラスチックごみが近い将来、海を漂うようになる。ならば、海にたどり着く前にプラスチックごみを回収すればいい――。そう思い立った英スタートアップは、衛星画像やAI搭載ソフトウェアなどの技術を駆使して、河川を流れるプラスチックごみの回収システムを構築した。南米ではすでに、地元の自治体や住民の手を借りて大きな成果を上げている。日本企業も注目する同社の包括的な試みを詳しく紹介する。(翻訳・編集=遠藤康子)
世界はプラスチックであふれている。海に流れ込むプラスチックごみは推定で年間1100万トンに上り、2040年には3倍に膨れ上がる見込みだ。河川はあたかもベルトコンベアのように、内陸部の都市から海に向かうプラスチックごみの80%を運んでいる。
この状況が続けば、2050年には海洋を漂うプラスチックの重量が魚の重量を上回る恐れがある。プラスチックの使用禁止措置やリサイクル、意識向上キャンペーンといった手段は有効だが、事態を本気で一変させたければ、プラスチックごみの発生源を断つ以外に打つ手はない。
プラごみの海洋流出を阻止
そんな中、プラスチックごみを巡る世界的な議論を「回収」から「阻止」に転換させるべく挑んでいるのが、英テクノロジー企業のイクティオンだ。ロンドンで生まれた同社は現在、南米で事業を展開。最先端の工学技術と衛星データ、AI搭載ソフトを駆使し、地域社会と連携しながらプラスチックが海に流れ着くのを阻止しようとしている。
イクティオンは2017年、最高経営責任者(CEO)のインティー・グロネベア氏がインペリアル・カレッジ・ロンドンの研究室に在籍し、河川からプラスチックを回収する技術を開発していた頃に創業した(当初の社名はリモラ・マリン)。その後、大学で開かれていたイベントを訪れたロイター記者が同社に関心を示し、開発初期の技術を紹介する短い動画を制作した。この動画が話題となり、85カ国で視聴されるほど大きな注目を集めた。これを受けて大学側がグロネベア氏に対し、知的財産を譲渡するか起業するかの選択を迫り、グロネベア氏は会社立ち上げを決めたという。
「それ以来、ずいぶん多くのことが変わりました」。グロネベア氏は米サステナブル・ブランドの取材に対してそう語った。「起業当初は、プラスチックごみ問題を解決するための技術開発に力を入れていました。しかし現在は、データ、イノベーション、技術、科学を駆使し、環境中のプラスチックごみを削減することを目指しています」
発生源から海まで全般的に取り組むシステム
イクティオンはプラスチックごみの削減にあたって、ごみの検知・追跡・回収という一連の技術を連携したシステムを採用している。要するに、ごみが発生して海に流れ着くまでの問題全般に対処しているわけだ。
システムの先陣を切るのはAIを搭載したソフト「Hyperion」だ。人工衛星とドローンのデータを解析し、プラスチックごみが集まっているホットスポットを特定している。ホットスポットが判明すれば、プラスチックが内陸部のごみ発生源から沿岸海域に流れ着くまでの経路を追跡して、対策を講じるべき位置を正確に見定めることが可能になる。
「私たちはプラスチックごみがたどる経路を詳細に把握しています」とグロネベア氏は話す。「まず、欧州連合(EU)の地球観測プログラム『コペルニクス』を活用して、沿岸部を流れるプラスチックごみの動きを追跡します。次に、高解像度の航空カメラと河川カメラを設置して、プラスチックが集中しているホットスポットをマッピングします。これを基に、当社が開発したAzureシステムの配置位置を決定します」
Azureは河川を流れるプラスチックごみを回収するシステムだ。浮遊式のフェンスでプラスチックごみを集め、回収機械で捕獲する。設計上は1日当たり80トンまで対応できるが、実際の回収量は現地の状況や配置規模によって異なる。位置を固定してシステムを稼働させ、回収したプラスチックごみを陸上に直接輸送し、水界生態系に与える影響を最小限に抑えている。
新技術をさらに導入
稼働中のシステムに加え、次の2つの新技術も近く導入する予定だ。
・Ultramarine:大型船舶向けの移動式プラスチック回収システム。海洋生物への悪影響を避けながら、主要な航路沿いにある重要度の高い沿岸地域で稼働する。
・Cobalt:自動洗浄機能が付いた膜状のシステム。水の自然な流れを利用してマイクロプラスチックを回収する。タービンや船舶に搭載すれば、拡張とエネルギー効率に優れた運用が実現できる。
同社はまた、ガラパゴス諸島のプラスチックごみ問題解決にも取り組んでいる。アンデス地域から排出されるプラスチックごみが一様にガラパゴス諸島の方向に流れており、すぐに対処しなければ世界有数の貴重な生態系が破壊されてしまう。そう懸念した同社が始めたのが、人々の行動変容を促してプラスチックがそもそもごみにならないよう防止する「Galapaxy」という事業だ。使い捨てプラスチックへの依存度軽減を目指し、無料の給水ステーションを設置したり、リユースできるボトルを提供したりしている。
南米で多数の実績
イクティオンは世界各地の国々と手を結んでプラスチックごみの削減に取り組んでおり、世界で最も汚染が深刻な河川で成果を上げつつある。例えば、南米エクアドルを流れるサンペドロ川では、同社の事業でプラスチックごみが40%減少した。
「サンペドロ川では、プラスチックごみのおよそ40%が、主に繊維工場が違法に投棄している産業廃棄物であることが分かりました」とグロネベア氏は言う。「このデータを自治体と共有することで、対象を絞り込んだ対策を講じることが可能になりました。上流に位置する工場が自らの行為を自覚したことと、取り締まりが行われたことで、廃棄物の投棄をやめざるを得なくなったのです」
同じくエクアドルを流れるタハマール川では、農村地帯で使用される肥料の容器がごみとして川に捨てられていることが判明した。現在は、地域社会と肥料メーカーが協力し、容器を返却するとデポジットが戻ってくる制度の導入を進めている。
3カ所目の大規模事業は、グアテマラを流れるモタグア川で実施されている。モタグア川は南米で最も汚染が進んでいる河川の1つだ。衛星画像と航空画像を分析した結果、プラスチックごみの75%以上が地元の埋め立て地を発生源としており、破損した下水管からの漏水が原因だったことが明らかになった。
「河川そのものが300kmに渡ってまるで埋立地のようになっており、実にひどい状況でした」とグロネベア氏は振り返る。「そこで私たちは、技術を導入する代わりに地元当局に助言し、ごみの発生源である埋立地で起きている大規模な下水流出という問題をまず解決するよう提案しました」
地元コミュニティと連携
廃棄物管理インフラが不十分もしくは皆無の地域では、自治体や地元のごみ収集業者、住民と手を組んで、対応力の向上と行動変容を促している。
「エクアドルの農村地帯では、ごみ回収サービスを利用できる住民は10人中2人に過ぎません」とグロネベア氏は話す。「住民はごみを川に捨てるか燃やしています。無関心だからではなく、他に手段がないからです」
イクティオンはごみ拾いで生計を立てている人たちと連携し、その労働力をリサイクルのバリューチェーンに組み入れている。「事業を展開してきた地域には必ずごみ拾いを生業にしている人たちがいます。そこで私たちは、社会的に責任のある形で彼らと協働していく方法を地元のごみ収集業者に指導しています。データを基に回収作業の方向性を決め、さらなる成果を得られるようにしているのです」
イクティオンはエクアドルで政策立案にも関与している。同国初となる循環経済と包括的リサイクル関連法の草案作成を支援したほか、環境プロジェクトに投資した企業向け税制優遇制度の策定にも一役買っている。この制度は英国の企業投資スキームに着想を得たものだ。
パートナーシップを拡大中
同社は、プラスチックごみを下流で単に回収しリサイクルするだけでなく、ごみの発生源を絶つことに真剣に取り組む意志のある組織とのパートナーシップに積極的だ。データ主導型の戦略を取り入れ、地域社会と連携し、仕組みを変更することにより、測定可能なシステムを構築し、長期的なプラごみの縮減を共に目指す組織を求めている。
これまで、ビールブランドのコロナをはじめとする企業とパートナーシップを結んできた。現在は、科学技術の発展に取り組む日本のリバネスグループや米カリフォルニア州に拠点を置く海洋科学グループ、エクアドルで稼働する中国の自動車メーカーなど世界18組織と協働中だ。また、ボトリング企業2社も新たに加わった。
「当初は本能的に、ボトリング企業との提携は避けた方がいいと思っていました。しかし、今ではぜひとも提携すべきだと考えています」とグロネベア氏は話す。「そうした企業には自社が及ぼす影響を把握するためのデータが必要です。そして、変化を促すのはデータなのです」
イクティオンは現在も英国に本社を置いているが、事業は急速に拡大している。南米エクアドル以外にもマレーシアで稼働しており、近く南アフリカにも進出する予定だ。アンデス地域では事業を本格展開しており、グロネベア氏によれば、世界中から寄せられた20件以上のライセンス申請について審査中だという。
事業をさらに拡大するため、イクティオンはハードウェアについて設計を見直し、より手頃な価格で簡単に製造できるよう改良を加えている。発展途上国でも同社技術を採用しやすくすることが目標だ。