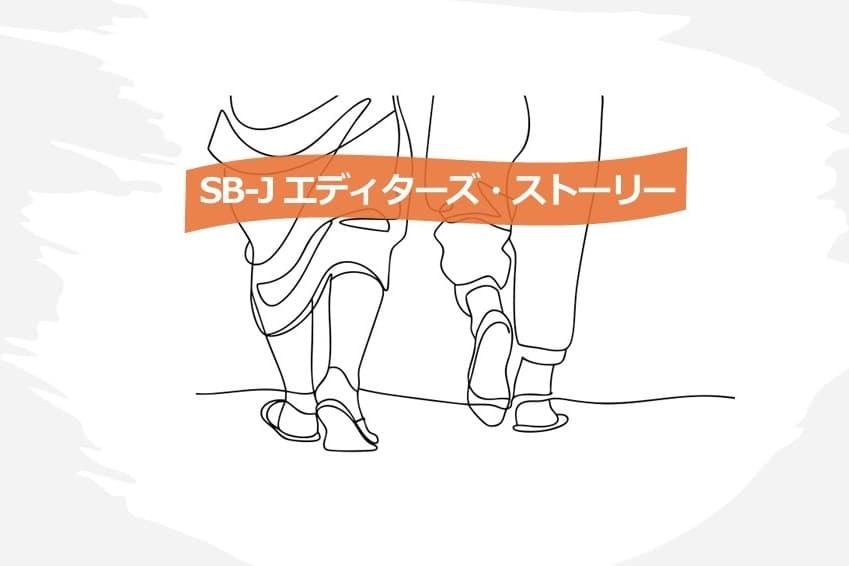日本の食料自給率の低下や第一次産業における人手不足、気候変動の深刻化といった複合的な社会課題に対し、テクノロジーの力で解決を目指す「フードテック」の重要性が高まっている。本セッションでは、「持続可能な生産・流通・管理」をテーマに、自動車部品メーカーのデンソー、通信大手のソフトバンク、製紙業の日本製紙という異業種の3社が登壇。それぞれの強みや技術を生かし、フードバリューチェーン全体における課題に挑む革新的な取り組みが共有された。
| Day2 ブレイクアウト ファシリテーター 大野泰敬・スペックホルダー 代表取締役社長 パネリスト 西部慎太郎・デンソー フードバリューチェーン事業推進部 課長 須田和人・ソフトバンク IT統括IT&アーキテクト本部 アドバンスドテクノロジー推進室 室長 針谷綾子・日本製紙 バイオマスマテリアル・コミュニケーションセンター センター長代理 |
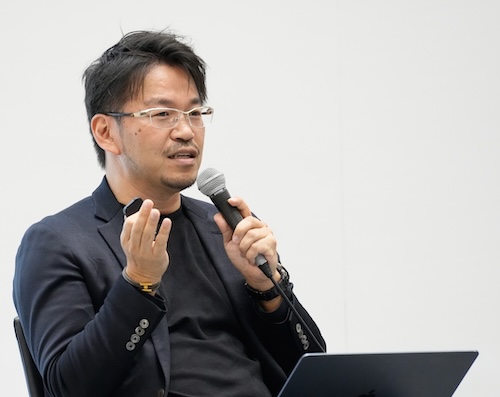
ファシリテーターの大野氏は、冒頭、日本の食料自給率が危機的な状況にあると説明し、一般的に知られている食料自給率38%という数字は、飼料自給率を考慮すると大幅に低下することを議題に挙げた。具体的には、卵、牛乳、豚肉、鶏肉の自給率が飼料自給率を考慮すると激減する現状を示し、本セッションに登壇する3社の取り組みがそれに対するソリューションになることを示唆。
さらに、大野氏によると、世界的にフードテックは一次産業をサポートする方向に投資が集中しているのに対し、日本においては代替肉や昆虫養殖といった分野に注目が集まる傾向が強く、フードテックの分野において日本だけが周回遅れになっていることが懸念されるという。セッションは、そうした「フードテック」への共通認識を深めた上でスタートした。
デンソー:自動車技術を農業と食の現場へ

自動車部品開発で培った技術を生かし、デンソーはフードバリューチェーン全体を視野に入れた事業を展開している。フードバリューチェーン事業推進部 課長の西部慎太郎氏は「一次産業の課題に対し、生産・物流・消費の3つの領域でソリューションを提供している」と説明した。
生産領域では、就農人口の減少という構造的課題に向き合い、収益性の高いスマート農業の実現に取り組む。具体的には、国内最大級の農業ハウスでの実証実験や、世界初のトマト収穫ロボットの開発など、技術の導入によって省力化と生産性向上を図っている。
また物流領域では、2024年問題(ドライバー不足および労働時間規制)への対応として、モバイル冷蔵・冷凍ユニット「D-mobico」を開発。これにより、ラストワンマイルの課題を解決し、フレキシブルな低温物流を実現している。さらに消費領域では、QRコードを活用したトレーサビリティシステムを構築しており、プレゼンテーションでは、アサリの産地偽装問題に対し、生産地から消費者までの情報を可視化する事例が紹介された。
ソフトバンク:AI×養殖で持続可能な海の幸を

ソフトバンクは、AI技術を核とした養殖業の効率化と品質向上に取り組む。IT統括IT&アーキテクト本部 アドバンスドテクノロジー推進室 室長の須田和人氏は、世界的な水産資源の減少と食料供給の不安定化を背景とする、AIを活用した養殖トータルソリューションを紹介した。
具体的には、水中カメラと連携したAIモデルによる魚の数やサイズの自動カウントや、漁網の損傷検知などの技術を開発し、これにより、人的コストの削減、餌の最適化、出荷時期の最適化などが期待されている。
さらに、NIR(近赤外)センサーを用いて魚の化学成分をリアルタイムで測定し、鮮度や旨味などの品質を可視化する取り組みも進めている。これは、従来は感覚に頼っていた部分の“見える化”を進める画期的な技術だ。
須田氏は「生産効率と品質の両立により、生産者が事業を持続可能にするための支援を目指している」と述べ、将来的にはこの品質情報を消費者にも提供し、食の新たな体験価値を創出する構想を示した。
日本製紙:木から生まれる、未来の飼料

製紙業を基盤に持つ日本製紙は、木材を原料としたバイオマス素材の研究開発を通じ、食料分野においても持続可能なソリューションを提供している。バイオマスマテリアル・コミュニケーションセンター センター長代理の針谷綾子氏は、木材由来のセルロースを活用した製品群として、牛用飼料「元気森森」とセルロースナノファイバー「セレンピア」を紹介した。
「元気森森」は、木材から取り出した高純度セルロースを飼料化した世界初の取り組みで、輸入飼料に依存する現状に対し、国産で安定供給できる代替飼料として注目されている。
また、食品の品質向上や賞味期限の延長などに貢献する「セレンピア」は、機能性素材としてさまざまなフードテック分野での応用が期待されている。
針谷氏は、自社の循環型森林経営にも言及し、「木材は再生可能資源であり、食料と競合しない点が最大の特徴。これを生かし、国産資源による食料自給率の向上にも貢献していきたい」と語った。
消費者の意識改革が食の未来を変える
フードテック分野で最先端のソリューションを開発する企業が、現在注目している社会課題は何か――。デンソーの西部氏は、最も深刻な課題として「気候変動による一次産業への影響」を挙げ、「今後は露地栽培に頼らない新たな栽培方法が必要となる」と指摘した。
また、針谷氏や須田氏も、飼料価格の高騰や漁獲量の減少など、生産者が事業を継続することの困難さに言及し、それぞれが直面している課題に対して事業を通じて取り組む姿勢を示した。
最後にファシリテーターの大野氏は、持続可能な食の未来においては、消費者の意識変革こそが不可欠であると強調した。製品の背景にある価値や意義を理解し、購買という行動を通じてそれを支援する姿勢が重要であると訴え、地元産品を積極的に選ぶことの意義を呼びかけて、パネルディスカッションを締めくくった。
井上 美羽(いのうえ・みう)
愛媛県松野町在住フリーライター。地方で農を実践しながら、地方での食の魅力化に取り組む。 食、環境、地方を専門として、主に取材・インタビュー記事の執筆を手掛ける。 日本サステイナブル・レストラン協会や日本スローフード協会の事務局として、食にまつわるイベントプロデュース、コーディネーターなどを担当している。