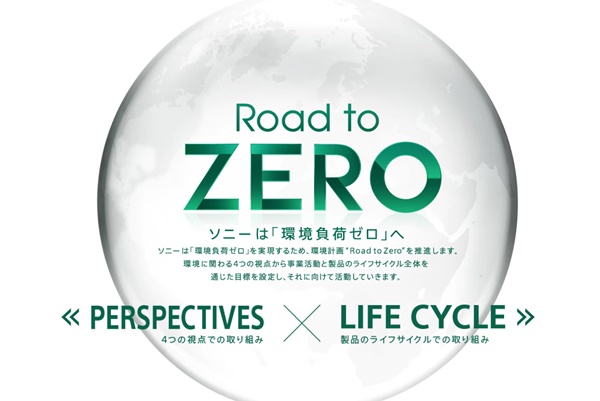 |
「当社では環境への取り組みを品質管理システムにビルドインしています」――そう話すのはソニーの鶴田健志・品質・環境部ゼネラルマネージャー。同社は2017年2月、日本企業として初めてSBT(Science Based Targets:科学的根拠に基づいた温室効果ガス削減目標)に認定され、10月に国際NGOのCDPが行った企業の環境対策に関する聞き取り調査の結果、「気候変動Aリスト」「ウォーターAリスト」の2部門でAリスト入りした。その環境への目標と実行計画を鶴田氏に聞いた。(オルタナ編集部=沖本啓一)
環境計画の根幹「Road to Zero」
ソニーの環境活動が本格化したのは1990年だ。社内報の号外で、環境保全に関する社長方針が通達され、同時に社内で地球環境委員会が発足した。1993年に環境基本方針と環境行動計画を策定し、2002年には全世界の製造事業所でISO14001の認証取得を完了した。
いち早く環境課題に取り組み始めたソニーが、2010年に策定したのが「Road to Zero」だ。環境負荷ゼロを達成するための計画で、2050年の達成を目標に達成年からのバックキャスティング(逆算)で具体的な施策を決定する。鶴田氏は「Road to Zeroはソニーの環境計画の根幹」と話す。
目標とする「環境負荷ゼロ」とは、気候変動、生物多様性、資源、化学物質の4つの視点で定義されている。さらにこれらが技術開発から回収・リサイクルまで6つのステージで構想される。鶴田氏は「Road to Zeroは長期目標で、マイルストーンとして5年ごとに中期目標を策定します。2020年までの中期目標はGreenManagement2020(GM2020)として社内に徹底的に浸透しています」と話す。
「環境への対応はマーケティングではない」
GM2020ではさまざまな具体的な目標値が設定され、それに沿った設計やオペレーション、調達、物流、リサイクルが行われる。例えば、熊本県のソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 熊本テクノロジーセンター(熊本テック)では、半導体の製造工程で地下水を使用する。そこで近隣の水田を利用した地下水かん養を行っている。5月から10月までの期間で作物の作付け前か収穫後の水田に、川から汲み上げた水を張り、浸透させて地下水に還元するという。
環境に対する直接的な取り組みだけではない。製品の省エネ化、製造や物流過程での温室効果ガス削減などの具体的な取り組みを下支えし、推進加速するためには「イノベーションが不可欠」(鶴田氏)だ。ソニーでは自然エネルギーを利用した「オープンエネルギーシステム」と呼ばれる、地理的に分散された再生可能エネルギーを主電力とした、効率的な電力の供給方式を研究、開発している。
「これらの環境への取り組みは、短期的に見れば必ずしもコストに見合う見返りがあるわけではありません。しかし、長期的に見れば、必ず利益に変わるという確信を持っています」と鶴田氏は力を込めた。さらに「当社の環境活動は、コンシューマー向けに大きくアピールしているわけではなく、マーケティングという意味ではありません。地球や社会に良いことをすること自体が、事業を持続可能にするのです」と続けた。
システムに組み込まれた環境対策
しかしRoad to Zeroで掲げられる「環境負荷ゼロ」という壮大な目標は、机上の空論ではなく、達成できるのだろうか。疑問を投げかけると、鶴田氏は「やり遂げることができると考えています」と力強く答えた。「具体的な道筋はできています。商品の小型化・省エネ化は、ソニーのような技術開発企業の使命です。省エネ化とは、環境対策に他なりません。つまり、品質管理と環境対策は一体で、システムの中に環境対策が組み込まれているのです」(鶴田氏)
ソニーでは今後、液晶テレビやデジタルカメラなどの、ハイエンドモデルを含めた全ての機種に再生プラスチックを導入していく方針だ。これも品質管理が環境への取り組みと一体化している具体的な事例だろう。
取材の最後に鶴田健志・品質・環境部ゼネラルマネージャーは「当社は、社会をリードし、世の中全体が良い方向に向かう一助となりたい」と語った。SONYの事業とサステナビリティへの取り組みは、同一だ。
沖本 啓一(おきもと・けいいち)
オルタナ編集部 編集局
好きな食べ物は鯖の味噌煮。










